
【おひとりさま終活まとめ】誰が納骨してくれる?死後に安心できる10の手続き<その1>
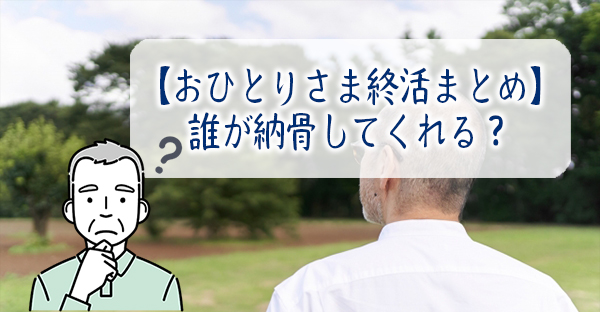
おひとりさま終活では、永代供養の生前契約をしても「誰が私の遺骨を納骨してくれるの?」など、自分亡き後に不安を感じる人も少なくありません。
けれども65歳以上の高齢者が住む2492万7千世帯の内、単身世帯は683万世帯、高齢者のいる世帯全体の27.4%もの世帯が「おひとりさま」です。
(出典:厚生労働省、平成30年「国民生活基礎調査」より)
現代は、おひとりさま終活の不安に応えた、さまざまな制度や民間サービスがあります。
元気なうちからおひとりさま終活を進めることで、余裕を持って不安を払拭できるでしょう。
【おひとりさま終活まとめ】誰が納骨してくれる?死後に安心できる10の手続き<その1>

身辺整理

おひとりさま終活の第一歩は、身辺整理です。
今住んでいる家や家墓(先祖代々墓)など、相続人や継承者が、その後の維持管理に困るような財産は自分の代で処分し、残された財産はどれくらいあるのか、改めて掘り起こしてみましょう。
(1)家じまい
(2)墓じまい
(3)財産の整理
・財産目録の作成
(4)デジタルデータの整理
賃貸アパートなど収入が伴う不動産財産や、築年数が20年以内の戸建て住宅であれば、相続後も定期収入が見込めたり、売却益を期待できます。
けれども築年数が30年以上経過した戸建て住宅などは、「空き家問題」の対象物件になるかもしれません。
家じまい
今、築年数の古い空き家が放置され、持ち主が分からなくなる「空き家問題」が深刻になっています。
空き家になった家の相続は、固定資産税も割高になり、維持管理費も大きな負担になりがちです。
<家じまいの選択肢>
・大規模修繕(リノベーション)・リフォームをする
・売却する(そのまま/更地にして)
・リバースモーゲージの担保にする
・寄付する
「相続放棄をすれば良いのでは?」と言う方もいますが、実は相続人が一人だった場合、相続放棄をしても、空き家の管理責任は残ってしまいます。
大規模修繕(リノベーション)・リフォームをする
現状では買い手が付かなそうな戸建て住宅でも、大規模修繕(リノベーション)やリフォームにより生まれ変わることもあるでしょう。
生前に預貯金財産を使って戸建て住宅を大規模修繕(リノベーション)・リフォームすることで、将来的に相続が発生した後、相続税の節約になり、一石二鳥です。
近年ではリノベーションを目的とした不動産売買を交渉する方法もあります。
売却する
生前に戸建て住宅を売却してしまえば、安心できるかもしれません。
最初に売却活動をしても売れない場合は、家屋を解体して更地にする方法もあります。
ただし解体費用が掛かり、家屋が経たない土地のみの不動産は、固定資産税が割高になるため、早々に売却をしたいところです。
また家を売却した後、家賃を払う形でその家に住み続ける「リースバック」の方法もあります。
※古い家を売却する
・【不動産の相続】相続した実家が売れない!空き家になった家でも買い手が付く5つの対策
リバースモーゲージの担保にする
「リバースモーゲージ」とは、高齢世帯が家を担保にして老後資金を借りる仕組みです。
今では国が運営する「不動産担保型生活資金」の他、3大メガバンクをはじめとする、民間金融機関でも扱っています。
生前は利息のみを支払い、家にはそのまま住み続けることができる点がメリットです。
(死後に担保としていた家を引き取って返済します。)
ただ変動金利のみで利息面でデメリットもあり、対をなして登場しているのが、先述した「リースバック」です。
いずれにしても、死後に「空き家問題」となりそうな不動産が残りません。
※リバースモーゲージ/リースバック
・【老後に破産しない資金計画】リバースモーゲージとは?決定前に押さえたい6つの基礎知識
家じまい
「空き家問題」と同様に、今深刻化しているものが「無縁墓」です。
お墓自体は相続税がかからない「祭祀財産」なのですが、継承するとお墓の維持管理や霊園への年間管理料、家墓になると親族の法要法事など、墓主(継承者)は多大な責任と、経済的・肉体的負担がかかります。
さらに今ではお墓を継承したからと言って、家財一切を相続する「家督を継ぐ」習慣も残っていません。
・墓じまい
・仏壇じまい
墓じまいも家じまい同様、生前にお金を出して済ませることで、遺産総額が少なくなるため、将来的に相続人にとって、相続税負担が軽減されます。
※ 墓じまい
・大阪で選ぶ「墓じまいパック」。業者選びのポイントや注意点
・墓じまいしないでお墓を放置したらどうなる?後継者の負担についても紹介
・墓じまい後の永代供養に掛かる費用。納骨後も支払いはある?選ぶ時の3つのポイント
・墓じまいのメリットとは?増えている理由や一般的な流れと掛かる費用などを解説
仏壇じまい
墓じまいをしたからと言って、必ずしも仏壇や位牌まで処分する必要はないのですが、位牌もお墓と同じように「魂の宿る物」として、相続時の扱いに困る祭祀継承財産のひとつです。
墓じまいでは取り出した遺骨を永代供養する流れが一般的ですが、位牌も永代供養ができます。
「位牌堂」「位牌供養塔」などを設けている霊園がありますから、遺骨の永代供養を依頼した時に、相談してみると良いでしょう。
財産の整理
おひとりさま終活の身辺整理では、財産整理も重要です。
特に子どもや孫など、直系血族の継承者がいない場合には、自分の望む人へ遺産を譲るよう、生前に対策を取る人は少なくありません。
墓じまい・仏壇じまいの項で相続税がかからない「祭祀財産」についてお伝えしましたが、一方で庭木や仏具など、思わぬものが骨董品や評価価値のある財産と捉えられることもあります。
(1)相続税が課税
・預貯金や現金
・有価証券、株券(ゴルフ会員権)
・不動産財産
・著作権、営業権など
・骨董品
・車
…など
(2)相続税が非課税
・祭祀財産(お墓・位牌・仏壇仏具など)
・生命保険
・死亡退職金
・葬儀費用
まずは今の財産を第三者にも分かりやすく示した、財産目録を作りましょう。
※相続税が課税される/されない財産
・【大阪のおひとりさま終活】相続税が掛からない財産の注意点。どうして課税されたの?
・【大阪のおひとりさま終活】相続税が掛かる財産をおさらい。家具家電まで課税対象なの?
財産目録の作成
保有している財産の一覧を示したものが「財産目録」です。
平成31年1月より、自筆証書遺言に添付する財産目録においても、ワープロやパソコン文書での提出が可能になりました。
そのため財産目録のテンプレートは、あらゆる業者で提供してることでしょう。
また裁判所webサイトでも、財産目録のテンプレートがダウンロードできます。
(裁判所webサイト:「書式集」)
特別な形式はないものの、財産を確実に特定しなければなりません。
例えば、不動産財産であれば日ごろ使用している住所ではなく、登記簿に記載された住所を書きます。
※財産目録の書き方
・【相続対策】財産目録の書き方☆記載する5つの項目や注意点|書き進める5つのポイント
デジタルデータの整理
近年の身辺整理で最も重要なものが、デジタルデータの整理でしょう。
・メール/スマートフォン情報(アドレス帳など)
・アプリ(有料サービスなど)
・写真/動画データ
・SNSアカウント
・ログイン情報
(ネット銀行/ネットショッピングサイトなど)
生前ギリギリまで使用している人も多いので、人に見られたくないデータや消去できるものは消去しながら、死後に削除して欲しいSNSアカウントなどについては、エンディングノートなどにIDを記載しておきます。
※デジタルデータの整理
・【おひとりさま終活】「デジタル遺品」ってなに?デジタル終活のメリットと5つの手順とは
葬儀や納骨先の生前契約

おひとりさま終活では、自分亡き後の葬儀やお墓(永代供養)の生前整理をメインとする人も多いです。
特に家墓(先祖代々墓)を墓じまいした場合、自分の入るお墓はありません。
おひとりさま終活で多い遺骨の納骨先は、継承者が必要ない永代供養でしょう。
(5)葬儀の生前契約
・遺影選び
(6)永代供養の生前契約
・墓友
・死後事務委任契約
葬儀は生前に葬儀を済ませる「生前葬」も稀に見掛けますが、ほとんどは葬儀の生前契約です。
ただおひとりさま終活だと思っていても、残された親族が積極的に葬儀や納骨を進めるかもしれません。
この時、生前契約の存在を知らないまま、他の業者と契約を進めると、後々トラブルの元にもなり兼ねませんので、生前契約の存在は知らせておくようにしてください。
(エンディングノートなどで詳細を明記する方法もあります。
この場合は、死後早々にエンディングノートの存在が分かるようにしなければなりません。)
葬儀の生前契約
葬儀の生前契約のメリットは、葬儀社に生前に一括支払いをするケースが多いため、故人の口座凍結により、喪主(施主)が立て替えなどを行わずに済む点です。
また、希望する自由な葬儀を設計することができます。
残された人々に余計な苦労を掛けることなく、滞りなく葬儀ができる点も、生前契約が人気の理由でしょう。
・一般的な葬儀(一般葬/家族葬/密葬など)
・個性的な葬儀(音楽葬など)
・自由な葬儀(無宗教葬/0葬/海葬など)
葬儀の生前契約でも「おひとりさま終活」だと思い、本人はあっさりとした0葬(火葬場で遺骨を引き取らない葬送)や、海葬(海に遺骨を撒く葬送)などを生前契約している場合があります。
この時、しばしば残された人々が抵抗を示し、トラブルや突然のキャンセルに発展することも少なくありません。
喪主を務めるであろう人にも相談をして進めることが、死後のトラブルを防ぐポイントです。
※葬儀の生前契約
・葬儀で使われる祭壇の役割や種類とは?選び方のポイントもあわせて解説
遺影選び
近年の遺影は、ある程度デジタル加工ができるため、昔のようにキレイな背景に拘る必要もなくなりました。
けれどもおひとりさま終活では、遺影用の写真を撮影する人も増えています。
ひと昔前までは、生前に遺影を撮影すると「迎えに来る」「縁起が悪い」と嫌がられてきましたが、今では最期まで美しく記憶に残りたいとして、遺影撮影サービスを提供する写真店も増えてきました。
※遺影選び
・遺影の選び方とは|葬儀後に飾る場所と時期についても解説
永代供養の生前契約
墓じまいを済ませると、自分の入るお墓はなくなりますから、遺骨の納骨先を生前契約します。
「せっかく墓じまいをしたのだから」と、ニーズが高い遺骨の納骨先は、合葬墓や納骨堂、樹木葬など、継承者が必要ない「永代供養」が付いた納骨先です。
・合葬墓
・納骨堂
・自然葬(樹木葬など)
・永代供養付きの共同墓(墓友)
・ペットと入るお墓
…など。
墓じまいで取り出した配偶者や子どもなど、家族の遺骨を、生前は自宅で手元供養にして、永代供養の生前契約によって、自分の死後、一緒に納骨を希望する人も増えました。
※永代供養の納骨先
・【大阪おひとりさま終活】独身女性に選ばれる永代供養墓の選び方
・【大阪の墓じまい】取り出した遺骨の永代供養の費用はどれくらい?予算に合わせた選択肢
・墓じまいしてから永代供養をする手続きの方法|生前予約の場合や注意点を解説
「墓友」の選択肢
また最近では、終活セミナーによって出会った人々が共同で建てる、血縁関係のない人々が共同で入る、有志の共同墓もニーズが高まっています。
今では「墓友(はかとも)」の造語まで産まれました。
おひとりさま終活では、お互いに葬送や供養をし合える点が大きなメリットです。
予算を出し合いお墓を建てて納骨されますが、永代供養が付いているので、一定年数が過ぎると合葬墓に改葬(かいそう)され、他の遺骨とともに永代に渡り合同供養されます。
ペットと入るお墓
さらにおひとりさま終活でニーズが高まっている、永代供養付きのお墓が、ペットと入るお墓です。
けれども動物とお墓に入る考え方を好まない人も多く、どの霊園でもペットと同じお墓に入れる訳ではありません。
まだまだ新しい分野ですが、大阪ではペット霊園や、ペットと入るお墓も提供されるようになっています。
死後事務委任契約で納骨も安心
では、おひとりさま終活で遺骨の納骨先や葬儀の生前契約をしたものの、自分亡き後に誰が葬儀を執り行ってくれるのか…、遺骨を納骨してくれるのか…、不安な人も多いのではないでしょうか。
このような場合は「死後事務委任契約」を生前に結ぶことで、死後の処理を請け負ってくれます。
・葬儀を執り行う
・納骨
・知人や友人、親族への連絡
・行政手続き(死亡届など)
・遺品整理
…などなどです。
永代供養を契約した霊園や葬儀社などで、死後事務委任契約を請け負う、紹介してくれることもあるでしょう。
まとめ
今回は家じまい・墓じまい、そして永代供養を中心とした、おひとりさま終活についてお伝えしました。
ただこの他にも、「発つ鳥、跡を濁さず」として、遺言書の作成による遺産相続の指定、孤独死を避ける対策などを必須とする人は少なくありません。
後半、「【おひとりさま終活まとめ】孤独死と相続対策?死後に安心できる10の手続き<その2>」で詳しくお伝えしていますので、こちらも併せてご参照ください。
まとめ
おひとりさま終活で行う10の事柄
(1)家じまい
(2)墓じまい
(3)財産の整理
・財産目録の作成
(4)デジタルデータの整理
(5)葬儀の生前契約
・遺影選び
(6)永代供養の生前契約
・墓友
・死後事務委任契約
(7)遺言書の作成
・遺言執行人の選任(8)相続税対策
・生前贈与
・生命保険
(9)かかりつけ医を決める
(10)エンディングノートの作成
・延命治療の有無
・臓器提供、献体の有無
お電話でも受け付けております

















