
墓じまいで必要な永代供養の費用はいくら?納骨後の追加費用はかかる?後悔しない選び方

・墓じまい後、永代供養に掛かる費用は?
・永代供養の後も支払いはある?
・墓じまい後に後悔しない、永代供養の選び方は?
墓じまいでは、取り出した遺骨を永代供養にする人が多いです。
墓じまい後の遺骨は何からの方法で供養しなければなりませんが、永代供養を選ぶことで、墓地管理者に委ねることができます。
ただ永代供養にはさまざまなものがあり、選択肢によって費用幅も広いです。
本記事を読むことで、墓じまい後、遺骨の永代供養に掛かる費用相場や選択肢、後悔しない選び方が分かります。
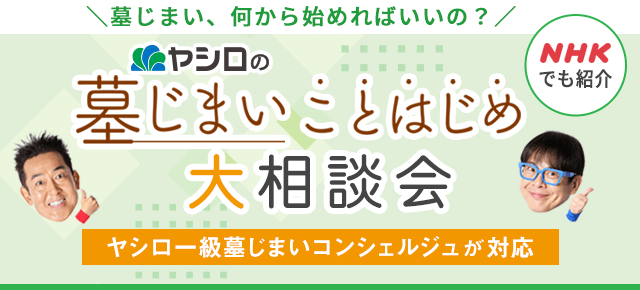
墓じまいと永代供養は違う

墓じまいはお墓を閉じること、永代供養はご遺骨の管理や供養を墓地管理者へ託すことを指し、両者は全く違うものです。
けれども「墓じまい」も「永代供養」も、1980年代以降に新しくできた言葉や考え方で、どちらも近代になってどんどん深刻化する、継承者問題を解決する糸口となっています。
そのため継承者問題を解消する際、墓じまいと永代供養がセットになって行われることも多いです。
墓じまいとは
◇「墓じまい」とは、お墓を閉じて墓地を返還することです
「墓じまい」は、所有しているお墓を閉じて墓地管理者へ永代に渡り墓地を使用する権利「永代使用権」を返還するまでを指します。
ただし墓じまいを進めるにあたり、墓地に埋葬したご遺骨は取り出さなければなりません。
お墓からご遺骨を取り出して、墓石を撤去し、墓地を更地にしてから墓地管理者へ返還する流れです。
墓じまいをせずに放置したお墓は、いずれ無縁仏・無縁墓として処理され、供養塔に合祀されますが、どこに合祀されたかも分からないケースもあります。
・お墓を放置したらどうなる?継承したけど維持費が払えない!管理できない時5つの対処法
永代供養とは
永代供養墓とは
◇永代供養墓とは、永代供養が付いたお墓です
一般的に永代供養墓のイメージは、霊園や墓地内にあるひとつの供養塔に、複数の他人のご遺骨を合祀するイメージがありますよね。
けれども「永代供養墓」とは永代供養が付いているため、継承者を必要としないお墓全般を指します。
もちろん、最初から骨壺や骨袋から出して、他のご遺骨と一緒に合祀される供養塔も「永代供養墓」のひとつですが、この他にも一般墓に永代供養を付けても永代供養墓です。
詳しくは「永代供養墓とはなにか?」について詳しく記した、下記コラムをご参照ください。
・永代供養墓はどんなお墓かわかりやすく解説!何年供養してくれる?選び方のポイントは?
墓じまい後の永代供養とは

◇墓じまいで取り出した遺骨は、何らかの形で供養しなければなりません
現存するお墓を撤去する墓じまいでは、お墓から遺骨を取り出します。
取り出したご遺骨は何らかの方法で供養しなければならず、人の遺骨を埋葬する場合、日本の法律では、行政が墓地と認めた場所以外では違法です。
●墓じまいをしてお墓がなくなると、取り出した遺骨の行く先がありませんが、そのまま放置する訳にはいきません。
どこかに埋葬することになりますが、墓じまいの多くは墓守がいないために決断しますので、墓じまいで取り出した遺骨は永代供養をし、そこで費用が掛かります。
墓じまい後の「永代供養」とは
◇「永代供養」とは、墓地管理者が遺骨を管理・供養するサービスです
「永代供養(えいたいくよう)」とは、様々な理由でお墓に行けない遺族(家族や親族)に代わって、墓地管理者である霊園や寺院が遺骨を管理・供養します。
「永代供養」は形のないものなので、状況や料金に合わせて選択肢はさまざまです。
| <永代供養の例> |
|
| [例] | [内容] |
| ①一般墓 | …一般墓に永代供養を付加 |
| ②永代供養墓 | …他のご遺骨と一緒に合祀埋葬 |
| ③納骨堂 | …屋内安置して永代供養 |
墓じまい後の永代供養の注意点として、1柱ごとの料金システムがあります。
お墓は1基に対する建墓費用ですが、永代供養の料金は1柱ごとです。
特に先祖代々墓の墓じまいでは、永代供養を行う遺骨の柱数に伴い費用もかさみますので、残されたご遺骨それぞれに、違う形の永代供養を選択するケースは少なくありません。
墓じまい後、永代供養をするメリット

◇取り出したご遺骨を永代供養することで管理負担が軽減します
墓じまいによって取り出したご遺骨は、何らかの方法で供養しなければなりません。
自宅でご遺骨を安置する手元供養の方法もありますが、墓じまいでは複数のご遺骨を取り出すことも多いでしょう。
また遠いご先祖様のご遺骨になると、ご自宅で手元供養をする決断はしにくいものです。
かと言って、新しいお墓を建てて埋葬するとお墓の維持管理や継承者問題は再発しますので、根本的な解消にはなりません。
けれども墓じまいで取り出したご遺骨を永代供養にすることにより、ご遺骨を寺院や霊園に託すことができて、継承者がいなくても無縁仏・無縁墓になる心配がありません。
①費用を抑える
◇永代供養は一般墓と比べて安価傾向です
墓石を持たない永代供養は、お墓を建てて維持管理をするよりも費用が安く抑えることができるでしょう。
また合祀墓など永代供養の方法によっては個別スペースを持たないため、一度納骨すると、年間管理料や修繕費など、納骨後の追加費用がかからず、初期費用のみで費用を納めることができます。
先祖代々墓(家墓)の墓じまいでは、複数のご遺骨を取り出すケースも多く、1柱ごとの費用を抑える工夫は必要です。
②お墓の維持管理の負担がない
◇永代供養はお墓の維持管理が必要ありません
永代供養は遺骨の維持管理を寺院や霊園に依頼するため、ご家族はお墓の掃除や維持管理の負担が軽減されます。
一方でお墓と同じようにお参りはもちろん、墓地管理者が主催する合同法要への参加や、個別の年忌法要ができる永代供養も多いです。
遠方に住んでいてお墓の掃除や管理ができない、高齢になってお墓の維持管理が困難になった方々にとっては、とても助かるでしょう。
③継承者が必要ない
◇永代供養により継承問題が解消します
墓じまいを決断する理由の多くが、現存するお墓の維持管理を負担に思ったり、将来的にお墓の継承者がいなくなるなど、お墓の継承問題です。
そのため取り出した遺骨を、今後も家族で維持管理・供養する負担があっては、墓じまいをしたからと言って、問題が解決したことにはなりません。
墓じまい後に取り出した遺骨を永代供養にすることで、ご先祖様の遺骨は墓地管理者に委ねられ、家族は維持管理や継承の負担がなくなります。
④宗旨宗派を問わない
◇永代供養は宗旨宗派を問わないプランが一般的です
特に民間霊園で提供する納骨堂や永代供養墓などでは、宗旨宗派を問いません。
これは永代供養が宗派と無関係であるためで、なかには神道で永代供養の納骨堂を運営しているケースもあります。
そのため墓じまいをして離檀したい方や、無宗教の方々にもおすすめです。
ただし永代供養は宗旨宗派を問わずとも、納骨後の供養においては特定の宗派で行う、法要は特定の宗派で行う寺院・霊園が多くあります。
寺院墓地でも永代供養においては宗旨宗派を問わない寺院が多いですが、契約後に檀家になることを求められてトラブルにならぬよう、最初に確認をしておきましょう。
永代供養のデメリット
墓じまい後、永代供養の費用内訳

◇永代供養には墓石代がかかりません
一般墓は「永代使用料(墓地代)+墓石代」が基本です。
そのうえで、ご遺骨を納骨する際の納骨料や、お墓の彫刻費用がかかります。
一方で永代供養はお墓のように墓石代がかからないため、一般墓と比べて安価に、ご遺骨を納めることが可能です。
また永代供養自体は形のないものなので、予算に合わせた永代供養を選ぶこともできるでしょう。
①永代供養料
◇永代供養料の費用幅は約5万円~150万円と広いです
墓石を持たない永代供養の費用は一般的に「永代供養料」に全ての費用が含まれています。
個別スペースを持たない、合祀墓などの永代供養では、納骨時の初期費用である「永代供養料」のみで、墓地・墓石がある一般墓のように年間管理料や修繕費用、お布施など、追加費用はかからないプランが一般的です。
ただし永代供養にはさまざまな形があるため、永代供養料には費用幅はあるでしょう。
合祀墓では約5万円~10万円の永代供養もありますが、墓石を伴うガーデニング型樹木葬などでは約80万円~150万円ほどのものも多く見受けます。
②納骨料
◇納骨料は約3万円~5万円、プラスαです
永代供養でご遺骨を納骨する際、僧侶をお呼びして納骨式を執り行います。
納骨式では読経供養のお礼として、僧侶へお布施を包みましょう。
お布施の相場は地域によっても違いますが、一般的に1回の読経供養につき、約3万円~5万円が相場です。
この他、寺院から納骨場所までの交通費「御車代」や、納骨式後に会食の場を設けたものの、僧侶が欠席された場合には「御膳代」も包みます。
納骨式や法要でのお布施マナーについては下記コラムも併せてご参照ください。
③印字料(必要な場合)
◇印字料がかかる場合、約2万円~5万円ほどです
集合墓や合祀墓に埋葬される永代供養でも、石碑に埋葬された方々の名前を彫刻する墓碑「礎(いしじ)」など、戒名や文字を刻字できる永代供養も多いです。
ワンプレート型の石碑に名前や文字を刻字し、小さな墓標が並ぶ永代供養もあります。
また納骨堂では、個別スペース前に戒名などを刻字できるプレートを備える施設もあるでしょう。
刻字料の費用目安は石材業者に依頼して個別墓に彫刻する場合、約3万円~5万円ほどです。
礎への刻字料は、約2万円ほどとなるでしょう。
墓じまい後の永代供養、費用相場

◇約5万円~30万円ほど/1柱が一般的な費用相場です
墓じまいの永代供養に掛かる費用相場は、約5万円~30万円ほど/1柱が一般的です。
ただ墓じまい後に選んだ永代供養の種類によって、費用幅が広くなります。
また墓じまいで取り出した遺骨の柱数によっても、永代供養に掛かる費用は大きく変わるでしょう。
●墓じまい後の永代供養の費用を見積もるには、お墓の内部調査がおすすめです。
…石材業者や永代供養先に相談をして、埋葬されている遺骨の柱数を把握します。
特に先祖代々墓は遺骨の柱数が多くなりがちですので、墓じまい後に掛かる永代供養の費用も高くなるため、注意をしてください。
永代供養の種類で違う費用相場
◇永代供養の費用相場の違いは、合祀埋葬か個別安置かの違いです
永代供養には、最初から骨壺や骨袋から取り出して、他のご遺骨と一緒に合祀埋葬し供養するタイプと、最初の一定期間は遺骨を個別安置するタイプがあります。
墓じまい後に永代供養を行うにあたり費用で分けると、下記3つのタイプが主流です。
| <墓じまい後の永代供養:タイプ> |
|
| [種類] | [費用相場] |
| ①合祀墓 | ・約5万円~30万円 |
| ②集合墓 | ・約20万円~60万円 |
| ③個別墓 | ・約50万円~150万円 |
永代供養に掛かる料金の内訳は「永代供養」「納骨料」「刻字料」、3つの料金で構成されています。
価格幅が広いですが、この3つの項目で調整すると考えてください。
永代供養に年間管理料は掛かる?
◇合祀墓(永代供養墓)に合祀埋葬されると年間管理料は掛かりません
最初から他のご遺骨と一緒に合祀埋葬される合祀墓(永代供養墓)は、最初に支払いを済ませたら、その後の費用が掛かりません。
墓じまい後に永代供養を費用を掛けてでも選ぶのには、年間管理料(寺院墓地であればお布施など)など、その後のお金が掛からない点が大きいでしょう。
正に、その後の継承者(墓守)の必要がない理由です。
・永代供養料
・納骨料
・刻字料(必要な場合)
この3つの費用を契約時に支払ってしまえば、特別な事がない限り、それ以上の費用が発生する事はありません。
ただし納骨堂など、遺骨の個別安置期間が設定された永代供養では、個別安置期間に対して年間管理料が発生する料金システムが多いですので確認をしてください。
では次に、墓じまい後に永代供養を行う場合に費用が大きく分かれる行く先、3つの種類を詳しくお伝えしていきます。
墓じまい後、永代供養をする方法と費用目安

◇墓じまい後の永代供養では、個別安置期間を設けた方法もあります
墓じまいで複数のご遺骨を多く取り出した場合、合祀墓による永代供養を選ぶことで、費用を安く抑えることができるでしょう。
ただし最初から他の方と一緒に合祀されてしまうため、個別安置期間を設けた永代供養を選ぶ方も多いです。
①合祀墓
②集合墓
③個別墓
④納骨堂
合祀されるまでの個別安置期間の長さと個別スペースの広さが、墓じまい後の永代供養料に影響します。
ただし永代供養は一般的にご遺骨1柱ごとの料金システムなので「ご遺骨が何人分入るか?」で計算することになるでしょう。
個別安置期間が長ければ長いほど、人数が多いほど、永代供養料も高くなります。
墓じまいで永代供養の費用①合祀墓

◇墓じまい後の永代供養では、合祀墓が最も安いです
「合祀墓(ごうしぼ)」とは、骨袋や骨壺から遺骨を取り出して、他の遺骨と一緒に合祀埋葬される永代供養のタイプで、「永代供養墓」「合葬墓」「供養塔」などとも呼ばれます。
個別スペースはありませんが、墓じまい後の永代供養では、最も費用が安いです。
| <墓じまいの永代供養①合祀墓とは> |
|
| [形状] | ・記念碑 ・石塔、モニュメントなど |
| [費用目安] | ・約5万円~30万円ほど/1柱 |
墓じまいによる永代供養で遺骨の数が多い場合、費用はまとめて見積りを出してくれる施設もあります。
合祀墓を選ぶメリット
◇合祀墓は墓じまい後の永代供養で、最も費用が安いです
最初から他の遺骨と一緒に合祀埋葬されますが、その分、墓じまい後の永代供養では、費用が最も安い選択肢でしょう。
古くからの先祖代々墓などで故人との関係性が薄い、遺骨の柱数が多い時などにも選ばれます。
| <合祀墓のメリット・デメリット> ●料金の内訳は、永代供養料のみ |
|
| ①メリット | ・費用が安い ・すぐに納骨できる |
| ②デメリット | ・個別スペースがない ・後々取り出せない |
基本的な料金の内訳が、永代供養料のみです。
個別スペースがなく、個別の墓石などがないため費用も安い一方、参拝対象は合同の供養塔となります。
納骨したものが取り出せない分、管理する側としても手間が掛からないため、管理施設側としては安く提供できるのでしょう。
合祀墓に納骨後の供養は?
◇合祀墓では、多くが定期的に合同供養されます
合祀墓(永代供養墓)は永代供養のお墓です。
永代供養は付いているため、合祀墓では埋葬後も合同で定期的に供養されます。
昔の日本では仏教宗派によって信徒のために本山納骨が行われてきました。
本山納骨とは、その宗旨宗派の総本山にある合祀墓に埋葬をすることです。
・【大阪の墓じまい】本山納骨とは。費用の目安と契約前のチェック事項
墓じまいで永代供養の費用②集合墓

◇集合墓は、ロッカーのように遺骨を収蔵するお墓です
「集合墓」とは、礼拝の対象となる記念碑・シンボルは共有しますが、納骨スペースは個別に分かれているタイプのお墓となり、納骨堂も集合墓の一種と言えます。
墓じまい後、永代供養にそれほど費用は掛けられないものの、両親や祖父母など近しい身内の遺骨などで、個別スペースで残したい方などに人気です。
| <墓じまいの永代供養②集合墓とは> |
|
| [形状] | ・個別スペースが並ぶ (ロッカーのような造り) ・墓石を使用 |
| [費用目安] | ・約20万円〜60万円ほど/1柱 |
また古い先祖代々墓で老朽化が進み、改めて建墓を行うには予算が足りなかったものの、後々はお金を貯めてお墓を建てたい家でも、遺骨の取り出しが可能です。
集合墓のメリット
◇契約した一定期間は個別に遺骨が安置されます
墓じまい後の永代供養に集合墓を選ぶと、一般墓などと比べて費用を安く抑えながら、個別に参拝できる点がメリットです。
ただ個別スペースが確保されるのは、契約した一定期間なので注意をしてください。
契約した期間が更新なく過ぎると、合祀墓に合祀埋葬するシステムが一般的です。
| <集合墓のメリット・デメリット> |
|
| ①メリット | ・個別の参拝対象がある ・遺骨が個別に安置される ・一般墓より費用が安い |
| ②デメリット | ・合葬墓より費用が割高 |
| [注意点] | ・年間管理料の確認 ・個別安置期間の確認 |
霊園によっては、個別安置期間に年間管理費が掛かる場合があるので、契約時には確認をしてください。
集合墓の注意点
◇集合墓の遺骨の取り出しや、個別安置期間は契約により違いがあります
ここで気になるのは個別スペースが確保される「一定期間」ですが、一定期間は3年・5年・10年・15年…、33年とさまざまです。
また、墓じまい後に永代供養の費用を抑え、集合墓を選んだ場合、後々遺骨を取り出す目的の方も見受けます。
けれども霊園や寺院など、墓地によっては遺骨を取り出せない規定もあるので、契約時に確認をしてから進めてください。
墓じまいで永代供養の費用③個別墓

◇個別墓は、永代供養を付加した一般墓です
「個別墓」は一般墓と同じタイプで、家族ごとに1つの墓標・シンボルがあります。
墓じまい後は永代供養を付加するので、費用は掛かりますが、お墓の形状を残しながら、継承者や墓守の負担がありません。
また個別墓とひと口に言っても、入る人々の人数や関係性により、さらにいくつかのタイプに分かれます。
| <さまざまな個別墓> |
|
| [形状] | ・お墓 |
| [費用目安] | ・約100万円~300万円以上 (平均…約175万円ほど) |
| [お墓のタイプ] | ・個人墓…個人で入る ・家墓…家族が入る ・友墓…知人友人(血縁関係なし) |
墓じまい後に永代供養として選ぶ場合、費用が最も掛かるタイプが個別墓であり、その分デザイン墓など自由度も高いのが特徴です。
個別墓のメリット
◇一般墓の形を保ちながら、無縁墓になる心配がありません
墓じまい後に永代供養の個別墓を選ぶ場合、費用にはこだわらない方が多いでしょう。
お墓が遠方にあってお墓の管理が大変、継承者がいないなどの理由で墓じまいを決断し、自宅近郊に遺骨を移す「改葬(かいそう)」が多い傾向です。
| <個別墓のメリット・デメリット> |
|
| ①メリット | ・一般墓と形は同じ ・継承者を必要としない ・お墓参りができる |
| ②デメリット | ・費用が割高 ・年間管理費が掛かる |
墓じまいの後、永代供養付きのお墓を建てると費用面では一般墓と同じでしょう。
お墓を建てる墓石代が掛かる他、墓地区画も必要ですから、建てた後には一般墓と同じく、年間管理料を支払います。
個別墓の注意点
◇個別墓は、全く管理が不要ではありません
個別墓は永代供養が付いている点が一般墓と違うだけで、墓地区画の定期的な掃除やお参りは、通常通りです。
また一般墓と同じく、墓地区画に対して年間管理料が掛かります。
個別墓の永代供養で個別にお墓が維持される期間は、約33回忌・50回忌など、一般的な弔い上げに倣った期間が多いです。
契約更新を検討する場合、忘れずに期間内に更新をしてください。
墓じまい後、永代供養の費用④納骨堂

◇納骨堂は屋内で個別にご遺骨を安置する施設です
現代において最も需要が高い墓じまい後の永代供養が納骨堂となります。
納骨堂は屋内でご遺骨を安置できる施設で、広い敷地を要する墓地とは違い、都心部に多く位置しているため、手軽に参拝できる点が魅力です。
| <墓じまいの永代供養④納骨堂とは> |
|
| [形状] | ●屋内でご遺骨を安置 ・ロッカー型 ・仏壇型 ・位牌型 ・自動搬送型(ビル型) …など |
| [費用目安] | ・約20万円~180万円ほど |
納骨堂は現代において最も需要が高い永代供養のひとつであり、ニーズに合わせてさまざまな種類が登場しました。
永代供養の費用を安く抑えたいならば、昔からあるロッカー型の納骨堂や、寺院などに多い位牌型の納骨堂が安い傾向です。
納骨堂のメリット
◇納骨堂は屋内環境で手軽に参拝ができます
納骨堂は前述したように集合墓のひとつの形ですので、個別にご遺骨が安置できることは大きなメリットのひとつです。
さらに納骨堂の場合、清潔な屋内環境下でご遺骨が保管されるため、納骨堂施設の開館時間内であれば、快適に手軽にお参りができます。
下記では納骨堂ならではのメリット、デメリットをお伝えします。
| <納骨堂のメリット・デメリット> |
|
| ①メリット | ・都心部に多くアクセスが良い ・清潔な環境下で参拝できる ・ご遺骨が清潔に保管される ・雨天など天候に左右されない |
| ②デメリット | ・参拝規約を設けた施設も多い ・屋内環境により周囲への配慮が必要 ・参拝は開館時間内に限る |
| [注意点] | ・年間管理料の確認 ・個別安置期間の確認 ・更新の有無を確認 |
納骨堂は都心部に多いため、電車など公共機関でのアクセスは便利です。
都心部に建つ納骨堂のなかには、雨が降っても駅から濡れずにアクセスできる施設もあります。
一方で立地環境によっては、充分な駐車スペースを備えていない施設もあるでしょう。
納骨堂はさまざまなので、現地見学をしてから決めることをおすすめします。
納骨堂の注意点
◇屋内施設の納骨堂は、参拝規約を設けた施設も多いです
納骨堂は集合墓の注意点と同じく、個別安置期間が何年あるかの確認や、更新の有無の確認が必要になりますが、この他にも参拝規約にも注目すると良いでしょう。
屋内施設である納骨堂では、火気を伴うお線香の使用を禁止したり、香りが強い供花、食べ物を禁止する施設も多いです。
また屋内での混雑を避けるため個別スペース前ではなく、参拝用の共同スペースを設けた施設もあります。
納骨後の参拝や供養の方法をイメージして、ご家族の要望に合う施設かどうか、現地見学で見極めてから決めましょう。
墓じまい後の永代供養に追加費用はかかる?

◇永代供養は基本的に、追加費用はかかりません
終活を伴う墓じまいの場合、永代供養の初期費用を生前契約時に支払ったものの、納骨や納骨後に追加費用がかかって、子どもや孫に経済的な負担がかからないか、心配をする声も多くあります。
基本的に墓じまい後の永代供養に費用はかかりませんが、永代供養自体が形のないものなので、その形式によっては追加費用がかかる可能性もあるでしょう。
ここでは初期費用の支払い後にかかり得る追加費用と、その内容を解説します。
①年間管理料
◇個別安置期間を設けた永代供養にかかる追加費用です
個別安置期間を設けた集合墓や納骨堂などの場合、個別安置期間においては一般的なお墓と同じく、年間管理料が毎年かかる施設が多いです。
「年間管理料」は、寺院では「護持会費」とも呼ばれ、公共部分の維持管理にかかる費用で、毎年かかるランニングコストとなります。
年間管理料は約3千円~3万円と施設環境により幅は広いですが、平均的な費用目安は約5千円~1万5千円ほどでしょう。
生前契約の場合、個別安置期間の年間管理料を、契約時に初期費用とともに、一括で支払うケースもあります。
②お布施
◇永代供養料と僧侶へお渡しする費用は別です
墓地管理者へ支払う永代供養料とは別に、僧侶へお布施をお渡しします。
もともとお布施はサービスに対して支払う「代金」「料金」ではなく、仏教における得行のひとつであり、仏教の修行ととらえるためです。
そのため納骨式の読経供養を行うなど、永代供養に伴い僧侶へ依頼する物事に関しては、その都度、追加費用がかかります。
納骨式や法要で読経供養を依頼するほか、戒名を名付けてもらった時にも、お布施を包む必要があります。
・永代供養をするとき戒名は必要?戒名にかかる費用は?戒名なし位牌なしで供養はできる?
③墓石代
◇個別墓に永代供養を付ける場合、墓石代がかかります
個別のお墓に永代供養を付ける場合、一般墓と同じように墓石代はもちろん、個別墓が一般墓であれば、墓地代となる永代使用料も不可欠です。
一般墓に永代供養を付加する場合は、一般墓の費用に永代供養料が追加されるため、「墓石代+永代使用料(墓地代)+永代供養料」となります。
ただし民間霊園など、現代の墓地のなかには、そもそも全てのお墓に永代供養が付いているシステムも増えました。
個別のお墓が伴う永代供養で、費用をできるだけ抑えたいならば、ランクや産地、質など、安い墓石を選ぶと良いでしょう。
④法要会場の使用料
◇法要会場を借りる場合、使用料を支払います
納骨式や年忌法要を執り行う際、自宅以外の場所を借りる場合は、会場使用料もかかるので注意をしてください。
納骨堂など施設によっては、施設内に個別の会場を用意したものもあります。
また納骨式や年忌法要の後、参列者に会食をふるまう場合には、会食会場や料理の費用もかかるでしょう。
ただ故人とごく近しい身内や家族のみで執り行う納骨式や年忌法要も増えました。
家族のみの納骨式では、墓前で済ませて会場を必要としないケースもあり、判断は施主により自由です。
墓じまい後、永代供養を選ぶ3つのポイント

墓じまい後に永代供養を選ぶ際、管理費用や埋葬する人数など、初めて墓じまいを進める墓主の方がほとんどですので、戸惑うことばかりではないでしょうか。
墓じまいでは、業者に内部調査を依頼して初めて、埋葬されている遺骨の数を知ることも多いです。
①埋葬する柱数
②供養の頻度や宗派
③年間管理料
前述したように、古くからの家墓(先祖代々墓)であれば、複数の遺骨が埋葬されていますが、この場合はそれだけ墓じまい後の永代供養に掛かる費用も高くなります。
また近しい身内であれば、墓じまい後にも頻繁に供養できる環境だと有難いですよね。そして負担の少ない管理費用は不可欠です。
①埋葬する柱数
◇永代供養の料金システムは1柱ごとが多いです
一般墓の建墓費用は1基あたりの費用ですよね。
お墓の大きさにより違いますが、一般的にはお墓1基あたり6柱~8柱ほどが入ります。
一方、墓じまい後の永代供養では、取り出した遺骨1柱ごとの費用ですから、6柱取り出していれば、それだけ費用も高くなる計算です。
また墓じまい後の永代供養に、費用を抑えた集合墓を選んだ場合、埋葬(収蔵)できる遺骨の数が制限されている施設は少なくありません。
スペースごとの利用が可能な場合でも、短期間の使用を前提にしているので、普通のお墓よりも納骨スペースが小さい傾向です。
②供養の頻度や宗派
◇永代供養はされますが、供養のやり方は施設により違います
例えば民間霊園は無宗教が多いですが、特定の宗旨宗派に倣い執り行うでしょう。
また墓じまい後は寺院墓地でも、永代供養の費用を抑えて提供してくれる墓所もあります。特定の宗旨宗派にこだわりがある場合、その宗派の総本山を選ぶのも一案です。
| <供養の頻度や宗派> |
|
| ①供養の頻度 | ・お彼岸やお盆などの行事ごと ・毎月の供養 ・毎日の供養 …など。 |
| ②供養の仕方 | ・合同供養 ・参列の可否 |
| ③宗旨宗派 | ・供養の宗派 |
家族に代わり永代に渡って供養をしてくれますが(その霊園が倒産などにならない限り)、供養の方法や頻度は、霊園によってそれぞれです。
また合同供養に遺族が参列できる施設もあれば、今ではネットを通して供養に参加できる施設もあります。
規約をよく読み供養方法や頻度を確認してから、契約へ進むと安心です。
③年間管理料
墓じまい後の永代供養で失敗しないためには?

◇希望をまとめ、要望にあった永代供養を選びましょう
永代供養は継承者問題が深刻化する現代においてニーズが高く、ニーズに対応したさまざまな供養や管理の方法が登場しています。
そのため墓じまいの後に、後々まで後悔しない永代供養を選ぶためには、納骨後の供養の頻度や個別安置期間、将来的な継承の有無まで検討して、選ぶと良いでしょう。
ひと口に永代供養といっても、1世代型の個人用や、夫婦用、家族用があります。
また近年では室内墓所を代表する、継承者の負担がない「継承型」の永代供養も登場しました。
家族や親族で話し合いながら、寺院や霊園を現地見学してプランの詳細を理解し、自分たちのニーズに適切なものを選ぶことが大切です。
まとめ:墓じまい後の永代供養は、費用を抑えた合祀墓が多いです

一般的に墓じまい後に選ぶ永代供養は、費用を抑えた約5万円~30万円ほど/1柱の合祀墓(永代供養墓)が多いです。
ただ合祀墓(永代供養墓)は一度埋葬されると、後々取り出しができません。
お墓の名義人である墓主は、行政上では一人で決断できますが、後々の親族トラブルを避けるため、事前に関係者に相談をすると安心です。
両親や祖父母など身近な家族の遺骨のみ、納骨堂や集合墓などへ個別に安置する選択もあるでしょう。
核家族化が進み、定期的なお墓参りができない家族も増えました。
こういった悩みを近年のライフスタイルに合った、新しい供養の形を取り入れることも大切です。
・【墓じまいの費用まとめ】平均や僧侶費用、離檀料は?遺骨供養まで手順5つでかかる費用
 
お電話でも受け付けております
















