
墓じまいをした遺骨はどうなる?永代供養の選び方|処分で後悔しない5つのチェック項目

墓じまいで取り出した遺骨は、どのように供養すればよいのでしょうか。
改葬手続きや永代供養の選び方を誤ると、後から「遺骨をどうすればよかったのか」と後悔する人も少なくありません。
本記事では、墓じまい後の遺骨の扱い方から、費用相場・手続きの流れ・永代供養の種類までを分かりやすく解説します。
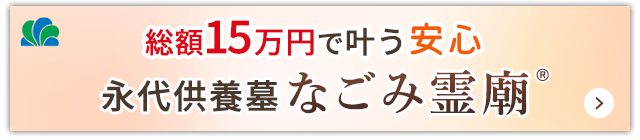
墓じまい後の手続きと遺骨の移動方法

墓じまいでお墓を撤去したあとは、遺骨をどう扱うかを決めなければなりません。
このとき必要となるのが「改葬手続き」です。
改葬とは、遺骨を別の墓地や納骨堂に移動させる正式な手続きのことです。
ここでは、改葬の流れと遺骨の一時保管について解説します。
改葬手続きと移動の流れ
遺骨を移動する際は、必ず自治体から「改葬許可証」を取得します。
これは法律で定められた手続きで、許可証がなければ遺骨を動かすことはできません。
1.現在の墓地の管理者に「埋葬証明書」をもらう
2.新しい納骨先(納骨堂・霊園など)に「受入証明書」を発行してもらう
3.それらを添えて役所に申請し、「改葬許可証」を受け取る
許可証が発行されたら、石材店などの専門業者に依頼して遺骨を取り出します。
地域によっては、取り出し時に立ち会いを求められる場合もあります。
書類の準備や流れを早めに確認しておくとスムーズです。
自宅で一時的に保管する場合の注意点
墓じまい後すぐに納骨先が決まらない場合は、一時的に自宅で保管しても問題ありません。
ただし、湿気が多い環境では骨壺の中にカビが発生することもあるため注意が必要です。
・直射日光を避ける
・換気の良い場所に置く
・除湿剤を入れて湿気を防ぐ
改葬先が決まるまでの間も、丁寧に安置しておくことで心残りなく次の供養へ進めます。
墓じまいをした遺骨はどうなる?

◇墓じまいで取り出した遺骨は、永代供養が一般的です
墓じまいで取り出した遺骨でも、人の遺骨は勝手に処分したり、公共の場に放置すると死体遺棄罪として扱われます。
また「墓地、埋葬等に関する法律」第4条により、火葬場で焼骨した遺骨であっても、人の遺骨は家の庭など、墓地以外の場所に埋葬できません。
●2018年、石材店経営者の男が、マンションのゴミ収集所に、墓じまいで取り出した遺骨を不法投棄したとして、死体遺棄・廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されました。
この他にも、2019年には父親の遺骨をトイレに放置して逮捕、2017年には妻の遺骨をJR東京駅コインロッカーに保管して逮捕された事例があります。
そのため墓じまいで取り出した遺骨の多くは、継承者を必要としない「永代供養」を依頼する方法が一般的です。
「永代供養」とは?
◇墓地管理者が家族に代わり、永代に渡って遺骨の供養を行います
「永代供養」は遺骨の家族に代わり、永代に渡り遺骨の供養を霊園などの墓地管理者が行うものです。
墓じまいによる遺骨の永代供養では、他の遺骨と一緒に合祀される「合祀墓」や、一定期間は遺骨を残す「納骨堂」などによる永代供養が選ばれています。
永代供養を依頼することにより、家族はその後の遺骨の維持管理や、供養継承の義務がなくなり、供養を託すことができる方法です。
墓じまいの遺骨を永代供養する選び方は?

◇遺骨を残すか・残さないかは、最初のチェック項目です
永代供養は遺骨を永代に渡り供養してくれますが、遺骨が永遠に現存する訳ではありません。
墓じまいによる遺骨の永代供養で最もニーズが高い「合祀墓」は、他の遺骨と一緒に合祀されるため、一度埋葬すると再び個別に取り出すことはできません。
| <墓じまいの遺骨:残すか、残さないか> | |
| [遺骨を残す] ●お墓を持つ |
①一般墓(個別墓) ②集合墓 |
| ●お墓を持たない | ③納骨堂 ④手元供養 (永代供養ではない) |
| [遺骨を残さない] ●墓標がある |
⑤合祀墓 ⑥樹木葬 |
| ●墓標がない | ⑦散骨 |
基本的に墓じまい後の遺骨の納骨先は、お墓を持たない合祀墓や納骨堂、樹木葬をはじめとした自然葬が人気です。
けれども継承者問題に端を発した墓じまいの場合、永代供養が付いた一般墓「永代供養墓(個別墓)」を建てるケースもあります。
同じ一般墓でも、永代供養を付けることにより、継承者を必要としないためです。
・お墓購入の項目「永代使用料」ってなに?永代供養料や管理費とは違うの?|永代供養ナビ
永代供養の種類と費用の目安
墓じまい後の遺骨をどこに納めるかを決める際は、「永代供養の種類」と「費用の相場」を知っておくことが大切です。
永代供養とは、家族に代わって霊園や寺院が継続して遺骨の供養を行う方法で、継承者がいなくても安心して供養を任せられる点が特徴です。
永代供養の主な種類には、合祀墓・納骨堂・樹木葬などがあります。
それぞれ費用の目安や供養の仕方が異なるため、希望する供養の形に合わせて選びましょう。
・合祀墓:約10万円~30万円前後(他の遺骨と一緒に埋葬)
・納骨堂:約30万円~80万円前後(屋内で個別に安置)
・樹木葬:約5万円~200万円前後(土に還る自然葬型)
費用だけで選ぶのではなく、「お参りのしやすさ」「個別安置期間」「供養方法」も確認しておくと安心です。
特に都市部の納骨堂はアクセスが良い反面、契約年数が限られている場合もあるため、更新や合祀の時期もチェックしましょう。
改葬手続きと遺骨の移動の流れ
墓じまいで取り出した遺骨を他の霊園や納骨堂に移す場合には、改葬手続きが必要です。
改葬とは、埋葬されている遺骨を別の場所に移動することで、「改葬許可証」がなければ運搬できません。
これは墓地、埋葬等に関する法律に基づく正式な手続きです。
手続きの流れは、まず現在の墓地の管理者から「埋葬証明書」をもらい、新しい受け入れ先(霊園や寺院)に「受入証明書」を発行してもらいます。
この2つの書類をそろえて役所に申請すると、「改葬許可証」が交付されます。
・現在の墓地の所在地を管轄する市区町村役場
・遺骨を移す先が県外の場合も、手続きは元の自治体で行う
改葬許可証が発行されたら、石材店や霊園と日程を調整し、遺骨の取り出しと移送を進めます。
書類に不備があると再申請になることもあるため、申請前に内容をしっかり確認しておくと安心です。
墓じまいの遺骨が多数あった時

◇予算に合わせて、残す遺骨・残さない遺骨を分けます
先祖代々墓の墓じまいでは、両親や祖父母など、直接思い出のある故人の遺骨と、全く面識のない遠いご先祖様の遺骨を取り出すこともあるでしょう。
永代供養は基本的に、1柱ごとの料金形態なので、全ての遺骨を残す選択では、予算と見合わないケースが多いです。
形を残さない遺骨は合祀墓へ、残したい遺骨は納骨堂など、遺骨により永代供養の種類を分けても良いでしょう。
粉骨や部分供養で分ける方法
墓じまいで取り出した遺骨が多い場合は、「粉骨」や「部分供養」で分ける方法もあります。
粉骨とは、遺骨を細かく粉状にして小さな骨壺へ収める方法で、限られたスペースでも複数の遺骨を保管できるのが特徴です。
・骨壺を小さくでき、自宅や納骨堂に納めやすい
・複数の遺骨をまとめて保管できる
・費用を抑えて永代供養や散骨にも対応できる
また、親しい故人の一部だけを残して手元に置く「部分供養」も選ばれています。
残りの遺骨は合祀墓や樹木葬に納めることで、気持ちの整理と費用の両立ができます。
すべての遺骨を残さず、想いに合わせて柔軟に供養を選ぶことが、後悔しない墓じまいにつながります。
墓じまいで遺骨を残す選択

◇墓じまいで遺骨を残したい場合、納骨堂が人気です
墓じまいで取り出した遺骨を残したい場合に最も費用が安く収まる方法は、永代供養ではなく、自宅に遺骨を保管する「手元供養」でしょう。
一般的に墓じまいで取り出した遺骨を粉骨業者に託し、パウダー状に粉骨して小さな骨壺に収めた後、用意したステージ(祭壇)などに祀ります。
けれども手元供養は賛否が分かれるため、屋内で保管できる納骨堂が人気です。
墓じまいをご検討の方はこちらも参考にしてみてください。
——————————————————-
参考記事
「みんなが選んだ終活」
悩ましい「墓じまい」の問題…お寺・親族とのトラブルをどうすれば?
URL→https://www.eranda.jp/column/53801
——————————————————-
①一般墓(個別墓)
◇一般墓を建て、永代供養を付ける選択です
[費用目安]約150万円~300万円以上
墓じまいで取り出した遺骨を、新しいお墓に納骨するケースでは、夫婦両家のお墓をひとつにまとめた「両家墓」などの事例を見受けます。
| <一般墓(個別墓)のチェック項目> | |
| [永代供養] | ・永代供養の年数 (お墓が残る年数) ・契約中の更新はできるか |
| [その他] | ・年間使用料 |
永代供養が付いているだけで、基本的には一般墓と同じです。
そのため後々支払う年間使用料を確認しましょう。
またお墓が残る契約年数や、契約年数を終えた時に合祀される合祀墓も見学しておくと安心です。
宗旨宗派を問わない民間霊園では、霊園により規定は異なりますが、血の繋がりがない友人同士の遺骨をまとめる、兄弟姉妹の遺骨をまとめる事例もありました。
②集合墓
◇「集合墓」は個別スペースに遺骨を納める形式です
[費用目安]約50万円/1柱~
集合墓は屋外の納骨堂のように、ロッカー式などの個別スペースが提供されます。
墓石で作られた棚のような造りなどがあり、住まいではマンションに近いのではないでしょうか。
| <集合墓のチェック項目> | |
| [永代供養] | ・個別安置の年数 ・個別安置期間の延長はできるか ・年間使用料 |
| [その他] | ・収骨できる柱数 ・思い出の品を置いても良いか ・お彼岸時期の混雑具合 |
集合墓は縦横に他のご家族が利用するため、時期が許すならば、春と秋のお彼岸など、お墓参り時期の混雑具合を確認します。
墓前での個別法要も検討しているならば、可能かどうか確認をしてください。
③納骨堂
◇「納骨堂」は、遺骨を屋内スペースに保管する永代供養です
[費用目安]約30万円/1柱~
現代注目される納骨堂は、遺骨を個別の専用スペースに収めて供養します。
屋内施設で都心に近い立地が多いため、アクセスがしやすい、気軽にお参りができると注目されるようになりました。
| <納骨堂のチェック項目> | |
| [永代供養] | ・個別安置の年数 ・個別安置期間の延長、契約更新はできるか ・年間使用料 |
| [その他] | ・収骨できる柱数 ・思い出の品を置いても良いか |
| [お参りの規定] | ・お参りの仕方 ・お線香やろうそくの扱い ・供花の扱い ・会館時間 |
ニーズに合わせて納骨堂の種類も豊富になり、なかにはお墓と同等のメモリアルサービスが行き届いた施設も増えています。
遺骨の前でお参りができる施設もあれば、お参りは一律供養塔に向かって行う施設、個別のスペースに案内されてお参りができる施設もあるでしょう。
④手元供養
◇手元供養は、遺骨を自宅で保管するため永代供養ではありません
[費用目安]約5千円/1柱~(粉骨:約3万円/1柱~)
手元供養は墓じまいの遺骨を自宅で祀り保管する供養方法です。
そのため永代供養ではありませんが、近年では手元供養専用の仏壇仏具が販売され、ニーズが高まっています。
手元供養は契約の必要はなく、その都度カスタマイズができるでしょう。
| <手元供養の手順> | |
| ①墓じまいで遺骨の取り出し | |
| ②遺骨の手入れ | ・洗浄 ・乾燥 |
| ③遺骨の粉骨 | ・約3万円ほど~ |
| ④手元供養の準備 | [方法] ・アクセサリー ・ステージ(祭壇) ・仏壇 |
| ⑤遺骨を祀る | |
手元供養は配偶者の遺骨の扱いで選ばれることが多いです。
配偶者の遺骨を手元供養にした場合、自分が亡くなった後の遺骨の扱いにも配慮しなければなりません。
夫婦で入る樹木葬など、生前に永代供養の契約をして、自分の遺骨が納められる時に一緒に供養してもらう契約を決めるケースが多いです。
墓じまいで遺骨を残さない選択

◇合祀墓や樹木葬など、費用を抑えた永代供養が選ばれます
墓じまいで取り出した遺骨を残さない永代供養では、費用を抑えた選択が多いです。
また契約時のみの支払いで、後々の年間管理料が掛からない永代供養が好まれます。
墓じまいで遺骨を残さない場合でも、納骨後に手を合わせる墓標があるか、ないかも後々まで後悔しない選択のポイントです。
⑤合祀墓
◇合祀墓は、他の遺骨と一緒に合祀する永代供養です
[費用目安]約10万円~
合祀墓は霊園や墓地施設内にある供養塔などに、他の遺骨と一緒に合祀される最も安い永代供養のひとつと言えます。
合祀墓は墓じまい後に遺骨が残らず、合祀墓に納骨した後は遺骨の維持管理なども発生しないため、チェック項目もあまり多くはありません。
| <合祀墓のチェック項目> | |
| [永代供養] | ・納骨式はできるか |
| [その他] | ・納骨後のお参りはできるか ・お参りの規定を確認 |
故人や家族が特定の仏教宗派に信心深い場合、信仰する仏教宗派の総本山で利用できる「本山納骨」も検討すると良いでしょう。
本山納骨は総本山で行う合祀なので、菩提寺に相談します。
菩提寺の寺院墓地に建つお墓を、墓じまい後に遺骨を合祀墓に納骨する場合には、菩提寺内の合祀墓を選ぶ選択も、トラブルリスクが軽減しておすすめです。
⑥樹木葬
◇いずれ土に還るよう、樹木のふもとに埋葬されます
[費用目安]約5万円(合祀型)~200万円以上
樹木のふもとに埋葬され、土に還り自然に還元される樹木葬は、自然葬のひとつで永代供養ではありません。
けれども決められた区画内で美しく手入れされた草花や樹々のなか、小さな墓石が並ぶ「ガーデニング型樹木葬(公園型・庭園型)」は、永代供養に近いです。
| <樹木葬のチェック項目> ●樹木葬の種類を確認 |
|
| [墓地の立地] | ●里山型 ・自然深い環境 ●都市型(公園型) ・霊園内で提供 (アクセス環境が良い) |
| [埋葬方法] | ●個別埋葬型 [費用目安]約20万円~60万円以上 ・個別区画に埋葬 ●合祀型 [費用目安]約5万円~20万円以上 ・他の遺骨と一緒に埋葬 ●ガーデニング型 [費用目安]約30万円~190万円以上 ・墓石がある ・夫婦型、家族型もある ・ペットと入る区画もある ・永代供養墓に近い |
| [確認事項] | ・個別安置期間 ・お参りの仕方 |
樹木葬は遺骨を土に還すことを目的としているため、いずれにしても一度埋葬した遺骨は取り出すことができません。
けれども他の遺骨と一緒にひとつの場所に埋葬される「合祀型」では、個別の墓標がない一方、個別区画に埋葬される「個別埋葬型」では、暫く個別の墓標に向かってお参りができます。
⑦散骨
◇散骨とは、遺骨を自然に撒く自然葬です
[費用目安]約5万円(委託)~
墓じまいで取り出した遺骨を粉骨して、2mm以下のパウダー状にした後に海や山林、空などに撒いて自然に還す自然葬なので、永代供養ではありません。
遺骨が残らないばかりか、合祀墓のような供養塔や、樹木葬の墓標となる樹木もないため、遺骨がなくなる選択です。
●メモリアルサービスはあるか?
・墓碑に名前を彫刻
・メモリアルプレート
●散骨後はどうなる?
・お参りはできるのか
遺骨を郵送して散骨を依頼する「委託」を受け付ける散骨業者もあります。
ただ心残りが起きそうな時には、現地に赴き散骨する方法を選ぶと良いでしょう。
思い出のある故人の遺骨であれば、散骨後の思い出となるメモリアルサービスの内容や、定期的なお参りの可否も確認すると安心です。
散骨・樹木葬で後悔しないための注意点
墓じまい後に人気の「散骨」や「樹木葬」は、自然に還る供養として注目されています。
ただし、一度埋葬・散骨した遺骨は取り戻せないため、選ぶ前に内容をよく確認しておきましょう。
・永代供養の対象かどうかを確認する
・合祀型か個別型か、埋葬方法の違いを理解する
・家族や親族と十分に話し合っておく
・費用の内訳(粉骨代・埋葬料など)を事前にチェックする
特に、自然葬ではお参りの場所が限定されるため、のちに「供養の形が合わなかった」と感じる方もいます。
後悔を防ぐためには、家族全員が納得できる方法を選ぶことが大切です。
契約前に霊園を見学し、供養の流れや年間管理体制を確認しておくと安心でしょう。
墓じまいする遺骨の永代供養方法もチェック

◇永代供養後にお参りができるか?合同供養もチェックします
無縁仏にならないよう、定期的に合同供養は行う霊園や墓地が多いです。
ただ、それぞれ供養方法や頻度が違います。
墓じまい後に遺骨を永代供養した後も、お参りがしたい、合同供養に参加したい場合には、霊園や墓地が行う定期的な永代供養の頻度や規定もチェックすると良いでしょう。
| <供養方法を確認> | |
| [供養頻度の一例] | ・月一回 ・年一回 ・お彼岸やお盆など宗教行事に合わせて |
| [供養方法の一例] | ・参加者なし ・自由参加型 ・ネット配信型 |
| [お墓参りの規定] | ・お墓参りが可能か ・供花やお線香、お供え施設があるか ・個別の法要ができるか |
昔の墓じまいでは、遺骨も合葬墓に埋葬して終了とする事例が一般的でした。
けれども近年では、墓じまい後も丁寧な参拝や供養は続けたい家族が増えています。
「お墓の継承問題から墓じまいをしたものの、遺骨の供養は続けたい」との声も多くあります。
このニーズに合わせて施設側もさまざまなシステムで対応していますので、見学時には確認をしてみると良いでしょう。
墓じまいの決断前に行うこと

◇墓じまいにあたりトラブルの芽は摘みましょう
寺院墓地に建つお墓の墓じまいを決断したら、遺骨の永代供養先を決める前に、まず寺院墓地を管理するお寺「菩提寺」のご住職に相談します。
菩提寺の場合、墓じまいをすると寺院を支える檀家から離脱する「離檀」となる流れが多いため、菩提寺にとっては、あまり嬉しい知らせではないためです。
| <墓じまいの決断前に行うこと> | |
| ①菩提寺に相談 | [折衷案] ・菩提寺内の供養塔で合祀 ・外檀家を検討 |
| ②親族や身内に相談 | [相談例] ●お墓の現状を知ってもらう ・維持管理が難しい ・継承者の当てがない ●遺骨が残らない場合もある |
また家族や親族にも話をして理解を得てから進めましょう。
なかなか理解が得られない時には、墓じまいを決めた経緯、墓主としての問題を相談する形も一案です。
お墓の維持管理や継承者問題について、一緒に考えることで、自分事として考えてくれる家族親族が増えるでしょう。
・「檀家」とは?かかる費用や義務、檀家になる・やめるには?檀家にならず法要はできる?
まとめ:墓じまいの遺骨は、お参りの有無で決めます

墓じまいで取り出した遺骨は合祀墓による永代供養が一般的です。
けれども両親や祖父母など、思い出深い故人の遺骨もあるでしょう。
その場合にも、遺骨を残しながら継承者を必要としない永代供養はあります。
例えば納骨堂や集合墓の他、費用は掛かりますが一般墓に永代供養を付けることも可能です。
墓じまい後の遺骨は、家族がその後にどのような供養がしたいのか?頻繁にお参りがしたい、個別法要がしたい、何もしなくて良い、など、希望を確認して決めましょう。
お電話でも受け付けております














