
樹木葬が今人気の理由とは?シェア率が1位になった背景や実態は?向いている人や選び方

・樹木葬が今、人気の理由とは?
・樹木葬って本当に需要があるの?
・樹木葬の実態は?後悔していない?
・樹木葬に向いている人はどんな人?
・樹木葬で失敗しない選び方は?
新しく購入したお墓のシェア率が約40%を超える樹木葬ですが、人気の理由に首をかしげる人もいますよね。
お墓や納骨堂、永代供養墓とさまざまなご遺骨供養の選択肢が増えるなか、2018年頃から急成長を遂げています。
本記事を読むことで、樹木葬の人気の理由と実態をご紹介するとともに、さまざまなニーズや目的に合わせた樹木葬の種類や選び方の基礎知識、向いているおすすめの人々が分かります。
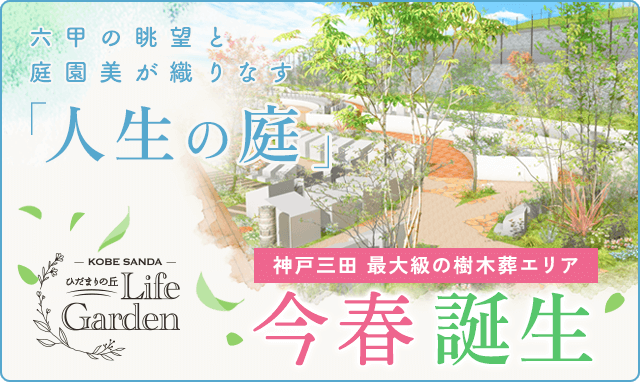
樹木葬が人気の理由

◇都市型樹木葬が登場し、お墓を建てない方法として注目されました
樹木葬はもともと自然を愛する人々の「亡くなったら自然に還りたい」と言うニーズに応えた「自然葬」のひとつとして登場した供養方法です。
ご遺骨は山林奥深くに埋葬され、樹木のふもとや、墓石の代わりに苗木を植樹したり、木の柱「木碑(もくひ)」などを墓標としてきました。
けれども樹木葬が広まるにつれ、墓石を持たない供養方法として注目されるようになります。
現代ではアクセス環境の良い霊園の敷地内で提供する、都市型樹木葬などが人気です。
①お墓の継承者問題の解消
◇樹木葬は継承者を必要としません
樹木葬でご遺骨はいずれ土に還る供養方法です。
一般墓のように代々継承者となる墓主が、お墓の維持管理をして守るものではありません。
現代の樹木葬のなかには、最終的に合祀墓に合祀される永代供養型もありますが、いずれにしても継承者を立てる必要がなくなります。
②維持管理の負担がなくなる
◇樹木葬は基本的に納骨するのみです
一般墓を建てると、定期的なお墓掃除をして環境を整えなければなりません。
墓主が高齢になるほどお墓掃除の負担は大きくなるうえ、遠方に住んでいるとお墓掃除のために帰省をする費用も掛かります。
また霊園では毎年年間管理料を支払ううえ、経年劣化が進むと修理修繕費や建て替えの可能性も出てくるため、経済的負担も懸念材料のひとつです。
樹木葬は納骨を済ませた後は、維持管理の負担がほとんどかかりません。
費用面でも基本的に、納骨時の初期費用で済む樹木葬プランがほとんどです。
③費用を安く抑える
◇樹木葬の費用目安は、約5万円~100万円/1柱ほどです
墓石を建てずに草花や樹木のふもとに埋葬される樹木葬は、一般墓と比べて費用が格段に安く収まります。
一般墓を建てる費用目安は約150万円~300万円/一基ほどとされますが、樹木葬の費用目安は約5万円~100万円/1柱ほどです。
ただし継承型の一般墓は一度建てると代々継承され、約6柱~12柱のご遺骨が納骨できます。
一方で樹木葬は個人単位のご遺骨供養なので、1柱ごとの費用システムです。
・樹木葬の費用や内訳はどれくらいかかる?費用は種類で違う?騙されない後悔しない選び方
④最終的に自然に還る
◇樹木葬でご遺骨は、ゆっくりと土に還ります
一般墓でご遺骨はお墓内部にあるスペース「カロート」に納骨されますが、樹木葬は一般的に、ご遺骨が土中に埋葬され、ゆっくりと時間を掛けながら、土へ還元される自然葬です。
骨袋や骨壺に入って埋葬される樹木葬も多いですが、綿や木など、土中で分解される素材に包まれて埋葬されます。
お墓を持たないばかりではなく、亡くなったら自然に還る意味を持つ遺骨供養の方法です。
⑤ペットと眠ることもできる
◇ペットと一緒に眠る樹木葬もあります
近年の樹木葬では人々のニーズに応え、ペットと一緒に眠る樹木葬も登場しました。
霊園内に特別区画を設けて、ペットと飼い主が一緒の区画で眠るプランです。
ペットと一緒に眠る樹木葬のなかでも、美しい草花や樹木に囲まれた庭園のなか、納骨スペースに納骨されるガーデニング型樹木葬タイプが注目されています。
ペットと一緒に眠る樹木葬では、最終的に合祀される仕組みが多いですが、「人と動物が一緒に埋葬されるなんて!」と考える人も多いため、合祀の際はペットはペット専用の、人は人専用の合祀墓に合祀されるプランが一般的です。
・【2024最新版】大阪でペットと一緒に入る樹木葬はどこが安い?13のおすすめ樹木葬
⑥一緒に眠る人を選べる
⑦美しい草花や樹木に囲まれる
◇美しい草花や樹木に囲まれて眠ることができます
都市型樹木葬を選ぶ人々のなかには「美しい草花や樹木に囲まれて眠りたい」と決めた人々も多いです。
霊園の特別区画に提供されるガーデニング樹木葬(庭園型樹木葬)を選ぶ人々に特に多い理由となり、よりお墓を持たない永代供養として選ばれるでしょう。
ただし自然葬として選ばれることの多い里山型樹木葬では、自然そのままの姿で埋葬されるため、秋冬には草木が枯れたり、雪山になることもありますので、目的に見合った樹木葬墓地を選ぶことが、後悔しないポイントです。
⑧墓標がある
◇樹木や草花など墓標があります
自然葬には海洋散骨などがありますが、散骨はご遺骨を撒くため墓標は残りません。
一方で樹木葬は自然葬でありながら、樹木や草花などの墓標に向かって参拝ができます。
また個別埋葬による樹木葬であれば、家族は個別区画に向かってお参りができるでしょう。
なかには埋葬した上に苗木を植える植樹型もあるため、個別の墓標を残す選択もできます。
この他、ガーデニング樹木葬(庭園型樹木葬)は、契約した一定期間は個別にご遺骨が安置され、墓碑に向かって参拝できる墓地も多いです。
⑨楽しくお参りができる
◇樹木や草花で囲まれた開放的な環境で参拝ができます
樹木葬墓地によって、さまざまな環境下で楽しくお参りできる点も人気の理由です。
公園型の樹木葬墓地では、敷地内に広い芝生広場を設けて、レジャーシートを広げてピクニックが楽しめるものもあります。
人気の桜の木のふもとに埋葬する樹木葬「桜葬」では、毎年桜の開花時期になると、花見をする気分で参拝する家族も多いです。
また里山型樹木葬では、自然を愛した故人を偲び、登山やハイキングを楽しみながら参拝をする様子も見受けます。
⑩宗旨宗派を問わない
◇樹木葬は基本的に宗旨宗派にこだわりません
人が亡くなったら自然に還る自然葬は、新しい供養の形・考え方に基づくため、基本的に宗旨宗派を問わない遺骨供養の方法です。
もともと宗旨宗派を問わない民間霊園はもちろん、寺院墓地で提供する場合でも、樹木葬においては宗旨宗派を問わない寺院が多いでしょう。
ただし、なかには檀家に入ることを条件とする寺院もあるため、契約前に確認は済ませておくことをおすすめします。
⑪維持管理費がかからない
◇樹木葬は基本的に、初期費用のみです
樹木葬は墓石を建てないため、納骨後に修理修繕や建て替えなどの懸念がありません。
またご遺骨が土に還る樹木葬は、基本的に納骨後に年間管理料もないでしょう。
初期費用のみでご遺骨供養ができるため、後々の支払いが必要なくなります。
ただし個別安置期間を設けた樹木葬プランの場合、個別安置期間は年間管理料を支払うものもあるので、契約前に確認をすると安心です。
⑫墓石を建てる必要がない
◇樹木葬は墓石を建てる負担がありません
樹木葬の墓標は樹木や草木となるため、契約をしたらいつでもご遺骨が埋葬できます。
生前契約をした場合、火葬場で埋葬許可証が発行されたら、四十九日前でも納骨はできるでしょう。
また一般墓は墓石代がかかりますが、樹木葬は墓石が伴わないため、各段に安く費用が抑えられる点も魅力です。
⑬樹木葬の種類が多様になった
樹木葬人気の実態や社会的背景は?

◇2022年の調査で、樹木葬が主流になりました
2022年1月に鎌倉新書により実施された「第13回 お墓の消費者全国実態調査」で、新しく購入したお墓のうち、樹木葬が41.5%を占めました。
2018年度は46.7%だった一般墓を抑えて、お墓のシェア率1位になっています。
2018年の樹木葬のシェア率は24.9%に留まっていましたが、2020年に樹木葬がトップになって以降、3年連続で樹木葬が主流です。
一方、樹木葬で後悔した人々の割合は、樹木葬が認知されるにつれ年々減少しています。
2016年には樹木葬で後悔したと答えた人々が全体の88.9%だった結果に対し、2021年度は20%となりました。
・鎌倉新書「第13回 お墓の消費者全国実態調査」
・全国石製品共同組合2022年「お墓を建てた後に後悔した事のアンケート調査」
・樹木葬で後悔しやすいこととは?土には還らないの?事例から欠点や注意点、対策を紹介!
①暮らしのグローバル化
◇遠方に暮らす子ども世代が増えました
先祖代々墓や家墓が残された時代は、継承者となる子ども世代が成人しても、同じ集落や地域で暮らしてきましたが、現代はより快適な環境や仕事を求めて、全国・世界へ移住する若い世代が増えています。
お墓はその土地に根付くものなので、遠方に暮らすことでお墓の維持管理は困難になったことも、継承問題が深刻化した一因です。
ひとつの集落に若い世代がお墓を守るためだけに残る時代ではなく、お墓を継承する風習自体が時代に合わなくなりました。
②時代に合わないお墓継承
◇お墓を継いでも負担しかない現状
長兄がお墓とともに家の全ての家督(財産)を継ぐ「家督制度」も、現代はありません。
現代の相続制度において、お墓や仏壇などの祭祀財産を継承しても相続税はかかりませんが、継承したからと言って、遺産分割の割合が増える訳でもありません。
けれどもお墓を継承することで、お墓の維持管理に経済的負担がかかります。
また菩提寺のご住職とのお付き合いや、お墓の定期的な掃除など、精神的・肉体的な負担もかかることが、継承者問題を深刻化しています。
③核家族化
◇核家族化により墓主の負担が大きくなりました
かつては同居による大家族も多く、親族もひとつの集落内に住んでいることで、墓主ひとりにお墓の維持管理への負担が集中する問題を避けることもできました。
親族が交代でお墓掃除をしたり、維持管理費を出し合う他、菩提寺のご住職とのお付き合いは高齢者が担うこともあったでしょう。
けれども核家族化が進み、親族とのお付き合いも希薄化するなかで、墓主ひとりにお墓の維持管理への負担が集中するようになっています。
④全国的な無縁墓の深刻化
◇全国的に無縁墓が問題になっています
墓主が亡くなった時に継承者不在のまま放置され、責任者が分からず放置されたままの無縁墓が増えたことで、全国的に無縁墓が問題視されるようになりました。
無縁墓になると自治体や墓地管理者がお墓を撤去しますが、無縁墓があまりに増え、充分な撤去費用を充てることができずに、無造作に放置されたままの無縁墓も多数あります。
このような事態を避けるため、元気なうちに墓じまいをする墓主が増えました。
また生前に樹木葬や永代供養など、無縁仏にならない契約を進める高齢者が増えています。
⑤少子高齢化
◇少子高齢化は継承問題に大きく影響しています
「お墓を建てても任せられる子どもや孫がいない」「継承者のあてがない」「お墓を残してもお参りする家族はいない」と、樹木葬を選ぶ人々も増えました。
厚生労働省が発表したデータによると1989年に125万人だった出生数が、2019年には87万人にも落ち込んでいます。
少子高齢化が進むにつれ、将来的な無縁墓への心配や、継承者となる子どもや孫への負担が集中することへの不安から、お墓のない樹木葬が注目されるようになりました。
・厚生労働省「図表1-1-7 出生数、合計特殊出生率の推移」
⑥家から個人へ意識の変化
樹木葬墓地で違う、人気の理由

◇樹木葬には3つのタイプがあります
樹木葬は立地環境で違う3つのタイプがあり、それぞれに人気の理由が異なるため、選ぶ時にはどのタイプを求めているかを家族で話し合うと良いでしょう。
自然回帰を優先事項としているならば、自然奥深くの立地環境が好まれますし、草花に囲まれた美しい環境で、快適なお墓参りがしたいならば、霊園・墓地内に設けられた樹木葬が適切です。
①公園タイプ
◇霊園・墓地内の区画に、公園のような環境を整えた樹木葬です
霊園や墓地内を公園のように整備し、芝生や花木を植えて整備された樹木葬が公園タイプとなります。
墓標としてシンボルツリーが1本植えられた墓地もあれば、区画を分けた樹木葬もあるなど、埋葬の種類は霊園・墓地によってさまざまです。
一般公開している墓地・霊園もあり、公園にピクニックに行く気分でお墓参りができるなど、明るい供養が魅力のタイプとなります。
②庭園タイプ
◇イングリッシュガーデンのような庭園風に整えられた樹木葬です
寺院の境内や霊園の特別区画に整備された庭園内の樹木葬です。
公園型よりもより、美しい草花で庭園風に整備された環境が多く、墓標はシンボルツリーのふもとに複数埋葬される種類が多いでしょう。
コンパクトな墓石を持つガーデニング樹木葬も、この庭園タイプが主流です。
③里山タイプ
樹木葬墓地には種類がある

◇樹木葬墓地には都市型と里山型の2種類があります
ゆっくりと長い時間をかけて土に還元される樹木葬は自然葬のひとつとなるため、一般的には自然深い山深くで、大樹のふもとに埋葬されるイメージが強いです。
けれども樹木葬のニーズには、費用を抑えた供養がしたい、継承者がいらないお墓のない供養がしたいなど、自然回帰だけではありません。
そのため樹木葬墓地は自然奥深い山林だけではなく、霊園などでも提供しています。
①都市型の樹木葬墓地
◇主に霊園の敷地内で提供する樹木葬墓地です
都市型の樹木葬墓地は「霊園型樹木葬墓地」とも呼ばれます。
樹木葬は墓石を建てないため、小さいスペースでも提供できることから、都市型の樹木葬墓地の多くは、敷地内に特別区画を設けて提供する霊園が多いでしょう。
大きな大樹のふもとに他のご遺骨と一緒に埋葬される合祀型もありますが、都市型樹木葬墓地では、ご遺骨ひと柱につき、ひとつの区画を提供する個別埋葬型が多い傾向です。
一年中整備された霊園内にあるため、里山型樹木葬と比較してアクセス環境が良く、手軽にお参りができます。
②里山型の樹木葬墓地
樹木葬の埋葬方法には種類がある

◇樹木葬には大まかに3つの埋葬方法があります
樹木葬はいずれ土に還ることを目的とするため、一度埋葬すると再び取り出すことが難しいプランが一般的です。
そのため合祀墓と同じように、骨壺や骨袋から出して、他のご遺骨と一緒に合祀されるイメージがありますが、この他にもいくつかの埋葬方法があります。
樹木葬での埋葬後に、個別の墓標に向かってお参りがしたいかなど、後々の供養まで想定して希望に適した埋葬方法を選びましょう。
①個別型の樹木葬
◇個別型では、個別の区画を購入し埋葬します
個別型の樹木葬では、大きなシンボルツリーとなる大樹のふもとに、個別区画が設けられたタイプです。
また、個別区画にご遺骨を埋葬した後、苗木を植樹する植樹タイプもあるでしょう。
故人が埋葬された区画がはっきりと分かるため、埋葬後も個別区画に向かって参拝ができる点がメリットです。
ただし契約時に個別区画に埋葬される期間が定められている霊園や墓地もあります。
この場合は一定期間が過ぎると、合祀埋葬となるでしょう。
②集合型の樹木葬
◇集合型では、骨壺や骨袋に入った状態で埋葬されます
集合型の樹木葬では、申し込んだご遺骨は全て同じスペースに埋葬され、個別区画は提供されません。
けれども土に分解される材質の木材や綿などの自然素材で作られた骨壺や骨袋に、ご遺骨を収めて埋葬されるため、埋葬の時はご遺骨が分かれます。
ただし長い時間をかけてゆっくりとご遺骨が分解され、土に還る過程では、一緒に埋葬された他のご遺骨と一緒になっていくことは否めません。
③合祀型の樹木葬
◇合祀型では、骨壺や骨袋から出して合祀されます
合祀型の樹木葬は、シンボルツリーのふもとでご遺骨を骨壺や骨袋から取り出し、他のご遺骨と一緒に合祀埋葬される仕組みです。
そのため最初から他のご遺骨と一緒になってしまうデメリットはありますが、その分、樹木葬のなかでも、最も安い樹木葬の埋葬方法です。
里山型樹木葬では、ご遺骨を埋葬した場所が分からなくなるケースもあるため、人工的なプレートなどで埋葬場所に印を設ける樹木葬墓地もあります。
樹木葬に向いている人

◇自然に還りたい、継承者がいない人に向いています
お墓のないご遺骨の供養方法は、樹木葬の他にも合祀墓などの永代供養墓や納骨堂など、さまざまです。
けれども樹木葬は自然葬の一種として、継承者を必要としない永代供養の要素を持ちながらも、ご遺骨が自然に還る特徴があります。
一方で自然葬にも海洋散骨や空葬など、さまざまな供養方法がありますが、樹木葬は唯一、樹木というハッキリとした参拝対象を持つ自然葬です。
①継承問題を解消したい
樹木葬は一度埋葬されると、後々の管理や継承を必要としません。
そのため、子や孫など後の世代に負担をかけたくない人に向いています。
・お墓のことで面倒をかけたくない
・継承者がいない
樹木葬は継承者を必要とせず、安価で自分だけの墓標を持つことが可能です。
一度埋葬するとご遺骨の供養や管理は墓地管理者が担ってくれるため、子どもたちへの負担を軽減したい人々の終活で選ばれています。
②自然に還りたい
近年は自然回帰志向が広がりつつあります。
「自分亡き後、自然に還りたい」との願いに対応する供養方法が、樹木葬です。
一般的なお墓は墓地として分けられ、怖い・暗いイメージを持つ人もいるでしょう。
「暗いお墓に入りたくない」と考える人にも最適です。
③費用を抑えたい
◇墓石を必要としない樹木葬は、費用を抑えたい人に最適です
合祀埋葬の樹木葬であれば、埋葬後の費用も一切かかることなく、埋葬料のみでご遺骨を供養できます。
夫婦や家族、ペットと一緒に入る樹木葬、長い個別安置期間を設けた樹木葬などは、一般墓を建てるよりも高い費用になることもあります。
樹木葬に向いていない人

◇従来の供養方法にこだわりがある人には向いていません
先祖代々継承してきたお墓、供養の慣習が根強く残る家系もあるでしょう。
お墓の継承を代々行い、後世まで守ってもらいたい場合、樹木葬は継承する形式の供養方法ではないので、その要望に対応できないためです。
| <樹木葬に向いていない人> | |
| [お墓を代々継承したい] | ・お墓を継承したい ・一般墓に埋葬したい ・親族の同意を得にくい |
| [お墓のデザインにこだわり] | ・デザイン墓に埋葬されたい |
ガーデニング樹木葬など、コンパクトな墓石が墓標として付くプランもありますが、目的は樹木葬なので、墓石の形はワンプレート型のシンプルなものが多いでしょう。
まとめ:樹木葬人気の理由には選択肢の多さもあります

樹木葬は美しい草花や樹木を墓標とした、墓石を持たないご遺骨の供養方法です。
もともとは「亡くなったら土に還りたい」と希望する方々に指示された、自然葬のひとつでしたが、現在ではお墓を持たない供養を目的として選ぶ方も増えました。
そのため樹木葬のなかでも特別区画にイングリッシュガーデンのような美しい草花で整えられた庭園を造り、そのなかで永代供養を行う「ガーデニング樹木葬」も登場し、多くの方々に選ばれています。
樹木葬を選ぶならば、費用を抑えたい、継承者のいらない供養がしたい、自然に還りたいなど、目的を明確にして優先順位を設け、複数の候補から選ぶことで、後々まで後悔しない樹木葬プランを選ぶことができるでしょう。
お電話でも受け付けております
















