
【死産とは】死産と流産の違いとは。いつから死産か…、処置や火葬まで分かりやすく解説
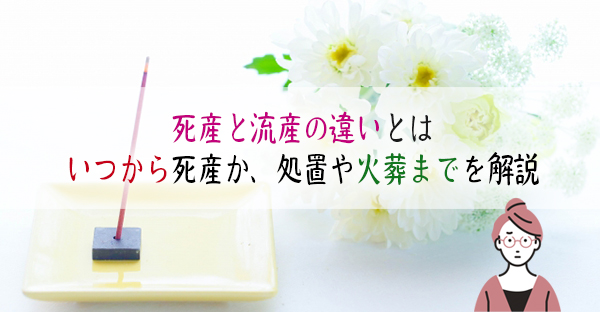
「死産」とは、法的に妊娠4か月目(12週)以降に胎内の赤ちゃんが亡くなることです。
医学的にはお母さんの胎外で生存できる時期(妊娠22週以降)の子が亡くなったことを差します。
担当医に死産と宣告された後、母体や赤ちゃんの処置はどうなるのか…、赤ちゃんの体はどのように扱われるのか…、不安も募りますよね。
・死産した赤ちゃんはどうなるの?
・赤ちゃんを死産で亡くした時の供養は?
死産であっても体を備えて産まれ出た赤ちゃんの命は、成人と同じように扱われます。
今回は死産とはなにか?流産との違いやいつから死産とされるのか…、死産の赤ちゃんを供養する流れを火葬まで解説します。

死産とは?いつから?

●死産は医学的には妊娠6ヶ月(22週)以降に赤ちゃんが亡くなったことを差し、法的には妊娠4ヶ月(12週)以降を差します
また出産してから間もなく赤ちゃんが亡くなることも「死産」です。
いずれにしても法的には妊娠4ヶ月(12週)以降に赤ちゃんが亡くなったことを「死産」とするため、「死産届」を行政へ提出しなければなりません。
[1]産婦人科学会(医学の定義)
・妊娠4ヶ月(12週)未満…初期流産
・妊娠6ヶ月(22週)未満…後期流産
・妊娠6ヶ月(22週)以降…死産
[2]法律の定義
・妊娠4ヶ月(12週)未満…流産
・妊娠4ヶ月(12週)以降…死産
妊娠4ヶ月(12週)以降にお腹の赤ちゃんが亡くなった場合、法的に死産とされるため、「死産届」を提出して火葬を行います。
●担当医から「死産証書」が渡されるので、これを役所へ提出してください
(死産証書と一枚ですので、隣側が「死産届」です。)
死産届の提出は死産の日から7日以内、お母さんは哀しみの真っただ中にいますが、届出をしないと罰則(過料)が請求されてしまうので、辛い時は代理を依頼しても良いでしょう。
※医師が発行する「死産証書」ですが、状況によって「死胎検案書」になることもありますが、いずれも同じです。
妊娠4ヶ月(12週)以降の中絶は?
死産で提出する、死産届と死亡届の違いは?

●死産届は戸籍が残らず、死亡届は戸籍として残ります
法的に妊娠4ヶ月(12週)以降で亡くなった赤ちゃんが、死産届を出さなければならないのは、火葬をするからです。
火葬には死産届を提出した時に返される「死胎火葬許可証」を火葬場に出さなければなりません。
一方「死亡届」を提出すると、戸籍を作った後で除籍の手続きを行います。
[1]死産届
・戸籍は作られない
[2]死亡届
・戸籍が作られる
・出生後、すぐに亡くなった
ですから赤ちゃんを出産して間もなく亡くなったケースでは、一度産まれた命として戸籍を作る「死亡届」を提出します。
死産届には性別を記入する欄がありますが、男女の性別が分かっている人は記入し、分からなければそのままで問題はありません。
死産届の提出
●死産届はお母さん以外の代理人でも提出できます
お母さんは死産後の処置で短くて1泊2日、長くて1週間ほど入院することもあります。
また赤ちゃんを失った哀しみや、体の負担も大きいでしょう。
代理で提出できる人は、厚生省令第42号第9条によると下記の人々です。
●亡くなった赤ちゃんから見て…
・両親
・同居親族(祖父母など)
・立ち会った医師
・立ち会った助産師
・その他、立会人
一般的には亡くなった赤ちゃんの父親が死産届を出すでしょう。
家族以外でも代理は可能ではあるものの、もしも書き間違えがあれば印鑑で訂正するなど、不具合も生じます。
・死産届
・死産証書(医師より発行)
・届出人の身分証明書
・届出人の印鑑
・死胎火葬許可申請書
死産届は大まかに、赤ちゃんの両親の情報(生年月日/本籍地/年齢/仕事/母親の住所など)を記入する他、死産を迎えた産院(死産の場所)、赤ちゃんの性別などを書きます。
少し辛い作業ですので、周囲の人々がサポートをしながら進めましょう。
死産の宣告後、病院では?

●死産では、お腹のなかの赤ちゃんを出産して子宮を綺麗にします
…出産後は一般的に3日~10日間の入院があるでしょう
流産の場合、手術によって子宮内の赤ちゃんを出してあげて、子宮の胎盤などを出しますが、死産では亡くなった赤ちゃんを出産する処置が取られます。
出産を促す措置が取られますが、通常の出産と同じ流れで行い、緊急時には帝王切開の可能性もあるでしょう。
・出産後赤ちゃんは、通常と同じように扱われます
・お母さんは病室へ戻り、数日間の入院です
…病院側も最大限の配慮をしますが、周囲は無事に出産を終えたお母さんばかりです。
羨ましく思えてしまったりと、哀しみや喪失感、罪悪感にも苛まれます。
●赤ちゃんを出産したその日、乳房の張りを抑える薬を内服した時、初めて涙が溢れました
お母さんの様子を見ながらお医者様と相談し、早めに自宅へ帰り、静養するのもひとつの方法です。
死産を経て、赤ちゃんと触れ合う体験談
●死産を経て安置されている間、病院へ相談して赤ちゃんと触れ合った体験談もあります
「病院から提案されないから…」「夫や家族に引かれそう」と遠慮をしていると、後々まで後悔や哀しみを引きずるお母さんも少なくありません。
けれども思い切って病院へ相談することで、赤ちゃんと触れ合う時間ができたお母さんは多いです。
●出産の時
・赤ちゃんを抱かせてもらう
・赤ちゃんに話しかける
・添い寝する
・お乳をあげる
●出産後
・赤ちゃんの手形・足形を取る
・赤ちゃんのへその緒など、記念品をもらう
・赤ちゃんの出生体重などを記録してもらう
・赤ちゃんを産湯に浸ける
・赤ちゃんのおむつ替え
●その他
・赤ちゃんと家族の時間をもらう
・赤ちゃんとの記念撮影
死産はその時以上に、後々ゆっくりと哀しみが襲うこともありますが、それも必要な時にお母さんが求めていることを行い、ひとつひとつを納得できることで軽減されます。
☆今では病院側が提案してくれることも増えましたが、興味があればぜひ、勇気を出して相談をしてください
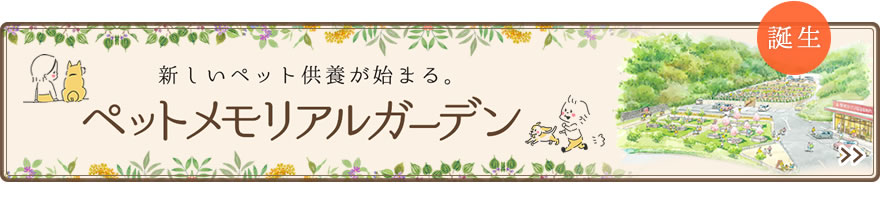
死産の赤ちゃんを自宅で安置する場合

●妊娠7ヶ月(24週)以降で死産をした赤ちゃんは、24時間経過した後の火葬です
妊娠7ヶ月(24週)以降の赤ちゃんの死産は、成人した人の法律と同じく、24時間経過しないと火葬できません。
反対に言えば、妊娠7ヶ月(24週)未満の赤ちゃんは24時間を待たずして、火葬・埋葬できます。(いずれにしても死胎火葬許可証は必要です。)
●ドライアイスが必要です
…葬儀社スタッフがドライアイス(5千円~1万円/1日)を用意してくれるでしょう。
タオルなどを挟んだ後、お腹部分と背中部分に挟むようにドライアイスを付けて冷やしてあげます。
…ただドライアイスは小さいからだに「冷たくて可哀そう」と感じるお母さんも多いです。
季節や火葬までの日数など考慮し、葬儀社スタッフとも相談しながら判断をしてください。
死産の赤ちゃんを火葬

●死産の赤ちゃんは小さく、体にぴったりの遺骨や骨壺が無い場合も多いです
一般的に死産では、葬儀社に依頼することが多いため、葬儀社スタッフが赤ちゃんの火葬に必要な棺や骨壺を用意してくれるでしょう。
けれども赤ちゃんは小さいため、ぴったりの棺や骨壺がない場合もあります。
・棺や骨壺のサイズを確認
(葬儀社、病院など)
小さい死産の赤ちゃんを火葬する際、最近では手元供養で扱う小さな骨壺を、自分達で準備する夫婦もいます。
手元供養で扱う骨壺なので、見た目にも愛らしいものが多く癒されるとの声も多いです。
火葬場での服装マナー
●昔は通夜などで着用した「平服」が多いです
死産による赤ちゃんの火葬は、家族やごく近しい親族・知人のみで執り行うことが多く、集まる人々の服装も、「平服」の服装マナーで参加することが多いでしょう。
赤ちゃんのご両親ではない一般の人が、死産の赤ちゃんの火葬に参加する場合、むしろ喪服だとご両親よりも「格が上がってしまい」浮く可能性があるので、気になる場合は確認します。
●平服の目安
①男性
・ダークグレー、濃紺などのスーツ(無地)
・白いYシャツ、グレーなどのネクタイ
・光沢のない革靴
・小物や腕時計などは避ける
②女性
・グレーや濃紺などのアンサンブルやワンピースなど
・スカート丈はひざ下
・パンツスーツでも良い(光沢なし)
・フラットなパンプスや革靴
・パール一連のネックレスなどに留める
…などなどです。
平服はグレースーツなど地味な色目であれば良いですが、アクセサリーの着用や光沢のある化粧など、派手なものは避けます。
死産の赤ちゃんの火葬
最後に
以上が死産とはなにか?
法律の見解、医学的な見解、それぞれから見た死産の定義と、死産と宣告されてからの病院での処置や、火葬までの流れです。
法律ではお母さんの胎内から産まれ出た赤ちゃんは、ひとりの人として扱われます
そのため死産届を出して火葬をする、大人と同じ一連のセレモニーがあるでしょう。
けれどもその後、遺骨を先祖代々墓に埋葬できるかと言えば、そうはいかない親族トラブルもしばしば聞きます。
死産した赤ちゃんは樹木葬・合祀墓・手元供養・納骨堂など、お墓を持たない供養も少なくありませんが、いずれも納骨後にお参りもでき、法要もできるでしょう。
・水子供養とは?いつまでにするといい?赤ちゃんの遺骨はどうする?12の方法と体験談
まとめ
死産とは。死産届と火葬までの流れ
●死産とはいつから?
・医学の定義…妊娠6ヶ月(22週)以降
・法律の定義…妊娠4ヶ月(12週)以降
●死産届と死亡届
・死産届…戸籍は作られない
・死亡届…戸籍が作られる
●出産と入院
・出産後赤ちゃんは、通常と同じように扱われる
・お母さんは病室へ戻り、数日間の入院
・赤ちゃんと触れ合うお母さんも多い
●安置~火葬
・自宅安置はドライアイスを使用
・赤ちゃんに合う棺、骨壺を確認
・手元供養で扱う骨壺も選ばれる
・火葬では遺骨がなくなることもある
・火葬場には胎児専用火葬炉を備えた施設もある
・胎児専用火葬炉は費用が割高傾向
・火葬は平服での参加が一般的
お電話でも受け付けております

















