
【樹木葬の体験談②】離婚した父、長男は「一緒のお墓に入りたくない」親族からは猛反対

56歳の中田晃子さん(仮名)は父親の納骨にあたり、樹木葬を選びました。
けれども父親は生前に、郷里の菩提寺に建つ先祖代々墓の建て替えを検討し、古いお墓を撤去して更地にしています。
<中田晃子さん(仮名)>
・プロフィール:女性/既婚
・子ども:なし
・兄弟:兄1人
・お墓に入る人:父親(78歳)
今回は、なぜ菩提寺に墓地が残っている父親の樹木葬を選択したのか…、中田晃子さんの体験談をご紹介します。
父親が生前に墓地を用意

●父親は古くなった先祖代々墓の建て替えを検討し、墓地を更地にしていました
取り出した遺骨は菩提寺の納骨堂に預けたまま「これから新しくお墓が建つ!」と言う時に、病気が発覚し、闘病の末に亡くなります。
そのため親族は墓地に新しくお墓を建て、そこに父親を納骨するものだと思っていました。
けれども晃子さんが樹木葬を検討し始めた背景には、父親の離婚があります。
●20年前に父親の事情により、晃子さんご兄弟の母親との離婚が成立しました。
そこで、父親の告別式で晃子さんの兄より、下記のような話があります。
・父親と同じお墓に入る気はない
・新しくお墓を建てても、墓主になるつもりはない
・母親は実家のお墓に入る
父親の離婚後、兄は母親と二人暮らしでした。
そのため兄は、両親の離婚後、父親とはあまり良い関係を築いていません。
このことも、今回の兄の意見に影響しているのでしょう。
母親の実家の先祖代々墓
●母親の実家は娘ばかりで、それぞれ他家に嫁いでいたため先祖代々墓の継承者がありませんでした
そこで昔から、母親の実家の先祖代々墓は墓じまいをするつもりでいましたが、母の離婚により、母がお墓を継承しています。
・母親は実家の先祖代々墓に入る
・独身の兄は、母方の先祖代々墓を継承したい
・兄は、母方の先祖代々墓に入りたい
一方で晃子さんは他家に嫁いでおり、子どももいません。
父親が残した墓地で父方の先祖代々墓を新しく建てても、そのお墓を維持管理する墓主がいないことになります。
●告別式では墓主について親族にも相談しましたが、それぞれすでにお墓を建てていたり、継承すべきお墓があり、継承者の検討が付かず仕舞いでした。

お墓を建てても、墓じまいが必要

●現在56歳の晃子さんが新しく先祖代々墓を建てても、将来的に墓じまいが必要です
晃子さん自身は他家に嫁いでいますが、一度は晃子さん自身が墓主として継承することも検討しました。
晃子さんのパートナーは長男で先祖代々墓を継承していましたが、「両家墓」を建てることで、夫婦の先祖代々墓を維持管理できるとも考えましたが、問題は後々の継承者です。
・子どもがいない(継承者がいない)
・あと4年で60歳、シニア層になる
・パートナー方の先祖代々墓も墓じまいを検討している
晃子さんはあと4年で60歳、パートナーも61歳で、すでにシニア層に突入している今、継承者の目途が立たないまま新しくお墓を建てても、10年・20年のうちには、墓じまいの必要性が出てくるでしょう。
建墓費用を出し合えない
●兄弟や親族間で、建墓費用を出し合うことが期待できません
墓地があるとはいえ、立派なお墓を建てようと思うと、約100万円~300万円ほどの建墓費用は掛かります。
けれども兄との確執を残したまま父親が亡くなった今、兄が父親のお墓を建てるにあたり、協力して建墓費用の準備はできないでしょう。
・父親と兄の確執により建墓費用の協力が期待できない
・新しくお墓を建てても、維持管理費用が掛かる
・後々墓じまいをする時も、費用が掛かる
…以上のことから、父親の兄弟である伯父や伯母からは「せっかく菩提寺に墓地があるのに!」と言われたものの、晃子さんご夫婦だけで、新しいお墓の建墓費用や後々の墓じまい費用を負担することは、負担が大きいと判断しました。
●「菩提寺(ぼだいじ)」とは、先祖代々から家で信仰する寺院を差し、寺院墓地に先祖代々墓が建っている場合は、その寺院墓地が菩提寺です。
・【大阪の墓じまい】離檀料の金額相場はいくら?墓じまいで菩提寺との離檀料トラブルとは
樹木葬を決断

●建墓費用と比較して樹木葬は安価で、しかも継承者を必要としません
晃子さんは告別式で兄や親族の意向を聞き、「樹木葬が適切では?」と考えます。
…と言うのも子どもがいない晃子さんにとって、最も気になる点は継承者です。
この点、樹木葬では永代供養が付いているため、継承者の必要がありません。
①永代供養が付いている
・継承者が必要ない
・無縁仏にならない
②価格が安い
③お墓参りができる
晃子さんが選んだ樹木葬では、名前こそ自然葬のひとつ「樹木葬」でしたが、埋葬されたまま土に還る仕組みではなく、一定年数経ってから合祀墓に合祀埋葬されます。
けれどもいずれも建墓費用と比較して安い価格で父親の遺骨を納骨でき、そのうえでお参りもできる樹木葬は、晃子さんにとってベストとも言える選択でした。
お墓参りができる「永代供養」とは
●霊園などの墓地管理者が、家族に代わり永代に渡って遺骨の維持管理、供養を行います
そのため永代供養が付加された葬送を選ぶと、継承者の必要がありません。
特に晃子さんが選んだ樹木葬の場合は、納骨後の年間管理料などのランニングコストもないため、最初の支払いで全てが終わります。
・継承者(墓主)の必要がない
・契約後のランニングコスト(年間管理料など)がない
・無縁仏になる心配がない
ただし契約後のランニングコスト(年間管理賞)が掛かるか掛からないかは、永代供養が付いていても、施設やサービスによって違いがあるでしょう。
例えば納骨堂にも永代供養は付いていますが、お墓として利用することも多い更新制の納骨堂では、年間管理料が発生する施設も多いです。
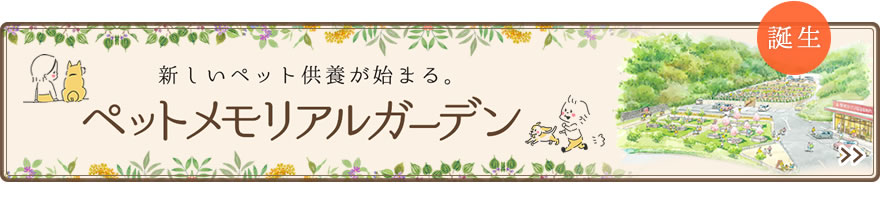
親族の反対、菩提寺への報告

●親族の反対により、晃子さんは「縁を切る」とも言われました
けれども父親が産まれる以前から続いてきた、先祖代々墓の墓じまいは、親族から大変な反発を受けました。
実際に父親も経年劣化によりボロボロになったお墓を建て替えるにあたり、墓じまいも検討しましたが、親族の反対によりお墓の建て替えに切り替えた経緯があります。
そこで晃子さんは、親族の話し合いにおいて、下記のような準備をしました。
●親族へ先祖代々墓を守るにあたり、現実的な数字を見てもらいます。
・建墓費用の見積もり
・建墓後の年間管理料(お布施)、維持管理費
・樹木葬の見積もり
・家系図を準備
このうえで「縁を切る!」と猛反対していた親族へ向け、父方の先祖代々墓を残すのであれば、下記の点を明瞭に決めるよう、求めました。
・誰が建墓費用を出すのか
・年間管理料(お布施)や維持管理費は誰が出すのか
・将来、お墓の継承者は誰がなるのか
このような具体的な問題点を親族に確認したところ、反対していた親族も現実的な側面を確認でき、墓じまいの反対を取り下げました。
納骨堂に預けていた遺骨
●先祖代々墓から取り出した遺骨は、菩提寺の合祀墓に合祀埋葬されました
父親がお墓の建て替えをするにあたり、先祖代々墓から取り出した遺骨は、菩提寺の納骨堂に預けていましたが、墓じまいの決断により、行き場を失ってしまいます。
また菩提寺としては晃子さん一家が、墓じまいを行うことにより、檀家(だんか)がひとつ無くなってしまうため、あまり良い決断ではないでしょう。
●そこで晃子さんは、菩提寺に預けていた納骨堂の遺骨を、菩提寺の合祀墓に合祀埋葬しました。
(遺骨6柱を合祀、15万円/1柱×6柱=90万円)
けれども樹木葬は菩提寺になく、また晃子さんとしてはより身近に葬送したい想いがあったため、自宅近くの民間霊園の樹木葬にしています。
※「檀家(だんか)」とは、先祖代々で菩提寺を信仰する家です。
樹木葬を契約、納骨式
最後に
以上が定年退職間際に両親が離婚し、長男である兄と確執があった、父親の樹木葬を決断した、中田晃子さんの体験談です。
遺骨が残らない点が懸念点ではありましたが、契約した樹木葬の霊園では、埋葬された人々の名前が石碑に彫刻され、合同ではありますが定期的に供養が行われます。
また三回忌、七回忌と、樹木葬を前に読経供養も可能で、個別の法要スペースも借りることができるため、「埋葬後の供養は、思ったよりもお墓の時と変わらなかった」と言うのが晃子さんの感想です。
また一方で簡略化した法要も可能になり、(兄が行わないため)「施主として法要を行う負担も軽減された」と感じています。
・【自然葬の種類】自然葬の種類と特徴。個別の墓標を残す自然葬もあるの?|永代供養ナビ
まとめ
離婚した父親の樹木葬を決断
●樹木葬を決断した理由
・父親が離婚し兄と確執があった
・父親は墓地を用意していた
・兄は継承する意思がない(継承者がいない)
・建墓費用が掛かる(協力者がいない)
・継承者の必要ない樹木葬を決断
●樹木葬までの壁
・親族の反対
・菩提寺との関係
・墓じまいの遺骨は菩提寺の合祀墓へ
●樹木葬の納骨式
・かつての菩提寺のご住職へ読経供養を依頼
・父親1柱のみの契約、25万円×1柱=25万円
お電話でも受け付けております
















