
身元保証人がいない高齢者はどうすればいい?老人ホームや病院へ入所する対策と注意点!

「身元保証人がいない高齢者はどうすればいい?」
「誠実な身元保証会社の見分け方は?」
「身元保証会社の平均的な料金システムは?」
核家族化・少子高齢化が進む現代の日本では、身元保証人がいないと悩む高齢者が少なくありません。一方で老人ホーム・高齢者住宅、入院時には身元保証人が必須です。
身元保証人を家族が担えなくなった今、身元保証会社が乱立しています。誠実な身元保証会社を見極めるためにも、依頼者側も充分な身元保証への知識と理解が必要になるでしょう。
本記事を読むことで身元保証がいない高齢者はどうすればいいのか?身元保証会社の探し方・選び方、契約前の注意点が分かります。
身元保証人がいない高齢者とは

少子高齢化・核家族化が進むなかで、65歳以上世帯の半数以上は独居・夫婦2人世帯となりました。独居率38%とされる65歳以上の高齢世帯は今後も増える傾向です。
そこで高齢者の間で身元保証人の不在が不安視されています。身元保証人がいなければ入院や施設へ入所できない事態も懸念されるためです。
・子どもがいない
・独身
・子どもと疎遠
・身元保証人を変えたい
(身元保証人とのトラブル)
問題に呼応するように、身元保証を請け負う「身元保証会社」が乱立しました。けれども法整備が充分とは言えず、身元保証会社トラブルが多発しています。
どんどん登場する身元保証会社の業務を監督する存在がいないためです。身元保証を検討する高齢者は、トラブル回避のための知識も必要と言えます。
・内閣府「第1節高齢化の状況(3)」令和5年
・厚生労働省「身寄りのない高齢者等への支援について」令和6年6月10日
①保証人の高齢化
優良老人ホーム等、長期間に渡る身元保証人が必要な施設もあります。このような施設では身元保証人の高齢化問題も増加傾向です。
夫婦での身元保証人・兄弟姉妹での身元保証人など、同世代が身元保証人を引き受けた場合、お互いに年を取ります。
優良老人ホームでご本人が亡くなり、身元保証人に連絡を取ったら身元保証人も亡くなっていた事例では、ご遺体の引き取りや死後事務手続きが問題になりました。
現状で身元保証人がいても、将来的に若い世代の身元保証人を立てる必要が予想されます。
②保証金を払った場合
現代では身元保証人がいない入所希望者に対して、一括で一時金を支払うことで身元保証人を立てなくても入所できる施設もあるでしょう。
けれども一時金は金銭的な保証ができたに過ぎません。取り合えずのところ入所できたものの、後々は身元保証人を探す必要があります。
高齢者の施設入所の場合は金銭的保証だけが身元保証人の役割ではないためです。
認知症になった時には、誰が財産管理・生活費の金銭管理をするのでしょう。介護・入退院時の手続きも身元保証人が担います。
・厚生労働省「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」
身元保証人がいない高齢者が困る時

身元保証人が求められる施設は主に病院・高齢者住宅・優良老人ホーム等です。
厚生労働省は身元保証人がいないことのみを理由に入院・入所を拒否することを法律(医師法19条1項)に抵触すると公的見解を示しました。
けれども現実的には身元保証人なしでは入所できない病院・高齢者施設は約9割です。ここでは病院・施設の立場から、身元保証人が必要な理由を解説します。
・総務省「高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)」
①入院・手術が必要な時
身元保証人がいない高齢者が困るシーンは入院・手術時です。医療を施す病院では、入院・手術時の契約で身元保証人が求められます。
身元保証人がいないまま本人が亡くなってしまった時、病院側は相続人に請求をしなければなりません。
けれども相続人を探す事務手続きは大変な作業です。このような作業を省略するために身元保証人が求められます。
②施設へ入所したい
長期間に渡り過ごす高齢者施設も、入居契約時に身元保証人が求められるでしょう。特に高齢者施設は最期まで見据えて入所する人も少なくありません。
高齢者施設の料金システムは、主に一時金を入所時に支払う施設・家賃のように施設の料金が毎月発生する施設の2通りがあります。
一時金(一括払い)で入所したとしても、毎月何かしらの料金が発生するため、いずれにしても身元保証人は必要です。
施設としては毎月の料金を払えなくなった時の連帯保証人としての立場、本人がなくなった時のご遺体の引き取り先が求められます。
身元保証人の役割

身元保証人は病院や施設に迷惑がかからないよう、サポートする存在です。
基本的にはご家族が身元保証人になるでしょう。身元保証人がいない高齢者の場合、第三者である身元保証会社等を頼ります。
契約者ご本人が存命の場合、身元保証会社の役割は家族代行としてのサポートです。緊急時の対応、入院・手術時の同意等がそれにあたります。
契約者ご本人が亡くなった後、身元保証会社の主な役割は死後事務手続きです。
①手続き
身元保証人がいない高齢者が困る場面は、高齢者施設の入所手続き・病院への入院手続きです。病院では入院手続きだけではなく、手術時にも身元保証人からの同意が求められます。
しばしば一時金を支払い入所する場合、入所時の契約時点では身元保証人を立てなくても入所できる高齢者施設もありますが、後々は必要になるでしょう。
②本人に代わって費用の支払い
病院や高齢者施設で身元保証人は、主に連帯保証人としての役割を求められます。病院では病院代や手術費用、高齢者施設では施設の料金などです。
③緊急連絡先
身元保証人は緊急連絡先としての役割も果たします。病院や高齢者施設で本人の意識が無くなった時、危篤時などに緊急連絡先が必要です。
また在宅介護では、認知症などの病状により本人と連絡が取れない、行方不明になった時にも緊急連絡先へ連絡が行くでしょう。
④身の回りの世話
身元保証人の役割として家族代行があります。家族の代わりに本人の身の回りの世話を担う役割です。
例えば本人が入居する高齢者施設へ請求書が届いたものの、本人は支払いができない時には、身元保証人が代わりにコンビニなどで支払いを済ませます。
病院で家族が病状の告知を受ける時にも、ご家族の代わりに付き添うこともあるでしょう。買い物や診察の付き添いに関しては、それぞれの契約内容によります。
⑤死後事務手続き
身元保証人の大きな役割として、本人が亡くなった後の手続き「死後事務手続き」があります。死亡届の提出・葬儀の手配・葬儀後の納骨などの手続きを身元保証人が担うケースが多いです。
また病院や高齢者施設で本人が亡くなった時、未払いの請求があれば身元保証人が代理で支払います。
相続手続きは法定相続人が進めますが、相続手続きの前準備にあたる財産の引継ぎ、遺品整理までは身元保証人が行う流れも多いでしょう。
・内閣府ホームページ「身元保証等高齢者サポート事業に関連する制度の概要等」
身元保証会社の料金目安

契約プランによりさまざまな支払い方法がありますが、一般的には身元保証会社へ依頼すると「契約金(初期費用)+月額料金」がかかります。
現代の身元保証会社は有象無象が乱立しているため、契約前には重要事項説明書を用いた重要事項説明がきちんと行われていることを確認してください。
丁寧な説明を受けて納得してから契約に進むことも重要です。不安があれば信頼できる専門的な第三者に立ち会ってもらいましょう。弁護士はもちろん、施設スタッフやケアマネージャーにお願いしても良いです。
①契約金
◇契約金の料金相場は約80万円~100万円です
契約プランやオプション内容により初期費用となる契約金は異なりますが、一般的に約80万円~100万円が目安です。契約の締結前に契約金の内訳もきちんと説明してもらいましょう。
契約金の内訳には一例ですが、高齢施設の連帯保証・入院時の身元保証料・財産管理・認知症になった時の代わりに判断(任意後見)料金などが含まれます。
②月額料金
◇月額料金相場は約5千円~1万円です
身元保証人のプラン内容・オプションにより月額料金が高くなるケースもありますが、一般的な月額料金相場は約5千円~1万円となります。
月額料金の内訳は一例ですが、基本サービス利用料(約1,500円)・生活支援サービス利用料(約5千円)・緊急連絡受付維持料(約1,500円)、合計8千円などです。
③その他の料金
身元保証人としての基本サービスの他に暮らしにおけるサポートを希望すると、内容に応じてオプション料金がかかります。基本的には時間制で請け負う身元保証会社が多いでしょう。
一例では病院や買い物の付き添いで1時間あたり2,500円~3,500円、その他の日常支援が1回あたり約3千円~5千円などです。
身元保証会社の選び方

身元保証会社は高齢者施設の見学時などに、病院や高齢者施設スタッフに相談すると紹介してくれます。近年ではインターネットで探す人も多いです。
一般的には紹介されたなかから最も対応するエリアが近い身元保証会社を選びます。ただし身元保証会社が乱立する現代では、依頼者の選ぶ目も必要です。ここでは信頼できる身元保証会社を見分けるポイントをご紹介します。
身元保証会社は大まかに運営母体から、一般社団法人・NPO法人・民間企業(株式会社)の3種類に分かれるでしょう。
①信託口座で財産管理をしている
身元保証人は本人の死後手続きも担うため、どうしても被契約者本人の財産をある程度管理しなければなりません。
死後手続き手数料の他にも・葬儀費用・供養に関する費用・納骨費用まで、身元保証人が立て替えることになってしまうためです。
そこで身元保証会社が本人の財産を管理するにあたり、信託口座を利用しているかどうかをチェックしましょう。信託口座は生前中、身元保証人でも勝手にお金を下ろせません。
信託口座の利用により生前中はお金をいじれないようにロックをかけ、不必要な支出・引き出しができないシステムです。
相続財産ですので身元保証人の横領対策だけではなく、親族とのトラブル対策にもなるでしょう。
②窓口がひとつにまとまっている
生前から死後手続きまで、窓口をひとつにまとめられる身元保証会社が便利です。また依頼内容の抜け落ちが無くなるため、安心して任せられます。
窓口をひとつにまとめたい依頼内容は・身元保証人・遺言執行者・死後事務受任者・身の回りの事務受任者です。
③運営状態を確認する
身元保証会社の注意点
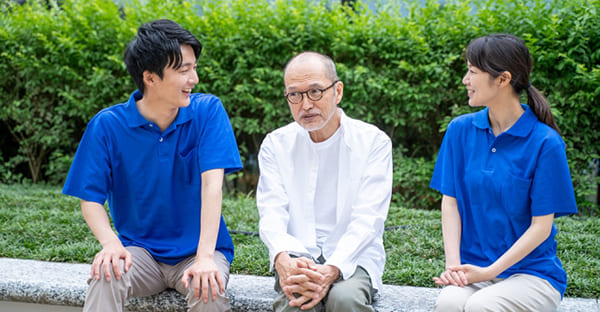
信頼できる身元保証会社を見分けるポイントをお伝えしましたが、反対に注意点も今一度確認してみましょう。
何度もお伝えしていますが、おひとりさま老後が多い現代において身元保証会社のニーズは急激に伸びています。乱立する身元保証会社から信頼できるひとつを選びましょう。
財産を預けるため、基本として不適切な支出・不適切な管理がシステム上できないよう、整備が整えられている身元保証会社を選びます。
①財産の寄付を求めて来る
身元保証会社から、財産の寄付を求められた場合は注意が必要です。特に本人が亡くなった後、財産の寄付を求める身元保証会社がありますがこれは危険です。
「最終的には自分達の財産になるのだから」と、身元保証会社による財産の使い込み・横領リスクがあるでしょう。
②個人法律家
現代、身元保証会社に対する法律による制限はありません。個人の法律家でも身元保証業務を請け負うことができますが注意をしましょう。
個人法律家による身元保証では、業務内容をチェックする充分な第三機関が存在しないためです。
ここでも第三者による監視の目がない個人法律家による、財産の使い込みや横領リスクがあります。もしも個人法律家に依頼するならば、第三者機関のチェックも併せて依頼する方法も一案です。
③窓口がバラバラになっている
身元保証人は一人が担当しなければ、仕事の範囲が不明瞭になってしまいます。主な業務内容は・身元保証人・遺言執行者・死後事務受任者・身の回りの事務受任者です。
これらの仕事を別々の人が担い業務の範囲が重なってしまうと、お互いに譲り合ってしまうリスクがあります。反対に業務の範囲が重なり合わない仕事はおざなりにされる傾向です。
最悪の事態では、担当者同士で責任の所在を巡って争いが起きてしまう可能性もあります。
身元保証会社との契約

身元保証会社を決めて契約に進んだ場合、後々本人や遺された家族ともトラブルに発展しないよう各種契約書類を交わします。身元保証会社やプランでも異なりますが、基本的には下記契約を書面で交わすと安心です。
・事務委任契約
・財産管理委任契約
・任意後見契約
・意思表示宣言書
・死後事務委任契約
・公正証書遺言書
本人が亡くなった後の死後手続きもあるので、特に家族・親族がいるものの「負担をかけたくない」などの理由で身元保証会社に依頼する人は、書面による契約がトラブル対策に不可欠です。
疎遠になった親族がいる
まとめ:身元保証人がいない高齢者は第三者と契約します

一般的に病院や高齢者施設の入所時に身元保証人が立てられない高齢者は、病院や施設スタッフに相談をすると身元保証会社を紹介してくれます。
ただし現代は身元保証会社が乱立しているため、紹介いただいた会社だからと契約を進めるだけでは危険です。
身元保証会社と契約を進める前に料金設定とサービスとともに、ホームページなどから運営母体の事業理念、経営状況・資金管理状況まで確認しましょう。
お電話でも受け付けております
















