
2025年の年金制度改正とは?在職老齢年金の基準引き上げ・給付額の変更点をわかりやすく解説

2025年に予定されている年金制度の改正では、在職老齢年金の支給基準引き上げや、基礎・厚生年金の給付額見直しなど、現役世代からシニア世代まで幅広い層に影響が出る見込みです。
厚生労働省が進める2025年の年金制度の改定は、「長く働く人を支える仕組みづくり」として注目されています。
本記事では、2025年の年金制度改正の背景や目的、変わるポイントをわかりやすく整理。支給額や上限、加入拡大の内容を確認しながら、2025年の年金制度改正を踏まえた将来の生活設計に役立つ情報をまとめました。
2025年の年金制度改正とは?概要と目的をわかりやすく解説

2025年に実施される年金制度改正は、少子高齢化の進行と就労環境の変化に対応するための大きな見直しです。
厚生労働省は「長く働く意欲を支え、将来の年金財政を安定化させる」ことを目的として、
在職老齢年金・基礎年金・厚生年金など複数の仕組みを段階的に改革します。
今回の改正は、法改定により2024年度中に成立し、2025年4月以降に順次適用される見通しです。
ここでは、改正の背景・目的・変更点の全体像をわかりやすく整理します。
年金制度改正の背景と成立までの流れ
日本では、老後の生活を支える年金制度が長年にわたり維持されてきましたが、
少子高齢化や非正規雇用の増加により、制度の持続が課題となっています。
特に「働けるうちは働きたい」という高齢者が増えたことで、
現行制度のままでは“働くと年金が減る”といった不公平感が指摘されていました。
こうした課題を受け、厚生労働省は2023年に年金制度全体の改革案を公表。
与野党協議を経て2024年度に法案が成立し、2025年施行が決定しました。
この改正により、働く世代・受給世代の双方にとって納得感のある仕組みを目指しています。
厚生労働省が示す年金制度改正の目的と方向性
厚生労働省が掲げる年金制度改正の主な目的は、次の3つです。
① 長く働く人の就労意欲を支える
→ 在職老齢年金の支給停止基準を引き上げ、働いても年金が減らない仕組みに。
② 将来の給付水準を安定させる
→ 物価・賃金に連動した「マクロ経済スライド」を見直し、給付額を調整。
③ 働き方の多様化に合わせた制度拡大
→ パートや短時間労働者にも厚生年金を適用し、保障の公平化を進める。
これらの改革は単なる「支給額の引き上げ・引き下げ」ではなく、
全世代が支え合う年金制度への転換を目指すものです。
[改正の詳細や最新情報は、厚生労働省の公式ページ]
・年金制度改正法が成立しました
2025年改正で変わるポイント①|在職老齢年金の見直しと支給基準の引き上げ

2025年の年金制度改正では、最も注目されているのが在職老齢年金の支給基準引き上げです。
これまで「働きながら年金を受け取ると減額される」という仕組みが課題とされてきましたが、
今回の見直しにより、働く高齢者が安心して収入を得られる制度へと変わります。
在職老齢年金の仕組みと問題点
在職老齢年金とは、厚生年金に加入したまま年金を受け取る人を対象に、
給与と年金の合計が一定基準を超えると支給額が減額される制度です。
これまでの基準は「月額47万円(賃金+年金)」が上限とされていました。
このため、再雇用やパート勤務などで一定以上の収入を得ると、
年金が減る・働く意欲が削がれるといった声が多く聞かれていました。
厚生労働省は、この「働くほど損をする構造」を見直すため、
2025年の法改正で支給停止基準の引き上げを決定しました。
2025年年金制度改正での支給停止基準と月額上限の変更
改正後は、在職老齢年金の支給停止基準が「月額47万円 → 50万円」へと引き上げられます。
また、年金と賃金を合算した総収入の上限も再設定され、
段階的に負担を軽減する仕組みが導入されます。
この変更により、働きながら一定の収入を得ても、
減額や支給停止の対象になりにくくなることが大きなポイントです。
| 改正前(現行) | 改正後(2025年) | 改正の目的 |
|---|---|---|
| 支給停止基準:月47万円 | 支給停止基準:月50万円 | 働く高齢者の就労継続を支援 |
| 調整ルールが複雑 | 段階的な調整方式に変更 | 公平でわかりやすい制度へ |
| 一律減額 | 所得水準に応じた調整 | 負担感の軽減・就労意欲の維持 |
この改革は、60歳以降も現役で働く人の増加を見据え、
「長く働きたい人が報われる年金制度」への第一歩といえます。
[詳しい計算方法や支給停止額の早見表について]
・在職老齢年金とは?年金が減額する『50万円の壁』の計算、年金停止額早見表もご紹介!
年金制度の対象となる年齢層と段階的な引き上げスケジュール
新制度の対象は、60歳から70歳までの在職者です。
特に60〜64歳の層において支給停止の緩和が大きく、
段階的に適用されることで、制度への移行負担が軽減されます。
● 2027年度以降:経済情勢や物価水準を踏まえ、さらなる調整を検討
● 2030年以降:65歳以降の働き方に応じた柔軟な支給制度へ移行予定
今後は、個人の就労状況に合わせて「部分的な支給」や「選択的受給」など、
より柔軟な仕組みへの改革が段階的に進む見通しです。
[支給停止の基準や在職老齢年金の詳細な仕組み]
・日本年金機構:「在職老齢年金(支給停止の基準)
2025年改正で変わるポイント②|基礎年金・厚生年金の給付額と保険料の見直し
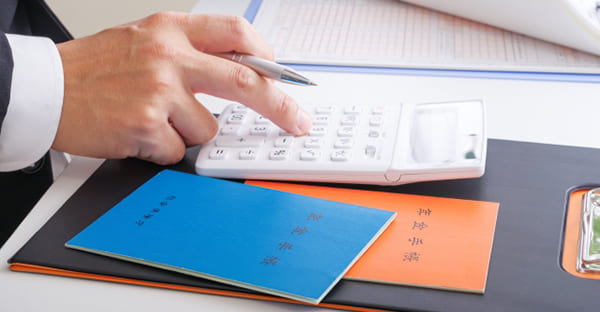
2025年の年金制度改正では、給付額の見直しと保険料の調整も大きな変更点です。
特に「基礎年金」と「厚生年金」のバランスを整えることを目的に、
将来の年金額を安定化させる仕組みが導入されます。
これは、現役世代の負担を抑えつつ、老後の生活水準を確保するための改革です。
基礎年金の支給額はどう変わる?
基礎年金(国民年金)は、物価や賃金に連動して毎年度見直される「マクロ経済スライド方式」が採用されています。
2025年改正では、このスライド調整の方法を段階的に緩和し、
高齢者の生活水準を一定に保つための調整が加えられます。
厚生労働省の試算によると、
平均的な受給額は 月6万5,000円前後 → 月6万8,000円程度 への微増が見込まれています(物価水準により変動)。
| 改正前(2024年度) | 改正後(2025年度) | 改正ポイント |
|---|---|---|
| 月額:約6万5,000円 | 月額:約6万8,000円(見込み) | 物価上昇に応じたスライド調整 |
| マクロ経済スライドの影響が強い | 緩やかに調整へ | 生活水準の安定化 |
| 給付額が年ごとに変動 | 中期的に安定推移 | 家計計画が立てやすく |
基礎年金の底上げは、低所得の年金受給者を中心に支援する「年金生活者支援給付金」と連動しており、
2025年度からは支給対象の拡大も検討されています。
厚生年金の保険料率と給付水準の調整方針
厚生年金では、企業と従業員が折半で保険料を負担しています。
今回の改正では、保険料率の上限を固定化し、将来的な引き上げを抑制する方向へ転換します。
これまで18.3%だった保険料率は、2025年度以降も同水準を維持。
その一方で、賃金の伸びや物価変動に合わせた給付水準の調整が導入されます。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年) | 影響 |
|---|---|---|---|
| 保険料率 | 18.3% | 18.3%(維持) | 負担増を回避 |
| 給付水準 | 名目維持 | 実質微調整あり | 財政安定化 |
| 上限月額 | 約65万円 | 約70万円 | 高所得層への対応 |
このように、働く世代の負担を抑えつつ、将来の給付を安定させる“調整型改正”となっています。
厚生労働省は「制度の持続可能性を高めることが最大の目的」と強調しています。
年金制度が老後の受給額に与える影響と将来見通し
2025年以降、基礎年金と厚生年金を合算した平均支給額の目安は以下の通りです。
| 世帯構成 | 改正前(2024年) | 改正後(2025年) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 単身世帯 | 約11万円 | 約11.3万円 | +0.3万円 |
| 夫婦世帯(2人分) | 約22万円 | 約22.6万円 | +0.6万円 |
| 共働き世帯 | 約26万円 | 約26.5万円 | +0.5万円 |
このように、給付額は大幅な増額ではないものの、
物価上昇に対して年金水準を維持する方向で見直しが行われています。
また、所得の低い高齢者を支援するため、
「在職高齢者への特例給付」や「私的年金との併用制度」など、
柔軟な仕組みも並行して整備される予定です。
2025年改正で変わるポイント③|パート・短時間労働者の加入拡大と企業対応

2025年の年金制度改正では、パートや短時間労働者への厚生年金の適用拡大も大きなテーマです。
これまで「一部の企業だけが対象」だった制度が、今後はより多くの労働者が年金に加入できる仕組みへと変わります。
働き方の多様化が進む中で、「働く時間や雇用形態による格差をなくす」ことが目的です。
どこまで加入対象が拡大されるのか
現行制度では、従業員が常時101人以上の企業に勤めている場合に、
パートやアルバイトでも条件を満たせば厚生年金に加入できます。
2025年改正後は、対象企業の規模要件が51人以上の企業へ引き下げられる見込みです。
つまり、これまで対象外だった中小企業の短時間労働者も、
条件を満たせば厚生年金に加入できるようになります。
| 項目 | 改正前(2024年度) | 改正後(2025年度) |
|---|---|---|
| 対象企業規模 | 常時101人以上 | 常時51人以上 |
| 勤務時間・日数要件 | 週20時間以上、月収8.8万円以上 | 同条件(維持) |
| 対象者数 | 約130万人 | 約200万人(見込み) |
この改正によって、パート・アルバイトなど非正規雇用層の約70万人が新たに年金制度に加入できるようになると試算されています。
企業・従業員双方の負担と年金制度の対応ポイント
企業側は、新たに加入対象となる従業員の社会保険料の負担が発生します。
従業員と企業が折半で負担するため、コスト増は避けられませんが、
同時に「従業員の福利厚生を強化できる」というメリットもあります。
企業が取るべき主な対応は次の3つです。
① 就業規則・雇用契約の見直し
→ パート・短時間労働者の雇用条件を明確化し、加入基準に沿った契約へ変更。
② 人件費・保険料負担の試算
→ 加入者増によるコスト影響を試算し、経営計画へ反映。
③ 従業員への説明・周知
→ 加入による年金額の増加や将来のメリットを共有し、安心感を与える。
特に中小企業では、準備期間を確保して段階的に対応することが重要です。
厚生労働省も、中小事業者向けに「社会保険加入支援ガイドライン」を公開しています。
社会保険制度全体との関係性
この加入拡大は、単に対象者を増やすだけでなく、社会保険制度全体の底上げを目指す改革でもあります。
健康保険・雇用保険と年金制度を連携させることで、より一貫した社会保障を構築するのが狙いです。
また、今回の年金制度改正は「将来の財政負担を抑えつつ、働く人を守る仕組み」でもあります。
長期的には、非正規雇用者の老後格差の是正や、
女性の社会進出に伴う年金保障の強化にもつながると期待されています。
2025年に年金額はどう変わる?給付水準の底上げと生活への影響
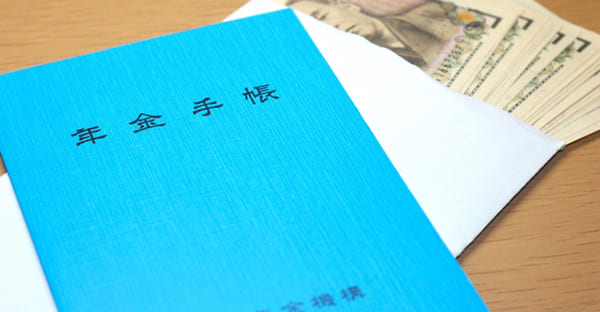
2025年の年金制度改正では、在職老齢年金の見直しに加え、給付水準の底上げも進められます。
これは、長期的な物価上昇や賃金変動に対応しつつ、年金生活者の暮らしを安定させるための調整です。
厚生労働省は「年金額の実質的な維持」を目標に掲げ、2025年度から段階的な引き上げを予定しています。
平均的な年金月額はいくらに?
2025年の改正後、平均的な年金月額は次のように変化する見込みです。
物価上昇を考慮したうえで、全体として0.3〜0.6万円程度の底上げが行われる想定です。
| 世帯構成 | 改正前(2024年) | 改正後(2025年) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 単身(国民年金) | 約6.5万円 | 約6.8万円 | +0.3万円 |
| 夫婦(厚生年金2人分) | 約22万円 | 約22.6万円 | +0.6万円 |
| 共働き(厚生+国民) | 約26万円 | 約26.5万円 | +0.5万円 |
この引き上げは「年金生活者支援給付金」や「物価スライド調整」によるもので、
今後も経済状況に合わせて見直される予定です。
大幅な増額ではないものの、将来の実質支給額の維持を狙った改正といえます。
[2025年4月からの国民健康保険料見直しについて]
・2025年4月の年金額と国保料が改正!老齢・障害・遺族年金など
物価・賃金との調整基準と今後の見通し
年金額の算定には、物価や賃金の変動を反映する「マクロ経済スライド」が使われています。
2025年改正では、この仕組みをより緩やかに調整する方式へ変更し、
景気や賃金動向に左右されにくい制度に改善されます。
たとえば、物価上昇率が2%を超えた場合でも、
給付額は一度に上げすぎず、段階的に調整する仕組みが導入されます。
これにより、急激な支給変動を防ぎ、長期的に安定した年金水準を確保します。
厚生労働省は、今後5年間の見通しとして、
「平均支給額を年0.2〜0.4%ずつ引き上げ、実質購買力を維持する」方針を示しています。
年金生活者支援給付金との関係
低所得の年金受給者を対象に支給される「年金生活者支援給付金」も、
2025年から支給基準と対象範囲が拡大されます。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年) | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 支給基準所得 | 年金年額 約87万円未満 | 約92万円未満へ引き上げ | 対象範囲拡大 |
| 月額支給額(単身) | 約5,020円 | 約5,500円前後 | 約+480円増額 |
| 対象者数 | 約430万人 | 約480万人(見込み) | +50万人増加 |
これにより、より多くの高齢者が生活支援を受けられるようになる見通しです。
年金額そのものの増加に加え、生活支援策も強化されることで、
老後の家計負担を少しでも軽減する狙いがあります。
2025年年金制度改正で注目すべきその他のポイント

年金制度の2025年改正は、在職老齢年金や給付額の調整だけでなく、
私的年金や企業年金など、周辺制度にも影響が広がる改革です。
ここでは、見落としがちなポイントや、今後の動向をまとめておきましょう。
私的年金(iDeCo・企業年金)との関係性
2025年改正は公的年金制度の見直しが中心ですが、
同時に私的年金制度(iDeCo・企業型DCなど)との関係性も見直されています。
iDeCo(個人型確定拠出年金)では、加入年齢の上限が60歳から65歳に延長されており、
今回の年金制度改正と合わせて、長く働く人が老後資金を形成しやすい環境が整備されています。
また、企業型確定拠出年金(企業DC)では、
退職金制度の代替として導入する企業が増加中です。
2025年以降は「公的年金+私的年金」の二層構造が一層明確になり、
企業・個人双方が老後の備えを自助努力で強化する時代が到来します。
2025年新制度に関する法改定スケジュールと今後の検討課題
厚生労働省による法改定スケジュールは以下の通りです。
| 年度 | 内容 | 対応状況 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 改正法案の成立・公布 | 実施済み |
| 2025年度 | 改正内容の段階的施行開始 | 予定 |
| 2026〜2027年度 | 制度の運用検証・追加改定案の策定 | 検討中 |
| 2030年度以降 | 次期年金改革(第3段階)へ移行 | 構想段階 |
今後の課題としては、制度を安定的に運用していくための視点が求められます。
● 働き方が多様化する中での「公平な負担と給付の調整」
● 非正規・自営業者を含めた加入率向上
● 少子高齢化に伴う年金財政の持続性確保
これらを踏まえ、政府は今後5年間で制度の定着を図りつつ、
2040年を見据えた次の年金制度改革に向けて準備を進めています。
2025年の年金制度改正を、今後の生活設計にどう活かすか
今回の年金制度改正をきっかけに、
多くの人が「自分の将来の年金額」や「老後の生活設計」を見直すようになっています。
今後は、社会全体としてバランスの取れた備え方が重要になります。
公的年金制度を中心に、老後の生活基盤を安定させる。
● 私的年金やNISA・iDeCoで資産形成を補う
自助努力による老後資金づくりを進める。
● 健康・就労期間を延ばし年金受給を安定化させる
働ける期間を延ばし、受給開始時期や金額を柔軟に調整する。
このように、「三本柱の老後対策」が今後さらに求められていくでしょう。
制度の改正は“終わり”ではなく、将来を考えるきっかけ。
2025年の年金改革を理解しておくことが、これからの暮らしの安心につながります。
まとめ|2025年の年金制度改正で何がどう変わるのか
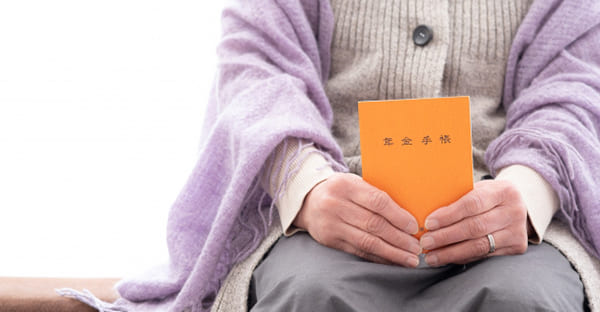
2025年の年金制度改正は、働く世代から年金受給者まで全世代に影響を与える大きな見直しです。
在職老齢年金の支給基準引き上げや、基礎・厚生年金の給付水準調整、
パート・短時間労働者の加入拡大など、改正の目的は「長く働く人を支え、安心して老後を迎えられる社会の実現」にあります。
改正の主なポイントを改めて整理すると、次のとおりです。
● 在職老齢年金の支給停止基準を月47万円→50万円に引き上げ
→ 働きながら年金を受け取っても減額されにくくなり、就労継続を後押し。
● 基礎・厚生年金の給付水準を段階的に底上げ
→ 平均年金月額が0.3〜0.6万円増加し、生活の安定を図る。
● パート・短時間労働者の厚生年金加入を拡大
→ 対象企業が「従業員51人以上」に引き下げられ、約70万人が新たに加入。
● 年金生活者支援給付金の支給基準を引き上げ
→ 対象者数が約50万人増加し、低所得層の支援が拡充。
● 私的年金(iDeCo・企業型DC)との連動強化
→ 「公的+私的+自助」の三本柱で老後の安定を確保。
これらの改革は、単なる「年金額の変更」ではなく、
長寿社会に合わせた“働き方と暮らし方の再設計”でもあります。
厚生労働省は、2030年以降も次の改革段階を見据え、
公平で持続可能な年金制度の確立を目指しています。
お電話でも受け付けております
















