
遺影の選び方とは?いつまでに決める?スナップ写真は大丈夫?画格や解像度、注意点は?
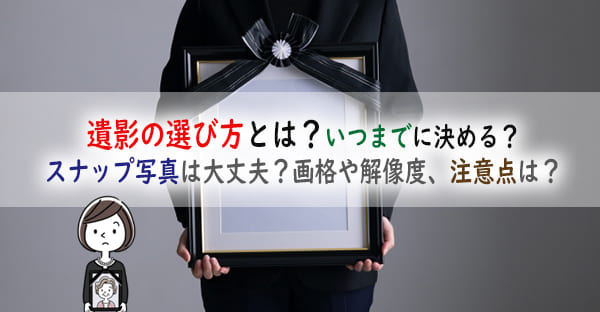
・遺影の選び方は?
・遺影はいつまでに決めたらいい?
・スナップ写真や古い写真でも大丈夫?
通夜、葬儀までに準備すべき遺影ですが、選び方が分からずに慌てる人は多いですよね。
証明写真のような遺影あれば良いのですが、一般的にはスナップ写真から選ぶ人も多くいます。
本記事を読むことで葬儀前の限られた時間に戸惑わない、適切な遺影の選び方や注意点が分かります。

遺影の選び方:ポイント

●故人の生前のお人柄がイメージできる遺影が好ましいです
遺影の選び方としては、正面を向いていた方が良い、背景がゴチャゴチャしない方が画像加工がしやすい、などのポイントはありますが、最後の最後は遺族が眺めて納得できる、故人らしい写真を選ぶ、遺影の選び方がベストでしょう。
①遺影のピントと解像度
②遺影から故人の人柄を感じる
③遺影の服装
④遺影の目線
⑤遺影は5年~10年前までがベター
⑥額縁は持ち歩くことも想定
などが基本的な遺影の選び方ですが、冒頭でお伝えしたように、必ずしも理想通りの写真が見つかる訳ではありません。
例えば、複数で写っているスナップ写真でも、写真加工により一人だけ取り出して修正をすることができます。
それぞれ多様性により受け入れられるようになったり、写真の加工サービスを利用する人も多いです。
①遺影のピントと解像度
●ピントが合っていて、解像度が高い写真が好ましいです
近年ではデジタルデータがほとんどですが、スナップ写真を引き伸ばして加工する事例は多いものの、祭壇に飾る四つ切サイズ(A4サイズもアリ)などでは、推奨されるサイズが1920ピクセル×2560ピクセルです。
| <遺影の選び方:ピントと解像度> | |
| [写真サイズ] | ・四つ切 ・A4サイズ |
| [画像サイズ] | ・1920ピクセル×2560ピクセル |
| [注意点] | ・ピントが合っている |
| [スナップ写真] | ・あまりに小さい写真は避ける (目安はお顔が10円玉サイズ以上) |
そう考えると、あまりに画像解像度が小さい場合、ピントが合っていない写真同様に、引き伸ばしてもぼやけることが予想されます。
スナップ写真を引き伸ばす場合、大きさの目安としては、顔が10円玉よりも大きい写真を選びましょう。
②遺影から故人の人柄を感じる
◇故人の生前の人柄がイメージできる写真を選びます
例えば、生前に仕事熱心で誠実だった故人であれば、スーツを着てキリッと真面目に映る写真が故人らしい遺影の選び方です。
| <遺影の選び方:人柄をイメージ> | |
| ●生前に真面目な印象 ・仕事熱心 ・誠実だった …など |
・スーツ姿 ・カメラ目線 ・落ち着いた表情 ・白シャツ …など |
| ●自由な人 ・アウトドアが好き ・陽気 ・仲間に囲まれていた …など |
・スナップ写真 (周辺を加工) ・満面の笑顔 ・普段着でも良い |
…など、故人の人柄で遺影の選び方も変わります。
一方でサーフィンや登山などアウトドアを楽しみ、仲間に囲まれて陽気に生きていた故人であれば、遺影であっても満面の笑顔で写っていても良いでしょう。
前述したように複数人で撮影をしていても、現代では写真加工技術によって、故人のみを取り出して大きくすることが可能です。
・【家族が亡くなったら】末期の水~枕飾り・枕経まで。遺体処置7つの事柄|永代供養ナビ
③遺影の服装

●服装は写真加工でフォローできます
祭壇に飾る遺影の選び方として、従来の考え方では、スーツなどキチンとした服装で写したものを選びたい家族が多いです。
けれども表情を見ると故人らしくてとても良いのに、パジャマを着ていた、上半身裸だった(男性には意外と多いです)、葬儀の席には相応しくない派手な服装だった、などの体験談は多くあります。
●現代の写真加工技術によって、首から下を着物やスーツに入れ替える修正が可能です。
そのため自然な写真としては、写真そのままの姿を遺影にしたいところですが、「この表情がとても良い!」と言う時には、葬儀スタッフなどに相談をすると良いでしょう。
遺影は後々、四十九日法要までは後飾りの祭壇に飾られますし、落ち着いた後もお仏壇の脇に飾る家も多いです。
家族も納得しながら、写真加工技術でフォローできる箇所はフォローしましょう。
④遺影の目線
◇従来の遺影の選び方はカメラ目線ですが、多様性が受け入れられています
従来の遺影の選び方では、故人がカメラ目線で写っているものが理想的でした。
故人がカメラ目線で写っていることで、遺族や弔問客は故人と目を合わせて、会話を交わしながらお焼香ができるためです。
●けれども現代では、故人の生前の人柄も踏まえ、カメラ目線でなくても受け入れられるようになりました。
今では花冠を被った横顔の穏やかな笑顔や、かつての文豪のように才能を感じる俯いたショットなども発見できます。
何よりも、故人らしいと思えるような遺影の選び方が主流となっているようです。
⑥遺影は5年~10年前までがベター
●遺影は一般的に、約5年~10年前までが理想的です
一般的な遺影の選び方では、葬儀から昔でも5年~10年前までとされますが、年数において決まり事はないので、故人が全く写真を撮らない人だった場合などでは、それ以前の写真も見受けます。
・一般的には、古くても5年~10年前まで
・闘病前の元気な頃
・弔問客が故人と分かる時代
なかには長い闘病生活の末に亡くなった人もいるでしょう。
この場合には年数にこだわらず、闘病前の元気だった頃の写真を遺影にする遺族が多いです。
ただ若すぎて葬儀に参列いただいた弔問客が、遺影を見ても故人と分からないような写真は避けたいところでしょう。
⑥額縁は持ち歩くことも想定

◇遺影は葬儀で喪主が持ち歩くため、安全な素材を選びます
普段、窓際に飾る写真の額縁であればガラス製などでも問題はないのですが、遺影は四つ切やA4サイズと大きく重いうえ、喪主が持ち歩くシーンも多いです。
その点も踏まえて、ふとした時に落としても割れにくいよう、ガラス製は避けるなどの注意をすると、なお良いでしょう。
・ガラス面はアクリル製がより安全
・木製の額縁は、裏面加工が施されたもの
・祭壇の遺影は四つ切、A4サイズほど
従来の遺影では額縁の選び方として、重厚感のある木製フレームが多かったのですが、最近では故人をイメージできるカラフルな樹脂製やアクリルフレームも増えました。
また遺影にはリボンを付けますが、取り外しが楽なワンタッチリボンも見受けます。
まとめ:終活で遺影撮影をしていないかも確認します

今回は遺影の選び方をお伝えしましたが、近年では終活の広がりにより、生前にカメラスタジオで遺影撮影を行う人も増えました。
けれども故人が終活をしていたことを知らないまま、バタバタと葬儀を済ませてしまった家族が、葬儀後に生前に撮影した遺影の存在をしった事例もあります。
終活をしている場合は、エンディングノートや遺言を残している人も多いですから、最初に探してみるのも一案です。
さらに近年では、遺影を遺族が自ら加工することも増えました。
背景を決して服をスーツに着せ替えるなど、本文でお伝えした遺影の選び方に沿って、加工してみると、より安心できるでしょう。
まとめ
遺影の選び方
①ピントと解像度
・ピントが合っている
・解像度が高い写真
・スナップ写真なら顔が10円玉以上
②故人の人柄
・故人の人柄がイメージできる
③服装
・キチンとした服装が良い
・加工で服装を変更する
④目線
・カメラ目線が良い
・多様になりカメラ目線以外も増えた
⑤何年前?
・5年~10年前までの写真
・闘病生活が長ければ元気な頃
・参列者が故人と分かる時代の写真
⑥額縁
・額縁は持ち歩くことも想定
・ガラスより安全なアクリル
お電話でも受け付けております
















