
お墓参りやお仏壇への、お焼香の正しいあげ方は?マナーや注意点、宗派で違う回数を解説
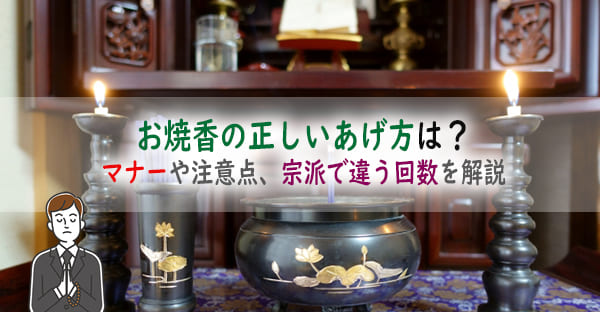
・弔問でお線香の正しいあげ方は?
・お墓参りでお線香の正しいあげ方は?
・お線香のあげ方にタブーはある?
・お線香のあげ方は、宗派で違うの?
・弔問できず、お線香をあげられない時はどうする?
お線香の正しいあげ方を理解しておくと、お通夜や葬儀後にご自宅を訪問する「弔問」や、お盆やお彼岸時期の帰省、お墓参りなどで役立ちます。
またお線香をあげる意味を理解することで、御仏前に適切なお声掛けができる、適切なタイミングでお線香をあげることができるでしょう。
本記事を読むことで、弔問や日々のお供養、お墓参りでのお線香の正しいあげ方やお線香の基礎知識、贈り方が分かります。

お線香の正しいあげ方

◇弔問では葬儀同様、お線香を正しい手順であげます
お通夜や葬儀に行けず、日を改めてご自宅へお線香をあげに行く行為が「弔問」です。
一般的に四十九日の忌中に弔問するとされますが、ご遺族も家族を亡くしてまだ心が落ち着かない時期でもあります。
そのため弔問する時は、事前にご遺族に連絡を取り、日程調整をするのがマナーです。
弔問の際は、濃紺やダークグレー、黒など、落ち着いた色合いで整えたお出かけ着「平服(略喪服)」で伺います。
そもそもお線香とは?
お線香のあげかたに細かなマナーがあるのは、長い歴史を持つためです。
お線香は遥か戦国時代まで遡る歴史のなかで、中国大陸から伝わり誕生しています。
●香木を細かく砕き、炭などと練り込み、細く形成した物が現代のお線香で、亡くなった人の「食事」です。
亡くなった人の魂を供養しますが、「四十九日まではお線香を絶やしてはいけない」いう風習を持つ地域もあります。
お線香を正しくあげる手順

◇ご家族に仏間に通された後、お断りをしてお線香をあげます
葬儀後、四十九日までの忌中であれば、まず「この度はご愁傷様でございます」などのお悔やみの言葉を伝え、ご遺族に仏間に通された後、「お線香をあげさせていただきます」など、ひと言お断りを入れてからお線香をあげましょう。
お仏前で一礼
「お線香をあげさせていただきます」とひと言お断りをした後、お仏壇前まで進んだら、お仏前で正座をして、お仏壇に向かって一礼します。
この時、ご遺族にも一礼すると良いでそう。
お線香に火を灯す
ご家族がロウソクに火を灯してくれることが多いですが、もしもロウソクに火を灯していなければ、「失礼します」とひと言、ご家族に伝えてから、仏壇のマッチなどを使って、ロウソクに火を灯しても構いません。
お線香は、ロウソクに火を付けた後、ロウソクの火にお線香をかざして火をつけます。
お線香の本数は仏教宗派により異なりますが、分からなければ基本的には1本です。
お線香の火を消す
お線香の火は、お線香を持つ逆の手で軽く扇ぎ火を消す方法が一般的です。
もしくはお線香をシュッと下に引くようにして、火を消すこともできます。
仏教の教えにおいて、人間の口は悪行を積みやく穢れやすいものなので、仏教的に口で吹き消すには向かないとされています。
お線香を香炉に立て、合掌
◇そのままお線香を香炉に立てた後、両手で合掌して一礼します
浄土真宗など、なかにはお線香を寝かせて供える宗派もありますので、予め確認をしておくと安心です。
ただ分からない場合は、香炉に立ててもそれほど失礼にはあたりません。
合掌した時、数珠の扱い方も宗派により異なります。
詳しくは下記コラムをご参照ください。
ロウソクの火を消す
お線香を立てて合掌し、故人のご冥福を祈った後、ロウソクの火を静かに消します。
ロウソクの火もお線香と同様、口で吹き消さないように注意をしましょう。
ロウソクの上から被せて火を消す仏具「火消し」あれば火消しを使い、ない場合は手で仰いでロウソクの火を消してください。
座布団から下がる
お線香のあげ方は宗派で違う

◇お線香の本数やあげ方は、宗派でも違います
宗派によるお線香のあげ方の大きな違いは、本数や立て方の違いになるでしょう。
不安があれば親族に事前に確認の連絡を入れると良いですが、お線香のあげ方の基本動作はほとんど一緒です。
ひと通りの違いを理解しておくと、先方に着いてから対応は可能です。
また、自分の仏教宗派によるお線香マナーに倣う方も見受けます。
| <宗派で違うお線香のあげ方> |
||
| [宗派] | [本数] | [立て方] |
| ①天台宗 | ・3本 | ・逆三角形に立てる |
| ②真言宗 | ・3本 | ・逆三角形に立てる |
| ③臨済宗 | ・1本のみ | ・真ん中に立てる |
| ④曹洞宗 | ・1本のみ | ・真ん中に立てる |
| ⑤日蓮宗 | ・1本、もしくは3本 | ・1本…真ん中に立てる ・3本…逆三角形に立てる |
| ⑥浄土宗 | ・決まりはない | ・決まりはない |
| ⑦浄土真宗 | ・1本 | (1)2つに折り火を灯す (2)横に寝かせて香炉に置く |
必ず相手の仏教宗派によるお線香のあげ方に添う必要はありませんが、先方に倣うと、より故人や相手の家への敬意、弔意を表すことができるでしょう。
お線香のあげ方:弔問できない時はどうする?

◇お線香を送り、弔意を表します
もしも海外在住などで、通夜や葬儀だけではなく、自宅への弔問も難しい場合には、ご遺族へ弔意を伝えて弔うため、お線香を送ると良いでしょう。
「ご進物」とも呼ばれる、仏前に供えるお線香は約3千円~7千円ほどが多く、桐箱などに納められたお線香のご進物も見つけるようになりました。
お線香には種類があるので、種類や特徴も理解して選ぶと安心です。
お線香の種類
お線香には大きく分けて「香り線香」と「杉線香」の2種類があります。
一般的にご進物として選ばれるお線香は香り線香ですが、杉線香はお墓参りなどで多く用いられるため、香りを嗅いで懐かしく感じる人も多いでしょう。
| <お線香の種類> |
|
| [種類] | [内容] |
| ①香り線香 | ●粉末にした木の皮が原料 ・伽羅(きゃら) ・白壇’びゃくだん) ・香木 ・炭 …などを配合 |
| ②杉線香 | ●粉末にした杉が原料 ・杉の香りがある ・お墓参りでよく使われる |
香り線香や杉線香にも特殊な形状があり、一般的に見る棒状ものの他、お通夜など長時間お線香を絶やさずに焚く必要がある場合の、渦巻き状のお線香があります。
お線香のあげ方:お線香の意味

◇お線香の意味を理解して、お線香をあげます
お線香の正しいあげ方を手順良く行うことも大切ですが、お線香をあげる意味を理解することで、心を込めた供養ができます。
お線香のあげ方が曖昧でも、自然と好感の高い行動を取ることができるでしょう。
①食事を供える
②心を通わせる
③自分の身や場を清める
お線香はご先祖様や故人だけではなく、仏様と繋がる煙の橋としても知られます。
お供養以外の意味では、生きる道に迷った時など、お伺いを立てる時に用いるとも言われてきました。
①食事を供える
◇亡くなった人の魂は「香」を食べるとされます
よく「霊媒師が太りやすいのは、故人の霊が霊媒師の体を借りて食事を楽しむため」などと言われるように、体を失った魂は食事を楽しむことができません。
…仏教では香りをいただくことを「食香(じきこう)」と言います。
特に亡くなられてから四十九日の間の魂は、まだあの世とこの世を彷徨う存在です。
そのため生きる者の食欲(食べ物)にも執着があるとされ、日々お線香を焚く家は多いでしょう。
②心を通わせる
◇お線香の煙を通じて、故人の気持ちを感じ取るとされます
亡くなった人は体を失っているため、生きる者と会話で絆を深めたり、ハグなど触れ合うこともできません。
けれどもお線香の煙を通じて、故人とこの世に生きる者との心が通じ合うとされてきました。
・偲ぶ気持ちに故人が気付く
お線香はあの世のこの世の掛け橋です。
お線香をあげる際には、日常で起こった出来事や思い出などを話すと、ご先祖様も喜ぶことでしょう。
③自分の身や場を清める
まとめ:お線香のあげ方は、故人を弔い心を込めます

お線香のあげ方は、その手順や作法も大切ですが、何よりも故人への贈り物として、心を込めて供えることが大切です。
またお通夜や葬儀に参列できずに、供物を送る時には、ご遺族へ向けて食べやすい渇き菓子などが人気ですが、故人へ向けてお線香を送る選択もあります。
またお墓参りのお線香は、香りによって虫も寄り付きにくく、場を清浄に保つ効果があるので、お線香選びを楽しみながらあげてみてはいかがでしょうか。
お電話でも受け付けております
















