
永代供養墓をわかりやすく解説!何年供養できる?選ぶポイントは?
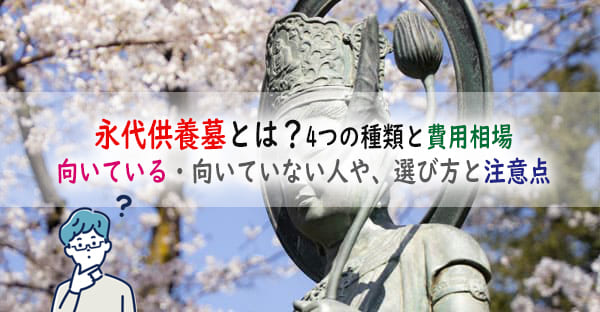
・永代供養墓とは?
・種類で違う費用相場は?
・向いている人、向いていない人は?
・デメリットや注意点は?
「永代供養墓」とは、墓地管理者が家族に代わりご遺骨を管理・供養する永代供養が付いたお墓です。そのため形は主に4種類、費用相場も形式も違いますが、いずれも継承者を必要としません。
本記事を読むことで、永代供養墓とはどのようなお墓か?4つの種類やそれぞれの費用相場、永代供養墓が向いている人やデメリットが分かります。

永代供養墓の特徴とは?

◇永代供養墓は継承者を立てる必要がありません
「永代供養(えいたいくよう)」とは墓地管理者が永代に渡り、家族に代わって遺骨を供養・管理する形のないサービスです。
「永代供養墓(えいたいくようばか)」は、永代供養サービスが付いたお墓ですので、永代供養墓を購入すると継承者を立てる必要がありません。
また「永代供養墓」の形式は納骨堂や合祀墓、個人墓までお墓の形式はさまざまです。
・永代供養とは?メリット・デメリットやリスクはなに?永代供養5つの種類を費用まで解説
「永代」とは永遠?
◇「永代」とは長い年月を意味し、永遠ではありません
永代供養の「永代」は永遠や永久と似たイメージがありますが、似て非なるものです。
永遠は無限の未来まで、際限のないことを表し、永久は果てしなく続くことを意味します。
けれども「永代」は長い年月を意味し、必ずしも永遠ではありません。
永代供養の場合、個別にご遺骨を安置する「個別安置期間」を契約時に定めるものが多いです。
個別安置期間が過ぎると一般的に合祀墓に合祀され、他のご遺骨と一緒に合同供養されますが、契約期間内に更新できる施設もあるでしょう。
個別安置期間に決まり事はないため、プランや施設によりさまざまです。
3回忌、7回忌など短い期間や、弔い上げとなる17回忌、33回忌、50回忌までとするプランもあります。
また寺院や霊園など、施設によっては続く限り永代に渡って個別にご遺骨を安置してくれる施設もあるでしょう。
永代使用の違いは?
◇永代使用(権)とは、永代に渡り墓地を使用する権利です
永代供養と永代使用は言葉は似ていても意味は全く異なります。
永代供養は、墓地管理者が家族に代わり、永代に渡ってご遺骨の供養や管理をしてくれることです。
一方「永代使用」は、墓地を契約(購入)した家族が、永代に渡り墓地を使用できる権利を指します。
現代の日本では、基本的に住宅地のように墓地を購入し、所有することはできません。
お墓を建てる場合、墓地を管理する霊園や寺院から、墓地区画を永代に渡り使用する権利「永代使用権」を購入します。
そのため契約した家族は、その墓地を永代に渡り使用することができますが、永代使用権を他者に売却することはできません。
供養する方法は?墓参りはどうなる?
◇永代供養墓の供養は合同供養が一般的です
一般的に永代供養墓に納骨した後、寺院や霊園など墓地管理者は定期的に合同供養、合同法要をします。
合同法要は春のお彼岸・お盆・秋のお彼岸に執り行い、家族が参加できるものも多いです。
ただ、納骨後の供養について決まり事はなく、施設によって違いはあります。
永代供養墓に納骨した後も、合同の慰霊碑を前に参拝できる施設が多いです。
お線香や供花、供物など、参拝ルールを設ける施設も多いので、規約を確認しましょう。
また回忌法要や祥月命日の法要を受け付ける寺院や霊園も多くあります。
僧侶による読経供養やお焼香、献花や供物など、お墓と同じ供養ができることが多いでしょう。
永代供養墓のメリット

◇永代供養墓は継承者を必要としません
永代供養墓の一般的なイメージは、最初から他のご遺骨と一緒に合祀される「合祀墓」「合葬墓」ですが、「永代供養墓」だからと言って、必ずしも合祀型ばかりではありません。
個別型の永代供養墓であれば、費用は掛かるものの、お墓と同じ形でご遺骨の供養をしながら、継承者問題が解消されます。
このように永代供養墓を選ぶ理由の筆頭は継承者がいない「継承者問題」です。
そして形のない「永代供養」は、予算や要望に合わせて選ぶことができます。
①継承者が必要ない
永代供養墓を選ぶことで、寺院や霊園など墓地管理者が家族に代わり、ご遺骨を永代に渡って供養・管理をしてくれます。
永代供養の形により、契約した一定年数が過ぎると施設内の合祀墓に合祀されますが、その後も定期的に合同供養をしてくれるでしょう。
そのため継承者がいない、後々まで継承者がいるか心配な方でも、現代において社会問題化している無縁仏・無縁墓になる心配がありません。
②生前契約が可能
永代供養墓に最も注目している世代は高齢の方々、ご自身のお墓に永代供養墓を選ぶためです。
お墓の維持管理はどうなるのか?無縁仏にならないか?ご遺骨を供養してくれる家族がこの世にもういない、など、自分亡き後のご遺骨の供養に不安を覚える方は少なくありません。
また子どもや孫がいても、お墓の維持管理や建墓費用など、子どもに負担をかけたくない方も多いです。
永代供養墓であれば、生前に自分で墓地見学に行き決めた後、寺院や霊園と生前契約をすることで、安心できます。
③寺でも宗旨宗派を問わない
寺院墓地以外の永代供養墓は一般的に宗旨宗派を問いません。
代々先祖代々墓を継承するなかで、お墓が建つ寺院墓地を運営する「菩提寺」とのお付き合いに疲弊した、子どもや孫への負担を軽減したい、などの理由で墓じまいを決断する方も多くいます。
霊園などの永代供養墓であれば、墓じまい・離檀した後でも宗旨宗派を問わずに契約できるでしょう。
また寺院墓地でも永代供養墓であれば、宗旨宗派を問わない寺院が多いです。
ただしなかには、条件として檀家になることを求める寺院もあるため、確認してください。
永代供養墓のデメリット|墓石を墓標としない

◇永代供養墓は、まだまだ新しい供養の形です
仏教が広まるその前から、ご先祖様を敬う民間信仰「祖霊信仰」が根付く日本では、古くから先祖代々墓や家墓など、ご先祖様が入るお墓を守る風習がありました。
一方、個人のご遺骨をご家族に代わり、寺院や霊園や供養・管理をする「永代供養墓」が広まり始めたのは、1980年代頃からとされます。
そのため永代供養墓への理解は、世代や考え方により、さまざまであることを理解して進めると良いでしょう。
①家族・親族との相談
◇永代供養墓への理解を得られない可能性があります
古くからの風習である日本のお墓は先祖代々墓や家墓であり、日本の人々は家に属し、自分が亡くなったら先祖代々墓に入ると考えてきました。
対して、1980年代から広まった永代供養墓は個人のご遺骨に対する供養であり、最終的には、他のご遺骨と一緒に合祀され、合同供養されます。
そのためなかには「家のお墓がないなんて!」「家のお墓に入らないなんて!」「他人と一緒に合祀されるなんて!」と、家族や親族から反対されるリスクも考慮しなければなりません。
なぜ永代供養墓を選んだのか、お墓を維持管理する負担や継承者問題などを相談し、理解を得ていくと良いでしょう。
②ご遺骨は最終的に合祀される
◇ご遺骨は最終的に合祀されます
先祖代々墓(家墓)は、地域や家により異なりますが、お墓下のカロートに骨壺に入れたご遺骨を納骨し、代々継承者がお墓を守るものです。
けれども永代供養墓のなかには納骨堂や集合墓など、一定期間の個別安置期間を設けたプランもありますが、最終的には、他の方と一緒に合祀され、合同供養されます。
合祀する時、ご遺骨は骨壺や骨袋から出して、他のご遺骨と一緒のカロートに納骨されますから、一度合祀をすると、再び個別に取り出すことはできません。
そのため合祀の後から改葬(ご遺骨の引っ越し)や、手元供養への切り替えができないことを理解しましょう。
最も安い永代供養墓の種類|費用相場と選び方

◇最も安い永代供養墓は合祀型で、約3万円~10万円以上です
納骨堂型や個人墓型など、さまざまな形式がある永代供養墓のなかでも、最も費用を安く抑えることが可能な種類は合祀型となります。
| <永代供養墓の4つの種類と相場> | |
| [種類] | [費用相場] |
| ①合祀型 | ・約3万円~10万円 |
| ②納骨堂型 | ・約10万円~200万円 |
| ③樹木葬型 | ・約5万円~100万円 |
| ④個人墓型 | ・約100万円~200万円 |
合祀型の永代供養墓の費用相場が安い理由は、個別の墓石が必要ないこと、また、個別のスペースを必要としないことが大きいです。
①合祀型の永代供養墓

◇合祀型の永代供養墓の費用相場は、約3万円~10万円です
合祀型の永代供養墓は、ご遺骨を骨壺から取り出して、他のご遺骨と一緒に合祀埋葬する永代供養の形です。
そのため一度ご遺骨を埋葬すると、後から取り出すことはできません。
後々、お墓を建ててご遺骨の引っ越しをする「改葬」を望むならば、納骨堂など、遺骨が残る永代供養墓を選ぶと良いでしょう。
②納骨堂型の永代供養墓

◇納骨堂型の永代供養墓の費用相場、費用相場は約10万円~200万円です
「納骨堂(のうこつどう)」とは屋内にご遺骨を安置する施設です。
費用相場が約10万円~200万円と幅があるのは、納骨堂システムによるものが大きいでしょう。
また法要室があるなど、施設のグレードによっても価格帯が大幅に変わります。
納骨堂にはロッカー式、仏壇式、自動搬送式など、タイプはさまざまです。
ロッカー式は昔からあるタイプで、ロッカーにご遺骨を納めるため、最も安い費用相場で契約ができます。
| <納骨堂型の永代供養墓:費用相場> | |
| [種類] | [費用相場] |
| ①ロッカー式 | ●約10万円~80万円/1柱 (低め傾向) |
| ②仏壇式(霊廟型) | ●約30万円~250万円 ・個人…約30万円~ ・家族…約100万円~ (中間層) |
| ③自動搬送式(ビル型) | ●約50万円~150万円/1柱 (高め傾向) |
納骨堂の永代供養墓はご遺骨が残るため、後々お墓を建ててご遺骨を埋葬することも可能です。
ただし契約した一定の年数のみ、個別にご遺骨を安置し、その間は年間管理料(約5千円~3万円ほど)が掛かります。
契約更新がされないまま、契約した一定年数が過ぎると、合祀墓に合祀埋葬されるシステムが一般的です。
③樹木葬型の永代供養墓

◇樹木葬型の永代供養墓、費用相場は約5万円~100万円です
樹木葬型の永代供養墓もシンボルツリー型(合祀型)や個別型、ガーデニング型とさまざまな種類があるため、費用相場の幅も広くなります。
| <樹木葬型の永代供養墓:費用相場> | ||
| [種類] | [内容] | [費用相場] |
| ①シンボルツリー型 (合祀型) |
・1本の樹木のふもとに合祀 | ・約5万円~20万円 |
| ②個別スペース型 | ・1本の樹木のふもとに個別で埋葬 | ・約15万円~80万円 |
| ③個別植樹型 | ・ご遺骨1柱に1本の樹木を植樹 | ・約20万円~100万円 |
| ④里山型 | ・山林奥深く、大樹のふもとに埋葬 | ●約5万円~80万円 ・合祀埋葬…約5万円~ ・個別埋葬…約30万円~ |
| ⑤ガーデニング型樹木葬 | ・草花薫る庭園に小さな墓石 | ●約60万円~150万円以上 ・個人…約60万円~ ・2人…約100万円~ ・家族…約150万円~ |
樹木葬型の永代供養墓も霊園や施設により、環境や設備は大幅に異なるため、後々まで手厚く供養がしたいならば、現地見学は欠かせません。
樹木葬は自然に還る自然葬の一種なので、一度埋葬したご遺骨は取り出すことができないので、予め供養の頻度や設備など、気になる点があれば確認しましょう。
④個人墓型の永代供養墓

◇個人墓型の永代供養墓、費用相場は約100万円~200万円です
個人墓型の永代供養墓とは、個人墓に永代供養サービスを付けたお墓です。
永代供養墓は形のない永代供養が付いたお墓なので、一般墓に永代供養を付けることもできます。
ただ墓石を建てて永代供養を付けるため、継承者は必要ありませんが、墓石や墓地に費用が掛かります。
| <個人墓型の永代供養墓を建てる人> | |
| ①継承者がいない | ・おひとりさま終活 ・子や孫に負担を掛けたくない |
| ②同世代だけで入る | ・夫婦墓 ・友墓 |
墓石を建てる一般墓でも、継承者を必要としない永代供養が付いているため、夫婦や血縁関係のない友人同士など、同世代のみで入るお墓が可能です。
また自分ひとりが入る「個人墓」も永代供養墓にすることで、建てることができます。
永代供養墓が向いている人

◇継承者がいない人には永代供養墓が最適です
永代供養墓は、家族・親族がお墓の継承や管理を必要としないことが何よりのメリットなので、継承者がいない、立てたくない人ならば永代供養墓が向いているでしょう。
おひとりさま終活をしている人
◇おひとりさまのご遺骨を墓地管理者が管理・供養してくれます
おひとりさま終活で、お墓のお世話をしてくれる人の目当てがない人なら、永代供養墓が安心です。
「死後事務委任契約」は、永代供養墓を提供する墓地や霊園で相談すると、焼成書士や司法書士など、信頼できる第三者を紹介してくれる施設が多いです。
継承者がいない人
◇永代供養墓の最も大きなメリットは、継承者が必要な点です
子どもがいないご夫婦や独身者、親戚とも疎遠になっているなど、継承者に目当てがない人々でも、無碍にお墓を放置される心配がありません。
永代供養墓はご遺骨の管理だけではなく、定期的な供養も行ってくれるため、無縁仏になる心配がありません。
夫婦墓を建てたい人
◇夫婦墓や友墓など、同世代で入るお墓も可能です
継承者が必要ない永代供養墓であれば、先祖代々墓に入らず、2人でお墓を建てたいご夫婦にも、永代供養墓が多く選ばれています。
継承者を必要としないため、同世代のみでお墓に入ることができるため、夫婦墓の他にも、血縁関係のない同世代で入る「友墓(ともばか)」も可能です。
終活仲間で永代供養墓を建て、友墓とするケースもあります。
墓じまいをしたい人
◇複数のご遺骨が手元に残る墓じまいで、安価にご遺骨を供養できます
「墓じまい」とは、お墓を閉じて撤去することで、墓じまいにより取り出したご遺骨は手元に残ってしまいます。
また、墓じまいを済ませた人の自分が入るお墓としても、お墓を後々まで残さない永代供養墓が選ばれます。
子や孫に負担をかけたくない人
◇継承者が必要ないため、子や孫に負担が掛かりません
将来はお墓の継承者となり得る子どもや孫がいても、「負担を掛けたくない」と永代供養墓を選ぶ人も増えました。
お墓を継承すると定期的な掃除や法要の主催など、肉体的な負担も掛かりますが、それ以上に、年間管理料など経済的な負担も掛かるでしょう。
将来的に継承の可能性があるならば、納骨堂や個別墓など、一定年数はご遺骨が残る形式を選ぶと良いでしょう。
お墓を安くおさめたい人
◇墓石を建てない永代供養墓であれば、お墓を建てるよりも安くおさまります
合祀型や樹木葬型の永代供養墓であれば、納骨後に掛かる費用もないでしょう。
ただし納骨堂型や個人墓型の場合、一般墓と同じように建てた後の年間管理料が掛かります。
一方、個別のスペースや墓地を持たない合祀型には、年間管理料が発生しません。
宗教的なしがらみから抜けたい人
◇永代供養墓の多くが宗旨宗派を問いません
葬儀での読経供養や法要など、仏教に基づいた儀式を行わず、無宗教を望む人には向いています。
また寺院墓地の墓じまいにより離檀して、宗教的に自由になった人々も宗教的なしがらみのない、永代供養墓を選ぶ人が多いです。
永代供養墓に向いていない人

◇先祖代々墓を残して手厚く供養したい人には向いていません
永代供養墓は墓地管理者が家族に代わり、お墓やご遺骨の管理や供養を行ってくれますが、ご遺骨やお墓が永代に渡り残るものではありません。
永代供養墓でご遺骨が個別に残る期間は、契約したプランによりさまざまです。
なかには約33年、50年と、半世紀近くご遺骨が残る契約もありますが、残された家族が契約更新をしない限り、いずれは合祀されます。
ご遺骨はいずれ合祀される
◇ご遺骨の合祀に抵抗がある人は向いていません
永代供養は契約更新をしない限り、いずれ合祀されるため、合祀に抵抗を感じる人は、継承できる一般墓が向いています。
高齢の家族や親族のなかには、「知らない人のご遺骨と一緒なんて」「体がバラバラになってしまう」と抵抗を感じる人もいるので、家族への配慮も必要です。
家族や親族の理解が不可欠
◇家族や親族の理解を得られず、トラブルに発展するケースもあります
永代供養墓は比較的近代の考え方による、ご遺骨の供養方法です。
そのため「先祖代々墓を継承し、残していくべき」とする家族や親族がいる場合、説得が難しいこともあるでしょう。
お墓の管理や継承が難しい現状など、永代供養墓を選んだ経緯を伝え、合意を得てから契約を進めましょう。
後々はお墓を建てたい
◇永代供養墓は合祀されると、個別に取り出すことができません
特に合祀型の永代供養墓は、すぐに他のご遺骨と一緒に合祀されます。
そのため後々新しいお墓を建てても、一度永代供養墓に埋葬したご遺骨を、個別に取り出して、新しいお墓に納骨することは不可能です。
納骨堂や個別墓型の永代供養墓の他、永代供養が付かない納骨堂などを選ぶ方法もあります。
永代供養墓によくある質問

永代供養墓は、お墓の継承者がいない現代の悩みに寄り添った、まだまだ新しいお墓の形なので、分からない部分や不安な点もあるでしょう。
お墓を継承すると年間管理料をはじめとする経済的負担はもちろん、今では遠方に暮らす継承者が定期的なお墓参りができず、墓じまいをして永代供養墓を選んでいます。
大きな決断ですので、よくある質問も確認してから、永代供養墓を選ぶと安心です。
永代供養墓のデメリットは?
◇永代供養墓のデメリットは、将来的にはご遺骨は合祀埋葬される点です
合祀型や樹木葬型の永代供養墓では、一度埋葬したご遺骨を取り出すことはできません。
ただし納骨堂や個別墓など、一定期間は個別にご遺骨が安置される永代供養の形式もあります。
なかには契約期間中に更新をすることで、個別安置期間が延長されるシステムもあるので、確認をすると良いでしょう。
納骨後の参拝や法要はできる?
◇永代供養墓では、納骨後の参拝や個別法要も可能な霊園や施設が多いです
合祀型の永代供養墓であれば、合同の参拝所を設けた施設もあるでしょう。
また事前に予約をすることで、墓前での個別法要を受け付ける施設もあります。
納骨堂では、法要室を設けた施設もあるほどです。
ただし公営施設など、個別法要を受け付けないこともあるので、契約時には確認をしましょう。
永代供養墓は本当に「永代」?
◇永代供養墓を管理する霊園や施設が存続する限り、永代に渡り定期的な供養が行われます
ただし納骨堂や個別墓など、個別でご遺骨が安置される永代供養墓であれば、契約した一定年数過ぎると、ご遺骨は合祀され、他のご遺骨とともに合同供養となるでしょう。
契約前に個別安置期間を確認するとともに、期間内の契約更新ができるどうかも確認すると安心です。
永代供養墓に納骨すると、供養は何年?
◇永代供養墓に納骨すると、契約した霊園や施設が存続する限り供養は永代です
霊園や施設が倒産しない限り、故人は永代に渡る供養が行われるでしょう。
けれども、ご遺骨を個別に安置するスペースや墓地には「使用期限」があります。
比較的多い年数は、弔いあげが行われる10回忌、33回忌などです。
使用期限が過ぎると、ご遺骨は合祀されるので、契約時に使用期限と、契約更新の可否を確認してください。
費用は毎年払うもの?
◇永代供養墓で費用が発生するタイミングは、一般的に契約時の一度のみです
特に合祀型や樹木葬型の永代供養墓は、一度の支払いで済むでしょう。
一方、ご遺骨の個別安置スペースが提供される納骨堂や個別墓では、使用期間内は年間管理料(約5千円~3万円/年間)が発生します。
終活による契約の場合、契約期間内の年間管理料もまとめて支払うシステムが多いです。
終活では、生前契約で支払いは終わるの?
◇永代供養墓は終活による生前契約で完結できます
継承者を必要としない永代供養墓は、生前契約で個人墓を建てることも可能です。
霊園や寺院墓地に永代供養墓を建てるケースでも、区画内にお墓が建っている間は、状況により下記の料金を定期的に払います。
| <個別スペースがある場合> | |
| ・年間管理料 | …公共施設の管理料金 |
| ・更新料 | …永代供養墓の更新料金 |
終活による生前契約では霊園や寺院によって、これらのランニングコストを、生前にまとめて支払うプランもあります。
ただし霊園や寺院、プランによって契約内容はさまざまですので、事前に確認をして契約を進めてください。
・終活でお墓を準備するメリットはある?デメリット・お墓選びのポイント、気を付けること
永代供養墓と一般墓の違いは?
◇永代供養墓は一般墓と違い、無縁仏の心配がありません
そもそも「永代供養墓」は、核家族化が進む1980年代、継承者問題が表面化したことで登場しました。
一般墓は代々継承し、継承者である「墓主」は墓地の管理や供養を担います。
この負担の大きさから、継承者のない放置された無縁仏が急増しました。
将来的に自分がお墓に入っても、継承者に不安があれば、無縁仏になる心配が生じるでしょう。
放置され朽ちた後、自治体により撤去され、どこの誰だか分からない、名前のないまま、無縁仏として供養塔に合祀される流れは、避けたい人々がほとんどです。
霊園のお墓はみんな永代供養墓って本当?
◇現代は多くの霊園で、永代供養が付いているお墓を基本に提供しています
現代では墓主が亡くなると、次の継承者がいないまま、責任の所在が分からず放置されたままの先祖代々墓が増えました。
霊園や墓地管理者側が撤去しようにも、墓主への許可も得られないなど、リスクや問題も多いため、永代供養墓を基本とする霊園が増えています。
一定年数が過ぎると霊園や墓地管理者により、墓主(継承者)の許可なくして撤去できるためです。
永代供養墓を選ぶポイント

◇永代供養墓は、公共機関で見学に行くと良いでしょう
百聞は一見にしかず、永代供養墓を選ぶポイントは見学です。
納骨後も定期的な参拝を予定しているならば、どのような状況でもお参りしやすい立地も大切になるでしょう。
郊外の霊園や墓地であれば、将来的に高齢になり、車の運転ができなくなっても参拝しやすい、アクセス環境もチェックしたいところです。
費用で選ぶ
◇永代供養墓の種類やサービス内容も併せ、総合的に判断します
永代供養墓を費用で選ぶ場合、総費用には何が含まれるのか、何が追加料金になるのかを明確にした比較検討が必要です。
費用や維持費は、パンフレットなどに詳細が記載されています。
分からない点は担当者に確認し、その対応もチェックしましょう。
・年間管理料の発生や払い方
・ローンや分割払いへの対応
・申込者ごとの料金の違い(1人、夫婦で違うか?)
・供養に関するオプション設定
なかには年間管理料が、管理費と維持費に分かれているプランもあります。
またローンや分割を利用する場合、自社で提供する分割払いは支払い回数が限られていることもあるでしょう。
経営母体で選ぶ
◇寺院墓地・民間霊園・公営墓地、それぞれの特徴があります
永代供養墓を扱う霊園や墓地は、寺院墓地・民間霊園・公営墓地のいずれかになるでしょう。
寺院墓地でも特に合祀型の永代供養墓では、宗旨宗派を不問とする寺院が増えましたが、なかには宗教的な条件を課す墓地もあります。
永代供養墓に納骨するにあたり、宗旨宗派に帰依し檀家になる必要があるのかも確認しましょう。
設備やサービスで選ぶ
◇永代供養墓は参拝した時を想定して、実際に見学します
合祀型の永代供養墓であっても、現代は供養塔を前に参拝できる施設が多いです。
納骨堂型でも同じで、参拝やお線香、献花などの規約がそれぞれ違います。
また定期的に合同供養を執り行う施設が多いですが、毎月か3か月ごとか、どれくらいの頻度で合同供養が行われるのか、家族の参列は可能かもチェック項目です。
実際に見学してみて、アクセスの良さやトイレやゴミ捨て場、水場などの整備状況もチェックしましょう。
・永代供養の選び方とは?場所や費用などのポイントや注意点も紹介
永代供養墓の注意点とは

◇契約内容をしっかりと確認し、分からない点は担当者に確認します
納骨堂型や個別型の永代供養墓であっても、一定年数を過ぎると撤去され、施設内の合祀墓に供養されます。
永代供養墓が永代に渡り供養・管理をする対象は、故人の魂であり遺骨です。
そのためお墓が永代に渡り残る訳ではありません。
| <永代供養墓は一定期間後、撤去される> | |
| [契約時] | ・契約年数を確認する |
| [残したい場合] | ・契約期間内に更新する |
納骨堂型や個別型の永代供養墓は契約年数をチェックし、年数の延長ができるかどうかも確認しておきます。
・永代供養と永代使用の違いとは?管理費との違いや「墓じまい」についても解説
納骨堂型や個別型の年間管理料
◇納骨堂型や個別型の永代供養墓は、年間管理料が掛かります
個別型の永代供養墓はお墓ですので、霊園や寺院墓地の一区画に建てます。
「永代供養」料金は契約時に支払いますが、建墓後の年間管理料は、永代供養墓が霊園に建つ限り、毎年掛かるので注意をしてください。
| <永代供養墓の年間管理料> | |
| ●年間管理料の費用目安 | …約5千円~3万円 |
| (平均約5千円~1万5千円) | |
ただし永代供養墓を個別に残す契約期間が終わり、お墓が撤去された後は、遺骨は合祀墓に入るため、年間管理料を支払う必要はありません。
また年間管理料は施設によって違うでしょう。
公営墓地であれば料金は抑えられ、約2千円~5千円ほどが目安です。
・霊園とはなに?墓地とは違う?民間霊園・寺院墓地・公営墓地のメリット・デメリットとは
まとめ:永代供養墓であれば無縁仏の心配がありません

家族に代わり永代に渡り遺骨の管理や供養を行ってくれる「永代供養墓」は、故人の家族や子孫にとっても、霊園管理者にとってもメリットが大きいです。
| ・家族や子孫 | …霊園や墓地管理者に管理や供養を任せられる |
| ・霊園や墓地管理者 | …手続きが複雑な無縁墓の撤去がしやすい |
ただ個別型の永代供養墓はお墓に永代供養を付けたものなので、墓石代金など約100万円~175万円ほどと、コンパクトなお墓でも割高にはなるでしょう。
少しでも安く抑えたい場合には、合祀型や納骨堂型など、違うタイプの永代供養も検討してみてはいかがでしょうか。
「遺骨を残したい」「墓標が欲しい」など、それぞれの目的や状況に合わせて、ムリなく決めていきましょう。
・お墓がない・予算がない時、遺骨はどうすればいい?お墓を持たずに供養する6つの選択肢
お電話でも受け付けております















