
終活でお墓を準備するメリットはある?デメリット・お墓選びのポイント、気を付けること

・そもそも「終活」とは?
・終活でお墓を準備するメリットは?
・終活でお墓を準備するデメリットは?
・終活で準備するお墓の選び方は?
・終活のお墓準備でトラブルにならないポイントは?
人生の終わりへ向けた活動「終活」ではお墓の準備が大きな柱のひとつです。
せっかく終活でお墓を準備するなら、残された子ども達が助かる、メリットを享受したお墓を選びたいですよね。
本記事では終活でお墓を準備するメリット・デメリット、後々後悔しないお墓の選び方をご紹介します。
本記事を読むことで、終活でのお墓の準備が、自分や残された家族にとって役立つものとなるでしょう。どうぞ最後までお読みください。
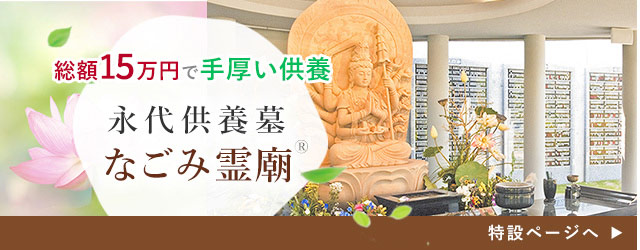
終活でお墓の準備:そもそも終活とは?
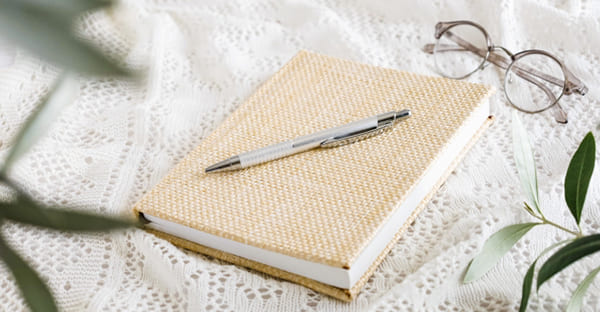
◇「終活」とは、人生の終わりを見越して準備を行うことです
終活を行うのにタイミングはありません。一般的には定年後、自分亡き後の相続や事務処理に残された家族が困らないように行いますが、20代・30代からでも構いません。
一般的に終活のガイドラインとしてエンディングノートに記入をしながら進めますが、具体的には下記に上げる3つの柱を整えます。
終活でお墓の準備:相続対策
◇相続対策では、財産の整理・相続対策を行います
財産目録を作成して財産の整理をしておくと、残された家族は期限に追われるなかで、財産や相続人の調査を行わずに済み、スムーズに相続が進むでしょう。
・財産目録で財産を整理する
・遺言書で相続の希望を記入する
特に遺言書を書いておくと、相続人同士の分割会議「相続分割会議」とスキップして相続が進むため、残された家族にとっては対異変助かります。
終活でお墓を準備する際には継承者を話し合い決めるとともに、お墓の存在も明記しておくと良いでしょう。
終活でお墓の準備:葬儀の準備
◇終活2つ目の柱は、葬儀の準備です
一般的な葬儀「一般葬」から、家族など10名ほどで執り行う小規模の「家族葬」、火葬場で全てを済ませる「直葬」など、葬儀も多様になりました。
・葬儀の生前契約をする
・葬儀費用を生前に支払う
本人が葬儀の生前契約を行い遺言書に残すことで、家族葬や直葬など、親族には理解されにくい新しい形の葬儀を執り行ったとしても、残された家族に批判が向けられません。
また亡くなった人の銀行口座は凍結されますが、生前に支払うことで、残された家族は費用面の不安なく、葬儀を執り行うことができます。
生前にお墓を準備することで、近年では葬儀当日の納骨式も増えました。
終活でお墓の準備:お墓
◇終活でお墓の準備を済ませることで、残された家族は負担のない納骨ができます
人は亡くなると火葬され、必ず遺骨になります。納骨するお墓がない場合、一般的に残された家族は1周忌を目安にお墓を準備し、納骨式を行うことになるでしょう。
けれどもお墓は平均的に150万円以上、お墓の準備は経済的にも労力的にも負担が大きいものです。
・遺骨をどうするか?
・お墓を準備する
そもそも「お墓はいらない」と言う人も遺骨は残りますので、自然葬や永代供養墓など、遺骨をどうするか?を決めて、生前契約を行います。
終活でお墓を準備するメリット

◇終活でお墓を準備することで、残された家族の精神的・経済的負担を軽減します
終活で本人が生前にお墓を準備することで、何よりも残された家族はお墓を購入せずに済み、いつでも納骨式を執り行うことができるでしょう。
特に近年人気の樹木葬や自然葬など、長く一般的だった「一般墓」ではない場合、終活で本人がお墓を準備することで、残された家族を親族の反対や批判から守ることができます。
終活のお墓準備①家族の負担が軽減する
◇終活でお墓を準備することで、家族は多くの負担が軽減します
人が亡くなった時に納骨するお墓がない場合、四十九日法要や一周忌を目途にお墓を建てます。また納骨式まで、遺骨は自宅や納骨堂などで安置しなければなりません。
(1)期限内にお墓を建てる
(2)遺骨の安置
・納骨堂約点3,300円~15,000円/月ほど
(3)費用の負担
(4)親族への配慮
(5)遺骨の扱いを決定する負担
2021年の調査では一般墓の平均購入価格は169.0万円、また購入者の25%は80-119万円でお墓を購入していることが分かりました。若い多くの世帯で、簡単に購入できる価格ではありません。
[参考]【第12回】お墓の消費者全国実態調査(2021年)
終活のお墓準備②相続税対策
◇終活でお墓を準備した場合、お墓に相続税が掛かりません
相続法ではお仏壇やお墓などの「祭祀財産」には相続税が課税されませんが、財産には当然相続税が掛かります。残された家族がお墓を継承した場合、相続税が掛かりません。
(1)祭祀財産…供養に必要なもの(仏壇仏具・お墓など)
(2)相続財産…不動産や預貯金財産など
仮に5,800万円を子ども1人が相続すると相続税額は約160万円、現金一括払いです。故人が終活で300万円のお墓を購入していたらどうなるでしょうか? 6,100万円(5,800万円+300万円)の相続税額が約310万円なので、約150万円の節税対策になります。
終活のお墓準備③いつでも納骨できる
◇終活でお墓を準備することで、一般的な四十九日法要後の納骨ができます
納骨するお墓がないとお墓を建てる家族が多いです。けれども一般的にお墓は契約してから1ヶ月~3ヶ月以上、お墓選びから始めるとなれば、半年は余裕を見ると良いでしょう。
この間、残された家族は遺骨を自宅や納骨堂などで安置しなければなりません。
・葬儀当日
・四十九日法要の後
・一周忌の後
本来、納骨式はいつ行っても良いのですが、一般的に納骨するお墓がある故人の遺骨は、忌中を過ぎた四十九日法要の後に行われます。近年では葬儀当日の納骨式も増えました。
終活のお墓準備④理想のお墓が実現する
◇終活で本人がお墓を建てることで、理想のお墓を確認できます
自分のお墓を見ることは生前に、終活でお墓を準備するからこそです。家族と話し合いながら、自分も残された家族も納得できるお墓が建つでしょう。 終活では本人が自由にお墓を準備するため、人気のお墓の傾向も下記のように違います。
・永代供養墓
・夫婦で入るお墓
・樹木葬(自然葬)
・ペットと入るお墓
・洋墓にメッセージを入れる
現代も家族で入る先祖代々墓は建てられますが、終活でお墓を準備する人々は、「亡くなったら気楽に過ごしたい」と、個人や夫婦のみが入る永代供養墓を選ぶ傾向です。
「永代供養墓」とは継承者を必要とせず、家族の代わりに霊園の管理御者が永代に渡り遺骨を管理・供養する「永代供養」が付いたお墓です。
・【おひとりさま終活】お墓をどうする?独り身でも安心、お墓がいらない永代供養の選び方
終活のお墓準備⑤親族トラブルが軽減する
◇終活で本人がお墓を準備することで、残された家族は親族から反対や批判を受けにくくなります
例えば、生前に口約束で子どもに「土に還る自然葬にしたい」と託すなどのケースです。 残された子どもが親族から「親が可哀そう」などと反対されるトラブルは多くあります。
・先祖代々墓に入りたくない
・自然葬など、新しい供養を希望している
・墓じまいをして、永代供養墓にしたい
「墓じまい」とは、今までの先祖代々墓を閉じて継承者を必要としない納骨先に切り替えることです。
長年墓守をしてきた本人が墓じまいをして、継承者を必要としない形に切り替えることで、子どもや孫がお墓を継承しなくても、親族の批判から守ることができます。
・大阪の墓じまいで選ぶ6つ選択肢とは。墓じまいの改葬(お墓の引っ越し)では何が違う?
終活でお墓を準備するデメリット

◇終活でお墓を準備するデメリットは、納骨していないお墓の管理です
終活でお墓を準備することで、納骨していないお墓が建つことになります。それでも霊園にお墓を建てたなら、お墓の管理をしなければなりません。
ただし「お墓」のなかには自然葬や合祀墓もあるでしょう。このようなお墓であれば、終活でお墓を準備するデメリットが大きく軽減されます。
①自然葬を生前契約する
・樹木葬
・自然葬
②合祀墓を生前契約する
ただし多くの自然葬や合祀墓では、一度埋葬されると遺骨を取り出すことができません。 また合祀墓になると、個別に手を合わせる墓標ではなく合同の供養塔でしょう。
・【自然葬の種類】自然葬の種類と特徴。個別の墓標を残す自然葬もあるの?|永代供養ナビ
終活のお墓準備①管理料
遺骨が埋葬されていないお墓でも、霊園にお墓が建つ限り管理料がかかります。管理料を滞納すると、せっかく購入したお墓は撤去されてしまうでしょう。
・年間管理料の相場…約2,000円~15,000円ほど
終活でお墓が準備できる霊園の年間管理料は、一般的には約10,000円前後です。納骨堂でも年間管理料が掛かるので、注意をしてください。
終活のお墓準備②遺骨がない
◇公営墓地では、遺骨がないと墓地契約ができない規約が多いです
墓地・霊園は経営母体によって、「民間霊園・寺院墓地・公営墓地」3つの種類があります。なかでも自治体が運営する公営墓地は、納骨できない家族へ墓地を提供する目的です。
・公営墓地…遺骨がないと契約できない
・寺院墓地…遺骨がないと、一部契約できない
・民間霊園…遺骨がなくても契約できる
※一般的な傾向です。墓地・霊園によっても違います。
公営墓地は費用も割安ですが、墓地購入も抽選があり要件を満たさなくてはなりません。この他、寺院墓地のなかにもご住職の方針などにより、遺骨のない墓地契約ができない墓所もあるでしょう。
・【大阪のお墓】寺院墓地・公営墓地・民営墓地を選ぶには?それぞれのメリットデメリット
終活のお墓準備③メンテナンス
◇遺骨がないお墓でも、定期的なメンテナンスが必要です
遺骨がないお墓でも霊園に墓石のお墓が建つ以上、定期的に掃除をする必要があります。また細かな部分では、墓石も家と同じように少しずつ劣化するでしょう。
・定期的な掃除
・修繕のタイミングが早くなる
御影石であっても屋外なのでいずれは劣化があります。ただ硬度が高い墓石は水が入り込みにくく、劣化もゆっくりになるでしょう。
終活のお墓準備④親族
◇まだ亡くなっていないうちから終活でお墓を準備するため、家族や親族のなかには嫌がる人もいます
そもそも人生の終わりに向けて準備をする「終活」も、必ずしも全ての人に受け入れられている訳ではありません。
●ただし生前に建つお墓は「寿陵墓(じゅりょうぼ)」と呼ばれ、歴史のなかでは世を統べる物が生前に建てることも多い縁起の良いものです。
何よりも自分のために終活でお墓を準備するのですから、よくよく家族で話し合い進めると良いでしょう。
・墓じまいや仏壇じまいで親族間トラブル☆話し合いがまとまらない事態を解決した3つの対策
終活で準備するお墓の選び方

◇終活でお墓を準備するなら、家族との話し合って進めます
お墓は残された家族が参るものです。自分亡き後は家族がお墓の維持管理、お参りを行うため、自分のお墓であっても家族との話し合いが大切です。
●「家族に負担を掛けたくない」として、合祀墓や自然葬など、終活では遺骨の残らないお墓を準備する人も多いですが、お墓参りがしたい家族もいます。
残された家族にとっては、お墓参りが哀しみを癒すグリーフケアになることも多いのです。
終活のお墓準備①予算を決める
◇お墓は価格幅が広いため、最初に予算と優先順位を決めます
お墓には大量生産の規格墓と、オリジナルの注文墓がある他、石材のランクなどによっても大幅に価格帯が変化するので、まず予算立てが不可欠です。
・規格墓か注文墓か
・石材のランク
・彫刻の複雑さ
・墓地の広さ
・墓地の立地
このような部分で価格に差が出てきます。特に立地環境は交通の便もあり、お墓参りに関わることなので、家族で見学をしながら優先順位を決めていきましょう。
終活のお墓準備②継承者
終活のお墓準備③見学
◇家族と希望のエリアや条件を相談し、複数の霊園を見学します
家族がお墓参りに行くため、霊園見学はできれば家族と行きたいところです。
1日に複数の霊園を回るならば3件ほどを目安とし、最初の霊園での印象が残るように、メモを残したり、写真を撮るなどします。
●家族での話し合いは、記憶が鮮明に残っている当日が良いでしょう
住まいと同じくお墓見学も体力とパワーが必要です。「終活はもっと後で良い」と言う人もいますが、早めの終活を勧める人が多いのは、このためでしょう。
・お墓を購入する注意点とは?見学・契約時に確認するチェックポイント|購入の手順も解説
終活でお墓を準備する注意点

◇最終的にお墓の契約をする時には、規制がないか確認します
最終的にお墓の契約をする前に、規約を確認して将来的に子ども達が困ることがないよう、規制の確認が重要です。
・宗旨宗派の自由
・お墓に入る人の自由
・お墓を残す自由
お墓は子や孫の世代まで続くため、将来的にどのような形にも変更できるよう、宗旨宗派や入る人、契約期間はできるだけ規制の少ない墓地・霊園に越したことはありません。
いざとなればお墓の引っ越し「改葬(かいそう)」などの方法もありますが、労力を要します。
終活のお墓準備①宗旨宗派
◇終活でお墓を準備する場合、菩提寺との関係や宗旨宗派の確認をします
菩提寺がある場合、菩提寺のご住職との関係にも配慮が必要です。特に墓主であれば今までのお墓は、他の人が継承しない限り墓じまいになります。
家族が宗旨宗派から自由になりたい、もしくはキリスト教など他の宗旨宗派であれば、宗旨宗派に規制がない民間霊園が良いでしょう。
<終活でお墓を準備する注意点①菩提寺>
(1)墓主の場合
・親族に墓守の交代を相談する
・ご住職に墓じまいの相談をする
(外檀家の提案もあり)
(2)墓主以外の場合
・親族に独立することを伝える
(先祖代々墓に入らない)
「外檀家」とは、寺院墓地お墓を持たないものの、法要では読経供養を依頼する檀家です。墓じまいでいきなり離檀をするよりも、菩提寺との関係は良好に保たれやすいです。
・「檀家」とは?かかる費用や義務、檀家になる・やめるには?檀家にならず法要はできる?
終活のお墓準備②入る人
◇お墓に入る人によって、終活で準備するお墓の種類が変わります
ガーデニング樹木葬などの小さなお墓は納骨できる人が個人1柱・夫婦2柱など限られているため、家族がお墓に入る場合は確認が必要です。
また寺院墓地では「お墓に入る人は第三親等まで」など、親族に限られる規制もあります。
・入る人数に規制はないか
・親族ではない人も納骨できるか
継承者がいないお墓でも子どもや家族が入るならば、一般墓に永代供養を付けたタイプを選ぶと良いでしょう。
終活のお墓準備③契約期間
◇終活で永代供養付きのお墓を準備する場合、契約期間を確認します
継承者の必要な永代供養は、墓地・霊園施設管理者が家族に代わって、遺骨を永代に渡り供養・管理をしますが、ずっと個別に管理・供養する訳ではありません。
永代供養の契約期間が過ぎると、遺骨は自動的に合祀墓に他の遺骨と一緒に合祀埋葬され、合同供養します。
・永代供養の契約期間はどれくらいか?
・契約更新はできるか?
・契約期間のカウントはいつからか?
継承者の充てはないものの、ずっと個別の墓標が欲しい場合には、契約期間と契約更新の可否を確認しなければなりません。
終活で複数の人が入るお墓を準備するなら、契約期間のカウントがいつから始まるかも確認してください。一般的には最後の人が納骨されてからのカウントが多いです。
終活でのお墓の準備は、家族と一緒に進めよう

終活の主役は自分ですが、お墓参りは残された家族が行くものです。納骨やお墓参りなど、亡くなった後の供養は、残された家族が主役とも言えるでしょう。
終活では「遺骨は海に撒いてもらえば良い」などとも聞きますが、故人と会話ができる個別の墓標を持つことで、大切な人を失ったショックや哀しみを癒す「グリーフケア」の一助となります。
本記事を参考にしながら、ぜひ家族で話し合い協力して、自分も家族も後々まで満足できるお墓を準備しましょう。
お電話でも受け付けております
















