
日本のお墓の種類は?埋葬する単位・お墓や埋葬の形式・墓所で違う種類をそれぞれ解説!
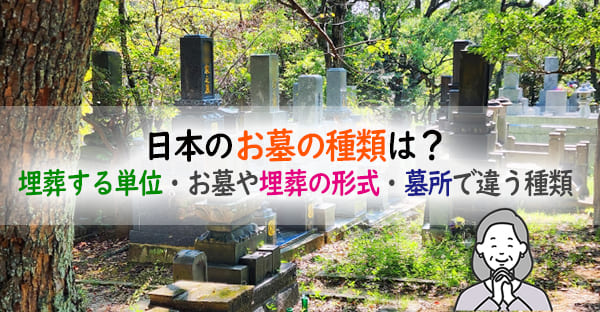
「お墓を建てるには、どんな種類がある?」
「遺骨をどこに納骨すれば良いか分からない」
「霊園・墓地の選び方、お墓の選び方が分からない」
永代供養が登場したことで日本のお墓の種類は大幅に増えました。お墓の種類が増えたことで、ご遺族も予算や希望に合わせたさまざまな選択ができます。
本記事を読むことで永代供養が登場した現代に知っておきたい、ご遺族が選択できるさまざまなお墓の種類が分かります。お墓に入る人や範囲・埋葬形式・お墓の形・墓所の種類など、複数の見解で分けました。
お墓のない葬送方法もご紹介していますので、どうぞ最後までお読みください。
お墓の種類(1)埋葬する人や単位

お墓の種類には埋葬する人の範囲・単位によるものがあります。一般的な先祖代々墓は家単位で入るお墓の種類です。
戦前までは家で代々に渡り先祖代々墓を守ってきましたが、現代では少子高齢化による墓主の高齢化・継承者不在の問題が出ています。
そこで霊園や墓地などの墓地管理者がご家族に代わり、ご遺骨の管理や故人の供養を担う「永代供養」が登場しました。埋葬する人や単位によるお墓の種類が広がっています。
①先祖代々墓(家墓)
先祖代々墓は「家墓(いえはか)」「累代墓(るいだいぼ)」とも言われる、従来から続く日本のお墓の形です。
先祖代々墓にはご先祖様のご遺骨が代々納められています。お墓は代々継承をする形で戦前までは遺産とともに嫡男が継承してきました。現代でも長男・長女による継承を慣習として地域が多くあります。
たえだし法的には誰がお墓を継承しても問題はありません。次男次女以降の子どもや親族はもちろん、状況によって血縁関係のない他人が継承することも可能です。
家で守るお墓なので墓石には「〇〇家之墓」「〇〇家」と彫刻された先祖代々墓が多いでしょう。側面には納められた故人の享年月日や戒名などを追加彫刻します。
②両家墓
両家墓とはご夫婦2つの家の先祖代々墓をひとつにまとめたお墓です。ご夫婦それぞれが先祖代々墓の継承者となった場合に、お墓を守る負担を軽減するためにまとめるケースが多いでしょう。
・1つの墓地区画に両家二基のお墓(墓石)を建てる
・ひとつのお墓(墓石)を建てて両家のご遺骨を納める
(竿石に両家の家名や家紋を彫刻する)
両家墓はお墓の維持管理への負担を軽減し無縁墓の問題を解消する良い方法ですが、両家の宗旨宗派が異なると、スムーズに進まないケースもあるでしょう。
宗旨宗派が異なる両家の場合は、民間霊園など宗旨宗派を問わない霊園や墓地にお墓を建てる方法もあります。
両家のお墓をひとつにまとめるための引越し「改葬」では、墓石のグレード・墓地や墓石の大きさなどにより異なりますが、一般的に約200万円以上が目安です。費用分担も含めて両家の家族・親族で話し合いながら進めましょう。
・【樹木葬の体験談③】両家で宗旨宗派が違い両家墓が建たない!家族型樹木葬の契約で解決
③夫婦墓
夫婦墓とはご夫婦のみが納骨されるお墓です。個別墓に永代供養を付けることで、継承者を立てる必要がなくなるため、一世代のお墓が実現します。
「永代供養」とは家族の代わりにご遺骨の管理や故人の供養を墓地管理者が担うサービスです。子々孫々と永代に渡り担ってくれるため、一度契約すると継承者が必要ありません。
・子どもがいないご夫婦
・子や孫にお墓継承の負担をかけたくない
・夫婦だけのお墓が欲しい(先祖代々墓に入りたくない)
夫婦墓は生前に一括で支払う流れが一般的です。子どもや孫に経済的負担をかけずに済みます。また子どもや孫が頻繁にお墓参りに来なくても、お墓が荒廃する心配が少なく、無縁墓の心配もありません。
④個人墓
個人墓とは個人で入るお墓です。夫婦墓と同じく永代供養を付けた個別墓になります。ご遺骨もひと柱のみなので、お墓もコンパクトなタイプが多く費用も安く収まるでしょう。
・先祖代々墓に入りたくない
・子どもや孫がいない
・子どもや孫に負担をかけたくない
永代供養の付いた個人墓は生前契約が一般的です。生前に一括で支払い契約を済ませるので、子どもや孫に経済的な負担をかけることがありません。
近年では人生の終末や葬送方法を生前に自らプロデュースする「終活」による個人墓の契約が進んでいます。
また弔い上げなど契約した一定年数が過ぎると合祀墓に合祀されるので、代々に渡る継承問題も解消するでしょう。コンパクトなお墓として樹木葬を選ぶ人もいます。
⑤家族墓
家族墓は家族単位で納骨されるお墓です。先祖代々墓とは違い、現在の家族単位で一緒のお墓に眠ることができます。
家族墓では契約した子どもまで入ることができますが、基本的に永代供養が付いているため、子どもや孫はお墓の継承負担がありません。
墓石が建つ限り定期的なお墓掃除は必要になりますが、近年では個別安置期間が長い永代供養として納骨堂の家族版「室内墓所」も登場しました。
この他永代供養型樹木葬では、一緒に納骨される人数が4名~6名以上と、家族単位のプランが増えています。このような永代供養では、定期的なお墓掃除の負担もなくなるでしょう。
墓石を建てる家族墓では、ワンプレート型の石碑を置く永代供養型樹木葬を含めると、約50万円~200万円ほどが費用相場です。合祀までは年間約5千円~2万円の年間管理料がかかるプランも多いので、契約時に確認しましょう。
・樹木葬の失敗しない選び方とは?欠点はある?目的で違う後悔しない選び方のポイント解説
⑥友墓
友墓は血縁関係のない知人友人同士で入るお墓です。友墓も継承者を必要としない永代供養の登場により実現しました。
墓石を建てる建墓費用を知人友人で分担して負担します。古くからの友人知人が一緒に入る友墓もありますが、現代では終活で集まった人々「墓友(はかとも)」が共同で墓石を建てる流れが多いです。
⑦村墓
古くからあるお墓に「村墓」があります。共同墓とも呼ばれ、地域の人々が入るお墓として利用されてきました。ただ現代ではほとんど見ることはありません。
村墓は基本的にひとつの場所に他のご遺骨と一緒に埋葬される「合祀墓」です。この他、一つの場所に骨壺のまま埋葬される村墓などもあります。
現在残る村墓は「共同墓」「共同墓地」などと呼ばれることが多く、共同墓地はお墓のある自治体が管理していることが多いです。
お墓の種類(2)埋葬形式

日本では家族が亡くなると先祖代々墓に納骨する、もしくは新しく墓石を建ててご遺骨を納めてきました。けれども近年では「お墓はいらない」と考える人が増えています。
お墓を建てると維持管理・継承者の負担が生じるためです。墓石を建てても永代供養を付けることで継承者問題は解消されますが、定期的なお墓掃除が必要になります。
このようなことから負担をできるだけ軽減したお墓の種類も数多く登場しました。
・【2024年最新動向】これからのお墓のあり方が変わっていく?今後のお墓事情6つの傾向
①永代供養墓
永代供養墓とは合祀墓・合葬墓とも呼ばれ、一般的にひとつの場所に他のご遺骨と一緒に合祀されるお墓です。
永代供養墓の費用相場は約3万円~20万円・平均額は約5万円~10万円となります。最も安い永代供養のひとつとも言えます。合祀後は供養塔を共有し、合同供養される流れです。
「合祀」とは不特定多数のご遺骨と一緒に、まとめて埋葬される葬送を指します。そのため永代供養墓に一度埋葬すると、ご遺骨は二度と個別に取り出すことはできません。
どのような永代供養も合祀までの猶予期間を設けるため、個別安置期間を設けますが、最終的には合祀されます。合祀までの猶予期間がないお墓が永代供養墓とも言えるでしょう。
・永代供養墓はどんなお墓かわかりやすく解説!何年供養してくれる?選び方のポイントは?
②樹木葬
樹木葬とは墓石の代わりに樹木を墓標とした葬送です。自然葬のひとつとして、樹木のふもとにご遺骨を埋葬します。
ご遺骨は長い時間をかけて自然に還すことを目的とするため、土に還る骨壺で埋葬されたり、骨壺や骨袋から取り出してご遺骨のみを埋葬するでしょう。樹木葬では一度埋葬したご遺骨を再び取り出すことができません。
永代供養型樹木葬は「ガーデニング型樹木葬(庭園型樹木葬)」とも呼ばれ、美しい草花に囲まれて眠ることを目的とします。霊園の特別区画で整備された美しい草花のふもとに納骨されるでしょう。
プランによっては納骨場所の上に名前やイラストを彫刻した石碑が置かれ、石碑を墓標としてお参りができます。
③納骨堂(集合墓)
納骨堂はご遺骨を収蔵するスペースを提供する屋内施設です。納骨堂にはロッカー型・仏壇型・自動搬送型(ビル型)など、さまざまな種類があります。
いずれも墓石を建てる必要がなく、ご遺骨を屋内で清潔に収蔵できるため、ご家族は定期的なお墓掃除などの負担がありません。気が向いた時に参拝するのみです。
納骨堂も永代供養のひとつとなり、契約した個別安置期間が過ぎると施設内の永代供養墓に合祀されます。合祀後は他のご遺骨とともに合同供養される流れです。
ただし納骨堂は個別安置期間であれば、ご遺骨を個別に取り出すことができます。更新できるプランであれば、個別安置期間を更新することもできるでしょう。
納骨堂は種類が豊富にあるので約10万円~150万円と幅広いです。一緒に納骨する人数によっても費用幅があります。詳しくは下記コラムをご参照ください。
・納骨堂で永代供養を行う費用はどれくらい?納骨堂5つの種類で違う費用相場を詳しく解説!
④個別墓
個別墓は墓石を個別に建てて納骨するお墓です。一般墓とも言います。先祖代々墓・夫婦墓・個人墓などは、このお墓の種類分けでは個別墓になるでしょう。
墓石を建てるため他のお墓の種類と比べると費用は割高です。鎌倉新書が実施した2024年度の調査では、平均的な個別墓の建墓費用は149.5万円でした。
ただ墓石のグレードや墓地の広さなどにより費用幅は広いので、約100万円~300万円以上と幅が広くなります。家族・親族と費用を負担しながら検討しましょう。
墓石を建てる個別墓は費用が高くなるので、メモリアルローンなどの分割払い方法もあります。検討している方はまず、霊園・墓地や石材業者で相談してみてはいかがでしょうか。
・【お墓の基礎知識】お墓の目的・構造・費用は?継承や建墓前に知りたい6つの知識を解説
・永代供養の費用の支払い方法は?いつ・どのように支払うの?ローンや分割払いはできる?
⑤屋内墓所
室内墓所は屋内にご遺骨を安置する墓所です。完全霊園型・納骨堂型・個別搬送型(ビル型)3通りの室内墓所があります。
いずれも一般的なお墓と比べて割安傾向です。特に納骨堂型・個別搬送型(ビル型)の室内墓所は駅近などアクセス環境が良い立地に多い点も人気が集まっています。
| <室内墓所の種類> | |
| ・完全霊園型 | …墓石のあるお墓が並ぶ室内の墓所 |
| ・納骨堂型 | …ご遺骨を家族単位で収蔵する墓所 |
| ・自動搬送型(ビル型) | …個別ブースに案内され、ご遺骨が自動搬送される |
自動搬送型(ビル型)の室内墓所では、お参りに行くと個別の参拝ブースに案内されます。個別の参拝ブースにはお墓があり、そこへご遺骨が自動搬送される仕組みです。
屋内施設なので屋外の一般墓と比べると定期的なお墓掃除など、メンテナンスの負担が大幅に軽減されます。
・納骨堂とお墓の違いとは?メリットデメリット、大阪で屋内で参拝する「室内墓所」も紹介
・納骨堂のお参りマナーとは?お墓と納骨堂で違うお参り、迷惑を掛けない5つのポイント!
⑥ペットと眠るお墓
ペットを家族の一員として迎え入れる家が増えた昨今では、ペットと一緒に眠るお墓のニーズが急増しています。
ただ一般的な霊園・墓地に建つ個別墓では、基本的にペットと一緒の納骨はできません。墓地管理者としては、周囲の人々とのトラブルが多発するためです。
そこで現在では、ペットと一緒に納骨できる特別区画を設けた霊園・墓地が登場しています。契約した一定年数、ペットとご家族で眠るお墓に納骨できます。
飼い主とペットが一緒に眠るお墓の相場は約20万円~150万円、個別安置期間は年間管理料が毎年約5千円~2万円かかるプランもあるので、契約時に確認をしてください。
・ペット供養とは?ペットの遺骨をどうする?7つの方法と費用相場、選び方のポイントとは
・お墓にペットと一緒に入ることはできる?メリットやデメリット、選び方や注意点はある?
お墓の種類(3)墓所

ご遺骨は知事が認めた墓地に埋葬しなければなりませんが、墓地には運営母体で違う3つの種類があります。寺院墓地・民間霊園・公営墓地です。
また民間企業が運営する民間霊園では、公園型墓地・芝生墓地なども見受けます。特別区画を設けた民間霊園もあるでしょう。
特別区画ではガーデニング型墓地・ペットと一緒に入る墓地区画などを見受けます。また山林奥深くに自然葬を目的とした墓地もあるでしょう。
・お墓を購入する注意点とは?見学・契約時に確認するチェックポイント|購入の手順も解説
①寺院墓地
寺院墓地とは寺院が運営する昔からある墓地です。寺院に隣接した墓地が多く、寺院墓地にお墓を建てる場合は檀家になることが求められるでしょう。
「檀家(だんか)」とは、その寺院に属して宗旨宗派に倣う家を指し、経済的にも寺院を支えます。一方で墓地を運営する寺院を「菩提寺(ぼだいじ)」と呼び、檀家の供養を担う相互関係です。
檀家は菩提寺に毎年お布施を包みます。民間霊園の年間管理料と同じ役割を果たし、約1万円~3万円が相場です。ただし近年では永代供養や樹木葬プランにおいて、檀家になることを求めない寺院墓地も増えました。
②民間霊園
民間霊園とは財団法人・宗教法人などの民間団体が運営する霊園です。民間団体が運営するためニーズに対応したバリエーション豊富なスタイルが登場しています。
サービスが充実しているので法要室や相談室を設け、故人の回忌法要の相談、終活相談などを受け付ける民間霊園もあるほどです。ただしサービスや設備が充実する民間霊園ほど、割高傾向にもなります。
・公園型墓地
・芝生墓地
・ガーデニング型墓地
・屋内墓所
・郊外墓地
また宗旨宗派を不問とする民間霊園が多いため、無宗教の方々にも人気です。また永代供養墓(合祀墓)では基本的に必要ありませんが、一般墓や納骨堂では公共施設や設備の維持管理費として年間管理料が発生するプランもあります。
年間管理料は約5千円~2万円、永代供養では個別安置期間のみ発生する費用システムが一般的です。生前契約では生前にまとめて支払う仕組みが多いでしょう。
③公営墓地
公営墓地は自治体が運営する墓地です。都立霊園・県立霊園・市営墓地などが公営墓地になるでしょう。地域住民が割安で納骨できることを目的としているため、寺院墓地や民間霊園と比べると割安傾向です。
公営墓地は石材業者や僧侶の手配を全て自分達で進めるため、お墓を建てるにあたり手間暇はかかりますが自由度が高いです。基本的に提携する石材業者はありませんし、宗旨宗派も問いません。
一方で公営墓地は募集時期が定められています。地域広報などで募集し、応募が多い時には抽選が行われるでしょう。また基本的に生前契約はできません。手元にご遺骨があるご家族のみ、契約できる公営墓地が一般的です。
自治体が運営しているので倒産・廃寺のリスクもありません。
・霊園とはなに?墓地とは違う?民間霊園・寺院墓地・公営墓地のメリット・デメリットとは
br>
お墓の種類(4)お墓の形

墓石の形状で違うお墓の種類もありますね。従来のお墓は「和墓(和型墓石)」「三段墓」などと呼ばれます。神道では和墓の頭部分が三角錐になっているでしょう。
民間霊園では規格墓を提案される流れが少なくありません。規格墓は墓石費用が安い傾向にあるので、予算を抑えたい方は検討すると良いでしょう。
①和墓
従来の一般墓が和墓です。三段墓とも呼ばれ、基本的にはご遺骨を納骨するスペース「カロート」の上に置かれる芝台と、中台・上台・竿石で構成されます。
昔ながらの先祖代々墓は和墓が多く、棹石部分に「〇〇家」「〇〇家之墓」などと彫刻されるでしょう。側面には納骨する故人の享年月日・戒名などを彫刻します。
和墓の側面に充分なスペースがない時には、墓地区画内に墓誌を建てて彫刻することもあるでしょう。五輪塔タイプなどもありますが、基本的には三段墓が多いです。
②洋墓
西洋風のお墓を和型墓石と比べて「洋墓」と呼びます。カロートを保護する芝台の上に、シンプルな横長の石碑を乗せるスタイルが一般的です。
洋墓には「芝台+台石(中台)+石碑」の二段型、石碑(竿石)が斜めにカットされているオルガン型、芝台の上に竿石が置かれているストレート型(洋一段型)の3種類があります。
洋墓は宗旨を問わない点がメリットです。キリスト教や無宗教でも建てやすく、竿石には必ずしも家名を入れる必要がありません。「思い出」「絆」など、抽象的な言葉やイラストを彫刻する墓主も多い傾向です。
・大阪でお墓に彫刻する文字にタブーはある?やすらぎなど抽象的な言葉や宗旨宗派で違う彫刻
③デザイン墓
デザイン墓は和墓や洋墓とは異なり、自由にデザインできるお墓です。生前の故人の人生・人柄をイメージさせるデザインや、ご遺族の想いを表現する目的が多い傾向にあります。
和墓や洋墓は左右対称の安定したデザインが基本なので、特にデザイン墓の多くは左右非対称に加工しています。
デザイン墓には完全オリジナルの「フルオーダー式」と、石材業者の提案を軸に希望を伝えてデザインしていく「セミオーダー式」があります。
和墓や洋墓と比べると費用は割高傾向ですが、予算を定めて担当者と打ち合わせを重ねながら折り合いをつけると良いでしょう。
④ワンプレート墓
ワンプレート墓は、ご遺骨を納骨するスペース「カロート」の上に石碑を置くスタイルです。主に永代供養型樹木葬墓地で見受けます。
石碑を置くだけなので費用相場が安い傾向にあり、永代供養型樹木葬では2名まで約65万円~のプランもあるでしょう。(個別安置期間・設備・埋葬方法などにより異なります。)
ワンプレート墓では石碑への彫刻に自由度が高い傾向です。洋墓と同じように抽象的な言葉を彫刻するご遺族が多い他、花や動物などのイラストを彫刻するケースも多く見受けます。
・選べるガーデニング樹木葬
⑤集合墓
集合墓はロッカーのようにご遺骨を収蔵するスペースが提供されるお墓です。納骨堂も屋内施設の集合墓と言えます。
屋外の集合墓の一例は、ロッカーのように上下左右にご遺骨を収蔵するスペースが提供されたスタイルです。墓石は建ちますが共有されるので、個別にご遺骨を安置しながらも安い価格帯で利用できます。
一方でお彼岸やお盆などのお墓参りシーズンは混み合う集合墓もあるでしょう。芝生墓地の集合墓では、墓前でのお参りを簡単に済ませて芝生広場で故人を偲びながら、食事を楽しむ様子も見受けます。
・お墓を購入する流れとは?費用相場と選び方のポイント、お墓が建つまで6つの手順を解説
お墓の種類(5)新しい形

以上がお墓の主な種類ですが、近年では新しい形も増えました。宗旨宗派にこだわらない・無宗教の家が増えたことで、自宅でご遺骨を安置する選択も増えています。
この他、宗旨宗派を問わない自然葬では、墓標を持たずに海や山を見ながら故人を偲ぶスタイルも登場しました。
①手元供養
手元供養とはご遺骨をご自宅や手元で保管し、供養する葬送です。かつては大切なご家族を失った喪失から、火葬場から引き渡された状態のまま仏壇に祀るご家族も多くいました。
近年の手元供養はご家族が日々供養をすることを目的としています。手元供養などの専門業者に、ご遺骨を2mm以下のパウダー状に粉骨してコンパクトに加工した後、小さな骨壺やアクセサリーに収めて供養するスタイルです。
小さな骨壺は小さな祭壇に祀り、日々ご家族が想い思いに供養します。アクセサリーに収めたご遺骨は、ご家族が日々持ち歩く供養方法が一般的です。
粉骨は手元供養用品を扱う仏壇・仏具店へ相談をすると、専門業者を紹介してくれるでしょう。
・【手元供養の体験談】娘の手元供養。娘の遺骨を納骨できないまま5年、分骨をして祭壇へ
・COCOテラス
②自宅墓
さらに手元供養が進化し、現代では「自宅墓」も注目されるようになりました。複数のご遺骨をご自宅で安置し、ご家族が供養する方法です。
手元供養と同じように粉骨されたご遺骨を真空パックにした後、ブック型の骨箱などに収めて仏壇下の戸棚などへ保管します。
墓地代・墓石代がないので費用が建墓費用ほどかからないこと、日々の暮らしのなかで供養できることがメリットです。
③自然葬
自然葬とはご遺骨を自然に還す葬送です。2024年現代では海洋散骨・樹木葬が最も注目される自然葬と言えるでしょう。
「樹木葬」では樹木を墓標として、そのふもとに埋葬します。大きな大樹のふもとに埋葬する「シンボルツリー型」・個別区画に埋葬した後に植樹する「植樹型」などがあります。いずれも長い時間をかけてゆっくりと、ご遺骨が土に還って行くスタイルです。
「海洋散骨」では粉骨したご遺骨を、海の沖合いまで出て散骨します。海洋散骨には墓標がありません。墓碑に故人の名前を彫刻する・メモリアルプレートを配布する、などのプランもあるでしょう。
まとめ:永代供養の登場によりお墓の種類が増えました

日本では江戸時代から続く檀家制度があり、従来は寺院墓地にお墓を建てる風習がありました。檀家制度は家と菩提寺の関係性があり、日本の人々は先祖代々墓を建てて子々孫々とお墓を守る慣習があります。
けれども人々の暮らしのグローバル化・核家族化・少子高齢化により、お墓の継承者がいない家が増えました。現代では無縁墓が行政レベルで深刻化しています。
けれども永代供養の登場により無縁墓の心配がなくなると、一代ではいる個人墓・夫婦墓・友墓をはじめとして、さまざまなお墓の種類が登場しました。
永代供養を利用することで、お墓の維持管理負担がない葬送が実現します。ご家族は気が向いた時にお参りするだけです。負担なく故人を偲び供養できるでしょう。
・永代供養の費用の平均は約10万円~150万円?種類で違う料金システムは一人いくら?
お電話でも受け付けております
















