
【2025年版】納骨堂と永代供養の費用相場は?内訳・種類を比較

納骨堂は、現代のライフスタイルに合わせて人気が高まっているお墓の形です。中でも永代供養付きの納骨堂は、後継者がいなくても安心して利用できる点が大きな魅力です。
ただし、納骨堂や永代供養にはさまざまな種類があり、費用の目安や相場も異なります。初期費用に加えて管理費や永代供養料が必要になるケースもあり、内訳を理解しておくことが大切です。
本記事では、納骨堂と永代供養の違いや費用相場、種類ごとの特徴を比較し、選び方のポイントをわかりやすく解説します。
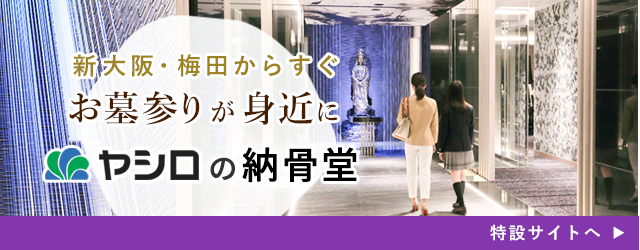
納骨堂とは?永代供養とは違う?費用相場は安い?

◇納骨堂とは、遺骨を室内に収める施設です
従来は、お寺などに設置されることが多く、遺骨の一時的な預かり所として使われてきましたが、最近では承継不要のお墓として広まっています。
最も特徴的な点は、室内で供養ができることで、天候や季節に関係なく快適にお参りすることができます。
ただし、納骨堂と言っても、現代ではさまざまな種類があり、遺骨の供養方法として広く知られています。
ロッカータイプや仏壇タイプなどの種類や、1つのスペースに納骨する遺骨の柱の数によって、費用相場は20万円から180万円ほどで幅広くなります。
納骨堂と永代供養の違いと費用を一覧で解説
◇納骨堂には、墓地管理者がご遺骨を管理・供養する「永代供養」が付いています
納骨堂と永代供養は違いを比べるものではありません。
「永代供養」とは、ご家族に代わり墓地管理者がご遺骨を永代に渡って管理・供養をする、形のないサービスだからです。
ただ、最近は「永代供養のついた納骨堂」を提供している施設がたくさんあるため、納骨堂は永代供養の一部と言えます。
違いを比較する場合は、合祀墓や永代供養墓との比較が適切かもしれません。
| <納骨堂とその他の永代供養との違い> | ||
| [永代供養の種類] | [費用] | [特徴] |
| (1)合祀墓 | ・約5万円ほど~ | ・最初から他のご遺骨と一緒に合祀 ・一度の納骨で支払いはない |
| (2)一般墓 (永代供養付き) |
・約175万円以上 (墓石が建つため) |
・一般墓に永代供養が付く ・納骨後、年間管理料が掛かる ・契約年数が過ぎると撤去、合祀 (契約更新により延長可能) |
| (3)納骨堂 | ・約20万円ほど~ | ・屋内に納骨スペースが提供される ・個別安置期間は年間管理料がかかる ・契約年数が過ぎると合祀 (契約更新により延長可能) |
このように「納骨堂と永代供養の違い」について聞かれた場合、納骨堂は「建物内に多くの収骨スペースがある」一方、永代供養は「寺院や霊園で納骨を管理してくれる」という違いです。
・納骨堂と永代供養墓の違いとは?合祀墓や樹木葬で行う永代供養と3つの違い|永代供養ナビ
納骨堂での永代供養、5つの種類で違う費用相場

◇納骨堂の費用相場は、約20万円~180万円ほど+年間管理料です
ひと口に「納骨堂」と言っても、費用形態はその種類や供養方法、規模などによりさまざまです。
例えば屋内に墓石を建てる納骨堂であれば、墓石を必要としないロッカー型やビル型(自動搬送型)と比べると、格段に高くなるでしょう。
| <納骨堂とその他の永代供養との違い> | |
| [永代供養の種類] | [費用] |
| (1)ロッカー型 | ・約20万円~80万円 |
| (2)仏壇型 | ・約30万円~150万円 |
| (3)ビル型 (自動搬送型) |
・約50万円~150万円 |
| (4)墓石型 | ・約50万円~180万円 |
| (5)位牌型 | ・約10万円~50万円 |
この他、利用年数・納骨するご遺骨の柱数や、納骨スペースの広さも、納骨堂の費用が変動する要素です。
| <人数で違う納骨堂の費用相場> | |
| [永代供養の種類] | [費用] |
| (1)個人用 | …約10万円~50万円 |
| (2)2人用(夫婦) | …約60万円~80万円 |
| (3)4人用(家族) | …約100万円~180万円 |
などが平均的です。
なお納骨堂の費用内訳には、永代供養料・永代使用料・開眼法要料・納骨費用の他、戒名料や位牌料が含まれる場合もありますので、詳しくは後ほどお伝えします。
一般的なお墓の費用相場は約100万円~350万円ほどになるため、納骨堂は従来の一般的なお墓と比べると、費用を比較的安く抑えることができる選択となるでしょう。
(1)ロッカー型(費用は安い)
◇ロッカー型納骨堂の費用相場は約20万円~です
昔から馴染み深い納骨堂のタイプがロッカー型です。
割安な点はメリットですが、その分簡素な印象が強いかもしれません。
| <納骨堂の永代供養の費用:ロッカー型> | |
| [特徴] | ・ロッカーに遺骨を収蔵 |
| [費用目安] | ・約20万円/1柱~ |
納骨堂の従来の使い道のように、お墓を建てるまでの一時的な遺骨の収蔵スペースとしても、多く用いられています。
・【お墓Q&A】ロッカー式納骨堂は誰が管理しているの?生前契約したいが、その実態は?
(2)仏壇型
◇仏壇型納骨堂の費用相場は約30万円~です
仏壇型は遺骨を納めるスペースが仏壇になっています。
仏壇型の納骨堂は、家族用での利用も多い傾向にあり、より供養の場としての役割を求める人々に好まれる傾向です。
| <納骨堂の永代供養の費用:仏壇型> | |
| [特徴] | ・仏壇に遺骨を収蔵 |
| [費用目安] | ・個人…約30万円/1柱ほど ・家族用…約100万円/3柱~5柱ほど |
仏壇型の納骨堂で永代供養を行う場合、費用は1柱ごとの料金体系が一般的です。
夫婦契約など複数の遺骨が入る納骨堂を生前契約した場合、最後の遺骨が収蔵されてから、個別安置期間がカウントされるでしょう。
(3)ビル型(費用は高め)
◇ビル型(自動搬送型)納骨堂の費用相場は、約50万円~です
「ビル型(自動搬送型)」とは、機械で動く可動性の納骨堂です。
日ごろは施設の遺骨収蔵スペースに収蔵され、お参りに行くと遺骨が繰り出します。
[仕組みの一例]
・受付
・個別の参拝スペースに案内
・ICカードをスキャン
・自動的に遺骨が繰り出される
ビル型納骨堂、可動型納骨堂、機械式納骨堂、繰り出し納骨堂など、また新しい施設になるため呼び方もさまざまにあります。
機能性が高いため、通常の納骨堂よりも永代供養の費用は割高傾向です。
| <納骨堂の永代供養の費用:ビル型(可動型)> | |
| [特徴] | ・機械で自動的に繰り出される ・個別スペースで参拝 |
| [費用目安] | ・約50万円~100万円/1柱 |
複数の参拝スペースが用意され、家族は個別の参拝スペースで遺骨を待つのみです。
年忌法要など、個別法要の専用スペースが常設されている施設もあります。
・納骨堂のお参りマナーとは?お墓と納骨堂で違うお参り、迷惑を掛けない5つのポイント!
(4)墓石型(費用は高い)
◇墓石型納骨堂の費用相場は、約50万円~100万円以上です
「屋内墓所」「墓石型納骨堂」「屋内墓苑」など、さまざまな呼び名があります。
納骨堂の多くが個人を基本とするのに対し、墓石型納骨堂は、家族など複数人のご遺骨が供養できる「家族墓」が多い点も魅力です。
| <墓石型納骨堂と費用相場> | |
| [特徴] | ・家族契約も可 ・お墓に向かって参拝できる ・永代供養は付いている |
| [費用目安] | ・約50万円~100万円/1柱 |
現代の墓石型納骨堂は、主に2タイプの施設があります。
屋内に墓石が並ぶタイプの墓石型納骨堂の場合、墓石代がかかるので、納骨堂と言っても費用相場は一般墓と同等ほどになるでしょう。
| <墓石型納骨堂2つのタイプ> | |
| ①墓石のお墓が並ぶ |
|
| [特徴] | ・室内に墓地区画がある ・墓石を建てる |
| [費用目安] | ・約100万円~350万円ほど |
| ②参拝スペースがある |
|
| [特徴] | ・参拝スペースに案内される ・ご遺骨が自動搬送される |
| [費用相場] | ・約80万円~150万円 |
墓石型納骨堂は、他の納骨堂施設と違い、契約する側も「永代供養を付けたコンパクトな屋内のお墓」と考える人もいるため、建墓費用と比較してコンパクトで割安と捉える人もいるでしょう。
墓石型でも永代供養が付き継承者は必要としません。
お墓を管理する負担が軽減、天候にも左右されずにお参りができます。
(5)位牌型(寺院に多い)
◇位牌型納骨堂の費用相場は、約10万円~です
位牌型の納骨堂も、昔から身近にある永代供養でした。
寺院の納骨堂に多く、一般的には位牌を並べて合同供養を行います。
昔は位牌が密集して並びましたが、近年増えた民営の位牌型納骨堂は、個別スペースで位牌を祀り、別スペースに遺骨を収蔵する仕組みも多いです。
| <位牌型納骨堂と費用相場> | |
| [特徴] | ・位牌を祀る ・遺骨は別に管理、供養 (合祀墓に合祀する施設も多い) |
| [費用目安] | ・約10万円/1柱~ |
なかには個別スペースを仏壇風にまとめ、仏壇型納骨堂に見える施設もあるでしょう。
位牌型は昔と今で、スタイルが大きく変化しています。
納骨堂での永代供養の費用内訳(墓じまい後)

◇納骨堂費用の内訳項目には、永代供養料や年間管理料があります
納骨堂の費用内訳は大まかに4つの内訳に分かれます。
納骨堂は費用の内訳項目を理解することで、予算に合わせてお金を掛ける箇所、抑える箇所を、優先順位に合わせて調整ができるでしょう。
| <納骨堂の費用内訳> | |
| [基本の内訳] | (1)永代供養料 (2)年間管理料 (3)納骨式の法要料 |
| [その他] | (4)戒名料 |
ただし墓じまいにより取り出した遺骨を、納骨堂で永代供養する場合、戒名料の費用は掛かりません。
また亡くなった時に納骨堂を選んだとしても、「無宗教なので戒名はいらない」との選択ならば、当然戒名料は必要なくなります。
・墓じまいの手順や手続きとは?しないとどうなる?9つの手順と行政手続き、費用も解説!
(1)永代供養料
◇「永代供養」とは、家族に代わり遺骨の管理・供養を施設側が行うことです
「永代供養(えいたいくよう)」とは、墓地や霊園、納骨堂などの施設が、子どもや家族に代わって、永代に渡り遺骨の管理や供養を行ってくれる、形のないサービスです。
ただ遺骨は、永代に渡って「個別に」管理・供養される訳ではありません。
5年・10年など、契約した一定年数が過ぎると、遺骨を合祀墓などに合祀埋葬、合同供養により、永代に渡り管理・供養する仕組みです。
●納骨堂では、永代供養料が費用に含まれる施設が多い。
一般的な永代供養は、霊園や寺院に遺骨を預け、供養・管理をしてもらいます。
納骨堂の永代供養は、費用内訳に永代使用料はなく、永代供養料のみの支払いです。
ちなみに「永代使用料」は墓地や納骨堂であれば収蔵スペースを、「永代に渡り使用する権利」を差し、永代供養料とは性質が異なります。
・お墓購入の項目「永代使用料」ってなに?永代供養料や管理費とは違うの?|永代供養ナビ
(2)年間管理料(管理費)
◇「年間管理料」とは、納骨堂で遺骨の管理を行うスペースの使用料です
「施設利用料」とイメージしていただけるとわかりやすいでしょう。
納骨堂での永代供養の場合、管理費用(施設利用料)も「永代供養費」に含まれてることが多く、ここでは毎年掛かる年間管理料について解説します。
| <納骨堂の費用内訳:年間管理料> | |
| [通常の契約] | ●遺骨の個別安置期間 ・毎年管理費料が掛かる ●遺骨の合祀後 ・年間管理料は掛からない |
| [生前契約] | ●遺骨の個別安置期間 ・年間管理料を一括払い |
ただ納骨堂は本人が終活を通して生前に予約する「生前契約」も多いです。
生前契約では契約者本人は納骨時に亡くなっていますから、当然、毎年の年間管理料も支払うことができません。
そこで予め、個別安置期間の年間管理料を一括払いする仕組みが多いです。
契約期間中に家族が更新をした場合、年間管理料は毎年払いに代わる流れが多いでしょう。
・お墓を継承したら維持管理費はどれくらい?負担を減らすには?維持管理ができない時は?
(3)法要料
◇「法要料」とは、住職やお坊さんに支払うお布施です
納骨堂にご遺骨を納骨する際、納骨式を執り行う家が多いでしょう。
この納骨式で読経供養のお礼としてお渡しする費用が「お布施」、法要料です。
この他、納骨堂を選ぶ家族のなかには、お墓と同じように納骨堂の個別スペース(仏壇や位牌など)に開眼供養を行うこともあります。
[法要料(お布施)]
・約3万円~5万円/1回
ただし納骨堂では法要料と永代供養の費用を、セットで提示する施設も多いです。
契約時に納骨式や開眼供養料について、詳しく確認してください。
墓じまいによる納骨堂の永代供養では、もともとお墓があった寺院墓地のご住職に読経供養をお願いする人もいます。
・菩提寺に相談
・納骨堂の管理者に相談
・インターネットの僧侶手配
もともとお墓があった寺院墓地は、墓じまいにより菩提寺ではなくなることが多いですが、墓じまいによる離檀トラブルを避けるためにも、法要をお願いすることがあるでしょう。
・「檀家」とは?かかる費用や義務、檀家になる・やめるには?檀家にならず法要はできる?
(4)戒名料(浄土真宗は法名)
◇「戒名」とは、お釈迦様の弟子として、現代は亡くなった時に付けます
亡くなってすぐに納骨堂に入る場合、納骨堂の費用内訳には戒名料も入るでしょう。戒名には位があり、位によって戒名料も幅があるので、予算に合わせて調整します。
| <納骨堂の永代供養の費用:戒名料> [戒名料の相場]…約2万円~50万円 |
|
| ・ネット名づけ | …約2万円~10万円以上 |
| ・臨済宗 | …約30万円~100万円以上 |
| ・真言宗 | …約30万円~100万円以上 |
| ・天台宗 | …約30万円~100万円以上 |
| ・曹洞宗 | …約30万円~100万円以上 |
| ・浄土真宗 | …約20万円~50万円以上 |
しかし「戒名」はお釈迦様の弟子としての名前であり、仏教の教えによるものです。
現在では無宗教の家も多く、必ず戒名が必要とは言い切れません。
戒名を付けることに違和感がある場合は、親族と相談して検討しても良いでしょう。
納骨堂・永代供養墓・一般墓・樹木葬の比較

お墓の選び方を考えるとき、納骨堂や永代供養墓だけでなく、一般墓や樹木葬との違いを比較することが大切です。費用だけでなく、契約年数や管理の方法、家族にかかる負担の有無なども大きな判断材料になります。ここでは代表的な4つの供養形態を比較しながら解説します。
費用相場の違い(納骨堂・永代供養墓・一般墓・樹木葬)
費用相場を見ると、納骨堂は種類によって大きく幅があり、おおむね20万円〜180万円程度が目安です。永代供養墓は合同墓のような形態が多く、5万円〜50万円前後と比較的低価格で利用できるのが特徴です。
一般墓は墓石代や土地代がかかるため、100万円〜350万円程度と高額になりがちです。樹木葬は地域差がありますが、10万円〜80万円程度が多く、自然志向の方に選ばれています。
永代供養の仕組み。管理方法や契約年数の違い
納骨堂は施設が管理するため、遺族が掃除や草むしりを行う必要はありません。 契約は13年や33年などの期限付きが多く、契約満了後は合祀墓に移されるケースが一般的です。
永代供養墓も同様に管理者が供養を続けるため、後継者が不要で安心です。一般墓は子や孫などが代々継承して管理することが前提で、維持費や墓守の負担が生じます。樹木葬は永代供養型が多く、契約期間後に合祀される仕組みが主流です。
メリット・デメリットの比較
納骨堂は都市部でもアクセスしやすく、後継者不要で利用できる点が大きなメリットです。ただし、期限付き契約が多いため、長期的な供養を望む場合には注意が必要です。
永代供養墓は費用を抑えられる一方で、他の方と合同で埋葬されることに抵抗を感じる人もいます。一般墓は「代々のお墓」としての象徴性や独立性がありますが、維持費や管理の手間が大きな負担となります。
樹木葬は自然志向で人気が高まっていますが、埋葬できる人数や立地に制限があるケースもあります。
納骨堂を選ぶ際の注意点とデメリット

納骨堂や永代供養は、費用面や管理面で大きなメリットがある一方で、注意しておきたい点やデメリットも存在します。契約前にしっかり確認しておくことで、後悔のない選択につながります。
納骨堂の立地やアクセスの確認
納骨堂は都市部の駅近に多く便利ですが、実際に通いやすいかどうかは大切な判断基準です。自宅や親族の住まいからアクセスしやすい立地でなければ、せっかく選んでもお参りの機会が減ってしまう可能性があります。
管理体制・宗派・契約年数
施設によっては、特定の宗派や檀家制度が条件になる場合があります。また、契約年数が13年・33年などと決まっており、更新しなければ合祀墓に移されるケースも多いです。契約内容や管理体制を事前に確認し、納得できるかどうかを見極めることが大切です。
費用以外で注意すべき料金のポイント(永代供養料など)
費用相場だけで比較すると、納骨堂が安く見えることもありますが、実際には管理費・永代供養料・法要料などの料金が追加で必要になる場合があります。
また、ロッカー型などはシンプルで費用を抑えられる反面、供養の場として簡素に感じる方も少なくありません。墓じまいの場合、墓じまい料金の他、取り出した遺骨の移動料金・メンテナンス料金なども掛かる可能性があります。
よくある納骨堂のトラブルやデメリット(お墓との違い)
契約後に「宗派が合わなかった」「思ったより管理費が高かった」などのトラブルが起きるケースもあります。また生前契約の場合、契約者が亡くなった後に親族が内容を把握していないと、合祀の時期や供養方法に不安を抱くこともあります。
デメリットを理解したうえで、家族とよく相談して決めることが望ましいでしょう。
まとめ:納骨堂と永代供養の費用目安と選び方

納骨堂や永代供養の費用相場は、種類や立地によっておおむね20万円〜180万円ほどと幅があります。一般墓や樹木葬と比較しても選択肢が多く、それぞれにメリット・デメリットがあります。
費用だけで判断せず、契約年数・管理体制・宗派なども事前に確認し、家族と話し合って納得できる方法を選ぶことが大切です。自分たちに合った供養の形を見つけることで、安心して大切な方を供養できるでしょう。
・納骨堂の永代供養とは?お墓との違いやメリットデメリット、大阪に多い納骨堂4つの種類
お電話でも受け付けております















