
墓じまいと位牌の供養方法|永代供養・閉眼供養・費用の目安と注意点
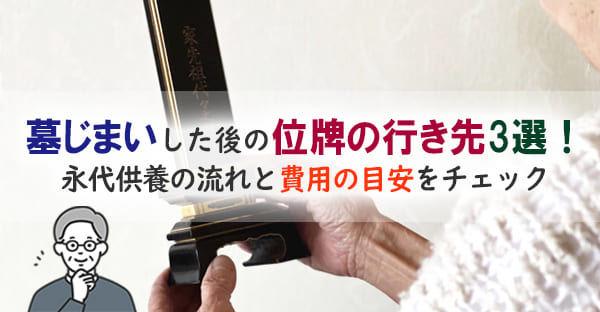
近年、墓じまいを行う家庭が増えるなか、「位牌はどうすればいいの?」と悩む声が多く聞かれます。
お墓の撤去や遺骨の永代供養を終えても、仏壇や位牌には「魂が宿る」とされ、簡単に処分できない大切な供養の対象です。
この記事では、墓じまい後に残る位牌の扱い方を中心に、永代供養・お焚き上げ・一時預かり・自宅供養などの主な方法と、それぞれの費用相場や注意点をわかりやすく解説します。
仏壇じまいや閉眼供養の流れ、お寺への相談の仕方まで触れていますので、墓じまいを検討中の方や、位牌の行き先に迷っている方はぜひ参考にしてください。

① 墓じまいと位牌の関係とは?|仏壇との違いと魂の意味

◇墓じまいを進める際、多くの方が迷うのが「位牌の扱い方」です。
お墓の撤去や遺骨の改葬手続きは明確でも、位牌は法律上の手続きがなく、各家庭やお寺の考え方によって対応が異なります。
しかし、位牌もまた「祭祀財産」のひとつとして、故人を供養するための大切な対象です。墓じまいでは遺骨をどうするかに加えて、仏壇や位牌の今後を考えることが重要になります。
位牌の役割と「魂」が宿る理由
位牌とは、故人の戒名(法名・法号)や没年月日、俗名などを記した木札であり、仏壇に安置して供養を行う対象です。葬儀で用いる白木の仮位牌をもとに、四十九日の忌明け後に本位牌を用意し、魂入れ(開眼供養)を行うことで、故人の「魂が宿る」とされています。
お墓の閉眼供養と同様に、位牌にも魂抜き(閉眼供養)を行い、適切な形で次の供養先へ移す必要があります。
つまり、位牌は「仏壇の中の小さなお墓」として、故人の象徴的な存在であると考えられているのです。
仏壇じまい・墓じまいで混同しやすいポイント
墓じまいと仏壇じまいは似ているようで、目的と手順が異なります。墓じまいでは遺骨の改葬や永代供養が中心ですが、仏壇じまいでは主に位牌や仏具の整理、魂抜き、お焚き上げなどを行います。
この2つを同時に進める場合、まずお墓→仏壇→位牌の順に閉眼供養を行うのが基本です。先に位牌を処分してしまうと、供養の対象がなくなってしまうため注意が必要です。
また、寺院に依頼する際は、墓じまいと仏壇じまいを一括で相談できるケースもあります。手続きの重複や費用トラブルを防ぐためにも、早めにお寺へ相談し、流れを確認しておくと安心です。
② 墓じまいを行うときに注意したい位牌と仏壇の整理ポイント

墓じまいは、単にお墓を撤去して更地に戻すだけでなく、仏壇や位牌などの供養対象をどのように扱うかを同時に考える必要があります。
遺骨の移動や改葬手続きには行政上の申請が伴いますが、仏壇や位牌は法律で定められた手続きがないため、対応を誤るとトラブルや後悔の原因になりかねません。
ここでは、整理を行ううえで注意したい2つのポイントを紹介します。
お墓・仏壇・位牌は「祭祀財産」
墓地や仏壇、位牌は「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、一般の相続財産とは異なる特別な扱いを受けます。祭祀財産とは、先祖の祭祀を継続して行うために必要な財産で、相続税の課税対象にもなりません。
そのため、墓じまいや仏壇じまいを行う場合は、親族間での承諾や継承者の確認が大切です。特に、複数の家族でお墓を共有している場合、位牌や仏壇を処分する前に関係者の意向を確認し、同意を得ておくことがトラブル防止につながります。
また、祭祀財産の扱いは法律よりも慣習に基づく部分が多いため、判断に迷う場合は菩提寺や霊園の管理者、または石材業者など専門家への相談をおすすめします。
墓じまい・仏壇じまいの「閉眼供養(魂抜き)」とは?手順と費用の目安
◇墓じまいや仏壇の整理で欠かせないのが「閉眼供養(へいがんくよう)」です。
閉眼供養とは、墓石や位牌に宿るとされる魂を抜き、ただの物に戻すための儀式を指します。
この儀式を行わずに解体工事や処分を進めてしまうと、宗教上「供養を怠った」とみなされる場合もあるため、注意が必要です。
閉眼供養は、菩提寺の僧侶に依頼し、読経をあげてもらう形で行われます。
一般的な手順は以下のとおりです。
② 当日は家族が立ち会い、僧侶による読経を受ける
③ 供養後にお布施を渡し、墓石や位牌の解体・処分を行う
費用の目安は、お布施として3万円〜5万円前後が相場です。
お墓や仏壇の解体・撤去費用は別途必要となるため、事前に見積もりを取っておくと安心でしょう。
また、墓じまいと仏壇じまいを同時に行う場合、閉眼供養をそれぞれで実施するか、一度にまとめて行うかをお寺に確認しておくと、費用や段取りの重複を避けられます。
③ 墓じまい後に位牌をどうする?主な3つの行き先

墓じまいを終えたあと、多くの方が悩むのが「残った位牌の行き先」をどうするかです。
遺骨は永代供養墓や納骨堂へ移すことができますが、位牌の扱いには明確な決まりがなく、対応を迷う方が少なくありません。
位牌は故人の魂が宿る依り代(よりしろ)とされるため、単なる「処分」ではなく、供養として扱うことが大切です。ここでは、墓じまい後に選ばれている代表的な3つの方法を紹介します。
① 永代供養に預ける(お寺・霊園に依頼)
◇もっとも多いのが、位牌をお寺や霊園に預けて永代供養をしてもらう方法です。
位牌専用の「位牌堂」や「位牌供養塔」を設けている寺院もあり、一定期間安置したのちにお焚き上げを行う形が一般的です。期間は三十三回忌を目安とするところが多く、契約年数によって費用が変動します。
また、墓じまいを依頼した霊園にそのまま位牌の永代供養をお願いできるケースもあります。お墓と位牌を同じ場所で管理できるため、供養が一括で完結しやすいのが利点です。
宗派による違いもあるため、依頼前にお寺へ確認し、永代供養の方法や費用相場(約3万円~50万円)を明確にしておくと安心です。
② 魂抜きしてお焚き上げする処分方法
「位牌を手放したいが、お寺に預ける予定はない」という場合は、魂抜きを行ったうえでお焚き上げを依頼する方法があります。
お焚き上げとは、故人の遺品や供養具を炎で焼き清め、感謝を込めて送り出す供養です。
まず菩提寺や僧侶に依頼し、読経による閉眼供養(魂抜き)を済ませてからお焚き上げを行います。
お焚き上げの費用は、お布施として1万円〜5万円前後が目安です。寺院や霊園によっては合同供養の一環として行われる場合もあります。
③ 一時預かり・自宅供養という選択肢
すぐに位牌を処分したくない場合や、家族が集まって供養を行う予定がある場合は、「一時預かり」や「自宅供養」という方法も選べます。
お寺や霊園では、1年〜数年間のあいだ位牌を預かってくれる「一時預かり供養」を設けており、預かり料の相場は1年あたり1万円〜3万円前後です。
また、近年は自宅に仏壇を置かず、位牌だけを残して手を合わせる「自宅供養」も増えています。管理費が不要で、いつでも故人に向き合える一方、後継者がいない場合は最終的な永代供養の検討も必要になります。
一時預かりや自宅供養を選ぶ際も、後の処分や供養方法をあらかじめ決めておくことが大切です。
④ 位牌の永代供養の流れと費用相場を解説

◇位牌の永代供養を希望する場合は、まず依頼先の選定と手順の理解が重要です。
墓じまい後にお寺や霊園へ位牌を預ける際、どのような流れで供養が行われ、どのくらいの費用がかかるのかを事前に把握しておくことで、後悔のない選択ができます。
ここでは、永代供養の依頼方法から流れ、費用の目安までを具体的に解説します。
墓じまい後、永代供養の依頼先を探すときのポイント
◇位牌の永代供養は、お寺・霊園・納骨堂などで依頼できます。
お寺に依頼する場合は、先祖代々の菩提寺に相談するのが基本です。すでに墓じまいを済ませている場合は、遺骨の永代供養をお願いした霊園に位牌も一緒に預けられるケースがあります。
永代供養の内容は施設によって異なり、以下のような違いがあります。
● 合祀墓と同じ敷地で位牌も供養されるタイプ
● 永代祠堂(浄土真宗など)で個別に供養を続けるタイプ
契約前に確認しておきたいのは、供養期間・費用・宗派の対応範囲・管理体制の4点です。
特に「永代供養」と言っても、実際には10年・33年など期間を設けている施設も多いため、契約内容を必ず確認しておきましょう。
依頼時は見積書を取り、複数施設の比較検討を行うことで、費用トラブルを防げます。
閉眼供養・開眼供養の流れ
◇位牌を永代供養に移す際は、まず魂抜きを行う閉眼供養(へいがんくよう)が必要です。
閉眼供養では、僧侶が読経を行い、位牌に宿る故人の魂を抜き取ります。
この儀式を行うことで、位牌は「ただの木の札」となり、永代供養先へ安全に移動できます。
永代供養先で安置する際には、改めて開眼供養(かいがんくよう)を行い、再び魂を入れることで供養が完了します。
流れの目安を解説すると次のとおりです。
② 日程を調整し、閉眼供養を実施
③ 位牌を永代供養先へ移動
④ 開眼供養を行い、位牌を安置
閉眼供養・開眼供養はいずれもお寺への依頼が基本で、お布施の目安は各3万円〜5万円前後です。
合同で行う場合や、遺骨の永代供養と同時に行う場合は、費用をまとめて相談するとよいでしょう。
[閉眼供養の進め方]
永代供養の費用目安(3万円〜50万円)と選び方
位牌の永代供養費用は、施設の規模や供養期間によって大きく異なります。
一般的な相場は3万円〜50万円前後ですが、個別安置型の位牌堂は費用が高く、合祀型やお焚き上げ型は比較的安価です。
以下のように供養方法によって目安を整理できます。
● 合祀供養塔タイプ:3万〜10万円
● お焚き上げ+過去帳記載:1万〜5万円
費用だけで判断せず、「供養をどの程度継続したいか」「お寺や霊園の信頼性」「家族の将来の訪問のしやすさ」なども考慮しましょう。
また、永代供養は一度依頼するとやり直しが難しいため、契約書の内容をよく確認し、疑問点は事前にお寺や管理者へ相談することが大切です。
⑤ 自宅で供養する場合の注意点と心構え

墓じまいを終えても、「位牌は自宅で供養したい」という家庭は少なくありません。
お墓を閉じても供養の気持ちは変わらず、仏壇や位牌を通じて日常的に手を合わせる方法を選ぶ人が増えています。
しかし、自宅で供養を続ける場合にも、いくつかの注意点があります。ここでは、仏壇や位牌を残す際のポイントと、後継者がいない場合の対処法を解説しますので、この機会に整理しておきましょう。
仏壇を残す場合のポイント
◇自宅で供養を行う場合、まず確認したいのが仏壇の設置環境と日常の供養方法です。
直射日光や湿気を避けた場所に安置し、定期的に清掃を行うことで、長期的にきれいな状態を保てます。
また、位牌は故人の魂が宿る依り代とされるため、扱いを誤らないよう注意が必要です。
…供花やお線香を欠かさず供えることも大切ですが、毎日でなくても「思い出したときに手を合わせる」気持ちが何よりの供養となります。
ただし、仏壇を残す場合は将来的な管理者(後継者)を決めておくことが重要です。
家のリフォームや転居に伴って仏壇の移動が必要になることもあるため、早めに親族と話し合い、今後の保管方法を共有しておくとよいでしょう。
後継者がいない場合の対処法
後継者がいない場合や、将来的に仏壇や位牌を維持できない見込みがある場合は、早めに永代供養やお焚き上げを検討しておくのがおすすめです。
自宅での供養は一時的には可能でも、将来残された人が困らないよう、次の段取りを明確にしておくことが大切です。
対処法としては、以下のような方法があります。
● お焚き上げ供養で魂抜きを行い、仏壇や位牌を丁寧に処分する
● 小型仏壇や写真立て型の「ミニ仏壇」に切り替えて省スペースで供養を続ける
特に、都市部ではマンション住まいの方が増えており、コンパクトな仏壇での自宅供養が主流になりつつあります。
自宅での供養を選ぶ際は、将来の暮らし方や家族構成の変化を考慮し、無理のない形を選ぶことが大切です。
⑥ まとめ|墓じまい後の位牌は「心を込めた供養」が何より大切

墓じまいを終えると、次に悩むのが位牌や仏壇の整理です。
お墓を閉じても、位牌には故人の魂が宿るとされているため、軽い気持ちで処分するのは避けたいところです。
永代供養に預ける方法や、お焚き上げ・一時預かり・自宅供養など、どの方法を選ぶ場合でも、共通して大切なのは「感謝の気持ちをもって供養する」ことです。
また、費用や手続きはお寺や霊園によって異なるため、必ず事前に確認しておきましょう。
特に位牌の永代供養は一度依頼するとやり直しが難しいため、費用の目安や供養期間、依頼内容をしっかり比較しておくことが後悔を防ぐポイントです。
墓じまいや仏壇じまいは、家族や親族との話し合いを経て決めることが何より大切です。
誰もが納得できる方法で位牌を供養することで、残された人の心にも区切りがつき、安心して故人を偲ぶことができるでしょう。
「墓じまいをした後の位牌」について迷っている方は、早めにお寺や専門業者に相談し、最適な永代供養の形を見つけてください。
[仏壇じまいについてより詳しく]
お電話でも受け付けております
















