
おひとりさま老後への8つの対策!貯金や身辺整理など早めの準備が大切

医学の進歩により、以前よりも長生きできる時代になりました。その分だけ生活、健康、自分が亡くなった後のことなど、心配事も増えているのではないでしょうか。
老後資金を貯えていても、年齢が進むに連れて衰えを実感する場面が多くなり、先々について不安を感じる人も多いでしょう。
身近に力になってくれる人がいれば心強いですが、独身者だけでなく、現在、家族と一緒に暮らしている方も、将来的におひとりさま老後を迎える可能性がまったくないとは言えません。
本記事では、おひとりさま老後で気がかりかな点や幸せに暮らしていくための備え、手続きになどに必要な契約について、解説しています。
記事に目を通しておくと、おひとりさま老後の対策や終活をスムーズに進められるでしょう。
おひとりさま老後に対する懸念を取り除き、活力あふれる日々を送れるよう、ぜひ本記事を役立ててください。
おひとりさま老後は増加している?

高齢化が進み男女ともに平均寿命が伸びていることから、おひとりさま老後は増加傾向にあるといいます。内閣府のデータによると1980年以降、65歳以上で一人暮らしをしている人の数は、右肩上がりです。
2015年には男性が約192万人、女性が約400万人でしたが、2030年には男性が293万人、女性が502万人を超え、その後もさらに増えると推測されています。
おひとりさま老後の懸念点
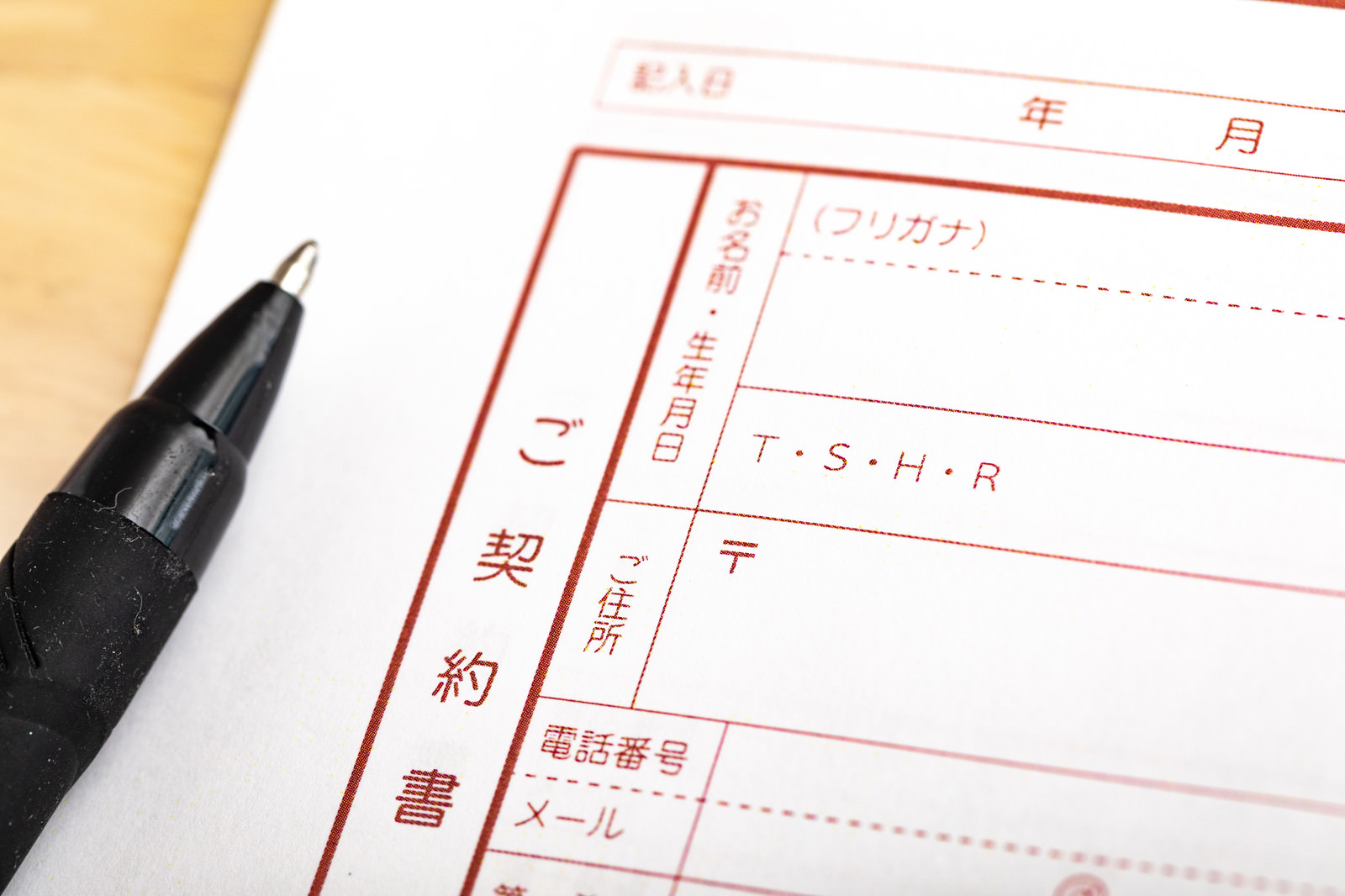
老後の一人暮らしには、さまざまなリスクが考えられます。頼れる人がいなければ何もかも自分で行わなければなりませんが、一人ではどうにもならないことも出てくるでしょう。
ここからは、おひとりさま老後で懸念される点を紹介していきます。どのようなことが快適な老後生活の障害になるのか、チェックしておきましょう。
経済的に厳しい側面がある
高齢者世帯の所得は、母子世帯を除いたそのほかの世帯の5割弱です。内閣府が行った経済生活に関する調査の「経済的な暮らし向きの問い」に対し、半数以上は「家計にあまりゆとりはないが心配なく暮らしていける」と答えています。
しかし、結婚したことがない方の約30%、配偶者と離別した方の約42%が、多少もしくは非常に心配であると回答していることから、一部の人を除いて経済的にはそれほど余裕のないことがうかがえます。
おひとりさま老後での主な出費
おひとりさま老後での主な出費は、下記のとおりです。
・食料
・住居
・光熱・水道
・家具・家事用品
・被服および履物
・保険・医療
・交通・通信
・教養娯楽
・交際費
・その他
65歳以上の単身無職世帯の家計収支データによると、食料、住居、高熱水道費が全体の46.5%を占めています。そのほか、お年玉などの贈与金を含む交際費、教養娯楽費、交通・通信費の割合が高めです。
身元保証人が見つからない
賃貸マンション、アパートの新規契約時などに、身元保証人を求められる場合があります。老人ホームなど高齢者施設の場合も、入居の際に身元保証人が必要になることが多いです。
身近に家族や親族、友達がいないおひとりさまは、身元保証人を求められても見つからず困惑してしまうでしょう。
契約書にサインすることで責任を負うことになるため、疎遠になっている人に急に身元保証人をお願いすることは難しく、代行業者へ依頼するケースも多いといいます。
気力が低下しやすい
おひとりさま老後で心配なのが、気力の低下です。新しいことをなかな覚えられず、新たなチャレンジがしにくいなど、気力が低下するきっかけはいくつかあります。
年を重ねていくうちに失う体験が増加するのも原因となるでしょう。例えば、定年退職により社会的な立場が失われます。また、身近な人との別れによって会話する機会が失われていきます。何かを失うことで環境が変化すると、寂しさや孤独を感じ、気力の低下につながるのです。
死後の財産処分やお墓の手続きをする人がいない
死後の準備をしていないと、亡くなった後に必要な財産処分やお墓の手続きをする人がいません。法定相続人、縁故者がおらず遺言も残していない場合、民法の相続財産管理制度に基づき、財産は国庫へ帰属されます。
葬式を出す人がいないときは、故人の戸籍から親族を探して遺体の引き取りをお願いすることになるでしょう。引き取り手がいなければ、法律に従い自治体で火葬し、決められた期間保管した後に無縁墓へ納められます。
出典:民法|e-Gov法令検索
おひとりさま老後への8つの対策

老後を一人で不安なく過ごしていくために、まずはできることから始めていきましょう。高齢になると、一人だけでは対処できないことも出てきます。
ここでは、おひとりさま老後に必要な8つの対策を紹介します。急なトラブルにも対応できるよう、早めに準備を進めておきましょう。
1:エンディングノートで準備すべきことを洗い出す
終活時に活用されているエンディングノートを使用すると、誰かに伝えておきたい内容や自分の気持ちを整理できます。ノートへ書き込むことにより、何を準備しておくべきか洗い出せるでしょう。
エンディングノートには、万が一の際に連絡してほしい人や、口頭では伝えにくい医療、介護、財産などについての記載が可能です。葬儀やお墓をどうするか、亡くなった後のことについても書き残せます。
2:かかりつけの病院を決める
高齢者が一人で生活する上でカギとなるのは、健康です。おひとりさまの場合は健康管理できるよう、かかりつけの医療機関を決めておきましょう。
かかりつけ医を持つと、健康に関して気になることを相談でき、必要なときに専門病院の紹介をお願いできます。
複数の医療機関から処方された薬を使用している場合は、かかりつけの薬局を決めておくと、服用の仕方についてアドバイスを受けられるでしょう。
3:万が一の身元保証人を探す
高齢になると病気やケガのリスクが高くなります。入院や手術が必要な際には、身元保証人のサインが必要です。突然の入院でも困らないよう、保証人になってくれる人を探しておきましょう。
万が一のときに入院にかかった費用を支払うのは、身元保証人です。身元保証人をお願いする場合は金銭面で迷惑がかからないよう、生命保険の受取人に指定する、遺言状を残すといった方法で、対策を講じておきましょう。
4:荷物や財産を整理する
おひとりさま老後では、不要な物や財産を整理しておくことも大切です。高齢になると家の中で転倒しケガをする可能性があります。体力があるうちに使わない物を処分して部屋の中をすっきりさせ、歩くスペースを作っておきましょう。
財産は後に相続問題へ発展する可能性があります。不要な不動産や銀行口座などを整理して、残す財産は財産目録へ書き残し、状況を明確にしておきましょう。
5:日頃から貯金を心がける
年金だけで生活費のすべてが賄えるとは限らないため、必要に迫られたときに使えるお金を用意しておくと安心です。
できれば受け取った年金の中から少しずつでも貯金するよう心がけてみましょう。たとえ少ない金額であっても貯め続けておくと、急にお金が必要になった場合に役立ちます。収入を意識し、お金の使い方が適切かどうかも考えてみましょう。
6:サービス付き高齢者向け住宅の入居を検討する
新たな住まいとして、サービス付き高齢者向け住宅への入居を検討してみましょう。バリアフリー構造の建物内には、生活に必要な設備が整っています。また、居室は広めに作られています。
ケアの専門家による生活相談や状況把握サービスを受けられ、介護と医療の両面で支えてもらえるため、おひとりさまでも安心です。
基本的なサービス以外は契約する住宅により内容が異なり、食事の提供や家事の援助を依頼できるところもあります。
7:社会との交流を保つ
スマートフォンやパソコンの普及により、誰かと直接会って話をする機会が少なくなり、高齢のおひとりさまがより孤立しやすい状況になっています。社会との交流を保っていると孤独を感じず、防犯の面でも安心できるでしょう。
日頃、連絡し合っている人がいると音信不通になった際、何かが起きていると気づいてもらえる可能性があります。家にこもらず、できるだけ趣味の仲間や地域の人々などとのコミュニケーションを図っていきましょう。
8:お墓や葬儀の準備をする
葬儀やお墓の手配は、自分でしておきます。どのようなスタイルを望んでいるのか、細かくエンディングノートに書き残しておくと分かりやすいでしょう。必要であれば、遺言状を準備します。
葬儀は、事前相談や自分の希望を伝えておく生前予約を受け付けている葬儀社に依頼しておくのも一つの方法です。
お墓は、生前に墓地や墓石を購入し準備できます。受け継ぐ人がいない場合は、維持管理の負担がないお墓を選ぶとよいでしょう。
おひとりさま老後で死後の手続きを進める方法

判断能力ができなくなった場合や死後に備えて、他人に財産の管理などをお願いできます。突然の出来事で困らないよう、前もって契約を結んでおきましょう。
ここからは、契約を含めさまざまな手続きを円滑に進めていくための方法を、5つ紹介していきます。
財産管理等委任契約
財産管理等委任契約は、自分で判断はできても、身体の自由がきかない、手が不自由などの理由で文字の記入が難しくなった場合に、信頼できる人物との間で交わす契約です。委任する内容は当事者で決められます。
契約を交わすことにより、財産管理や生活、療養面で必要な事務手続きの代理権を与えることが可能です。役所での書類取得、預貯金の引き出しなど、自分では困難なこともお願いできます。
死後事務委任契約
死後事務委任契約は、亡くなった後に必要となる諸手続きや事務を委任する契約です。契約により、死後のこまごまとした手続きを第三者に任せられます。第三者であれば個人、法人どちらでも契約可能です。
行政に対する書類の届け出、医療費の支払い、葬儀から埋葬までの手続き、賃貸住宅や入居していた施設に関連した支払いなど、幅広くサポートしてもらえます。
任意後見契約
任意後見契約は、将来に備えて結ぶ契約です。判断能力が欠けてきたとき、あらかじめ選んだ代理人に医療や介護、生活で必要な事務や財産管理を任せられます。
実際に判断能力が低下したときは、家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てが必要です。任意後見人は、任意後見監督人のもと契約で定めた事務や管理を適切に行い、支援していきます。
遺言書の作成
財産を譲りたい人がいる場合は、遺言書を作成しておきます。遺言書を準備しておくと、遺贈しやすくなるでしょう。
民法968条の要件を満たしている自筆証書遺言の形式に適合した遺言書は、申請が通れば法務局の遺言書保管所に預けられます。民法上の要件以外に、用紙、筆記具から様式に至るまで記載に関するルールが設けられているため、不備がないよう注意しましょう。
出典:03 遺言書の様式等についての注意事項|自筆証書遺言書保管制度
永代供養の契約
お墓を受け継ぐ人がいない、家族や親族に負担をかけたくないおひとりさまは、永代供養の契約をしておきましょう。永代供養にすると、お墓の掃除やメンテナンスの手間がかからず、法要の手配も必要ありません。お墓の管理や法要は、墓地の管理者に任せられます。
永代供養のお墓は、複数が一緒に埋葬される合葬型と個別埋葬型の2タイプあります。個別埋葬型は個別安置期間が決まっており、最終的に合葬となり供養されていくケースが多いでしょう。
おひとりさま老後の対策は早めに始めよう

おひとりさまは、誰にも気兼ねせず自由に生活できるイメージですが、老後の一人暮らしには懸念材料も多くあります。想定外のことが起きたときにスムーズに対処していくためには、さまざまな場面に対応できるよう、準備することが欠かせません。
準備を進めていくには、体力や気力が必要です。本記事で紹介した方法を参考にして、できるだけ早くおひとりさま老後の対策をして、不安を取り除きましょう。
お電話でも受け付けております















