
樹木葬の7つのデメリット!種類や埋葬までの流れもあわせて紹介

「樹木葬に興味があるけれど、どのようなデメリットがあるか知りたい」
「樹木葬の種類や埋葬方法の違いは?」
「樹木葬は実際にどのように行われる?」
樹木葬に興味がある人には、このような疑問や悩みがあるのではないでしょうか。
この記事では、樹木葬の種類や埋葬方法の違いを解説し、デメリット・メリット、樹木葬の埋葬までの流れを紹介しています。
樹木葬の種類と埋葬方法を知ることで、どの種類が自分に合っているのかが分かるでしょう。また、樹木葬のデメリット・メリットや埋葬までの流れを知っておくことで後悔することを防げ、事前の準備に役立ちます。
樹木葬がどのようなものか、全体的な流れや具体的な方法を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
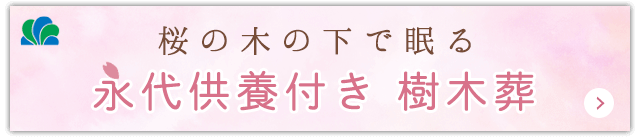
樹木葬とは?

近年、終活情報が取り上げられて樹木葬という言葉を耳にすることが増えていることでしょう。漠然としたイメージはあるものの、詳しい内容についてはご存じない方が多いのが実情でしょう。
樹木葬の大きな特徴としては、墓石の代わりに樹木や草花をシンボルとしたお墓であること、基本的に継承を必要としない永代供養であること、一般的なお墓よりも費用が安価であることが挙げられます。これらの特徴が現代社会の生活様式にマッチして注目が高まっているようです。
・樹木葬とはどういうものかを簡単解説!購入前に理解する4つのこと
樹木葬を行える墓地の種類

樹木葬を行う墓地の種類は、立地や埋葬方法などによって違ってきます。大きく分けると、一般的な自然葬というイメージに近い里山型と、都市に多く見られるタイプがあります。
寺院や霊園によって埋葬方法が限られていたり、埋葬後の管理方法などが違ったりするため、疑問点があった場合などは各施設に問い合わせることが必要です。
都市型の場合
申し込みごとに新しく樹木が植えられる場合もありますが、一般的な都市型の樹木葬ではシンボルツリーの周りに遺骨を埋葬するタイプが多いです。
比較的少ない土地でも樹木葬として埋葬できるという特徴があるため、都市部の霊園や寺院に樹木葬専用エリアとして設置されています。
都市型は、里山型と比べてアクセスが良い点や管理が行き届きやすいというメリットがあります。霊園によっては名前を彫刻した墓誌が設置されるため、お墓参りしやすいでしょう。
里山型の場合
自然豊かな地方に多いのが里山タイプの樹木葬です。山林などの広大な土地がある場所に、一区画に1本ずつシンボルツリーを植えて供養するケースが多いようです。
申し込みごとに新しい樹木を植えるタイプと、元から自生している樹木を利用するタイプがあります。
人は亡くなったら土に還るという思いがある方が希望されるタイプで、自然と密接した環境の中で供養をして欲しい方におすすめです。人を弔う墓地を里山のように自然保全も兼ねて整備するタイプの樹木葬です。
・樹木葬の里山型とは?決断前に確認したい、メリットやデメリットを解説!
樹木葬の埋葬方法の種類

一般的に自然に還る埋葬方法というイメージがある樹木葬ですが、 埋葬方法の選択を間違えると希望と違う結果になりかねません。
3つの埋葬方法の違いを理解して、自分の理想に合った選択ができるようにしましょう。
個別型の場合
シンボルツリーの周りに埋葬されるものの中でも、個人の区画が設けられているものを個別型と言います。1人分の埋葬場所が用意されており、土に分解されやすい骨袋や骨壺で埋葬されます。
メリットは、お参りする際に個人の区画があるためそこに向かってお参りできる点です。里山型の樹木葬に多く取り入れられています。
霊園によっては個別埋葬で契約したとしても、一定期間が経過した後に合祀埋葬になることがあるため、契約前に確認する必要があります。
集合型の場合
集合型の場合はシンボルツリーの周りに骨袋や骨壺などに入れて埋葬しますが、1人ずつ区画が分かれているわけではありません。
カロートというお墓の納骨室に当たる空間がないため、骨袋や骨壷が分解された後は遺骨が土に還っていく中で、他人の骨と混ざっていきます。
家族や友人など、希望する人と一緒に埋葬されたいという方に利用されます。
合祀型の場合
合祀型の樹木葬は、合祀墓や供養塔などの合葬墓と同じように、他人の遺骨とまとめて埋葬する方法です。
骨を骨袋から取り出し、まとめて一箇所に埋葬します。施設によっては遺骨を布で包んだり、埋葬場所を判別するためのプレートが置かれたりします。
低コストというメリットがありますが、他人と遺骨が混ざってしまうため、後で取り出すことができません。
・樹木葬で納骨する方法とは?メリットや手順についてもあわせて解説
樹木葬の7つのデメリット

新しいお墓のスタイルとして、樹木葬は明るい自然に囲まれたイメージが先行していますが、デメリットについても十分に検討をした上で選択されることをおすすめします。
後でトラブルにならないためにも樹木葬のデメリットについて、しっかりとチェックして理解を深めてから樹木葬を選ぶかどうかを考えましょう。
1:不便な場所にある場合もある
樹木葬のある霊園や寺院などへのアクセスも重要なポイントです。埋葬後に定期的なお参りをしたいと考えている場合は、交通手段が不便な場所にあることはデメリットだと言えるでしょう。
特に里山型の樹木葬は、都市部に設置することが不可能なため、どうしてもアクセスが悪くなってしまいます。山中にある場合は気軽にお参りに行くことは難しいでしょう。
契約する前に、実際にその場所を訪れてみることが大切です。その際、通いやすいかどうか、どのような交通手段を使うかなどを確認しましょう。
2:家族に理解されにくくトラブルになる場合もある
樹木葬は近年増えている新しい埋葬方法であるため、代々継いでいく伝統的なお墓を希望する方がいると家族で意見が分かれてしまうケースがあります。子供たちに迷惑をかけたくないと樹木葬を希望する親と子供の意見が合わず、トラブルに発展する可能性もあるでしょう。
購入予約をしたあとに家族に反対され、お墓選びを初めからやり直すなどのトラブルがあると、余計な労力がかかってしまうことになります。
お墓に対する考え方は親子でも違うことがあるため、家族間でしっかりと話し合っておくことをおすすめします。
3:家族全員が入るには狭い場合もある
樹木葬で使用できるスペースは限られており1人や2人の遺骨を入れるには問題ありませんが、家族全員が入るには狭い場合があります。また1人で契約する場合は一般的なお墓に比べて割安となりますが、人数が多くなると総額が高くなるため注意が必要です。
樹木葬を検討される場合は、事前に入れる人数の確認や家族で入る場合の費用を確認しておきましょう。
4:粉骨をしなければならない場合もある
5:墓参りや法事を行えない場合もある
樹木葬の霊園は屋外にあるためお供えや線香、ロウソクの使用を禁止している場合があります。火災予防の観点や清潔なイメージを保つこと、周りから虫や動物が集まることを防止する目的があります。
そのような施設ではシンボルツリーの樹木とは別の場所に、お供えや線香をあげて手を合わせることができる祭壇を備えている場合もあるため、事前にチェックしてください。
また、散骨などと比べればお参りする場所が分かりやすくはありますが、里山型の場合は一般のお墓参りのように目印や祈る対象となる墓碑はありません。
6:遺骨の取り出しや移動が難しい
樹木葬は一般的に自然の中で土に還す弔い方法のため、多くの霊園では遺骨を骨壺から取り出して土に埋める供養法を採用しています。そのため埋葬後に遺骨を取り出したくなっても対応できないことが多いため、注意しましょう。
また、樹木葬は多数の人が一緒に埋葬される合祀形式が多く、特定の個人だけの遺骨を取り出したり、ほかへ移動させたりすることはできません。樹木葬の中にも骨壺に入れて納骨するタイプもあるため、事前に確認しておけばデメリットではなくなります。
将来、お墓を購入したいなどの理由がある場合は、自宅で遺骨を保管したり、納骨堂を利用したりすることも検討してみてください。
7:季節によっては見た目が寂しくなる
樹木葬のデメリットの1つとして、季節によって景観が左右されやすいことが挙げられます。シンボルツリーの種類やその土地の特徴によって変わってきますが、一年中美しい景観が楽しめるとは限りません。
桜などのように、春に明るい雰囲気の場所であったとしても、冬になると葉が落ち寂しい印象の埋葬場所になるという可能性もあります。
できれば季節ごとにどのような景観になるか見学するか、問い合わせておくと良いでしょう。
ヤシロの樹木葬では、期限付きで個別の墓碑があり、お客さまのご要望に合わせて墓石への彫刻を依頼することができます。子どもにお墓の心配をかけさせたくない方や、自分らしいお墓に眠りたい方に選ばれています。
季節ごとにどのような景観になるか実際に見学してみたいという方は下記の資料を請求して相談してみましょう。
・樹木葬にデメリットはある?13のデメリットと欠点にならない対策、メリットまで解説!
樹木葬の7つのメリット

樹木葬のメリットは大きく分けると、埋葬後の負担、金銭面、心理的な面に関するものです。すべての人に当てはまるとは限りませんが、自分の理想は何かということと比較してみてください。
1:永代供養である
2:お墓を建てるよりお金がかかりにくい
個別に墓石を準備するにはかなりの費用が必要ですが、樹木葬ならそれよりも割安で購入できることが大きなメリットです。特に都会では土地代も高く、墓石まで考えるとお墓を持てない方も多くいます。樹木葬であれば費用面での負担を抑えられるでしょう。
中でも合祀埋葬は安価なタイプなため、お墓が高いことにデメリットを感じている方にとっては、樹木葬を選択する上で大きな理由になります。
また、従来のお墓にかかる維持費にはお寺への寄付金なども含まれますが、樹木葬の場合は不要なため、総合的にみても出費を抑えられます。
3:埋葬後に遺族が行う負担が少ない
埋葬後、一般的なお墓では、墓石を維持するための年間管理費が必要です。樹木葬の場合は埋葬後、一定期間個別に供養される間だけ維持費が必要となる場合が多いです。
また、樹木葬は永代供養であることが多い点も、埋葬後の負担が少ないことの理由です。永代供養であれば、従来していたような頻度でのお参りやお墓の掃除をする必要はありません。
4:一般の墓に比べて明るい雰囲気がある
樹木葬は、墓石ではなくシンボルツリーや草花を墓標とした葬送形式のため、桜やクスノキ、紅葉などが植えられた公園のような雰囲気で供養ができます。屋外の緑が多い景観の中で開放的な施設が多いことが、樹木葬を希望する方が増えている要因です。
施設によってガーデン風に植樹されたり里山の雰囲気の中で埋葬されたりするケースもあり、自分が希望するタイプの樹木葬を選ぶことができます。
5:花や木の下に埋葬できる
樹木葬では墓石ではなく、桜やハナミズキなどの樹木を墓標にします。中には、樹木ではなく草花が配置された庭園風になっているものもあります。
遺骨を直接土に埋葬するタイプの樹木葬では、自然の力で遺骨が土に還っていきます。故人が自然好きだったり、亡くなった後に自然に還りたいという希望があったりする場合は、故人が安心できるというメリットがあります。
自然に還るという点を重視する場合は、霊園や寺院によって遺骨の扱いが異なるため、埋葬方法の種類を事前に確認しましょう。
6:故人が見守ってきてくれた歳月を感じることができる
樹木葬でのシンボルツリーの魅力の一つは、植えられた後に育っていくということです。お参りに来た人が、シンボルツリーの成長を見て故人を重ねたり、見守ってくれているという感覚を抱いたりする人も多くいるでしょう。
7:宗旨宗派を問わない
樹木葬は自然の中に眠ることが基本思想のため、宗旨宗派を問わず埋葬できるところが多く、宗教によるしきたりにも縛られません。無宗教の方が自然の中で安らかに眠りたいという願いを叶えることが可能です。
中には、個別の法要は寺院の宗派で行うという条件を付けているケースがあるため、契約前にしっかりと確認しておきましょう。
・樹木葬とは?特徴やかかる費用、メリット・デメリットについても紹介
樹木葬の埋葬までの流れ

ほとんどの霊園では、生前から樹木葬の申し込みを受け付けています。
樹木葬の埋葬までの流れを確認し、亡くなってから埋葬までが円滑に進められるよう、事前にできることはすべてやっておきましょう。
特に、どの埋葬方法か決める、樹木葬について家族と合意を持つなど、トラブルになりそうな項目はなるべく解決策を用意しておくと安心です。
樹木葬を行う霊園の情報収集
樹木葬を検討する場合は、初めに樹木葬を行っている霊園について情報収集を行いましょう。近所の石材店に足を運んだり、ネットで霊園の情報を探してみたりして好みに合った施設には資料請求をしてもよいでしょう。
樹木葬を購入した方の評価が見られる総合サイトなどもあるので、見学する前に大体の雰囲気を掴むのがおすすめです。
霊園の現地見学
ネットなどで情報収集をして、ある程度希望に沿った施設を絞り込んだら、次に霊園に直接訪問して現地見学を行いましょう。お世話になる施設のため、慎重に細部まで確認しながら希望も伝えて納得できるまで何度も足を運んでください。
可能であれば家族も一緒に現地見学を行うことをおすすめします。墓地の実際の雰囲気や近隣の環境についても確認し、具体的な供養のプラン・料金のほか交通アクセスについても確認してください。
樹木葬の契約
現地を確認して家族も含めて納得し気に入ったら、次は樹木葬の契約をして申し込み、費用を支払います。1人で結論を出さず家族と一緒に見学して了解を得てから契約することが、後でトラブルにならない最善の方法です。
墓地選びは焦って短期間で決めてしまわず、じっくりと比較検討を重ねてから結論を出してください。
墓地使用許可証の受取
樹木葬の契約が終わり、墓地使用料と管理費を支払うと墓地使用許可証が発行されるため、受領します。ここまでの手続きを終えておけば、契約者が亡くなってからスムーズに埋葬が行えます。
墓地の使用は誰でもできるものではなく、自治体に届け出をして正しく手続きをしなければいけません。生前の元気な間にこれらの手続きを済ませておけば安心です。
死亡届の提出
故人が病院で亡くなった場合は病院で死亡診断書が発行され、事故などの場合は警察による検視の後に死体検案書が発行されます。それらの書類を元に死亡から7日以内に市役所や区役所に死亡届を提出しなければなりません。
火葬証明証は納骨当日に持参しなければならない重要書類で、これがないと火葬ができないため、注意が必要です。
出典|参照:死亡届|法務省
納骨式の日程などの打ち合わせ
生前に契約している霊園に家族が連絡をして、納骨式や埋葬の日程などの打ち合わせを行います。遺骨は霊園に預けて事前に粉骨して埋葬するため、通常は一週間程度の時間が必要です。
埋葬と同時に法事を行う場合は、その旨を伝えて霊園と打ち合わせを行っておけばスムーズに進めることができます。
火葬・埋葬許可証の受取
故人の火葬が終わると埋葬許可証がもらえますが、一般的に火葬許可証と埋葬許可証は同じ用紙になっていることが多いです。火葬許可証を火葬場の担当者に渡して、火葬許可証に日付を押印したものが埋葬許可証になります
火葬場や葬儀業者の担当者が、書類の紛失を防ぐために納骨した骨壺の箱に埋葬許可証を入れるのが一般的です。
納骨式・埋葬
一般的な墓石のお墓も樹木葬の場合も同様ですが、納骨する際には墓地管理者へ埋葬許可証を提出します。これがなければいくら生前に契約していても納骨することができません。
実際の埋葬方法は施設によって違いはありますが、樹木葬の所定の場所を掘り遺骨を埋めます。次に土を埋めたらお花をお供えして、最後に住職によるお経の供養などがあり終了です。
樹木葬以外で供養する方法

樹木葬以外にも、お墓を建てない供養方法があります。自然に還すか埋葬かなどの違いがあるので、埋葬後の管理やお参りを希望するかなどの条件から比較できるでしょう。
海洋葬
海洋葬は遺骨を海に散骨する供養方法です。散骨した後はそのまま海に還ることになります。海が好きだった故人にとっては、安心して眠れる方法だと言えるでしょう。
一般的な海洋葬では、クルーザーで外洋に出て、セレモニー後に散骨を行います。
納骨堂
納骨堂とは、遺骨を納めるための専用の施設です。一時的に預かってくれるような施設もありますが、一般的には永代供養を請け負ってくれる施設とされています。
ロッカー型が主流でしたが、現代の納骨堂は充実した設備を備えているものも増えており、気軽にお参りができる新しい形の葬送として認識されています。
特に都心部に多く、お墓の継承問題を解消する目的で利用されるケースが増えています。個別スペースが確保され、運営側との付き合いなども不要な点が、現代人のライフスタイルに向いていると言えるでしょう。
樹木葬のデメリット・メリットを知って自分に合う供養方法を見つけよう

ここまで樹木葬の種類や埋葬方法の違い、デメリット・メリットについて解説しました。樹木葬といっても様々なタイプがあることが分かったのではないでしょうか。
埋葬までの流れや、ほかの供養方法も紹介しました。全体の流れやいくつかの選択肢を知っておくことで、比較して検討することができます。
本記事を読むことで、希望する供養方法がどのようなものなのか、より具体的に考えるための参考にしてください。
お電話でも受け付けております















