
墓じまい後の遺骨の供養方法は?取り出す際の注意点や処分方法も解説

「墓じまいではどのようなことをするの?」
「後継者がいないから墓じまいしたいけれど、その後の遺骨はどうなる?」
「墓じまいした後の供養はどうしたらいい?」
このように、将来お墓を維持していくのは困難だと感じ、墓じまいしたいと考えながらも、やり方や、取り出した遺骨の扱い、供養方法についてよく分からず、不安を抱いている方もおられるのではないでしょうか。
本記事では、墓じまいについての説明、行う手順、墓じまい後の遺骨の供養方法、実際に行う際に起こりやすいトラブルや注意点を紹介するとともに、その後の供養を自分で行わない方法も取り上げています。
記事を読むと墓じまいの流れや遺骨の扱い方、トラブルを回避する方法などについて把握でき、遺骨を正しく取り扱えるようになるでしょう。
お墓の扱いに悩んでいる方、墓じまいに不安がある方は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。
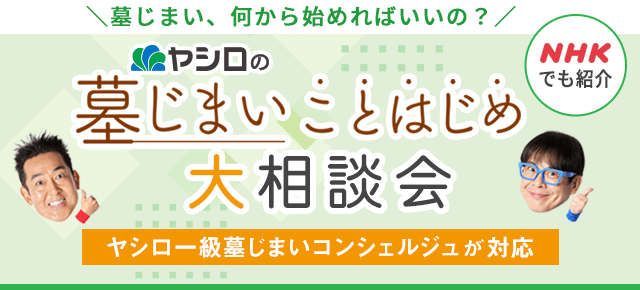
そもそも「墓じまい」とは?

お墓の中に眠っている家族や親族、ご先祖の遺骨を取り出し、新しい場所に移すことを墓じまいと言います。居住地と離れていて墓参りやお墓の管理ができない、跡継ぎがおらず継承が難しいとの理由から、墓じまいしたいと考える方は増加傾向にあります。
墓じまいには実際に墓地で行われる作業の他、行政手続きも必要です。親族や墓地の管理者など、周囲へも気を配りましょう。
墓じまいの6つの手順

手続きが必要な墓じまいは、思い立ってもすぐに実行するのは難しく、場合によってはお墓に関わる人々との間でトラブルとなり円滑に進まないこともあるでしょう。
ここからは、順調に進める上で欠かせない墓じまいの手順をご紹介します。スムーズに墓じまいをするポイントとともに、しっかり把握しておきましょう。
1:親族に相談して理解を得る
たとえ自分が継承し管理しているお墓であっても、親族に相談せず墓じまいをしてしまうと、トラブルの火種となります。墓じまいを考えている時は、お墓参りに来る親族のことをないがしろにせず、事前に相談して理解を得ましょう。
相談せずに墓じまいしてしまうと、後になって勝手に行ったことを批判され、関係にひびが入る可能性もあります。自分だけで決めて行動せず、親族が納得した上で準備を始めましょう。
2:墓地のあるお寺に墓じまいの意向を伝える
お墓のある寺院にも墓じまいの考えがあることを伝えておきましょう。墓じまいは、その寺院の檀家を離れることを意味します。離壇はお寺の経営に影響するため、前もって話をして、できる限り迷惑がかからないよう心掛けましょう。
話す時はまず、これまでの感謝を伝えてから墓じまいする理由を丁寧に説明します。長年にわたりお世話になってきた寺院との関係を大切にしながら、話を進めていくのがポイントです。
3:墓じまいに必要な書類の手配と行政手続き
埋葬されている遺骨を取り出して別の場所に移す場合には、現在遺骨が埋葬されている墓地のある市区町村から改葬の許可を得る必要があります。
墓じまいの際は、改葬許可申請証、埋蔵証明書、受入証明書など、決められた必要書類を準備して担当の役所へ提出し、改装許可証の交付を受けましょう。
改葬許可申請書は遺骨1柱につき1枚必要です。あらかじめ納骨されている遺骨の数を確認しておきましょう。
4:閉眼供養を行う
お墓から遺骨を移動する際に必要になるのが閉眼供養です。閉眼供養はお墓に宿っている魂を抜く儀式で、魂抜き、お精根抜き、抜魂などとも呼ばれ、亡くなった後、すぐに成仏すると考えられている浄土真宗では遷仏法要と言います。
お墓は建立時に開眼供養によって魂を入れることで、物から礼拝対象へと変わります。ですから、墓じまいでは閉眼供養によって魂を抜いてお墓を礼拝対象でなくした後に、処分した方が良いとされているのです。
5:遺骨の取り出し
お墓の中の遺骨は、閉眼供養終了後に墓じまいを依頼していた石材店や代行業者などに取り出してもらいます。取り出し時に、自分が把握していない遺骨がないか確認しましょう。
代々受け継がれている古いお墓は、先祖の遺骨やお墓の持ち主が知らない親族の遺骨が埋葬されていて、カロート内に想定していたよりも多くの遺骨が並んでいる場合があります。新たに見つかった遺骨の分も改装許可証を追加しましょう。
6:お墓の解体を行う
墓じまいをして遺骨を墓地から取り出す際の注意点

悩んだ末に墓じまいを決めた時には、できるだけトラブルが起こらないよう細かい部分にも目を向けましょう。墓じまいは、きちんと手順を踏んでいないと思い通り進まないおそれがあります。閉眼供養の必要性や石材店が請け負える仕事の範囲も把握しておきましょう。
ここでは、墓じまいで遺骨を取り出す際に気をつけておくべき点についてご紹介します。
親族や墓地の管理者に事前にしっかり相談する
墓じまいを考えた時点で、親族や墓地の管理者へ相談しましょう。お墓を移すのは良くないなど、考えの違う親族がいる可能性もあります。事前に新たな供養方法を伝えて親族の了承を得て、費用の負担についても話し合っておくと問題が生じにくくなるでしょう。
寺院内にお墓がある場合は、きちんと話し合う場を持ち、墓じまいしたいことを相談しておくと、離壇に関するトラブルを回避でき、手続きがスムーズに運ぶ可能性が高まります。
閉眼供養を行ってから遺骨を取り出してもらう
お墓には埋葬されている方の魂や想いが宿っていると考えられているため、できるだけ閉眼供養を行ってから遺骨を取り出すようにします。親族の中には、閉眼供養の儀式をせずに墓石に魂が宿ったまま遺骨を取り出すことを、快く思わない方もいるでしょう。
また、魂を抜いていないと、業者から遺骨の取り出し、解体、撤去を断られる可能性もあります。滞りなく墓じまいを進めるには、閉眼供養をきちんとすることが大切です。
石材店は遺骨の預かりや引取りをしない
石材店に墓じまいを依頼しても、取り出した後の遺骨の預かりや引き取りまでは請け負ってもらえません。
依頼すれば遺骨の移動や処分までトータル的に引き受けてもらえると思いがちですが、墓じまいの際に石材店が行うのは遺骨の取り出し、解体、撤去、整地までです。
墓じまい前に、取り出した遺骨をどのような形で供養していくのか考えて具体的な方法を決めておきましょう。
墓じまいで取り出した遺骨の供養方法

墓じまいで取り出した遺骨はどうするのが良いのでしょうか。遺骨の供養は、新しいお墓に移す方法だけではありません。手を合わせる場所を残したい、自然に還したい、身近に置きたいなど、管理していく方の希望や費用の負担を考えて供養の形を選んでみましょう。
ここでは、スタイルの異なる3つの方法を紹介します。それぞれのメリットとデメリットを比較してみましょう。
永代供養墓で供養
海や山に散骨
遺骨の新たな埋葬や供養に困った場合、散骨も1つの手段となります。散骨とは火葬した後の遺骨を粉末状にし、山や海などに撒く供養の方法です。一定の場所へ遺骨を納めないことから、改葬や埋葬には当たりません。
散骨についての法律はありませんが、ルールやマナーに反する場所を避けて行われています。市町村によっては条例で散骨が禁止されている場合や、散骨場が規制されていることもあるため注意が必要です。
自宅で保管し手元供養
手元供養とは、墓じまい後の遺骨を改めてどこかへ埋葬せず、身の回りに置いて故人を偲ぶ方法です。
控えめなデザインの小さな骨壷を部屋に置く、遺骨を納められるペンダント、ロケットペンダントなどを肌身離さず持ち歩くなどいくつかの方法があります。
手元に置くと供養が楽になり、新たな費用も発生しませんが、通常のお墓とまるで違うスタイルは、親族からの理解を得にくい場合もあるでしょう。
遺骨を処分したい場合はどうすれば良い?

墓じまいした後の遺骨をどうすべきか、悩んでしまう場合もあるのではないでしょうか。先祖の遺骨とはいえ、自分の手で供養し続けていくのは負担がかかります。
ここでは、将来を見越して遺骨の処分を決めた際にどういった方法があるのかを解説します。やってはいけない遺骨の処分方法も一緒に確認しておきましょう。
業者に散骨してもらう
取り出した遺骨は、業者へ依頼すると代理で散骨してもらえます。散骨は個人でも行えますが、規定の確認や散骨場所周辺への配慮も必要になり簡単にはできません。
ルールやマナーを守らない代行業者も見受けられるため、依頼する前に、散骨に関する資格や知識を持ったスタッフの在籍、プランの詳細をしっかり確かめましょう。値段を重視し料金の安い業者を選んでも、散骨にかかる費用が全て含まれているとは限りません。
合祀墓に納骨・埋葬する
遺骨をそのまま捨てるのはNG
墓じまい後の遺骨の扱いに困っても、ゴミとして処分したり、埋葬したりすることは法律で禁じられているため注意しましょう。遺骨を捨てる行為は、刑法190条の死体損壊等の罪にあたり処罰の対象となります。遺骨を処理し粉末状にしてから廃棄、埋葬した場合も同様です。
また、墓地、埋葬等に関する法律でも、墓地以外の区域への埋葬及び埋蔵を禁じています。自宅の庭であっても勝手に埋葬することはできません。
出典|参照:刑法 |e-Gov法令検索
出典|参照:墓地、埋葬等に関する法律|e-Gov法令検索
遺骨や骨壺を新しい供養先に移動する方法
墓じまい後に遺骨や骨壷を供養先へ移動させる場合、いくつかの方法から選択できます。直接遺骨を運ぶほか、宅配や納骨を支援している法人のサービスを利用し運んでもらう方法を選ぶことも可能です。
遺骨を荷物として取り扱っている宅配業者は限られています。ここでは、各方法とそれぞれの注意点について紹介していきます。
車や電車などを利用して自分で運ぶ
遺骨はマイカーや公共交通機関を利用し自分で運べます。自動車で運ぶ場合は、座席から骨壷が移動、落下しないよう注意し、運転手以外の人が遺骨の入った骨壺をしっかり抱えるか、シートベルトをかけ、固定するようにして運びましょう。
公共交通機関を利用する際は、他人の迷惑にならないように注意します。中が見えない専用のバッグや風呂敷を使い遺骨が安定するようにして、丁寧に運びましょう。
ゆうパックで郵送する
宅配サービスを使って供養してもらう場所まで遺骨を届けてもらう送骨は、遺骨を運ぶ手段として徐々に定着してきています。遺骨の宅配を受け付けているのは、日本郵政のゆうパックのみです。ヤマト運輸や佐川急便では送れないものに遺骨が含まれています。
ゆうパックで遺骨を送る際は、蓋部分をガムテープなどで固定し、緩衝材を使って割れないように保護しましょう。
NPO法人の納骨サービスを利用する
墓じまい後の遺骨はきちんと供養しよう

墓じまいした後の遺骨の供養は様々な方法があります。直接接点のなかった先祖の遺骨であっても、敬う気持ちを忘れずきちんと供養しましょう。
遺骨の処分を考える場合には、違法になるようなやり方を取らず、正しい方法で手放すことをおすすめします。
記事で紹介した内容を参考に、遺骨の供養方法についての知識を深め、自分たちの希望に合う供養方法を見つけてみましょう。
お電話でも受け付けております
















