
永代供養の費用は誰が払う?相場と分担方法、払えない時の対策まで解説

永代供養の費用は誰が払うのか──お墓の継承や墓じまいが増える中で、多くのご家族が直面する疑問です。
一般的には祭祀継承者が負担しますが、家族や親族で分担する場合や、生前に本人が契約して払うケースもあります。永代供養の費用は誰が払うかによってトラブルにつながることもあるため、相場を知り、事前に話し合っておくことが大切です。
本記事では、永代供養の費用は誰が払うのか、相場の目安や分担方法、支払いが難しい時の対策まで分かりやすく解説します。
永代供養の費用は誰が払う?
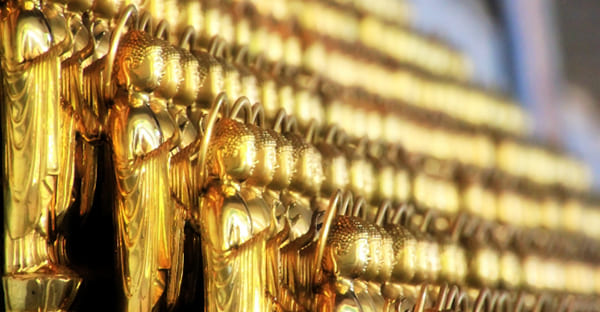
「永代供養」とは霊園・墓地などの墓地管理者がご家族に代わって、ご遺骨の供養や管理を永代に渡り行うことです。永代供養自体には形がないため、さまざまな形態があります。
最初から不特定多数のご遺骨と一緒に同じ場所へ合祀埋葬される「合祀永代供養」もあれば、墓石を建てた個別墓に永代供養を付ける形態もあるでしょう。
そのため永代供養は約5万円~150万円と費用幅が広いです。永代供養は1柱ごとに費用を出すでしょう。そのあめ墓じまいなど複数のご遺骨を永代供養する場合は、それだけ費用が高くなります。
永代供養の費用は誰が払う?①祭祀継承者
一般的に永代供養の費用は祭祀継承者が払います。「祭祀継承者」とは、お墓やご位牌など先祖供養のために用いる祭祀財産の継承者です。相続財産とは別の扱いになります。
相続税はかかりませんが、家庭裁判所の判断で最終的に祭祀継承者に決まると、相続放棄をしても祭祀財産は放棄できません。
祭祀財産の放棄はできませんが、祭祀財産に対する決定権があります。お墓やご位牌の維持管理が難しい場合には、墓じまい・仏壇じまいもできるでしょう。
一方で墓じまいや仏壇じまいは、名義人(持ち主)である祭祀継承者が払う流れが一般的です。永代供養の費用を分担するためには、ご家族や親族との話し合いが不可欠です。
・お墓の継承は相続放棄をしたらどうなる?永代供養・相続税の負担についても詳しく解説!
永代供養の費用は誰が払う?②家族や親族で分担(注意点)
ただ祭祀継承者がひとりで永代供養の費用を負担するばかりではありません。ご家族・親族で話し合いの場を設けましょう。
割合はご家族によりさまざまですが、先祖代々墓や両親のお墓であれば、故人やお墓に関わるご家族や親族が共同で負担するケースは多いです。
まずはご家族から理解を得て、複数人で納骨検討先の見学などの準備を済ませた後、見積もりをもらって親族へ相談してみるとスムーズに進むでしょう。
・墓じまいで親族トラブルは起きやすい?起きる割合や理由、穏やかに墓じまいを進める対策
永代供養の費用は誰が払う?③本人が生前に
生前契約により本人が永代供養の費用を払うケースが増えました。
継承者のあてがないお墓は生前に墓じまいを済ませ、取り出したご遺骨の永代供養まで済ませる墓主も増えています。
自分亡き後の葬儀・葬送・相続をプロデュースする、人生の終末に向けた活動「終活(しゅうかつ)」の広がりが背景にあるでしょう。
お墓代やご遺骨の納骨費用は遺産から出すことができません。そのため生前に本人が永代供養の費用を払うことで相続財産が減り、相続税対策にもなります。
・【大阪の終活】生前にお墓を建てると相続税が軽減されるの?体験者が語る、生前墓を建てる3つのメリット
永代供養の費用相場と形態や負担の違い

永代供養の費用は、納骨方法や形態によって大きく異なります。一般的な相場は1柱あたり5万円~150万円前後ですが、合祀型か個別型かによって費用の幅が変わります。ここでは代表的な2つのタイプについて、永代供養の費用相場を整理します。
合祀永代供養は誰が払う?費用相場は?
複数のご遺骨をまとめて埋葬する「合祀永代供養」は、最も費用を抑えやすい方法です。
相場は5万円~15万円程度が一般的で、年間管理費も不要な場合が多く、将来的な負担が少ないのが特徴です。ただし一度合祀するとご遺骨を取り出すことはできませんので、納骨方法を選ぶ際には注意が必要です。
個別永代供養は誰が払う?費用相場は?
一定期間は個別にご遺骨を安置できる「個別永代供養」の場合、相場は30万円~150万円程度となります。安置期間が過ぎると合祀に移されるプランも多く、その場合は契約時に管理費が必要です。
個別に墓石や納骨堂を設けるタイプではさらに費用が高くなる傾向がありますが、合祀よりも丁寧に供養を続けたい方に選ばれています。
永代供養と納骨堂の費用はどう違う?

お墓の選択肢として「永代供養」と「納骨堂」はよく比較されます。どちらも後継者がいなくても利用できる点が共通していますが、費用の仕組みや相場には違いがあります。
永代供養と納骨堂の費用を正しく理解することで、将来の負担を見据えた選択がしやすくなるでしょう。
納骨堂は誰が払う?費用相場は?
納骨堂とは、屋内にご遺骨を安置する施設のことです。霊園や寺院が管理しており、個別に遺骨を収めるロッカー型や仏壇型、自動搬送式など種類が豊富です。納骨堂の費用相場はタイプによって大きく異なり、10万円台から200万円前後まで幅があります。
例えば、ロッカー型納骨堂は比較的安価で20万円~50万円程度、仏壇型や自動搬送式は50万円~150万円前後が目安です。さらに年間管理費が5千円~2万円程度必要になるケースも多く、長期間安置するほど費用がかさむ点には注意が必要です。
永代供養との費用比較
一方、永代供養は合祀型や個別安置型などにより費用が異なりますが、相場は5万円~150万円程度が一般的です。合祀永代供養であれば5万~15万円程度と低価格で利用でき、管理費がかからない場合もあります。
納骨堂との大きな違いは「期間と管理費」です。納骨堂は契約期間や年間管理費が発生する場合が多く、長期的には費用が高くなることがあります。これに対して永代供養は、初期費用だけで永続的に供養が続けられるプランも多く、後継者に負担を残さない選択肢として注目されています。
永代供養の費用はいつまで払う?

「永代供養だから一度払えば安心」と思う方も多いですが、実際には契約内容によって費用をいつまで払うのかが異なります。永代供養の費用はいつまで払う必要があるのかを確認しておくことで、将来の負担や親族間のトラブルを防ぐことができます。
初期費用のみで済む場合
合祀型の永代供養では、契約時に初期費用を支払えばその後の管理費は不要となるケースが一般的です。
例えば、1霊あたり5万円~15万円程度の費用を支払うと、永続的に納骨・供養を霊園や寺院に任せることができます。この場合、家族や親族が追加で費用を払う必要はなく、後継ぎがいない方や将来の負担を減らしたい方に選ばれています。
管理費がかかる場合
一方、個別安置型の永代供養では管理費が必要になる場合があります。
最初の契約で30万円~150万円程度を支払ったうえで、安置期間中は年間5千円~2万円程度の管理費を納めるのが一般的です。一定期間が過ぎると合祀に移されるプランも多く、その時点で管理費の支払いは終了します。
「永代供養の費用はいつまで払うのか」は契約した墓の形態によって変わるため、契約前に納骨の方法や管理費の有無を必ず確認することが大切です。費用の仕組みを理解しておけば、誰が費用を負担するのかを家族で話し合う際にも安心です。
永代供養の契約や手続きは誰がする?

永代供養を利用するとき、「契約や手続きは誰がするのか」と迷うご家族も多いです。永代供養は費用を誰が払うかと同じく、契約や納骨の手続きを誰がするのかを明確にしておかないと、後々のトラブルにつながります。ここでは一般的なケースを整理してご紹介します。
祭祀継承者が行う場合
通常、祭祀財産の継承者が永代供養の契約や手続きを行うのが基本です。お墓や仏壇などの管理を担う立場にあるため、永代供養の契約もその延長として任されることが多いでしょう。
契約の際には、納骨の方法や費用の相場、管理費がかかるかどうかを確認し、家族や親族に共有しておくことが大切です。
生前に本人が契約する場合
近年は、お墓に入る本人が生前に永代供養を契約するケースも増えています。
いわゆる「寿陵(じゅりょう)」と呼ばれる生前契約は、残された家族の負担を減らし、誰が手続きをするかを明確にできる点で安心です。本人が契約しておけば、親族間で「誰がするのか」と揉めることもなく、費用もあらかじめ本人が用意するため、スムーズに永代供養を進められます。
葬儀費用は誰が払う?

経済産業省が発表した2023年度に行われた葬儀費用の全国平均額は、約120万円でした。
棺や祭壇などの葬儀用品一式で約112万円、参列者への飲食振る舞いが平均約12万円、お布施が通夜から告別式まで通して約20万円~50万円と言う結果です。
ただし現代の葬儀は一般葬ばかりではなく、参列者の人数が限られた「家族葬」・葬儀を1日に省略した「一日葬」なども見受けます。規模の小さい家族葬では約40万円ほど葬儀プランもあるでしょう。
・経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」2023(葬祭業)
①一般的には誰が払う?喪主
葬儀費用は一般的に喪主が払います。喪主は故人と最も近しいご遺族から選ばれるでしょう。ご遺族で話し合い決めますが、配偶者や長男・長女が喪主になることが多い傾向です。
故人が国民保険に加入していれば、自治体の役所窓口で申請をすることで葬儀費用の補助金が支給されます。自治体によって金額は異なりますが、約3万円~7万円が相場です。
生活保護を受けていた場合は、葬祭扶助制度が利用できます。葬祭扶助は支給する自治体により異なりますが、子どもは約15万円以内・大人は約20万円以内が金額相場です。
・喪主が行う葬儀の準備とは何?喪主や遺族にしかできない確認事項、8つのチェックリスト
②誰が払う?施主の場合
喪主が高齢であるなど事情があり、葬儀費用を負担できない時には施主を立てます。高齢の配偶者が喪主となり、子どもが施主として裏方を務めるケースなどです。
「施主」は葬儀社との打ち合わせや葬儀費用の支払いなど、喪主をサポートします。
施主を立てる場合、喪主は僧侶や参列者への御挨拶・喪主挨拶を担い、施主は葬祭業者との打ち合わせや葬儀費用を払う流れになるでしょう。
また喪主となるご遺族にショックが大きい時にも、施主を立てることがあります。この場合は臨機応変に対応することが多いです。
③遺産から支払う
葬儀費用に関しては、故人が亡くなった後も遺産から支払うことができます。ただし相続人全員の同意が必要になるでしょう。
故人の預貯金口座から葬儀費用を捻出できますが、金融機関は故人が亡くなったことを把握した時点で口座を凍結するので注意をしてください。
本来であれば故人の預貯金口座からお金を引き出すためには、遺産分割協議により相続人全員の同意が必要ですよね。
けれども葬儀費用であれば故人の口座凍結中であっても「遺産分割前の相続預金の払い戻し申請」として仮払いができるでしょう。ただし法定相続分の1/3までと言う制限があるのでご注意ください。
・【家族が亡くなったら】故人の銀行口座の手続き。相続人が行う3つのこと |永代供養ナビ
④生前に本人が支払う
祭祀財産と同様に終活をきっかけとして、生前に本人が葬儀予約をしているケースがあります。この場合は本人が葬儀費用を生前に支払っている流れが一般的です。
また遺言書で「葬儀費用は遺産から支払うように」と指定していることもあります。遺言に故人の遺志が遺されていた場合には、遺産から葬儀費用が支払われるでしょう。
ちなみに遺言書には葬儀費用を遺産から支払う指定はできますが、葬儀費用を負担するご遺族の指定はできません。
⑤家族・親族で出し合う
葬儀費用を誰が払うかについて法的に決まりはないため、柔軟な対応ができます。喪主の負担が大きい場合、相談をすることで相続人で出し合うことができるでしょう。
また参列者が持参する香典は相互扶助の意味があります。葬祭業者も葬儀から7日後の支払いなど、葬儀後に支払う仕組みが多いです。
ただ喪主は四十九日の忌明けに香典返しを送ります。香典返しはいただいた香典金額の約1/3~1/2を目安に品を選ぶので、この点まで考慮しなければなりません。
一家の大黒柱が亡くなったケースなど、事情によって「香典返しは辞退させていただきます」などの手紙を添えた香典があるかもしれません。香典返しを送らない場合でも、忌明けのお礼状は送りましょう。
親の墓代は誰が払う?

かつて昭和時代には、お墓を建てる費用相場は約300万円~600万円と言われてきました。けれども2000年代に入り、お墓を建てる費用相場は年々下がっています。
鎌倉新書が2024年に実施した「第15回 お墓の消費者全国実態調査」によると、費用平均は一般墓149.5万円・樹木葬63.7万円・納骨堂80.3万円の結果となりました。
一方、先祖代々墓を継承する場合でも、約5千円~2万円ほどの年間管理料を毎年支払います。この他、墓石の経年劣化による修理修繕にも対応しなければなりません。
・お墓を継承したら維持管理費はどれくらい?負担を減らすには?維持管理ができない時は?
・お墓の継承とは?継承者の順位とは、誰がなるの?継承者の役割とは?継承の手続きや費用
・鎌倉新書「第15回 お墓の消費者全国実態調査」
①祭祀継承者
親の墓代は祭祀継承者が払う流れが一般的です。先祖供養の儀式で扱うお墓や仏壇など「祭祀財産」を継承する「祭祀継承者」は、祭祀財産の維持管理責任が伴います。
けれども複雑になるため法的に、祭祀継承者はひとりです。兄弟姉妹が共同で祭祀継承者になることはできません。ひとりで親の墓代を全額負担する負担は大きいでしょう。
かつては家督制度があったため、遺産とともに祭祀財産も長男が継承してきました。けれども家督制度が廃止された現代では、誰が祭祀継承者になっても問題はありません。
祭祀継承者になったからといって負担こそ増えるものの、相続する財産の権利「遺留分」が増える訳でもないため、お墓の継承者問題は深刻化しています。
お墓を継承する場合には、ご家族や親族で話し合い祭祀継承者を決めるとともに、ご家族・親族のみなで協力しあう姿勢が求められるでしょう。
・遺産分割がまとまらない!トラブル6つ事例と、たった2つの解決法を解説|永代供養ナビ
②お墓に入る人同士で分担
先祖代々墓は一般的に継承した墓主のご家族、墓主が許可した人々のご遺骨が納骨されます。そのため将来的にお墓を利用する人々で親の墓代を払うケースも多いです。
近年では一緒に終活を進めた仲間「墓友(はかとも)」で費用を出し合い、永代供養を付けたお墓を建てる「友墓(ともばか)」もあります。(永代供養が付いているので継承者を立てる必要がありません。)
一般的なお墓の場合、一基で約8柱~12柱が目安です。
カロートがご遺骨でいっぱいになった時には、弔い上げにより永代供養墓へ合祀する方法があります。この他、粉骨してコンパクトにしたご遺骨を納めるご家族もいるでしょう。
地域の慣習として、次男以降は新しくお墓を建てる考え方はありますが、法的な決まり事はありません。お墓に関わる人々で墓代を分担し合うことで、経済的負担が偏り過ぎることもなくなるでしょう。
・大阪で建てるお墓、誰が・何人まではいれるの?お墓に入れない時、5つの対処法を紹介
③生前に本人が払う
終活の広がりにより、近年では納骨される本人が生前契約を済ませる「生前墓(寿陵墓)」も増えています。
墓じまいを行った場合には、同時に自分の納骨先も見つける方が多いでしょう。生前墓を建てることにより、子や孫の経済的負担が軽減されます。
被相続人が自分でお墓代を支払うため、相続発生後は相続財産が少なくなるので相続税対策にもなる点もメリットです。
ただし遺されたご遺族が生前契約の存在を知らないと、別の場所に納骨されてしまうリスクもあるので、注意をしてください。生前契約を行う時にはご家族にも相談しながら決めると行き違いがありません。
・お墓の生前購入で相続税や贈与税はどうなる?相続後の相続税との差額は?葬儀や戒名は?
墓じまいでの永代供養の費用は誰が払う?

「墓じまい+永代供養」の費用は、平均的に約50万円~250万円ほどです。
墓石を撤去するだけならば約20万円~30万円(1㎡あたりの平均約10万円~15万円)なのですが、取り出したご遺骨の永代供養方法によって費用は大幅に変わるでしょう。
まずは墓石業者や霊園・墓地に相談をして、お墓の内部調査を依頼してください。お墓内部やご遺骨の柱数・状態によって、より正確な見積もりが算出されます。
近年では、墓じまいから永代供養までをセット料金で提供する「墓じまいサポートパック」なども見受けます。まずはご遺骨の納骨先を決めて、墓じまいの相談をするとスムーズです。
・墓じまいから始める新しい供養
①先祖代々墓は関係者で分担が一般的
先祖代々墓の墓じまいは、お墓に関わるご家族・親族で話し合い進める流れが一般的です。
墓じまいの決定権は祭祀継承者である墓主にありますが、永代供養の費用負担を抜きにしても、しっかりとご家族・親族が納得して進めないと、後々トラブルの種になりかねません。
寺院墓地に建つ先祖代々墓の墓じまいでは、ご住職へお布施をお渡しすることになるでしょう。本来は必要ありませんが、現代では「離檀料」を包むようになっています。
お布施や離檀料ではご住職とのトラブルも散見されますので、墓じまいを決めたら早々にご住職へ相談をしましょう。ご家族・親族の複数人で相談に伺うことも、スムーズな墓じまいのポイントです。
そのためにもご家族・親族で話し合いを重ねて、墓じまい・ご遺骨の新しい納骨先・墓じまいの永代供養にかかる費用負担に納得して進めて行きましょう。
②補助金を確認する
現代の日本では継承者がいない無縁墓問題が深刻化しています。墓主が亡くなり継承者がいないまま放置されたお墓は、年間管理料の滞納により墓地管理者に認識されるでしょう。
墓地管理者は年間管理料催促状の送付など、決められた工程を経て墓石を撤去します。眠っていたご遺骨は取り出されて、霊園・墓地内の供養塔に合祀される流れです。
けれども無縁墓が多く、墓石撤去の充分な予算を算出できないまま放置されたお墓もあります。このような事態を解決するため、補助金を出す自治体も増えました。
墓じまいを検討する際には、お墓がある自治体の墓じまい補助金を確認してみましょう。毎年更新されたり、全体の予算があるのでその都度確認することをおすすめします。
・墓じまいで補助金はもらえる?自治体で違う補助金制度と費用を抑える方法|永代供養ナビ
永代供養の費用を払えない時は誰が払う?対策は?

永代供養の費用がない時には、まずご家族や親族に相談をしましょう。祭祀継承者が負担する慣習はありますが、お墓はご家族や親族のみなで守っていくものです。
突然ご家族が亡くなりご遺骨の納骨先がない場合、手元供養などの選択肢もあります。「手元供養」とは、ご遺骨をご自宅で安置し供養することです。粉骨してブック型の骨箱に納め、複数のご遺骨を祀る「自宅墓」も登場しました。
一般的にご遺骨は忌明けの四十九日法要で納骨する風習がありますが、自宅に置いていても法的に問題はありません。金銭的な問題ではなく、ご遺族が喪失のショックから立ち直る「グリーフケア」としても手元供養が選ばれています。
・墓じまいの遺骨を手元供養にする手順と費用。家族の遺骨を納骨する「自宅墓」も作れる?
①納骨方法を再検討する
永代供養の費用が充分にない時には、納骨先を再検討する方法も一案です。冒頭でお伝えしたように永代供養は1柱約5万円~150万円と、費用に幅があります。
ただし永代供養で費用が安い形態は、一度埋葬すると二度と個別に取り出すことができないプランが多い点にはご注意ください。
例えば、最も安い傾向にある永代供養は合祀永代供養となります。合祀永代供養墓の費用相場は約5万円~15万円です。一方で最初から骨壺や骨袋から出して、他のご遺骨と一緒に合祀されます。
墓じまい後の永代供養であれば、個別に残すご遺骨・合祀するご遺骨の2つに分けて検討する方法も一案です。
・お金がない時の、最も安い永代供養はどれ?安い永代供養の注意点や選び方、対策も解説!
②メモリアルローンを利用する
メモリアルローンは葬送を目的とした融資商品です。お墓を建てる費用・葬儀費用・永代供養の費用などがあたります。
メモリアルローンは霊園・墓地の運営会社や寺院・石材業者などが提携する信販会社での取り扱いが一般的です。そのため永代供養の契約時などに相談すると良いでしょう。
メモリアルローン以外にも、多目的ローンやカードローンも利用できますが、目的を限定したメモリアルローンは金利も低く、審査が早い・通りやすいメリットがあります。
・メモリアルローンとは?永代供養での利用は?カードローンとの違い、メリットデメリット
③家族や両家墓で協力する(注意点)
ご家族の納骨先がなく永代供養に充てる予算が充分にない場合には、両家墓の相談も一案です。「両家墓」とは、夫婦両家のお墓をひとつにまとめた個別墓です。
一般的には夫婦共に墓主として先祖代々墓を継承した場合、お墓の維持管理の負担を軽減するためにひとつにまとめます。けれども親のお墓や納骨先がない場合に、墓主であるパートナーに相談するケースが増えています。
実家のお墓があれば、墓主であるご家族や親族に相談してみても良いでしょう。日本では次男以降は別にお墓を建てる慣習がありますが、法的には墓主さえ許可すれば次男以降の納骨も可能です。
ただ両家墓の場合お墓に入る人を、第三親等までと限定している霊園・墓地もあります。寺院墓地では宗派の違う故人のご遺骨を納骨できない場合もあるので、事前に確認をしてみると良いでしょう。
・娘だけどお墓を継承したい!両家墓で二世帯をひとつにまとめる|種類や注意点まで解説!
まとめ:永代供養の費用を誰が払うかに、決まり事はありません

永代供養の費用は一般的にお墓や仏壇を引き継ぐ祭祀継承者が払います。日本では古くからの慣習として長男が祭祀継承者になりますが、法的には誰がなっても構いません。
また戦前の旧民法では、長男が遺産とともにお墓も引き継ぐ「家督制度」が定められていましたが、1947年に廃止されて以降、必ずしも長男が継承する義務もないでしょう。
そのため現代のお墓は、ご家族や親族みなで負担するものです。祭祀継承者は名義人として祭祀財産を守る義務はありますが、現実的にはご家族や親族で負担を分担するケースが増えています。
ご家族や親族で話し合いを進めて経済的負担は分担し、納得しながら墓じまいや永代供養を進めていきましょう。
・大阪でお墓の改葬(引っ越し)はどう進める?納骨先の選択や、改葬前に読む7つのコラム
お電話でも受け付けております
















