
永代供養なのに費用が毎年かかるなんて!いつまで払う?かからない永代供養との違いは?
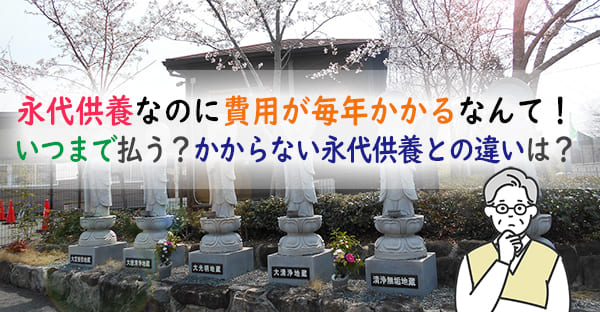
「永代供養なのに費用が毎年かかるの?」
「永代供養の費用はいつまで払うの?」
「毎年の支払いがない永代供養の種類は?」
負担を軽減するために永代供養を選んだのに、費用が毎年かかると言われて驚く人がいるかもしれません。確かに永代供養には費用が毎年かかる種類もあります。
本記事を読むことで永代供養なのに費用が毎年かかる種類と仕組み、かからない永代供養との違いが分かります。永代供養の費用や仕組みを理解して、適切な選択ができるでしょう。
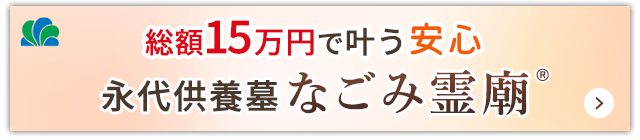
永代供養の費用は毎年払う必要はありません

基本的に永代供養の費用は毎年払う必要はありません。けれどもご遺骨の個別安置期間を設けた永代供養の種類では、納骨後も毎年管理料を支払うプランも多くあります。
「永代供養料」は契約時に支払う初期費用なので、追加費用はかかりません。永代供養にはさまざまな形式や種類があるため、追加費用が一切かからないプランもあります。
①「永代供養料」とは?
「永代供養料」とは、ご家族に代わりご遺骨を永代に渡って供養をするサービスに対する料金です。永代供養料を支払うことで、ご家族は継承者を建てる必要がありません。
ちなみに永代供養料と永代使用料は違うものなので注意をしてください。「永代使用料」は墓地を永代に渡って使用する権利です。
永代供養を付けた個別墓の場合は、永代供養料と永代使用料の双方を支払うでしょう。どちらも契約時に初期費用として一括で支払います。
②永代供養の注意点
永代供養はご家族に代わりご遺骨を永代に渡って供養しますが、ずっと個別に管理する訳ではありません。この点は勘違いをしやすいのでご注意ください。
ご遺骨の個別安置期間を設けた永代供養では、契約時に個別にご遺骨を管理する期間「個別安置期間」を設定します。個別安置期間は5年・10年・17年・25年など、プランによりさまざまです。
契約更新なく個別安置期間が過ぎると、そのご遺骨は施設内の永代供養墓(合祀墓)へ他のご遺骨と一緒に合祀されます。「合祀」とは不特定多数のご遺骨を一緒の場所に納骨することです。
合祀後、他のご遺骨と一緒に永代に渡って合同供養されます。そのため継承者がいないご遺骨やお墓でも、永代供養を付けることで無縁墓・無縁仏になる心配がありません。
・永代供養について後悔しないように改めて考えよう。永代供養のその後、供養はどうなる?
永代供養の契約で毎年払う費用はある?

永代供養で費用を毎年請求されるとしたら、年間管理料が一般的です。基本的にご遺骨の個別安置期間を設けた永代供養プランで請求されます。
年間管理料は個別安置期間のみ、毎年払うプランが多いです。そのため契約更新をしない限りは、ずっと支払う費用ではありません。
①「年間管理料」とは
「年間管理料」とは、施設の公共スペースや設備の維持管理料です。分譲マンションの年間管理料と同じ役割だと考えると分かりやすいでしょう。
一般墓を建てる時にも、霊園や墓地の公共スペース・水場などの設備に対して年間管理料を支払います。
けれどもご遺骨が合祀されて個別スペースがなくなると、年間管理料の支払い義務もなくなるプランが一般的です。
②年間管理料の費用相場は?
年間管理料の費用相場は約3千円~3万円です。公共スペースや設備・運営母体によって費用幅があるでしょう。
利用者を対象とした法要・会食施設や車椅子・造花の貸し出しなど、サービスや環境が行き届いた公園型霊園や納骨堂などは、約1万2千円~2万円の年間管理料が相場です。
一方で公営墓地は約3千円~1万円内の年間管理料相場となりますが、納骨式や僧侶などは利用者が全て手配しなければなりません。申し込み期間が設けられ抽選もあるでしょう。
③寺院墓地の護持会費
寺院墓地の場合は年間管理料の代わりに、永代供養の他の費用として毎年お布施や護持会費を求められることがあります。
従来の慣習に倣い、ご遺骨を納骨する際その寺院の檀家になることが求められる寺院墓地もあるでしょう。その寺院の檀家である限り、毎年の護持会費やお布施の支払いが求められる仕組みです。
ただし永代供養の種類によっては、檀家になることを求めない寺院墓地も増えました。檀家としての支払いを辞めたい時には、墓じまいをして檀家を辞める「離檀」の選択肢もあるでしょう。
・離檀とは?檀家をやめる離檀のやり方、メリットデメリット、トラブル対策をくわしく解説
年間管理料がかかる永代供養の種類は?

永代供養で費用が毎年かかる種類は、ご遺骨の個別安置期間を設けたプランです。最初から他のご遺骨と一緒に合祀される合祀永代供養墓では、一般的に追加費用はかかりません。
またご遺骨を土へ還す樹木葬も、ご遺骨は骨壺や骨袋から取り出して土に埋葬するため、初期費用のみのプランが一般的です。
ただし合祀永代供養墓や樹木葬では、一度納骨すると二度と個別に取り出すことができません。この点に注意をして永代供養の種類を選びましょう。
・永代供養墓はどんなお墓かわかりやすく解説!何年供養してくれる?選び方のポイントは?
①納骨堂
「納骨堂」とはご遺骨を収蔵する屋内施設です。ロッカー型・仏壇型・ビル型(自動搬送型)・墓石型・位牌型など、ご遺骨を収蔵する形式はさまざまにあります。
納骨堂での個別安置期間、ご遺骨は埋葬せずに骨壺のまま屋内施設に収蔵されるので、いつでもご遺骨を手元に戻すことができる点がメリットです。
墓石を建てないため個別墓と比べて費用が安い傾向にあります。スペースに限りがあるため収蔵するご遺骨の柱数が限定されてくるでしょう。
・納骨堂の永代供養とは?お墓との違いやメリットデメリット、大阪に多い納骨堂4つの種類
②室内墓所
「室内墓所」とは屋内に建つお墓です。納骨堂と同じように屋内にご遺骨を収蔵できますが、ご家族で代々継承して利用できる点が違います。
ご家族で代々継承することはできますが、永代供養が付いているので墓主を立てる必要はありません。個別安置期間が15年・25年・50年など長期間に渡るプランが多いです。
更新時には更新料がかかりますが、子や孫は更新の可否を判断できるでしょう。墓石がないので定期的なお墓掃除などのメンテナンスも必要ありません。
屋内に墓石を建てる室内墓所もありますが、最近では個別の参拝ブースに案内され、ご遺骨がブースに搬送される「ビル型(自動搬送型)」による室内墓所が人気です。
③集合墓
「集合墓」とは、ロッカー型納骨堂のようにご遺骨を収蔵するスペースが提供されるお墓です。個別墓が戸建てならば、集合墓は分譲マンションのような感覚です。
個別の墓地区画や墓石を必要としないため、個別墓と比べて安い傾向にあります。屋外の開放的な環境でお墓参りができますが、お彼岸やお盆時期には混み合う可能性もあるでしょう。
また合祀永代供養墓を集合墓と呼ぶこともあります。合祀永代供養墓とは、個別安置期間を設けずに、最初から他のご遺骨と一緒の場所へ埋葬する「合祀」を行うお墓です。
④永代供養付き個別墓
「永代供養付き個別墓」とは、永代供養を付けた一般墓です。
従来の一般墓でありながら継承者を建てる必要がないので、個人墓・夫婦墓・友墓など、同世代でお墓を建てることができます。
永代供養付き個別墓は個別安置期間が約25年・50年など、長期間に渡る傾向です。契約更新がないまま個別安置期間が過ぎると、お墓は撤去されご遺骨は永代供養墓に合祀されます。
個別安置期間に子や孫が契約更新を行う場合、お墓はそのまま残るでしょう。継承者は不要ですが、墓石が建つので定期的なお墓掃除やメンテナンスは必要です。
・お墓参りのお線香・服装マナーは?水をかける順番・かける言葉は?手ぶら行ってはダメ?
永代供養に追加費用はかかる?

永代供養では基本的に追加費用はかかりません。ただし僧侶へ支払うお布施は、一般的に永代供養料には含まれません。
納骨式や年忌法要で僧侶を手配する場合には、霊園(墓地)へ支払う永代供養料とは別に、お金を包んで僧侶へ直接お渡しします。
①法要
ご遺骨の納骨にあたり納骨式を執り行う場合には、納骨式当日に僧侶へ読経供養のお礼としてお布施を包むでしょう。
お布施の金額相場は1回の読経供養につき約3万円~5万円ですが、お布施は本来「財施」と呼ばれる財を施す仏教修行のひとつなので、明確な金額は提示されていません。
墓じまいで閉眼供養を行った後、納骨式を同日に執り行うならば、約5万円~10万円と2回分のお布施を包む方法が一般的です。
・合祀・永代供養ではお布施を包む必要はある?金額相場やお布施を包む場面・包み方を解説
②納骨費用
納骨堂・室内墓所などでは、夫婦・ご家族が一緒に収蔵される複数人数の永代供養プランもあります。このような複数人数のプランでは、後から納骨されるご遺骨に対して手数料がかかる施設もあるでしょう。
全ての霊園(墓地)で手数料がかかるわけではないので、契約時に確認をしてください。また納骨式を執り行う場合には、その都度お布施を包む必要があります。
③彫刻費用
石碑や墓碑に故人の戒名・俗名を彫刻する際にかかる費用が彫刻費用です。戒名・俗名の彫刻費用は、1人あたり約3万円~5万円が相場になります。
また近年では花などのイラスト彫刻も見受けますよね。イラスト彫刻は約5万円以上と高くなる傾向にあるので、事前に確認をしてください。
石碑・墓碑の彫刻を伴う永代供養プランでは、1人までの彫刻費用が永代供養料金に含まれていることもあります。
永代供養の費用を毎年払う契約、生前契約では?

永代供養の費用を毎年払うプランは、基本的に個別安置期間の年間管理料です。生前にご遺骨の納骨先を決める生前契約では、毎年の支払いができませんよね。
継承者を必要とせず子や孫に負担をかけない永代供養プランは、本人による生前契約が増えています。ここでは、永代供養の費用を毎年払うプランでの、生前契約の対策をお伝えします。
①年間管理料がかからない永代供養を選ぶ
個別安置期間を設けていない永代供養では、初期費用のみで追加費用や年間管理料がかからないプランが一般的です。
子どもや孫がいない、余計な負担をかけたくない方は、合祀永代供養墓などの個別安置期間がない永代供養を選ぶと良いでしょう。
自然葬のひとつである樹木葬も、永代供養ではありませんが毎年払う費用はありません。ご遺骨は取り出すことができないものの、個別の墓標を設置した樹木葬もあります。
・合祀墓や永代供養墓のお参り手順と注意点。合葬墓・合祀墓・永代供養の違いとともに解説
②個別安置期間の年間管理料を先払いする
納骨堂などの永代供養プランでは、当初の個別安置期間が決まっています。そのため生前契約では、個別安置期間のみ年間管理料を先払いする方法が一般的です。
先払いしている期間は子や孫が、永代供養の後で費用を毎年支払う必要がありません。契約更新ができる永代供養プランでは、子や孫が望んだ時に更新・年間管理料の支払いをすることになります。
・50代から備える!手作り終活ノートの作り方|家族が助かる13項目・注意点とポイント
③残されたご家族が払う
もちろん家族間で話し合っているならば、永代供養後に遺されたご家族が年間管理料等の費用を毎年支払うこともできるでしょう。
室内墓所・永代供養付き個別墓などでは、将来的に子どもや孫が代々年間管理料を支払う選択もあります。
ただし永代供養を付けているので無縁仏・無縁墓になる心配はありません。個別安置期間の契約更新時に、更新の有無を判断すると良いでしょう。
まとめ:永代供養の費用は毎年払うものではありません

ご家族に代わり墓地管理者が、ご遺骨の供養や管理を永代に渡って担ってくれる永代供養の費用は、契約時の初期費用です。毎年払う種類の費用ではありません。
もしも永代供養プランに費用を毎年払う項目があるならば、年間管理料でしょう。年間管理料は個別安置期間のみ支払うプランが一般的です。
ただし寺院墓地で永代供養を依頼する場合に檀家義務があれば、檀家としてお布施や護持会費の支払いを毎年求められることがあるので、契約時に確認しましょう。
お電話でも受け付けております















