
四十九日法要とは?いつ・何をする?しなくちゃダメ?遺族が四十九日までに行うことは?
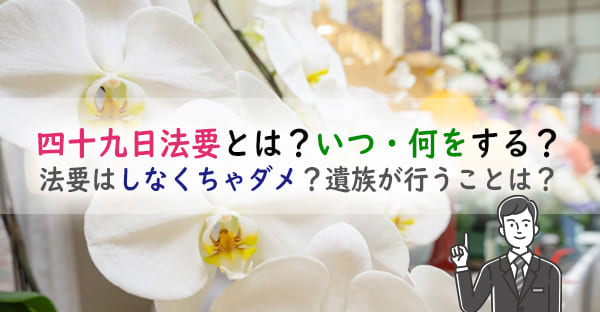
「四十九日法要の目的は?しなくちゃダメ?」
「四十九日の数え方は?何をする日?」
「遺族は四十九日法要までに何をする?」
仏式の法要では人が亡くなると49日目に、追善供養として四十九日法要を執り行います。
従来の風習では四十九日法要と同日に納骨式、本位牌への交換が行われるでしょう。遺族は行政手続きも重なるため、葬儀を終えたら早々に準備を進めて後悔のないよう供養します。
本記事を読むことで四十九日法要の意味や目的、四十九日法要の準備や進め方、繰り上げ四十九日法要等についての基礎知識が分かります。
後半では当日の服装やマナーもご紹介していますので、どうぞ最後までお読みください。
四十九日法要とは?

四十九日法要は故人の命日から数えて49日目に執り行う「追善供養」です。「追善供養」とは、故人が極楽浄土へ行けるよう遺族が後押しをするために執り行う法要を指します。
遺族は故人が亡くなると通夜・葬儀を終え、遺族は初七日・ニ七日・三七日・四七日・五七日・六七日と7日ごとに、故人の冥福を祈り追善供養を行ってきました。
その締めくくりとなる追善供養が四十九日法要です。一般的に初七日の後、四十九日法要までは遺族のみで執り行いますが、四十九日法要は広く参列者へご案内をします。
①四十九日法要の目的
仏教の教えにおいて故人の魂は亡くなってから49日の間、冥土の旅のなかで7日ごとに極楽浄土へ行けるかの裁判が行われると信じられてきました。
この世での行いに対する裁きを7日ごとに受ける旅の最終日が四十九日法要です。この日が最後の判決の日となり、故人の魂が極楽浄土へ行けるかどうかが分かります。
生きる者は追善供養を執り行うことで、極楽浄土への道を応援することができるのです。7日ごとの追善供養として四十九日法要は「七七日(しちなぬか)」等とも呼ばれます。
②「忌中」とは
故人の逝去日から四十九日法要までの期間が忌中です。遺族は忌中のお出掛けや会食、お祝い事等を極力避けて家にこもり、故人の追善供養を行います。
神道では五十日祭までの50日間が忌中となるでしょう。
また神道において死は穢れたものとの考え方があります。遺族は忌中に死の穢れを他人に移さぬよう、他者との接触を断ちます。
忌中の贈り物も避けるため、通夜や葬儀の香典返しも忌明けのタイミングで送るのがマナーです。忌中の神社参りも禁忌ですが、仏教では考え方が異なるため寺院参拝はできます。
・喪中と忌中の違いとは?やってはいけないことは?初詣や七五三、お祭りに行ってもいい?
③法要をしないとどうなる?
四十九日法要は故人の成仏を祈り執り行う法要です。仏教に基づく儀式なので、必ず行わないといけない訳ではありません。
無宗教であれば49日目を目安に僧侶をお呼びせず、読経供養を省いた「偲ぶ会」を開催する遺族もいます。
ただ現代ではまだ、四十九日法要をなしとする選択は稀です。遺族・親族のスケジュールにより四十九日法要をしない場合には繰り上げ法要等の選択もあるでしょう。
四十九日法要に案内されたものの欠席する場合には、理由とともに早い段階で遺族へ伝えてください。四十九日法要当日に供え花を贈る等も良いでしょう。
四十九日法要はいつ行う?

故人の逝去日から49日目が四十九日法要です。一般的には故人の逝去日を1日目として「命日+48日」で数えます。ただし地域によって異なる数え方もあるでしょう。
全国的な四十九日法要の数え方の場合、3月1日に亡くなった場合、3月1日を1日目として48日目の4月18日が命日です。
①四十九日法要の前倒し
四十九日法要は参列しやすいよう、平日を避けた日程調整が一般的です。
49日目が土日祝日でない場合「祝い事は先延ばしでも良いけれど、仏事は前倒しに」と言われ、前倒しで執り行うように調整します。
四十九日法要の日程を前倒し調整する場合、三七日にあたる35日目以降が良いでしょう。
②四十九日法要が遅れるとダメ?
四十九日法要の日程調整は前倒しが良いとされる理由は、故人を待たせてしまう・忘れていると思われるためです。
ただ、本来であれば四十九日法要は前倒しが良いが事情により遅れることもありますよね。このような場合は、49日目から後にずらしても構いません。仏壇等へ故人に手を合わせ待っていただくと良いでしょう。
③「三月またぎ」とは
繰り上げ四十九日法要とは

「繰り上げ四十九日法要」とは、葬儀の日に四十九日まで法要を繰り上げて行うことを指します。
四十九日法要まで繰り上げることもありますが、一般的には初七日まで繰り上げて行う「繰り上げ初七日」が多いでしょう。また初七日法要の日に、繰り上げ四十九日法要を行うこともあります。
繰り上げ四十九日法要にすることで、遠方の親族が参加しやすくなる点がメリットです。施主も僧侶・会場の手配、法要後の会食「お斎」の手配が楽になるでしょう。
①お布施はどうなる?
葬儀や初七日法要と同日に行う繰り上げ四十九日法要では、ひとつの封筒に複数回分のお布施金額を包むのが一般的です。
1回の読経供養へのお布施相場は約3万円~5万円なので、2つの法要を執り行うならば約1.5倍~2倍となる約5万円~10万円、納骨式等があるならば3回分を目安に金額を決めましょう。
お布施の他、交通費「御車代」、僧侶が法要後のお斎を欠席するならば食事代「御膳料」も別封筒に包んでお渡しします。
ただし葬儀後に火葬場に行き、再び葬儀会場に戻る「戻り法要」を選ぶ場合、往復の交通費が加算されることにも配慮して、交通費となる「御車代」を多めに包むのがマナーです。
お布施全般の金額相場・包み方・渡し方マナーは下記コラムに詳しいので、こちらも併せてご参照ください。
②香典はどうなる?
繰り上げ初七日・四十九日法要に参列する香典は、葬儀とは別に包むと丁寧です。
香典の表書きは通夜・葬儀・初七日法要の忌中は「御霊前」、四十九日法要は「御仏前」で準備をします。
繰り上げ四十九日法要は日数としては忌中にあたるものの、葬儀・初七日法要とは別に包むならば「御仏前」が適切です。
ただし葬儀や初七日法要と併せて包むこともあるでしょう。
この場合は法要後の引き物等にも配慮し、約1.5倍~2倍の金額を目安に包むと良いです。知人友人であれば1回の香典の金額目安は約5千円~1万円なので、約1万円ほどを包みます。
・御霊前・御仏前・御香典の違いは何?香典で表書きの意味・使い分け・包み方を詳しく解説
③香典返しはどうなる?
繰り上げ四十九日法要を執り行う場合、一般的に香典返しも早めて送ります。ただし、忌明け後の7日間を目安に送っても失礼にはあたりません。
繰り上げ法要での香典返しは、香典額の約1/3~1/2の価格帯で選びます。
掛け紙はお祝いの熨斗(のし)はなし、水引きは黒白・黄白の結び切りが印刷されているものが適切です。
「不幸が消える」ため、飲み物・和洋菓子・洗剤等の消え物が縁起が良いとされるが、近年ではカタログギフトが好評でしょう。
・香典返しはいつ送る?「当日返し」とは?早く送るとダメ?品選びのタブーや金額相場は?
四十九日法要に行う儀式

四十九日法要は、仏教において故人が成仏する節目の儀式です。遺族は49日日を目安に準備を進めます。四十九日法要と同日に納骨式や、仮位牌(白木位牌)から本位牌へと位牌の交換を行う家も多いでしょう。
①本位牌へ魂を移す
人が亡くなると四十九日法要まで、仮の位牌となる「仮位牌(白木位牌)」を使用します。仮位牌は、四十九日法要まで飾る祭壇「中陰壇(後飾り祭壇)」に祀る位牌です。
そのため四十九日法要までに遺族は本位牌を準備し、位牌交換の儀式を行います。
仮位牌(白木位牌)には故人の魂が宿っているため、儀式ではまず魂を抜く「閉眼供養」を行わなければなりません。その後に本位牌に故人の魂を込める「開眼供養」を行うことで、位牌交換ができます。
ちなみに位牌交換を済ませた後の仮位牌(白木位牌)は不要です。納骨式を行う場合、仮位牌は遺骨と一緒に納骨する流れも多いでしょう。
閉眼供養を行った仮位牌(白木位牌)は、すでに魂の抜けた「物」にすぎません。けれども遺骨と一緒に納骨されない場合でも、一度は故人の魂がこもっていた仮位牌(白木位牌)をゴミとして捨てるのは避けましょう。
なかには塩を振ってからゴミとして出す人もいますが、僧侶や葬儀社にお願いしてお焚き上げをしてもらうと安心です。
②納骨式
四十九日法要の後、納骨式を執り行う流れが多いです。納骨するお墓がすでにある場合、お墓に側面に戒名・俗名・享年(行年)・没年月日等を彫刻します。
お墓への追加彫刻は、石材業者に依頼してください。霊園や墓地管理者に相談すると、提携している業者を紹介してくれます。
故人1人につき約3万円~8万円が費用相場で、墓石の場所や地域性、戒名等の文字数によっても違うでしょう。
お墓がない場合、四十九日法要に間に合わなくても問題はありません。現代ではお墓のない納骨堂等での遺骨供養も増えました。納骨堂等の施設でも納骨式を執り行うことができます。
③神棚の扉を開ける
神道では死を穢れとするため神様へ穢れを見せぬ・移さぬよう、神棚がある家では扉を閉める「神棚封じ」を行います。
神棚封じの期間は四十九日法要まで、神道では五十日祭までです。ただし地域によっては故人との関係性により、祖父母なら30日間・両親は50日間等と期間が変わることもあります。
家族が亡くなったらすぐに神棚の扉を閉めて白い紙を貼り付け、神棚封じの期間中はお供えや参拝も避けましょう。
四十九日法要を済ませ忌中を過ぎたら神棚封じを開放します。白紙を取り除き扉を開ける前に、遺族は塩を振って身を清めましょう。神棚の扉を開いた後は、通常通りお供え物・参拝ができます。
・神式の法要「五十日祭」の進め方とは?四十九日法要との違いや流れ、準備やお供えを解説
四十九日法要までに行うこと

四十九日までに、遺族は四十九日法要の準備を進めなければなりません。四十九日はあっと言う間なので、喪主や遺族は葬儀が終わったらすぐに準備を始めましょう。
四十九日法要の準備と並行して、社会保険・世帯主変更届等の行政手続きも進めなければならないため、できる事柄は周囲に頼りながら計画的に進める必要があります。
四十九日法要を目安に済ませたい行政手続きについては、下記コラムをご参照ください。
・世帯主が亡くなったら家族は何をすればいい?世帯主変更届・社会保険・税金はどうする?
①四十九日法要の準備
四十九日法要の準備は日程を決めることから始まります。菩提寺があればご住職に相談し、菩提寺がない家では僧侶の手配が必要です。
葬儀社や霊園等に相談すると僧侶を紹介してくれます。また近年ではインターネットで僧侶派遣を行っている業者もあるでしょう。
自宅で執り行わない場合は、法要会場の手配も必要です。寺院の部屋・斎場の法要室等を利用することが多いでしょう。
また四十九日法要では、参列者がお帰りの際に引き物を準備する流れが一般的ですので、香典返しとは別に引き物を準備します。
現代では葬儀社に四十九日法要の進行やサポートを依頼することが増えました。僧侶や会場の手配等、困ったことがあれば葬儀社スタッフに確認できるので安心です。
四十九日法要の準備について、下記コラムではより詳しく解説しています。
・四十九日法要の準備とは?いつから始める?何を用意する?呼ぶ範囲や、お布施の金額は?
②会食の手配
四十九日法要の後、喪主(施主)は一般的に僧侶や参列者へ会食「精進落とし」を振る舞います。
自宅でなければ法要会場から移動がしやすい、レストラン・セレモニーホール・寺院の一室等を事前に予約すると良いでしょう。
自宅で四十九日法要が執り行われる場合、仕出し弁当を手配します。精進落としで振る舞う料理は精進料理なので、弔事用として注文をしてください。
法要後に喪主(施主)が振る舞う会食全般は「お斎(おとき)」と呼ばれ、精進落としは四十九日法要の後、忌中が明ける際にいただく料理を指します。
精進落としのお食事にかかる費用相場は約3千円~1万円、内容によってはビール等のお酒代金が加算されるでしょう。
・お斎(おとき)とは?精進落としとは違うの?お弁当でも良い?お斎の相場や準備を解説!
③引き物の手配
四十九日法要では参列者がお帰りの際に引き物をお渡しします。四十九日法要の後に郵送する「香典返し」とは違うので注意をしてください。
四十九日法要で準備する引き物の費用相場は、香典の1/3~1/2です。知人友人であれば約5千円の香典なので、1人あたり約2千円~5千円を目安に選びましょう。
当日にお渡しする四十九日法要の引き物には、お礼状等の一筆箋は必要ありません。
・四十九日法要の引き出物とは?香典返しとは違う?料金相場や選び方、熨斗や表書きを解説
④香典返しの準備
四十九日法要を終えた後、7日間までを目安に香典返しを送ります。香典返しは通夜・葬儀に参列いただいた方々へのお礼の品です。
忌中は死の穢れを他者へ移さぬよう、喪主や遺族は贈り物を送ることもできません。そのため忌明けとなる四十九日法要の後に、葬儀での香典へお礼を送ります。
四十九日法要の引き物と同様に金額目安は香典の約1/3~1/2の価格帯となるため、一般参列者には約2千円~5千円、いただいた香典金額を考慮して選びます。香典返しは郵送が一般的ですので、一筆箋等でお礼状を添えましょう。
・香典返しの挨拶状(お礼状)の書き方ポイントとは?マナーや5構成、3つの例文を紹介!
⑤遺品整理
遺品整理に期限はありませんが、家族が亡くなった後に整理をしていると遺書やエンディングノートを見つけることがあります。
故人が生前に終活をしていた場合、葬儀社や遺骨の納骨先との生前契約を済ませているケースもあるため、最初に大まかにでも遺品整理を行うと、後々のトラブルは軽減されるでしょう。
葬儀は故人の遺産から差し引くことができますが、遺骨を納骨する費用は遺族負担です。近年では生前契約で故人が決めているケースでは、遺族の経済的負担も軽減します。
・親の遺品整理を自分で進める方法は?いつから・なにから始める?業者に依頼する費用は?
四十九日法要当日の流れ

四十九日法要の当日、喪主(施主)は早めに会場に到着して僧侶をお迎えします。僧侶を迎えたら控室にご案内して、法要が始まるまでのお茶・お茶菓子をお出ししましょう。
充分な時間があれば、僧侶が控室にいるタイミングでお布施もお渡しします。
お布施をお渡しする際には「本日はお越しいただきありがとうございます、本日はどうぞ、よろしくお願いいたします。」等とひと言添えると良いでしょう。
・【図解】お布施マナーとは?封筒や書き方、金額は?お札の入れ方・渡し方もイラスト解説
①喪主の持ち物
四十九日法要当日には位牌の交換、納骨式を併せて行う家が多いですよね。
この場合は仮位牌(白木位牌)の他に本位牌も必要になる等、その日に執り行う法要内容により持ち物は異なります。
・遺骨
・仮位牌(白木位牌)
・本位牌
・遺影
・お布施
・お茶代
・香典返し
・供え花
お茶代は四十九日法要にあたり、寺院の客間をお借りした時に包むお金です。白い封筒にお茶代と記し、お布施とは別に約5千円~1万円をお渡しします。
葬儀社に四十九日法要を依頼した場合、祭壇・お供え物等も準備してくれるでしょう。生前に故人が好きだった食べ物等、特別に用意したいお供え物があれば各自で準備をします。
②服装
四十九日法要において喪主・遺族の服装は、正式な喪服「正喪服」とされてきました。
昔ながらのしきたりでは一周忌を迎えるまで正喪服とされますが、近年では喪主・ご遺族も略式喪服が一般的です。
| <四十九日法要の服装> | |
| [喪主・遺族] | ・正喪服 ・略式喪服 |
| [参列者] | ・略式喪服 |
| [平服指定があった場合] | ・平服 (喪主の意向に倣う) |
その後、喪主や遺族は三回忌まで略式喪服・七回忌以降になって平服を着用します。
「平服」とは畏まったお出掛け着となり、皇室ファッションがひとつの目安です。弔事なので黒・グレー等の落ち着いた無地の色合いで整えます。
略式喪服は一般参列者が葬儀に参列する際の服装ですね。
基本的に光沢や柄等、デザイン要素のない無地の黒で揃え、男性は黒ネクタイ・ダークスーツ、女性は黒のアンサンブルやワンピース等です。
正喪服・略式喪服・平服等、法要によって違う服装マナーは下記コラムで詳しくお伝えしています。
・弔事での「平服」は普段着ではない?「平服でお越しください」と指定されたらどうする?
③法要の流れ
四十九日法要の当日、施主は僧侶・参列者をお迎えした後、喪主・遺族席に着席します。四十九日法要では施主挨拶の時間があるため、事前に挨拶を準備しておきましょう。
四十九日法要の後、会食の場「精進落とし」がある場合、食事の前に献杯の挨拶を行うプログラムが一般的です。親族等に献杯の挨拶をお願いしておきましょう。
—–四十九日法要—–
①僧侶入場
②施主挨拶
③読経供養
④焼香
⑤僧侶の説法
(施主による中締めの挨拶)
—–納骨式がある場合—–
(お墓に移動する)
⑥納骨式
—–精進落としがある場合—–
(会食会場へ移動)
⑦献杯の挨拶
⑧会食(精進落とし)
⑨施主挨拶
⑩引き物
一般的には参列者がお帰りになる際に引き物を手渡しますが、規模の大きな四十九日法要等では、参列者の席にそれぞれ引き物を置いて準備することもあります。
規模に合わせて調整しましょう。
まとめ:四十九日法要は故人が成仏する節目の法要です

四十九日法要とは故人が極楽浄土へ行く道を遺族が後押しする「追善供養」です。
故人が極楽浄土へ行くかどうかが四十九日にして分かるため、最後の追善供養であり節目の法要となります。
仏教の考え方に基づいた法要なので、必ず四十九日法要を執り行わなければならない訳ではありません。けれども無宗教の家であっても、何らかの形で故人を偲ぶ会を催す遺族が多いでしょう。
お電話でも受け付けております
















