
墓じまいはなぜ必要?お墓を放置したらどうなる?墓じまい費用や進め方、後々の供養は?
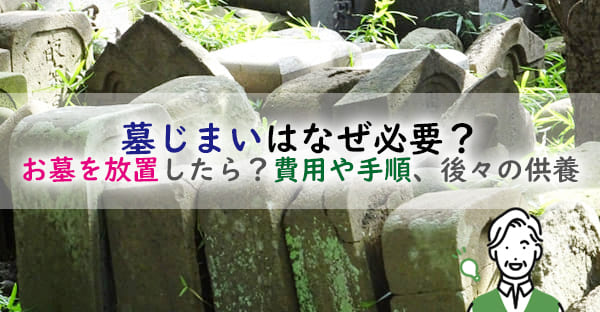
・墓じまいせずに、お墓を放置したらどうなる?
・お墓を放置すると通達はくる?
・お墓が維持できない対処法は?
お墓を継承したものの維持管理が負担になり、悩む墓主は多いですよね。
墓じまいをせずにお墓を放置すると、いずれは無縁墓になりますが、無縁墓になるまでには催促状など、経緯があります。
本記事を読むことで、墓じまいをしないままお墓を放置したらどうなるか?無縁墓になるまでの経緯、お墓を維持管理できない時の5つの対処法が分かります。
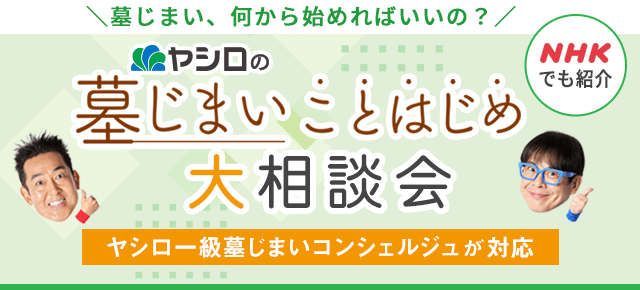
墓じまいは必要?お墓を放置したらどうなる?

◇墓地・霊園によって対応も変わります
少子化が進み、人々の暮らしがグローバル化する現代では、墓主のいないお墓やご遺骨「無縁墓」「無縁仏」が増えています。
墓主が亡くなった時にお墓の継承者がいないまま、墓じまいをしないでお墓を放置するケースも増えました。
またお墓を継承したものの、遠方に住んでいて維持管理ができない、経済的・体力的な負担が大きいと悩む方々もいるでしょう。
墓じまいをせずにお墓を放置した場合、その対応は霊園や墓地によっても違いがあります。
①お墓を放置され続ける
◇お墓を撤去する作業にも大きなコストがかかります
墓じまいをせずにお墓を放置し続けた場合、本来であれば、墓地管理者がお墓を撤去し墓地を元の状態に戻すことが理想です。
けれども一部の民間霊園や公営墓地では、お墓を撤去するための充分な予算がないために、お墓がそのまま放置され続けることが多くあります。
墓地管理者はご遺骨を取り出して墓石を解体・撤去し、墓地を更地にしなければなりません。
また撤去した墓石の処分にもお金が掛ります。
現代は無縁墓も社会問題化しているほどなので、このような墓地では、お墓は誰にも管理されないまま放置し続けることになるので、荒れ果ててしまうでしょう。
②撤去されて供養塔に改葬
◇一定期間を過ぎてお墓を撤去する霊園もあります
お墓を解体・撤去し、取り出したご遺骨を供養するだけの充分な予算と時間がある場合、一定の手順を経て、墓地管理者によりお墓は撤去されるでしょう。
この場合、取り出したご遺骨は「無縁仏」と判断されます。
無縁仏は一般的に施設にある合同供養塔へ、他のご遺骨と一緒に合祀される流れです。
墓じまいをせずにお墓を放置した結果、無縁仏と判断されるまでには一定の期間と手順を経ていますので、ご家族はどこに供養されたのか、分からないでしょう。
無縁仏と判断されるまでの手順は、後ほど詳しく解説します。
③訴えられる可能性
④墓じまいをしない寺院
◇「墓じまい」の概念がない寺院も稀にあります
もともと日本ではご遺体を土葬して土に還す土葬文化がありました。
けれども伝染病や公衆衛生面に配慮して1875年に撤廃され、現在では基本的に火葬が義務付けられています。
この土葬文化は「いずれ人は土に還る」と言う考え方に基づいているため、自然葬と同様に、そもそも「墓じまい」の考え方も持たない寺院もあるでしょう。
ただ、このような寺院は現代の日本であまり多くはありません。
お墓の継承者がいない、維持管理が困難などの問題が生じたら、まず寺院や墓地管理者に相談をしましょう。
⑤永代供養の付いた霊園
◇基本的に一般墓に永代供養を付ける霊園が増えました
永代供養とは、家族に代わり墓地管理者がご遺骨の管理や供養を担うことです。
ただしご遺骨を永代に渡って個別に安置するのではなく、条件によってお墓は撤去され、ご遺骨は合祀して、永代に渡り供養します。
ご家族は永代供養を一般墓に付けることで、将来的にお墓の継承者が見つからないまま放置された時にも、寺院や霊園がご遺骨の管理や供養を担ってくれる点がメリットです。
無縁墓が増え続けて社会問題化する現代、全てのお墓に永代供養を付ける民間霊園が増えました。
この場合、17年・33年・50年など、契約した一定年数が経ち、なおかつ、その間に契約更新がなかったお墓について、独自の判断で墓じまいを行ってくれます。
取り出したご遺骨も施設内の永代供養墓に合祀、合同供養してくれるでしょう。
墓じまいせずにお墓を放置すると訴えられる?

◇お墓を放置して問題になるのは、維持管理費です
お墓を継承すると、維持管理費として「年間管理料」を定期的に墓地管理者へ支払います。
「墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)」により、遺骨は知事が認める墓地以外で埋葬できません。
そのため遺骨は公営墓地・民間霊園・寺院墓地など、いずれかの霊園・墓地で埋葬していますが、お墓を放置しているとみなされるのは、霊園や墓地に定期的に支払う維持管理費の不払いです。
| <霊園・墓地の維持管理費> ●公共部分の維持管理費用 |
|
| [墓地の種類] | [費用目安] |
| ・公営墓地 | …約2,000円/年~ |
| ・寺院墓地 | …約9,000円~15,000円/年~ |
| ・民間霊園 | …約9,000円~15,000円/年~ |
以上が目安ですが、高い霊園や墓地になると約30.000円掛かることもあるほどです。
お墓を放置したくない、今後も維持したい場合、維持管理費が高いと感じたら、公営墓地などへお墓の引っ越し「改葬(かいそう)」を検討するのも良いでしょう。
お墓の維持費は墓地管理者へ毎年支払う、管理費が最も気を付けるべき費用です。
年単位で支払う費用なので、それほど大きい金額ではないのですが、しばしば滞納が続いて大きな金額になり、「お墓の維持費が払えない」との相談もあります。
お墓の掃除を放置するとどうなる?
◇周辺区画の墓主から、墓地管理者へ苦情が来ることもあります
また定期的に掃除に行かない墓地区画は草花が茂り荒れるため、周辺区画の墓主から苦情が来ることもあります。
掃除業者へ依頼することができますが、掃除業者にも費用が掛かるでしょう。
●費用相場…約15,000円~20,000円/1回~
遠方にお墓がある場合、自分達でお墓掃除をしても交通費が掛かります。
お墓近郊に住む親族に相談して、掃除をしてもらうこともできますが、高齢など事情がある相談が多いです。
墓じまいなく、お墓の管理費を放置したら?

◇お墓の維持管理費を払わずにいると、まず催促の通達が届きます
墓主がお墓の維持管理を行う責任を放棄したとみなされるきっかけの多くは、霊園や墓地に支払う維持管理費の滞納です。
ただ、お墓の維持管理費を放置しても、すぐに墓石の撤去に至る訳ではありません。
①督促の通達
②官報の情報登録
③お墓が撤去
④合祀墓に移動
以上4段階でお墓の撤去が進みます。
「合祀墓(ごうしぼ)」とは、ひとつの供養塔に、不特定多数の人々の遺骨を合祀埋葬するお墓です。
墓じまいとは違い、個人への適切な供養が行われない可能性もあるなか、他の遺骨とともに合祀墓に埋葬されます。
そのためお墓の維持費が払えなくても、墓地管理者へ相談だけはしたいところです。
…それでは、それぞれの段階と注意点をお伝えします。
①督促の通達
◇まず最初に、墓地管理者から維持費の催促状が届きます
この段階で何らかの対応を行えば良いのですが、なかにはお墓の維持費が払えないため、催促状に反応せず、放置してしまう墓主が少なくありません。
相談を受けた墓地管理者からは、分割の提案などを受けるかもしれません。
催促状に応じない場合、内容証明郵便でお墓の使用権を解除されてしまう恐れがあります。
②官報の情報登録
◇お墓の維持費を3年間滞納すると、官報へ情報登録されます
「官報(かんぽう)」とは国が発行している情報で、法改正などの情報提供の他、個人的な破産や相続情報、裁判内容まで記録される、新聞のようなものです。
お墓の維持費を3年以上滞納すると、この国が発行する「官報」に、個人名が登録されてしまいます。
・お墓の名義人(墓主)の氏名
・埋葬されている故人の氏名
墓地管理者としては、この官報にお墓の維持費を滞納した情報を登録してから1年が経つと、墓主の許可を得ずともお墓の撤去ができる流れです。
そのため墓主は、この官報に情報登録されてから1年以内(目安としてお墓の維持費滞納から4年以内)には、墓地管理者へ相談や支払いをした方が良いでしょう。
③お墓が撤去
◇官報に登録された後、1年経つと撤去の可能性があります
現在では墓主が行う「墓じまい」によるお墓の撤去もありますが、墓地管理者が行う場合は、個別の丁寧な供養も期待できません。
後々、思い立った時にお墓参りに行ってもお墓がない、放置されて朽ちているなどの事例の他、「埋葬されていた遺骨の納骨先も曖昧」と言う体験談もありました。
※ただし無縁仏になったお墓の扱いは、墓地管理者によって対応が違うでしょう。
④合祀墓に移動
◇無縁仏になったお墓が撤去されると、遺骨は合葬墓に移動します
…官報に登録してから1年で、無縁仏と認定されます。
無縁仏と認定されたお墓は、撤去・粉砕され、埋葬されていた遺骨は無縁仏専用など、敷地内にある合祀墓(供養塔)に合祀埋葬される段階です。
合祀墓に埋葬される時には、骨壺や骨袋から遺骨を取り出して、他の不特定多数の人々の遺骨とともに、ひとつのカロートに合祀埋葬されます。
「お墓を継承する」とは

◇お墓を継承する人は「祭祀継承者」です
今までお墓の維持管理を担ってきた「墓主」は、お墓の名義人であり祭祀継承者として、先代からお墓を代々継承してきました。
祭祀という特徴から、祭祀継承者は一人と法で定められているため、お墓や仏壇などの祭祀財産は分けることはできず、法的に継承の負担を兄弟などで分担することはできません。
民法第897条において、お墓を継承する「祭祀継承者」は、下記のように決められます。
●祭祀に関する権利の継承
「慣習によって継承者を決めるが、被相続人による指定があればその者が継承する。
それでも決まらない場合は、家庭裁判所が継承者を決める。」
そのため実際には、お墓を継承する人は必ずしも嫡男や子どもである必要はありません。
けれども近年では、墓主が亡くなったまま、次世代の後継者が決まらず、不在のまま墓じまいをせずに、お墓が放置されるケースが増えています。
墓主が亡くなると家の嫡男を筆頭に、相続人のいずれかが祭祀継承者としてお墓を引き継ぎ、お墓の名義変更をします。
ただしお墓や仏壇など、祭祀にまつわる継承は相続ではなく、相続税はかかりません。
墓じまいをせず、お墓を継承したら?
◇墓主としてお墓を維持管理する責任が生じます
墓主が亡くなった時に墓じまいをせず、お墓を放置しないためには、祭祀継承者としてお墓の名義変更を行い、新しい墓主としての責任を果たさなければなりません。
寺院墓地にお墓が建つ場合、運営する寺院は墓主にとって菩提寺となるため、ご住職とのお付き合いも生じるでしょう。
| <お墓を継承した場合に生じる負担> |
|
| [経済面] | ・維持管理費 ・お墓の修理修繕費 ・法要の際の費用 |
| [体力面] | ・定期的なお墓掃除 ・法要を執り行う |
| [精神面] | ・ご住職とのお付き合い(寺院墓地) ・後の継承者を立てる |
前述したように祭祀継承者は法律で一人と定められているため、お墓やお仏壇を分担して引き継ぐことはできませんが、兄弟で負担を分担しあうことは可能です。
けれども、お墓の維持管理にまつわる話し合いが、兄弟間の溝を作ることもあります。
一方でお墓を維持することで、お盆やお彼岸など、定期的に家族や親族が集い、絆を深めるきっかけになる家族もいるでしょう。
お墓を放置する要因は?

◇お墓の放置で多い要因に、相続があります
嫡男に家の財産を全て譲る家督相続があった時代には、お墓の継承に意義がありましたが、均等に分ける現在の相続法では、お墓を相続しても得はありません。
祭祀財産であるお墓は相続財産とみなされないため、相続税は掛かりませんが、お墓を継承しても、その負担に見合った財産が分割される訳ではないためです。
そのため、なかなかお墓の継承者が決まらない、曖昧になるケースは増えています。
お墓の継承者が曖昧
◇前の墓主が亡くなり、相続時に継承者が曖昧になったケースです
新しい継承者が決まっていないため、責任の所在も曖昧になり、お墓の維持管理費の支払いも放置されます。
お墓の名義人の変更もないため、霊園・墓地管理者が催促通知を出しても届かない、返事が来ないケースも多いです。
墓主が急に亡くなった
墓じまいをおすすめするケース

◇お墓の維持管理に負担を感じているならば、墓じまいがおすすめです
墓じまいをする時には労力や費用がかかりますが、問題がひとつ解消されます。
墓じまいをすることでお墓は放置されることなく、無縁墓・無縁仏と判断されません。
家族としては無縁墓・無縁仏として処理されたり、ただただ無造作に放置されるよりも、墓じまいをしてしっかりと供養して、気持ちの良い解決になるでしょう。
ただし墓じまいはお墓がなくなることですから、家族や親族への相談は不可欠です。
お墓の維持管理への負担を説明して理解してもらいましょう。
①墓主が高齢で問題が生じている
次のお墓の継承者が決まらないまま墓主が高齢になり、定期的なお墓掃除などが負担になっているケースは多いです。
公共部分が整っているお墓でも、高齢者にとってお墓掃除は大変な労力です。
草むしりや砂利の掃除、水を使ってのお墓掃除は足元が滑るリスクもあります。
また辺境地に建つお墓もあるので、そもそもお墓参りが困難な墓主もいるでしょう。
お墓掃除は定期的に続くものですから、負担を感じた時には墓じまいを検討してみるのも一案です。
②遠方でお墓の維持管理が難しい
昔は子ども達が成長しても、代々同じ地域に住んでいましたが、人々の暮らしがグローバル化した現代では、墓主が遠方に住んでいて、お墓の維持管理が困難になることも多いでしょう。
お墓は定期的な掃除をして衛生環境を保たなければなりません。
定期的なお墓掃除のために、飛行機や新幹線を使うのでは経済的な負担も大きいです。
最近ではお墓の掃除業者も登場しましたが、依頼するのにも費用が掛かります。
墓主が気軽にお墓掃除に行ける環境ではない、近所に住む親せきもいない場合には、墓じまいを検討してみてはいかがでしょうか。
③維持管理費の負担が大きい
お墓の維持管理費の負担が大きくなり、墓じまいを決断する墓主も多いです。
特に墓主が高齢になると収入も少なくなるため、負担の割合は大きくなります。
寺院や霊園など、墓地管理者に支払う毎年の年間管理料の他、お墓の修理修繕費も必要です。
またお墓の経年劣化がさらに進むと、建て替えも考慮しなければなりません。
さらにお墓の維持管理費への負担が大きくなる前に、墓じまいを検討する方は多いです。
④継承者がいない
将来的な継承者がいない場合、墓主が亡くなった後、墓じまいがされないまま、お墓が放置される状況が予想できます。
祭祀継承者である墓主は、お墓に対して決定権がありますよね。
そのため墓主が亡くなり継承者がいなくなると、墓じまいを決定する人もいなくなります。
また、そもそも継承者がいない、お墓を管理する人がいなくなるため、いずれお墓は墓じまいしないまま放置され、無縁墓・無縁仏と判断されます。
⑤子どもや孫の負担が心配
お墓を放置しない方法

◇墓じまいにより、お墓の放置問題は解決されます
継承者が曖昧になりお墓が放置されるようならば、墓じまいが有効です。
またお墓を継承したものの、維持管理費や掃除が負担になる人もいます。
墓主が高齢になってきて続く継承者に不安がある場合にも、生前に墓じまいをしてしまうことで、後々にお墓が放置されるリスクも軽減されるでしょう。
墓じまいとは?
◇「墓じまい」は、現存のお墓を撤去し閉じることです
墓主が墓じまいを行う場合、石材業者に依頼して遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓地管理者へ返還します。
・子孫が遺骨を取り出す
(丁重に供養して取り出す)
・新しい納骨先でも供養ができる
・遺骨の所在が分かる
また霊園や墓地によっては経済上の問題から、無縁仏と判断されたお墓を撤去せず、放置したままの状態も見受けます。
お墓を放置したままだと、草木で荒れ果ててしまうでしょう。
その様子を見て、子孫の手で遺骨を丁重に取り出し供養を決断する人もいます。
墓じまいの手順

◇墓じまいは新しい供養先を、先に決めるとスムーズです
墓じまいは、埋葬されているご遺骨を取り出して墓石を解体・撤去して更地にした状態で、墓地管理者に返還します。
取り出したご遺骨は放置したり、むやみに破棄することは法に触れるためできません。
納骨堂や合祀墓など、何らかの永代供養を行うため、まずは取り出したご遺骨の新しい供養先(納骨先)を決めてしまうとスムーズです。
新しい供養先となる霊園や寺院では、僧侶や石材業者の手配なども相談できるでしょう。
また霊園や寺院によっては「墓じまいパック」などのプランも提案してくれます。
・墓じまいとは?やることは?「墓じまいパック」費用目安や納骨先、提供業者の種類とは?
①ご遺骨の新しい供養先を決める
◇新しい供養先を決めて「受入証明書」をもらいます
取り出したご遺骨は新しい供養先(納骨先)へ移動する必要があり、多くは合祀墓や納骨堂などの永代供養を選ぶでしょう。
永代供養はご遺骨を個別に安置できる期間、ご遺骨の柱数によって費用幅があります。
最も安く抑えたいならば、最初から他のご遺骨と一緒に合祀埋葬される合祀墓が適切です。
合祀墓の目安としてはおひとり約3万円~10万円ほどとなるでしょう。
ただし、一度合祀されてしまうと、ご遺骨は再び取り出すことができません。
一定期間はご遺骨を個別に安置したい場合、納骨堂や集合墓などの選択肢もあります。
この他、近年ではいずれ土に帰る樹木葬も人気です。
・墓じまいで必要な永代供養の費用はいくら?納骨後の追加費用はかかる?後悔しない選び方
②寺院や霊園に相談する
◇お墓が建つ墓地や霊園の、墓地管理者に相談します
今お墓が建っている墓地や霊園の墓地管理者に相談をして、行政手続きで必要になる書類「埋葬証明書」をいただきましょう。
 
役所によっては、窓口で発行する書類「改葬許可申請書」に、現存する墓地や霊園の墓地管理者から印をもらう形式もあるので、最初に役所へ電話で確認しても良いです。
ただし民間霊園の場合、事務的な相談でスムーズに進むことが多いですが、寺院墓地の場合はご住職が「今までお墓を守ってきた」という想いもあります。
墓じまいを進めるにあたり、閉眼供養やお墓の解体工事など、スケジュール調整もありますから、トラブルのないよう、感謝とともに早い段階でご相談すると良いでしょう。
③役所で行政手続きをする
◇役所で「改葬許可申請」を行います
「墓じまい」は民間用語で行政手続き上はご遺骨を引っ越す「改葬」の手続きが必要です。
改葬の手続きでは、役所窓口で「改葬許可申請書」を、必要書類とともに提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
●第5条
「改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村区長の許可を受けなければならない。」
ご遺骨を扱うにあたり改葬許可申請は、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)にて定められたことであり、改葬許可申請がなければ石材業者も受け付けてくれません。
 
必要書類とは申請者の身分証明の他、新旧の霊園や墓地でいただいた「受入証明書」「埋葬証明書」です。
④石材業者に依頼する
◇まず墓地や霊園に指定石材業者があるか相談しましょう
墓じまいではお墓の解体・撤去作業、墓地を更地にする作業があります。
またご遺骨を取り出す作業においても、石材業者に依頼することがほとんどです。
| <墓じまいで石材業者への費用目安> |
|
| ①内部調査 | ・無料~約3万円 |
| ②ご遺骨の取り出し | ・約3万円~5万円/1柱 |
| ③解体・撤去 | ・約10~20万円 |
| ④墓石の処分 | ・約10万円/1㎡ |
現在の霊園や寺院墓地では、多くが提携する石材業者があります。
料金が高いこともありますが、提携石材業者であれば信頼性もあるでしょう。
 
なかには特定の石材業者しか利用できない霊園や寺院墓地もあるので、トラブルにならぬよう、まず墓地管理者へ確認すると安心です。
公営墓地では、自分たちで石材業者を探し依頼する流れです。
⑤閉眼法要をする
◇お墓の魂を抜く作業が閉眼法要です
一般的に仏教の教えに倣い、墓じまいにあたりお墓の魂を抜く「閉眼法要(閉眼供養)」を執り行ってから、墓石の解体・撤去作業に入ります。
 
寺院墓地であればご住職に閉眼法要を依頼し、民間霊園や公営墓地であれば、僧侶を手配する流れです。
| <お布施の費用目安> |
|
| ①お布施 | ・約3万円~5万円 |
| ②御車代(必要あれば) |
・約3千円~5千円 |
| ③御膳代(必要あれば) |
・約5千円~2万円 |
お墓を前に家族のみで執り行う閉眼法要も多いですが、別会場を借りたり、閉眼法要の後に会食をふるまう場合には、その分費用も掛かるでしょう。
御車代は僧侶に寺院からお墓まで出張いただいた場合の交通費ですので、タクシー代を目安に包みます。
御膳代は閉眼法要の後に会食をふるまう場合に、僧侶にお声かけをしたもののお断りがあった時に包むものです。
お布施マナーについて、詳しくは下記コラムをご参照ください。
⑥新しい供養先に納骨する
◇取り出したご遺骨を、新しい供養先に納骨したら終了です
取り出したご遺骨を新しい供養先に供養します。
永代供養が付いた個人墓など、納骨先によっては開眼法要も必要になるでしょう。
 
開眼法要とは、閉眼法要の反対で墓石であるお墓に魂を込める儀礼です。
僧侶をお呼びして行うため、同じく約3万円~5万円のお布施を包みます。
・【墓じまいの費用まとめ】平均や僧侶費用、離檀料は?遺骨供養まで手順5つでかかる費用
お墓を放置しない墓じまいの後は?

◇墓じまいで取り出した遺骨は、永代供養や自然葬で処理します
ただ墓じまいをしても、取り出した遺骨は何らかの形で処理しなければなりません。
主には永代供養、自然葬が選ばれます。
| <霊園・墓地の維持管理費> ●公共部分の維持管理費用 |
|
| [墓地の種類] | [費用目安] |
| ・公営墓地 | …約2,000円/年~ |
| ・寺院墓地 | …約9,000円~15,000円/年~ |
| ・民間霊園 | …約9,000円~15,000円/年~ |
また一般的に、お墓の継承者がいない場合には墓じまいを選びますが、「お墓を残したい」「次の代でお墓の継承者が現れるかもしれない」と考える時には、お墓に永代供養を付ける選択もあるでしょう。
ただし永代供養料が掛かるうえ、毎年の維持管理費は払い続けなければなりません。

①永代供養
「永代供養」とは、家族に代わって墓地管理者が、お墓や遺骨の管理・供養を担うサービスです。
永代供養は遺骨やお墓の管理や供養を担う、形のないものなので、さまざまな供養の形に付加できます。
| <永代供養の一例> | |
| [供養塔のみ] | ・合祀墓 |
| [個別の墓標がある] | ・納骨堂 ・集合墓 ・ガーデニング型樹木葬 |
個別スペースに遺骨を収蔵する納骨堂や集合墓では、契約した一定年数は個別に遺骨が残り、個別に手を合わせる墓標もあります。
けれども個別スペースが確保される契約年数期間は、お墓と同じく維持管理費を支払うシステムが多いです。
生前の終活などで一括契約をしたい場合、事前に契約年数分の維持管理費を支払う流れになるでしょう。
②自然葬
◇遺骨を自然に還す自然葬では、継承の必要がありません
自然葬は海や山林に遺骨を撒いたり、ゆっくりと土に還元する埋葬方法です。
いずれ遺骨は自然に還ることを前提とするため、そもそもお墓のように管理者や継承者が必要ありません。
| <自然葬の種類> | |
| ①樹木葬 | ・合祀型(シンボルツリー型) ・個別区画型(植樹型) |
| ②散骨 | ・里山散骨 ・海洋散骨 ・空葬(バルーン葬) ・宇宙葬 |
土に還る樹木葬では、ゆっくりと土に還る骨壺や骨袋を用いたり、骨袋から出して遺骨を埋葬するため、最終的に遺骨自体が残りません。
散骨でもパウダー状に粉骨した遺骨を撒く葬送なので遺骨が残らず、結果的にお墓の維持費を支払う、継承者を残す必要がないでしょう。
⑤手元供養
◇「手元供養」では、遺骨を自宅で供養します
手元供養とは、自宅で遺骨を管理・供養する方法です。
自宅で遺骨を供養するため、遺骨の手入れや粉骨費用以外に費用が掛からず、予算に合わせた準備ができます。
| <手元供養の種類> | |
| ①アクセサリー | ・ペンダント ・ブレスレット ・キーホルダー |
| ②ステージ(祭壇) | ・骨壺を祀る |
現代は新しい供養の形として根付き始め、仏壇仏具店では手元供養専用の小さなステージ(祭壇)や骨壺も販売されるようになりました。
美しく遺骨を祀るため、粉骨業者に粉骨を依頼する流れが一般的です。
粉骨は業者により費用幅がありますが、約3万円/1柱を目安にすると良いでしょう。
散骨も粉骨をするため、家族など身近な故人の遺骨だった場合、セレモニーとして散骨を行い、残りを手元供養にする体験談もあります。
・【手元供養の体験談】娘の手元供養。娘の遺骨を納骨できないまま5年、分骨をして祭壇へ
まとめ:お墓を放置すると無縁仏とみなされます

継承者が曖昧なまま、お墓を放置すると無縁仏として撤去され、取り出した遺骨はどこかの供養塔に納骨されるでしょう。
一方で家族や親族が同じ集落に住んでいた頃と違い、お墓を継承すると、維持費はもちろん管理も、墓主ひとりに負担が掛かりがちです。
さらにお墓もいずれは老朽化するため、お墓の修繕や建て替えを必要とする事態にも直面します。
お墓の維持費が払えないということは、無理があるということです。
この機会に、誰もが無理をしないお墓の維持管理方法を検討してみてはいかがでしょうか。
・お墓の継承をしたくないなら、継承後の墓じまいがベスト|継承手続きから墓じまいの手順
お電話でも受け付けております















