
【大阪のお墓】先祖代々墓を継承すると何が大変?継承を決める前に押さえたい7つの記事
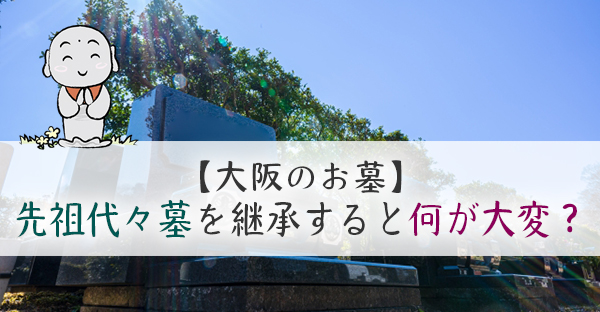
大坂ではお墓の継承に関するご相談も少なくありません。
大坂ではシニア層を中心に墓じまいが広がっていますが、一方で30代前後の大阪の若い世代では、お墓の継承が見直されています。
不安定な日本の経済やコロナ禍の影響のなか、昔に立ち戻り家族でのお墓参りをしたい、子どもに供養文化を残したい、との声が増えているためです。
では、実際に大阪で先祖代々のお墓を継承するには、どのような問題があるのでしょうか。
今回は、大阪でお墓の継承に迷う人々が判断しやすい7つの記事を、概要とともにご紹介します。
【大阪のお墓】先祖代々墓を継承すると何が大変?継承を決める前に押さえたい7つの記事

大阪でお墓は誰が引き継ぐべき?
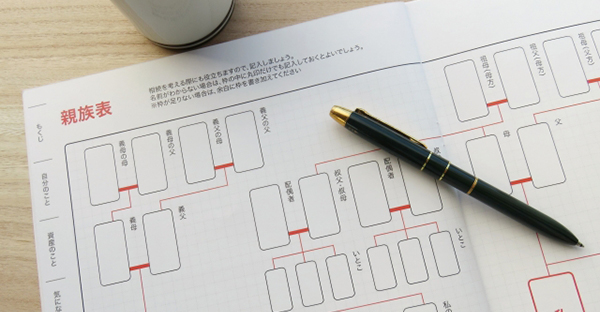
以前の大阪では寺院墓地に建つお墓がほとんどでしたので、寺院の仏教宗派に倣った継承者が代々墓主となってきました。
その昔は、大阪や全国でもお墓の継承は家督相続と対になっていましたから、長男が引き継ぐ流れがあったでしょう。
けれども近年は、寺院墓地から離檀(信家から離れる)して、宗旨宗派不問の民間霊園へ改葬(お墓の引っ越し)を行う家が増えたため、大阪ではお墓の継承者も自由になっています。
(1)慣習では長男が多い
(2)霊園の規定
(3)故人が遺言などで指定する
(4)家庭裁判所で決める
(5)法的には誰でも良い
…などなどのポイントがあります。
法的には誰が継承しても良いのですが、大阪では霊園の規定でお墓の継承者の範囲(第三親等までなど)が定められていることもあるでしょう。
このような規定は、特に寺院墓地で厳しい場合が多いので、確認をしてください。
また、大阪ではお墓の継承者が決まらずに揉める家族も多いのですが、この場合には家庭裁判所が継承者を指定することがあります。
・残されたお墓は、誰が引き継ぐ?
大坂でお墓を継承すると「負担」はある?

大坂でお墓の継承者がなかなか決まらない理由は、墓主の負担が大きいためでしょう。
お墓は相続税の掛からない祭祀財産なので、継承時に相続税の心配はないのですが、維持管理のためには経済的な負担も伴います。
・霊園への年間管理料…約1万円~3万円ほど/年間
・定期的なお墓の掃除
・お墓の修繕やメンテナンス
・施主として法要を執り行う
・次期継承者を決める
…などなどです。
ちなみに寺院墓地では年間管理料を「お布施」として毎年包むこともありますが、内容としては日ごろの管理へのお礼なので同じでしょう。
また墓主になると施主として年忌法要などを執り行わなければなりません。
この点も、精神的・体力的な負担として、避けられがちです。
ただ最近では親族と話し合い、年忌法要を繰り上げて弔い上げ(年忌法要を終えること)とするお墓が増えました。
・大阪でお墓の継承者に!経済的な負担はどれくらい?年間管理料やメンテナンスコスト、法要まで解説
大阪でお墓を継承する時の手続きは?
大坂でお墓を継承する時には、名義変更の行政手続きが必要です。
お墓の名義変更について、法的には明瞭な期限は定められていませんが(2022年現在)、霊園の規定として期限を設けていることは多いため、大阪でお墓を継承したら、早々に手続きを行ってください。
下記の書類を用意して、お墓が建つ地域の役所で手続きを進めます。
●お墓について
・名義変更の申請書
・墓地使用許可証
●継承者の証明書
・継承者の戸籍謄本/本籍記載の住民票
・継承者の実印/印鑑登録証明書
…などです。
「墓地使用許可証がない!」などのご相談も多いですが、この場合には大阪でお墓を継承した役所の、生活環境課で再発行ができます。
(墓地使用許可証再交付申請書の提出が必要です。)
・大阪でお墓を継承するといくら掛かる?手続き・必要書類や金額目安や、墓じまいの選択肢
夫婦両家のお墓を継承したい!

また近年大阪のお墓継承で多い相談が「娘ばかりで実家の継承者がいない」と言うものです。
この場合、もちろん墓じまいなどで先祖代々のお墓を閉じる選択もありますが、なかには「何とかお墓を継承したい」との声も少なくありません。
このようなケースで近年増えた解決策が「両家墓」です。
●夫婦両家のお墓を一つのお墓、もしくは墓地にまとめたまとめたお墓を差します。
お墓の維持管理が一か所で済む点が大きなメリットですが、将来的に大阪で両家のお墓を一手に継承するため、後の継承者の負担が大きくなる可能性も否めません。
この場合、長男が父親の家のお墓を継承し、次男(やそれ以降の兄弟姉妹)が母親の家のお墓を継承する解決策もありました。
また継承者を必要としない、永代供養を両家墓に付加する解決策も有効です。
・娘だけどお墓を継承したい!両家墓で二世帯をひとつにまとめる|種類や注意点まで解説!
そもそも「檀家制度」ってなに?

この他、大阪では「お墓を継承して初めて、檀家制度を知った!」と言う声も少なくありません。
●檀家制度は、仏教寺院において信徒(家)と寺院の関係性です。
・檀家…その寺院の信徒(信家)
・菩提寺(檀那寺)…その人(家)が入信する寺院
→ただし江戸時代から広がる制度で、多くは寺院墓地にお墓を建てている寺院となります。
江戸時代の昔には檀家制度によって、現代の戸籍のように庶民を把握していたようです。
そのため多くの家で菩提寺は地域に根差した寺院が多く、その地域に住む家々の先祖代々墓を管理する寺院墓地になっています。
「檀家制度を知っていたら継承しなかったのに…」などの声もありますが、檀家制度に悩む場合には、宗旨宗派不問の民間霊園へお墓の改葬(引っ越し)を検討するのも一案です。
(改葬については「大坂でお墓の改葬(引っ越し)はどう進める?決める前に押さえたい、7つのコラムを紹介」に記事がまとまられていますので、コチラをご参照ください。)
大坂では寺院墓地のお墓を継承すると、菩提寺と檀家として、一定のマナーなどがあるため、継承者は予め理解しておくと、トラブルも少なく済むでしょう。
・大阪でお墓を建てたら「檀家になる」ってどういうこと?菩提寺・檀那寺との関係性とは?
大阪でお墓の継承トラブル事例はある?

大坂でお墓の継承トラブルが起きるケースでは、主に下記2つの種類が多いです。
ただ体験談は多いものの、両親の死別や再婚によるトラブルは心の問題とも言えるでしょう。
(「【大阪でお墓の継承問題】母と死別した父が子連れ再婚。父と継母亡き後に起きた兄弟間トラブルと体験者の後悔」の体験談をご参照ください。)
・お墓継承の譲り合い
・両親の再婚による継承者問題
お墓の継承は相続税の対象外ですし、遺産分割では遺留分に入らないため、大阪でお墓を継承したところで、相続に損はないのですが、やはり継承後の負担が大きい点がトラブルの原因でしょう。
(ちなみに生前にお墓を贈与した場合、贈与税が課税されますので注意をしてください。)
また同じく、相続において問題になりやすい財産が空き家になった古い実家ですが、この場合は最終的に(あまりおすすめはしませんが)兄弟で共有財産とし、負担を分け合うこともできます。
けれどもお墓は法律で「継承者は一人」と定められているので、「口約束では負担が一点に絞られないか」と、大阪では兄弟間でお互いにお墓の継承を渋るトラブルが起きやすいです。
・【大阪の相続】実家とお墓を兄弟で一緒に相続・継承はできる?トラブルになるってホント?
大阪でお墓の継承ができない時の対処法

…では、大阪で誰もお墓を継承できない場合はどのように対処すれば良いでしょうか。
現在では墓じまいの選択が多いです。
墓じまいとは、名前の通り先祖代々墓を閉じて撤去する作業です。
兄弟親族間で話し合う必要はあるものの、最終的には墓主が決断するため、まずは誰かがお墓を継承し、その後で墓じまい、…と言う流れになるでしょう。
・親族へ相談
・現在の墓地(旧墓地)へ相談
・取り出した遺骨の納骨先を決定
・墓じまいの手続き(役所)
・墓じまいの閉眼供養(僧侶)
・墓石の撤去(石材業者)
・取り出した遺骨を納骨供養(納骨先)
…一連の流れを見ても分かるように、ひと口に墓じまいと言っても、石材業者への依頼や僧侶へのお布施、何よりも取り出したご遺骨の納骨先にもコストが掛かります。
最初に兄弟親族間で相談して皆で決め、費用を出し合うと負担も偏らず、トラブルも少ないでしょう。
・【墓じまいの手続きまとめ】スムーズに進める7つのステップ|取り出した遺骨の永代供養
最後に
ここまでお伝えしましたが、今大阪では若い世代でお墓の継承を検討する人々も増える一方、65歳以上のシニア世代では、墓じまいが急増しています。
どちらを選ぶか選択するために、まずは大阪でお墓を継承した場合の負担を、経済的・精神的・肉体的、それぞれの側面から具体的にチェックしてみると、後々まで後悔しません。
また最近の大阪ではお墓継承後の管理を楽にするため、遠方にある霊園から、管理の必要がない都心の納骨堂などへ改葬(ご遺骨の引っ越し)する選択も増えました。
(納骨堂については「永代供養と納骨堂の違いとは|それぞれのメリットとデメリットについても解説」などにも詳しいです。)
またお墓に永代供養を付けることにより、後々の継承者を危惧しなくても済みます。
(【大阪の永代供養まとめ】勘違い「永代供養」はお墓じゃない!最初に押さえる7つの記事)
まとめ
先祖代々墓の継承が分かる7つの記事
・残されたお墓は、誰が引き継ぐ?
・大阪でお墓の継承者に!経済的な負担はどれくらい?年間管理料やメンテナンスコスト、法要まで解説
・大阪でお墓を継承するといくら掛かる?手続き・必要書類や金額目安と、墓じまいの選択肢
・娘だけどお墓を継承したい!両家墓で二世帯をひとつにまとめる|種類や注意点まで解説!
・大阪でお墓を建てたら「檀家になる」ってどういうこと?菩提寺・檀那寺との関係性とは?
・【大阪の相続】実家とお墓を兄弟で一緒に相続・継承はできる?トラブルになるってホント?
・【墓じまいの手続きまとめ】スムーズに進める7つのステップ|取り出した遺骨の永代供養
お電話でも受け付けております















