
離檀とは?檀家をやめる離檀のやり方、メリットデメリット、トラブル対策をくわしく解説
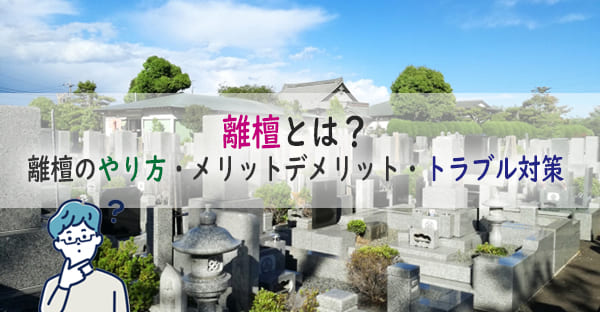
・「離檀」とは?
・離檀のメリット、デメリットはある?
・トラブルのない離檀のやり方は?
離檀とは、菩提寺から檀家を離れることを差します。
一般的に寺院墓地にお墓が建つ家は、墓地を管理する寺院の檀家であり、寺院は菩提寺です。
離檀はこの菩提寺と檀家の関係性を絶つことを意味します。
今回は離檀とはなにか?メリット・デメリットを理解して、トラブルなく離檀するやり方をくわしく解説しますので、どうぞ最後までお読みください。

「離檀」とは?

◇「離檀」とは、代々家が信仰する寺院「菩提寺」から抜けることです
「離檀(りだん)」とは檀家から離れることを差します。現代の「檀家(だんか)」は、一般的に寺院墓地にお墓が建つ家でしょう。
檀家のお墓が建つ寺院墓地の母体を「菩提寺(ぼだいじ)」「檀那寺(だんなでら)」と呼び、檀家のお墓の管理や、供養を担います。
江戸時代から始まった檀家制度は、現代の戸籍と同じ役割を果たし、集落の寺院が住民を把握するため、檀家になることを義務付けられてきました。
| <離檀とは> | ||
| ・檀家 | 特定の寺院を信仰する家 | 菩提寺にお墓がある |
| ・菩提寺 | 檀家が支える特定の寺院 | 檀家のお墓を管理・供養する |
| ・離檀 | 菩提寺と檀家の関係を解消 | 墓じまい、改葬 |
このように、檀家はあくまでも特定の寺院を信仰する家なので、檀家だからと言って、必ずしも寺院墓地にお墓を持つ必要はありません。
ただ檀家であれば、一般的に寺院墓地にお墓を建てているでしょう。
先祖代々墓など代々檀家であることが多く、檀家は特定の寺院に、毎年檀家料を支払い、代々家で支えてきました。
離檀にはお墓の撤去が必要?
◇寺院墓地に建つお墓の墓じまいや改葬に伴う、離檀が多いです
離檀を検討する菩提寺にお墓が建つ場合、基本的にはお墓を撤去します。
また現代は、寺院墓地のお墓を管理・供養してもらうため、檀家になっている家も多いでしょう。
墓じまいやお墓の引っ越し「改葬(かいそう)」に伴い、菩提寺を離れる流れが一般的です。
| <離檀するとお墓はどうなる?> | |
| [お墓の撤去] | ・墓じまい(お墓の撤去) ・改葬(お墓の引っ越し) |
| [離檀料] | ・約5万円~20万円 |
また墓じまいや改葬により離檀する場合には、法的な決まり事ではありませんが、長くお墓を管理・供養していただいたお礼として、離檀料を包みます。
ただし離檀料を支払う法的根拠はなく、あくまでも感謝の気持ちを形にしたお布施なので、法外な離檀料を請求されても支払う必要はありません。
離檀トラブルを回避する、スムーズな離檀の交渉ポイントは、詳しく後述しますので、どうぞ最後までお読みください。
檀家料は年間管理料?
◇檀家料は本来、仏道への修行「お布施」であり、檀家が菩提寺を支えるものですが、現代は民間霊園の年間管理料と同じ役割です
「年間管理料」とは、宗旨宗派を問わない民間霊園において、公共部分を清潔に保つための管理料となります。
檀家は毎年、菩提寺にお布施として「檀家料」を支払いますが、現代の檀家料は宗旨宗派を問わない民間霊園における「年間管理料」と同じ役割を果たします。
| <霊園や寺院墓地に毎年支払う管理料> | ||
| ●管理料の費用目安は、約2千円~2万円です | ||
| ・檀家料 | 寺院墓地 | お布施 |
| ・年間管理料 | 民間霊園 | 管理料 |
檀家である限り、毎年ランニングコストとしてお布施を支払う必要はありますが、民間霊園へ改葬しても、年間管理料の支払いはあるでしょう。
※ただし墓じまい後、取り出した遺骨を合祀墓など、後々の管理を必要としない永代供養にした場合には、納骨後の年間管理料や檀家料は掛かりません。
離檀が進む背景とは

◇宗旨宗派を問わない民間霊園の登場で、離檀が急増しました
昭和の時代は大阪でも檀家制度が広く根付き、菩提寺に建つ先祖代々墓に納骨する流れが一般的でした。
けれども宗旨宗派不問の民間霊園により、離檀の流れが起きています。
| <離檀が進む理由> | |
| [利便性] | ・菩提寺が住まいから遠い ・菩提寺が辺境にありお墓参りが大変 |
| [自由度] | ・宗旨宗派を問わない墓地が良い ・無宗教 |
| [関係性] | ・ご住職とのお付き合いが大変 ・ご住職と相性が悪い |
昔は家族が亡くなると、通夜や葬儀について菩提寺に相談し、近所の人々がお手伝いをしてくださる中、菩提寺のアドバイスにより、一切の法事を進行しました。
けれども現代は葬儀社に依頼し、スタッフが全てをサポートしてくれます。
このような時代の変化も、離檀の流れに繋がっているのでしょう。
・霊園とはなに?墓地とは違うの?大阪の民間霊園・寺院墓地・公営墓地、3つの違いを解説
離檀するメリットとは

◇離檀するメリットは、負担の軽減です
現代は「お墓の撤去=離檀」と考える家が多いため、離檀の理由にはお墓の管理や継承が困難になって、遠方にあるお墓を身近な墓所へ改葬する、などがあるでしょう。
けれどもそれ以外にも、仏教宗派や規律、経済的負担からの解放もメリットです。
経済的負担の解消
◇離檀することで菩提寺へ、毎年の檀家料などのお布施を払わずに済みます
ただし民間霊園へ改葬しお墓を建てた場合、檀家料に代わり「年間管理料」を支払わなければなりません。
それでも寺院は檀家がお金を出し合い支える制度ですので、定期的な寺院の修理修繕費をお布施として包むこともあり、経済的負担は軽減されるでしょう。
宗旨宗派の自由
◇寺院墓地は檀家になり、菩提寺の仏教宗派に属する必要があります
けれども離檀することで菩提寺から抜けるため、その後の信仰は自由です。
民間霊園は宗旨宗派不問が多いため、墓石の形や供養も自由でしょう。
現代は離檀して無宗教になり、ホテル葬など、読経供養を伴わないカジュアルな葬儀も見受けるようになりました。
寺院の規律から解放
お墓の管理が楽になる
◇遠方にお墓がある場合、改葬して身近にお墓を建てることで管理が楽になります
「改葬=離檀」とした場合、遠方の寺院墓地に建つ先祖代々墓を改葬し、住まいの身近に置くことで、お墓の管理や負担が軽減されるでしょう。
特に現代は永代供養が付いた納骨堂や集合墓、コンパクトなお墓も増えました。
継承問題とともに希望に見合った適切なお墓の形態を選ぶと、後々まで安心です。
・お墓を継承したけど維持費が払えない!放置したらどうなる?5つの対処法|永代供養ナビ
離檀のデメリット

◇離檀により、菩提寺との関係性が絶たれます
離檀により菩提寺との関係が絶たれることは、理解して進めなければなりません。
また菩提寺にとって離檀は、信家が少なくなることで、あまり良い気持ちがするものではない、と言う点も理解しておく必要があります。
今まで家の人々の供養やお墓の管理を担ってきてくれた菩提寺へは、感謝の意を込めて、離檀を検討すると良いでしょう。
法要の相談先が無くなる
◇離檀により、今後の葬儀や法要における相談先が無くなります
江戸時代の昔から今日まで檀家制度が続いてきたのには、かつては義務もありましたが、先祖代々から、その家の生死にまつわる供養や法要を、菩提寺が担ってきたためです。
けれども離檀により、菩提寺と檀家の関係性は経たれ、自由になった反面、法要を自分達で進めなければなりません。
・法要とは?いつまで、なにをするの?法事との違いや意義、会食の内容やお布施相場も解説
無縁仏になる可能性
◇墓じまいをせず、離檀をした場合には無縁仏になる可能性があります
菩提寺から離檀しご遺骨(お墓)が取り残された場合、そのご遺骨は「無縁墓」として扱われます。
離檀した家のお墓を、菩提寺は管理・供養を続ける必要はありません。
| <お墓を残して離檀するとどうなる?> | |
| [お墓] | ・お墓の撤去 ・墓地区画は更地になる |
| [取り出された遺骨] | ・供養塔に合祀埋葬 |
一般的に無縁墓になったお墓は撤去され、取り出した遺骨は供養塔などに、他の遺骨とともに合祀埋葬されます。
離檀前に墓じまい
◇無縁墓として処理されぬよう、離檀前に自分達で墓じまいをします
名前も所在も分からない無縁仏として埋葬されてしまうので、離檀前に墓じまいを行わなければなりません。
墓じまいがスムーズに進むためにも、菩提寺のご住職に納得いただいた上で離檀ができるよう、相手を慮った、離檀交渉は不可欠です。
・大阪で起きた離檀トラブルにどう対応する?離檀料の金額相場や体験談に見る5つの解決策
スムーズな離檀のやり方

◇離檀を決めたら早めに、まずは「ご相談」をします
葬祭業や民間霊園が広がる今、全て契約により結ばれていると考えがちです。
けれども江戸時代から続く檀家制度は「信頼」や「信仰」のうえに成り立つ関係であることを理解して、交渉を進めなければなりません。
お墓を撤去するから離檀しなければならない寺院ばかりではなく、お墓を持たない「外檀家」の選択もできるため、検討するのも一案です。
菩提寺の心中を慮る
◇事務的ではなく、誠実に向き合う
菩提寺と檀家の関係性は単なる契約で結ばれた関係ではありません。
そのためお互いに誠実に向き合う気持ちが大切です。
・突然「墓じまいをするので離檀料をお支払いします。おいくらでしょうか?」とのメールが来て戸惑った。
菩提寺としては、責任を持って預かってきたお墓を、日々美しく維持管理をし、毎日手厚く供養をしてきた自負があります。
菩提寺からは突然事務的に離檀を通知され、戸惑いを隠せない相談事例も少なくありません。
まず離檀の相談を持ち掛ける
◇余裕を持って離檀の相談を受けることで、菩提寺の理解も深まります
菩提寺としては「突然」の離檀でも、檀家からは「突然ご住職が怒った!」とのトラブル相談が多あります。
冷静にお互いの立場を理解し合うためにも、余裕を持った相談が有効です。
●「どうしても、このままではお墓を維持できない!」
・離檀をせざるを得ない事情
・長年、お墓の維持や管理への感謝
・なかなかお参りに伺えないことへのお詫び
菩提寺との関係性はとても有難く感謝をしているものの、「致し方なく」離檀を検討している、とお伝えすることで、随分と印象も変わります。
離檀のご相談に伺えない
◇手紙やメールでも良いですが、心を込めた文面にしましょう
離檀は関係性が絶たれることを意味するため、できれば直接お伺いして相談する方法がベストですが、難しい事情があれば手紙やメールでのご相談でも構いません。
ただし事務的ではなく、心を込めた文面を心掛けましょう。
また気持ちとして約5千円ほどの渇き菓子など、お礼の品を送っても喜ばれます。
・お中元はいつからいつまで?関東と関西で違う?初盆はどうする?おすすめの品やのしは?
離檀は、まずご相談から始めます

現代は寺院墓地にお墓を建てるために檀家になる家が多いため、墓じまいや改葬により離檀を検討する家がほとんどです。
菩提寺のご住職に理解していただき離檀をすることで、スムーズな墓じまいや改葬にも繋がりますので、まずはご相談から始めると良いでしょう。
墓じまいや改葬をしたからと言って、必ずしも離檀しなければならない訳ではありません。お墓のない「外檀家」の選択もあります。
賢い離檀のやり方は、菩提寺に理解され応援してもらい進めることです。
離檀料は墓じまいで行う閉眼供養の際、お包みすると良いでしょう。
お電話でも受け付けております
















