
墓じまいの閉眼供養でお供え物はなにを揃える?必ず必要な5つの供物とタブーまで解説
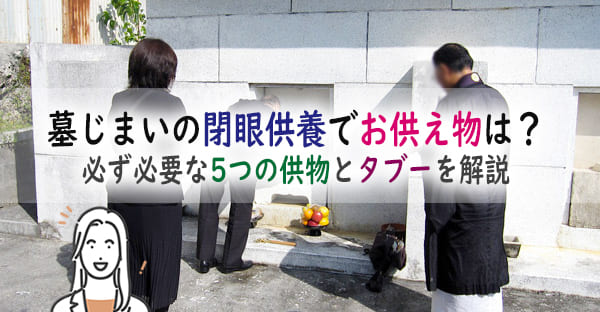
・墓じまいの閉眼供養、お供え物は?
・墓じまいの閉眼供養にお供え物は必要?
・墓じまいの閉眼供養に必要なものは?
・墓じまいの閉眼供養、お布施相場は?
・墓じまいでは、石屋さんに心付けが必要?
「墓じまい」とは、お墓を撤去して墓地管理者へ返還することです。
お墓には魂が宿るとされ、墓じまいの前に閉眼供養を行います。
本記事を読むことで、墓じまいのお供え物や、当日持参するもの、僧侶へのお布施や石屋さんへの心付けなど、必要な準備が分かります。

墓じまいとは?閉眼供養のお供え物は?

◇「墓じまい」とは、お墓を撤去して更地に戻し、墓地管理者へ返還することです
お墓には遺骨が納骨されているため、墓じまいでは遺骨を取り出して墓地管理者へ返します。
また取り出した遺骨は石屋さんが引き取ってくれる訳ではありません。
納骨堂や合祀墓など、何らかの形で供養します。
| <墓じまいの手順とは> | |
| [準備] | ・新しい納骨先を探す ・既存の墓地に報告 |
| [既存墓地] | ・閉眼供養 ・遺骨の取り出し ・お墓を撤去 ・墓地を更地にする ・墓地管理者に返還 |
| [新しい墓地] | ・遺骨の納骨 (永代供養) |
新しい納骨先は合祀墓など、納骨後の遺骨の管理や供養を任せる「永代供養」を選ぶことが多いでしょう。
・墓じまいの手順や手続きとは?しないとどうなる?9つの手順と行政手続き、費用も解説!
墓じまいの閉眼供養やお供え物は?

◇墓じまいは一般的に、家族など関係者のみで行います
日本では昔から、お墓には魂が宿るとされ、ご先祖様や故人を供養する対象として、むやみに移動したり処分するものではありません。
墓じまいでは閉眼供養を行い、お供え物をして儀礼を行うことで、魂をお墓から抜いて墓石を撤去します。
| <墓じまいの閉眼供養とは> | |
| [別名] | ・魂抜き ・抜魂式 ・お性根き …など |
| [行うこと] | ・お供え ・読経供養 ・お焼香 |
| [行うタイミング] | ・墓じまい ・お墓の引っ越し ・お墓の建て直し |
墓じまいの閉眼供養で施主は、お供え物の準備、僧侶へ読経供養の依頼をします。
僧侶には読経供養のお礼(本来は布施行)として、お布施の準備も必要です。
浄土真宗の墓じまい
◇浄土真宗には「閉眼供養」の概念がありません
霊魂はご臨終後、すぐに極楽浄土へ成仏するため、お墓に魂が宿る概念がない浄土真宗では、魂を抜く「閉眼供養」も行われませんが、「遷仏法要」があります。
●「遷仏法要(せんぶつほうよう)」とは、お墓に鎮座される御本尊様に、一時的に移動してもあらう儀礼です。
基本的に遷仏法要も、墓じまいの閉眼供養と同じく、お供え物を用意する儀礼です。
「遷座法要(せんざほうよう)」とも呼ばれますが、意味は変わりません。
・浄土真宗の墓じまいで閉眼供養は必要ないの?遷仏法要の手順と流れを解説|永代供養ナビ
墓じまいの閉眼供養:お供え物は?

◇墓じまいの閉眼供養では、基本のお供え物「五供」を供えます
「墓じまいの閉眼供養に、お供え物を供えるほど大掛かりに行う必要はある?」との質問も多いです。
家族やお墓の関係者のみで行うことの多い墓じまいの閉眼供養では、豪勢なお供え物は必要ありませんが、基本のお供え物「五供(ごく)」を揃えると良いでしょう。
●五供…仏様を敬う気持ちを表す5つのお供え物
・水
・供花(くげ)
・飲食(おんじき)
・灯明(とうみょう)
・香(こう)
墓じまいの閉眼供養で、基本のお供え物「五供」は、お墓参りや日々のお仏壇へのお世話などでも供える基本で、それぞれに意味と役割があります。
墓石を清める「水」
◇「水」は墓石や場を清めます
「水」は喉が渇いているであろう故人へ供え、墓じまいの閉眼供養では、お清めのお供え物です。
| <墓じまいの閉眼供養:お供え物「水」> | |
| [役割] | ・ご先祖様へ供える ・墓石を清める |
| [注意点] | ・水道の水とは別に用意 |
ほとんどの霊園で柄杓や水桶とともに水場が設けられていますが、墓前に供するお水は別に準備すると良いでしょう。
水筒やペットボトルなどにお水を入れて持参すると便利です。
心の拠り所となる「供花」
◇「供花」は故人へ供える他、生きる人に儚さを教えます
墓じまいの閉眼供養ではお供え物に「供花」が大切です。
供花は故人へ供えるばかりではなく、生きている者にとっても心の安らぎとなり、儚い生を表すお供え物となります。
| <墓じまいの閉眼供養:お供え物「供花」> | |
| [役割] | ●故人へ ・故人の拠り所 ・心を清める ●生きる者へ ・儚さを表す ・心を癒す ・忍辱の修行 |
| [注意点] | ・タブーの花がある ・仏花の決まり事 |
「忍辱(にんにく)」とは、じっと耐え忍ぶことです。
花の置かれた場でじっと耐え忍び、通りゆく人々へ美しい花姿を見せて、心を癒す姿から、仏道で供花は忍辱の修行の象徴とされてきました。
墓じまいの閉眼供養では、お供え物に決まり事はありますが、基本的に生花店で「仏花」を選ぶことで、マナー違反はないでしょう。
日々の感謝「飲食」
◇「飲食」は、毎日の食事があること、日々への感謝を表します
墓じまいの閉眼供養では、りんごやバナナ、みかんなどの果物が多いでしょう。
料理を供える場合、仏式で行われるため、精進料理が中心です。
| <墓じまいの閉眼供養:お供え物「飲食」> | |
| [役割] | ・日々への感謝 |
| [注意点] | ・仏教によるタブー ●生臭もの ・肉・魚 ●五辛 ・にら・にんにく ・ネギ・らっきょう ・生姜 |
殺生を連想する肉や魚は、生物なので痛みやすいことからも、墓じまいの閉眼供養ではお供え物に適さない側面もあるでしょう。
墓じまいの閉眼供養では、お供え物に故人が生前に好きだったもの、季節を感じる果物なども見受けます。
道を照らす「灯明」
◇灯明であるロウソクも、お供え物のひとつです
墓じまいの閉眼供養では、お供え物にロウソクも数えます。
お線香に火を付けるための仏具と捉える人もいますが、ロウソクは仏道においても「道を照らす灯り」として、瞑想や修行にも役立つでしょう。
| <墓じまいの閉眼供養:お供え物「灯明」> | |
| [役割] | ・この世とあの世を繋ぐ道を照らす ・故人の歩く道を照らす ・慈悲の心 |
| [注意点] | ・火を消す時は口で吹き消さない ・風に強いロウソクが便利 |
生きている者にとっては、ロウソクに火を灯すことは「気付き」です。
そのため、冥土への道を照らすとともに、生きる者にも「人生の行く先を照らす」役割があります。
故人へ供える「香」
◇「香」はお線香や焼香です、故人は香りを食べます
墓じまいの閉眼供養でのお供え物「香(こう)」はお線香や焼香を差し、場を浄化するとともに、故人が喜ぶお供え物です。
| <墓じまいの閉眼供養:お供え物「香」> | |
| [役割] | ・故人の食べ物 ・その場を清める ・心を清める |
| [注意点] | ・一般的に1~3本供える (宗派により供え方が異なる) |
故人は生きている者の食べ物をいただくことはできません。
その代わり、仏教では「故人が香りを食べて生きる」とされます。
お線香や焼香の供え方は宗派によっても異なるため、墓じまいで閉眼供養を行う僧侶へ、お供え物の供え方、本数や置き方を確認しても良いでしょう。
・お墓参りやお仏壇で、お線香をあげる基本的なマナーとは☆宗派によって違う本数まで解説
・【葬儀マナー】数珠の持ち方扱い方に作法はある?焼香でのマナー、持ち歩く時タブーまで
墓じまいの閉眼供養、お供え物の置き方
墓じまいの閉眼供養、お供え物の扱い
◇墓じまいの閉眼供養でのお供え物は、家に持ち帰りいただきます
お菓子や果物など、墓じまいの閉眼供養でのお供え物は捨てるのも忍びないですよね。けれども「食べるなんて、ご先祖様や仏様に悪いのでは?」との質問も多いです。
| <墓じまいの閉眼供養:お供え物の扱いは?> | |
| [共食(きょうしょく)] | ・お供え物を下げる (家に持ち帰る) ・生きる家族がいただく |
墓じまいの閉眼供養では、お供え物を墓前に揃えている時点で、ご先祖様が召し上がっているとされています。
ですから供えた供物を閉眼供養後にいただくことは、何も問題ありません。
むしろ「共食」と言い、ご先祖様や故人と共にいただく歓談の時間を設ける地域もあるほどです。
ですから閉眼供養が終わったら家に持ち帰り、いただきましょう。
・【2023年春のお彼岸】お墓参りにマナーはある?お参りの手順や持ち物、タブーを解説
墓じまいの閉眼供養:お布施相場は?
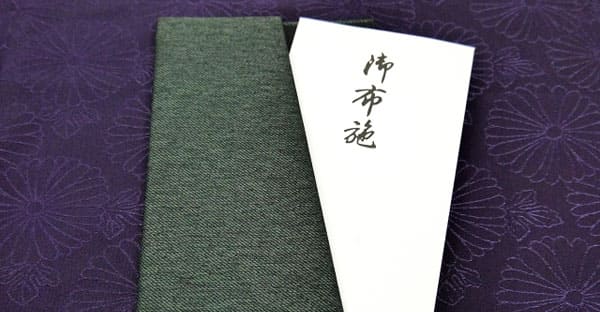
◇墓じまいの閉眼供養でお渡しするお布施相場は、約3万円~10万円です
墓じまいの閉眼供養で、お布施相場は約3万円~10万円ですが、お布施に墓じまいによる「離檀料」が含まれた場合、約5万円~20万円ほどになるでしょう。
「離檀料」とは寺院墓地に建つお墓で、寺院の信家「檀家」を辞めることです。
| <墓じまいの閉眼供養:お布施> | |
| [お布施相場] | ●お布施 ・約3万円~5万円/1回 ●御車代 ・約3千円~1万円 (タクシー代) ●膳代 ・約5千円~1万円 (会食を欠席された場合) |
| [離檀料相場] | ・約3万円~20万円 |
墓じまいで取り出した遺骨を、新しい納骨先で納骨する際、納骨式や開眼供養(お墓)などを行う場合に、一度に包んでお渡しするならば約3万円~5万円の1.5倍~2倍を目安とします。
石屋さんへ心付けは必要?
◇墓じまいの閉眼供養では、石屋さんへ心付けをお渡しすることがあります
「心付け」とは「寸志」とも言い、墓じまいなど供養を行うにあたり、お世話になった人々へ感謝を表し、包むお金です。
心付けに決まり事はありませんが、お礼の気持ちとして用意しておき、当日にお渡しします。
| <墓じまいの閉眼供養:石屋さんへ心付け> | |
| [渡し方] | ・ポチ袋に入れる ●表書き ・寸志 ・心 ・心付け |
| [金額相場] | ・約千円~3千円 |
一般的には約千円ほど、ほんの気持ちとして包むことが多いでしょう。
石屋さんも業者によって、心付けを受け取らないことがあります。
そのような場合は無理強いをしないようにしましょう。
墓じまいや弔事では、予め多くの寸志を用意して、気付いたら渡す施主もいます。
まとめ:墓じまいの閉眼供養でのお供え物は「五供」です

家族や故人と近しい親族のみ、約5人~10人以下で行うことも多い墓じまいの閉眼供養では、規模も小さく「お供え物を供える必要がない」と感じる人も少なくありません。
けれども僧侶への敬意として、またそれぞれの役割を理解して、墓じまいの閉眼供養では基本のお供え物「五供」は準備をした方が良いでしょう。
反対に墓じまいの閉眼供養に案内された場合、お供え物を持参すべきでしょうか。
墓じまいの閉眼供養で御香典は一般的に必要ありません。
一方、建墓やお墓の引っ越しでで行う「開眼供養」はお祝いの席です。
御祝儀を準備すると良いでしょう。
お電話でも受け付けております

















