
2026年の彼岸でお布施は必要? 金額相場・宗派ごとの違い・渡し方を解説
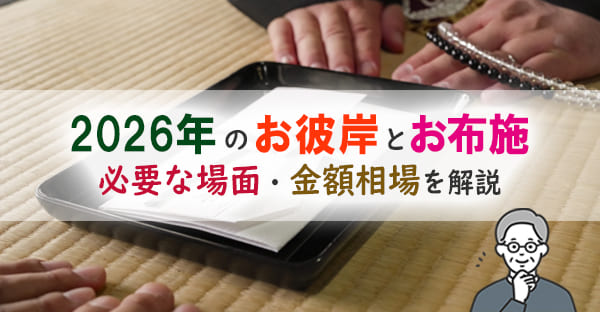
◇2026年の春のお彼岸は、3月17日(火)から3月23日(月)までです。
この時期になると、「お彼岸でお布施は必要なの?」「いくら包めばいい?」と、迷う方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、2026年のお彼岸でお布施が必要かどうかは、法要の有無や寺院との関係性によって異なります。必ず包む場面もあれば、任意でよいケースもあります。
本記事では、2026年のお彼岸でお布施が必要になる場面を整理しながら、金額相場や宗派ごとの違い、失礼にならない渡し方のポイントまで、分かりやすく解説します。

【2026年度版】春のお彼岸でお布施は必要?
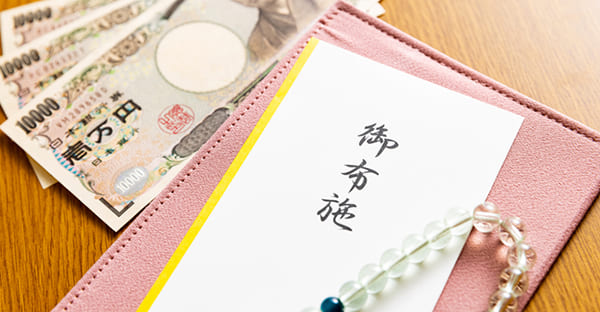
◇寺院墓地のお墓参りでは、お布施が必要な時があります
お彼岸でお布施が必要になるのは、主に寺院墓地へのお墓参りや彼岸会です。
また法要を執り行うお彼岸の場合、読経供養へのお布施をお渡しするでしょう。
特に昔ながらの寺院墓地で、先祖代々墓へお墓参りをする場合、家が代々寺院と関わりのある「檀家(だんか)」であることが多いため、お彼岸のお墓参りにお布施を持参することがあります。
①法要
・初彼岸
②彼岸会
③合同供養
④ご住職へご挨拶
⑤ご住職へご相談
ご住職へのご挨拶・ご相談は、檀家の判断でお彼岸にお布施を包むのですが、初彼岸など、僧侶を呼んで法要を行うお彼岸では、お布施は必要です。
春彼岸のお布施①法要
◇初彼岸ではお布施を読経供養のお礼として包みます
初めてお彼岸を迎える「初彼岸」など、僧侶をお呼びして読経供養を依頼する法要を執り行うならば、お布施は必ず必要です。
また法要ではお彼岸のお布施の他、お車代やご膳代にも配慮しましょう。
お車代は法要会場までの交通費、ご膳代は会食を僧侶がお断りになった時、代わりにお渡しするものです。
| <春彼岸のお布施①法要> | |
| ●お布施相場 | ・約3万円~5万円 |
| ●お車代 | ・約5千円~1万円 (タクシー代が目安) |
| ●ご膳代 | ・約3千円~1万円 (会食代が目安) |
ただし本来のお布施は仏道への修行、徳行のひとつと捉え、法要当日にはお布施をいただかない僧侶もいらっしゃいます。
この場合には、後日寺院へ伺い、改めてご挨拶をしながらお布施をお渡ししてください。
春彼岸のお布施②彼岸会
◇寺院が主催する彼岸会に参加する場合、お布施をお渡しします
「彼岸会(ひがんえ)」とは、春と秋のお彼岸に行われる仏教の法会です。
寺院が行う彼岸会やお施餓鬼(おせがき)に参加する人もいるでしょう。
彼岸会のお布施で包む相場は寺院では明示していないのですが、ご自身の判断で包みます。
●彼岸会のお布施相場
・約3千円~2万円
彼岸会は大勢の人々が参加する寺院もあるので、必ずしも必要ではありませんが、お布施箱が用意されていることが多いので、準備をしておくと良いでしょう。
不安があれば、親戚や地域の人々に相談すると安心です。
春彼岸のお布施③合同供養
◇合同供養に参加するお彼岸でも、お布施を用意します
「合同供養(ごうどうくよう)」とは、合祀墓などに埋葬された人々を供養することです。
墓じまいを済ませたなど、合祀墓や自然葬で故人の遺骨を埋葬した場合、お彼岸の合同供養を行う霊園や施設も多くあります。
●合同供養のお布施相場
・約3千円~1万円
このような合同供養に参列する時、お布施の明言はない施設が多いものの、お礼として約3千円~1万円をお渡しすると丁寧です。
一般的には約5千円ほどの相場で、お布施を包む人が多いでしょう。
春彼岸のお布施④ご挨拶
◇菩提寺の御本堂にご挨拶する際、お布施をお渡しする人もいます
菩提寺との関係性が深い家では、お彼岸のお墓参りにお布施を持参して、お参り前に御本堂に立ち寄り、ご住職へご挨拶する家もあるでしょう。
●ご挨拶でのお布施相場
・任意で約3千円~5千円
ただし菩提寺との関係性は家によって千差万別です。
昔は地域密着型の寺院がほとんどで、お彼岸のお墓参りでは、まず御本堂へ立ち寄りご本尊へご挨拶をして、ご住職へのご挨拶も行う家が多くありました。
| <2026年春彼岸:ご挨拶の目安> | |
| ・関係性が深い | …お墓参りの前に御本堂へ |
| ・関係性が浅い | …直接お墓参りをしてOK |
現代では民間霊園に倣い、檀家制度を撤廃する寺院も増え、昔ほど檀家と菩提寺の関係性が深くない寺院墓地が多いでしょう。
この場合は、お墓参りの前後でご住職へご挨拶を行う家も、ほとんどありません。
春彼岸のお布施⑤ご相談
◇お彼岸のタイミングでご住職へご相談をする場合にお布施を包みます
お彼岸のタイミングで、菩提寺のご住職へお墓の継承問題や墓じまいに関するご相談や、次回の法要での読経供養依頼をするなど、ご相談をすることも多いです。
ご住職へご相談する時には、お線香代金や供物代金を金額目安として、お布施を包むと良いでしょう。
●ご相談のお布施相場
・任意で約3千円~5千円
仏教行事全般に対する質問や、暮らし事に関する相談などでも、ちょっとした心づけとしてお布施を用意すると好印象です。
春のお彼岸にご相談をする時には、お布施の他にもお線香などの供物を持参しても良いでしょう。
【2026年度版】春彼岸のお布施マナー:服装は?

◇寺院墓地のご本堂に行くならば、服装も畏まると良いでしょう
春のお彼岸にお布施を持参して、ご本堂へご挨拶やご相談に伺うならば、服装は「平服(ひらふく)」が適切です。
| <平服とは> ●地味な色のお出かけ着 |
|
| [色] | ●落ち着いた色 ・黒 ・グレー ・深い緑 …など |
| [服装] | ・ビジネススーツ ・無地のアンサンブル …など |
本来お墓掃除なども行ったり、身内のみでお参りすることが多いため、ご本堂へ立ち寄らないお墓参りでは、動きやすいカジュアルな服装、歩きやすい運動靴が多いでしょう。
けれどもお彼岸のお墓参り前後にご本堂へ立ち寄るならば、ご住職へのマナーとして、平服を基準に畏まった服装を心がけます。
春彼岸のお布施:宗派で金額相場は変わる?

◇お彼岸法要でのお布施には、宗派による相場があります
同じ宗派でも家や地域によって、お彼岸で包むお布施の相場に違いがあるほどなので、最終的には自分の判断で良いのですが、宗派により相場の違いはあるでしょう。
| <春彼岸のお布施相場:宗派による違い> | |
| [浄土真宗] | |
| ・墓前 | …約3千円~5千円 |
| ・自宅 | …約3万円~5万円 |
| ・彼岸会や合同供養 |
…約3千円~1万円 |
| [真言宗] | |
| ・法要全般 | …約1万円~3万円 |
| ・彼岸会や合同法要 | …約5千円~1万円 |
| [曹洞宗] | |
| ・法要全般 | …約3千円~1万円 |
全国的にお彼岸にお布施を包む金額相場ですが、傾向として曹洞宗はお布施の金額相場が少なくなります。
【2026年度版】春彼岸でお布施を包むマナー

◇お布施はご香典ではありません
お布施は布施行のひとつで、通夜や葬儀で包むご香典とは違うため、基本的には白と黒の不祝儀袋で包むものではなく、白封筒や黄色と白の封筒で包みます。
これはお彼岸のお布施に限らず、お通夜や葬儀の席でも同じです。
地域によって黄色×白や双銀の水引きを付けることもありますが、迷ったならば厚手の白封筒で良いでしょう。
| <春彼岸のお布施:包み方マナー> | |
| ①包み方 | ・厚手の白封筒 |
| ②お札の入れ方 | ・開けた時、お札のお顔が見える |
| ③表書き | ・黒墨で書く ・「お布施」「御布施」 |
| ④封筒の裏側 | ・左下に住所と氏名 ・郵便番号まで書く |
基本的には御香典とは反対、祝儀を包む作法で包みます。
封筒は市販のもので構いませんが、二重封筒は避けてください。
また、お札の柄が外映りしないよう、厚手の一枚封筒を選びます。
春彼岸でお布施を渡すタイミング
◇春のお彼岸でお布施は、ご挨拶のタイミングでお渡しします
合同供養や彼岸会では受付時にお渡ししたり、会場に設置されている「お布施箱」などに収める法会が多いです。
| <2026年春彼岸:お布施を渡すタイミング> | |
| ●ご挨拶、ご相談 | ・最初のタイミング |
| ●彼岸会や合同供養 | ・受付 ・お布施箱に入れる |
特に決まり事はありませんが、お布施をお渡しする時には、
「本日は故人のためにお供養いただき、ありがとうございます。」
など、シーンに合わせて一言添えると良いでしょう。
春彼岸での、お布施の渡し方
◇袱紗を切手盆代わりに扱います
「袱紗(ふくさ)」とは、御香典やお布施を持ち歩く際に包む小さな風呂敷や、入れ物です。
葬儀や通夜、年忌法要などでは切手盆を用いてお布施をお渡ししますが、お彼岸でお布施を渡す時には、わざわざ切手盆を持ち歩くこともありません。
袱紗の上にお彼岸のお布施を乗せて、切手盆代わりにお渡しします。
・袱紗を切手盆代わりにする
・表書きがご住職に読める方向で差し出す
・両手でお布施の袋を持つ
・机をまたかず、遮るもののない場所で渡す
・お辞儀をする
基本的にお彼岸のお布施や御香典は、裸で持ち歩くことは避け、専用の袱紗に包んで持参してください。
袱紗は祝儀用ではなく、黒や深緑、紫などの地味な色目のタイプを選びます。
春彼岸でお布施は、奉書紙に包む?
◇春のお彼岸に限らず、お布施は白封筒で問題ありません
昔は春のお彼岸に限らず、お布施を奉書紙に包む習わしがありましたが、現代では厚手の白封筒に入れて準備をする人がほとんどです。
もしも春のお彼岸でお布施を奉書紙に包むならば、お札のお顔が見えないように一度半紙に包み、その上から奉書紙に包むと良いでしょう。
この時、最後に奉書紙を折り畳むのは上の紙、上から下へとお辞儀をしている方向になるよう、注意をしてくだい。
・【図解】お布施マナーとは?封筒や書き方、金額は?お札の入れ方・渡し方もイラスト解説
【2026年度版】春彼岸:そもそも「お布施」とは?

◇「お布施」とは、現代では僧侶へのお礼です
もともとは「布施行」と言い、お金などを施す仏道の修行道なのですが、現代においては、主に読経供養や戒名を付けていただいた時などに、「料金を支払う」のではなく、「お布施を包み」お礼を示すものです。
●現代では僧侶へのお礼
①読経供養
②戒名
③墓地やお墓の管理や供養
(寺院を経済的に支える)
現代では主にお通夜や葬儀、法要などで行う読経供養に対してのお礼、戒名の名づけに対するお礼でしょう。
この他、寺院墓地にお墓が建つ家では、管理運営をする寺院の「檀家」になりますので、墓地やお墓の管理や供養に対してのお礼として、毎年お布施を支払います。
①読経供養
◇読経供養のお礼として、お布施をお渡しします
お布施の金額目安は、約3万円~7万円/1回の読経供養が一般的です。
寺院墓地ではない家で、インターネットの僧侶派遣などを利用すると、読経供養の料金は約3万円/1回ほどが目安になるでしょう。
・約3万円~5万円ほど/1回
菩提寺を持たない民間霊園などで、お彼岸の法要を行う際のお布施は、約3万円~5万円が一般的ですが、菩提寺のご住職であれば、家や地域で相場が分かれるでしょう。
②戒名
◇戒名のお礼として、お布施を納めます
戒名には「ランク」があり、ランクによって価格幅が広いです。
本来は僧侶でなくても戒名を付けることができるため、近年ではインターネットで約3万円~5万円/1柱ほどのお布施で、戒名を付けてくれるようになりました。
・約3万円~100万円以上
ただ菩提寺があり、遺骨を菩提寺のお墓に納骨する場合は、菩提寺のご住職に戒名を付けてもらうのがマナーで、この場合は約20万円~100万円以上になることもあります。
③墓地やお墓の管理や供養
◇寺院墓地では、毎年お布施をお渡しします
民間霊園の年間管理料に代わる費用が、寺院墓地で毎年納めるお布施です。
寺院墓地にお墓を建てる家は、代々その寺院を経済的に支える檀家として、毎年お布施を納めたり、寺院の改修時には檀家で資金を出し合ったりします。
・約1万円~5万円ほど/年間
そのため毎年のお布施を納めなかった場合、民間霊園と同じくお墓は無縁墓と判断され、撤去される可能性もあるでしょう。
【2026年度版】春彼岸のお布施:本来の意味

◇お布施は本来、仏教道の修行のひとつ「布施行」です
お布施は本来、仏道の修行「六波羅蜜(ろくはらみつ)」のひとつであり、他人へ自身の財を無償で施す意味があります。
現実的には、お彼岸の読経供養でお布施をお渡しする場合、これが飲食店などの店舗であれば、「料金」「支払う」ことになりますが、得行としてお渡しするので、これらの言葉は使いません。
| <春彼岸のお布施:本来の意味> | |
| ●財施(ざいせ) (無償で施す) |
・僧侶への支払い(報酬)ではない ・お布施は「包む」「納める」もの |
| ●言葉の扱い方 | ・[NG]読経料(戒名料) ・[OK]お布施 ・[NG]支払う ・[OK]包む、お渡しする |
例えば僧侶にお彼岸で行う読経供養での、お布施の金額相場を聞くとします。
一般的な店舗とは、言葉の扱い方が下記のように変わるので注意をしてください。
できれば親族や葬儀社など、周囲の人々へ聞ければ良いのですが、難しければ言葉の扱い方に配慮しながら、僧侶へ直接確認しても良いでしょう。
そもそも春のお彼岸とは?
◇あの世とこの世が最も近くなる、繋がる日です
「お彼岸(おひがん)」とは、春分の日・秋分の日を中日として、前後3日間を加えた7日間、あの世の「彼岸(ひがん)」と、この世の「此岸(しがん)」が繋がる日です。
立秋や立冬などの二十四節気の他に、日本の季節を感じるための節目「雑節(ざっせつ)」でもあります。
お彼岸は「至彼岸(とうひがん)」と言われるように、あの世である「彼岸(ひがん)」と繋がる日とされ、お墓参りの風習があります。
| <2026年春彼岸:お彼岸とは?> ●2026年3月17日(火)~23日(月) |
|
| [行うこと] | ・お墓参り ・仏壇供養 |
| [行事食] | ・ぼた餅(おはぎ) ・彼岸団子 ・彼岸蕎麦(彼岸うどん) ・小豆粥 ・季節を感じる精進料理 |
お彼岸にお布施の有無を相談する人が多い理由は、日本ではお彼岸にお墓参りに行くため、供養行事のひとつと捉えるためでしょう。
まとめ:春のお彼岸でもお布施が必要な場面があります

春のお彼岸でお布施が必要になる場面は、寺院墓地でご本堂へ立ち寄る時や、供養祭、彼岸会などに参加する時です。
合同供養や彼岸会などに参加する時、基本的にお布施は任意とされますが、読経供養の間にお布施箱が回ってきたり、会場にお布施箱が設置されています。
そのため約3千円ほどでも、気持ちとしてお布施を用意しておくと、より心置きなく参加できるでしょう。
合同供養や彼岸会でも、白封筒にお布施を包むことが丁寧です。
まとめ
お彼岸でお布施を包む場面とは?
●お彼岸でお布施が必要な場面は?
①僧侶を呼んで法要
・初彼岸
②彼岸会
③合同供養
④ご住職へご挨拶
⑤ご住職へご相談
●お彼岸のお布施、包み方
・封筒は厚手の白封筒
・お札の入れ方…開けた時、お札のお顔が見える
・黒墨で書く
・「お布施」や「御布施」
・左下に住所と氏名
・郵便番号まで書く
●お彼岸でのお布施の渡し方
・袱紗を切手盆代わりにする
・表書きがご住職に読める方向で差し出す
・両手でお布施の袋を持つ
・机をまたかず、遮るもののない場所で渡す
●そもそも「お布施」とは?
・現代では僧侶へのお礼
①読経供養
②戒名
③墓地やお墓の管理や供養
(寺院を経済的に支える檀家として)
●本来の「お布施」の意味は?
・無償で施す「財施(ざいせ)」
・僧侶への支払い(報酬)ではない
・お布施は「包む」「納める」もの
お電話でも受け付けております
















