
葬祭とはどんな意味?葬儀と葬祭では違う?「冠婚葬祭」の意味や行事一覧・マナーの違い
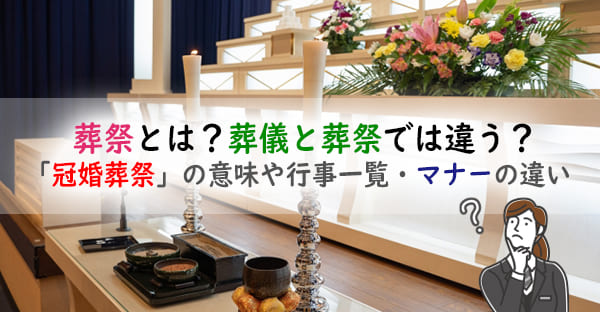
「いろいろな呼び方があるけど『葬祭』の意味は?」
「葬祭・葬儀・葬式・弔事・告別式・葬送・祭祀等、それぞれ何が違うの?」
「冠婚葬祭には、どんな行事が含まれる?マナーや服装は?」
「頼りになる葬祭ディレクターとは何者?」
家族が亡くなると通夜・葬儀後の法要が続きますが、喪主(施主)として葬祭業者と打ち合わせを進めるにあたり、葬祭・葬送・葬儀・弔事等の言葉選びに戸惑う方も多いですよね。
正確な意味の違いが分からないばかりに、打ち合わせですれ違うケースも見受けます。
本記事を読むことで葬祭・葬儀・葬送・告別式・弔事等々、扱う言葉の意味やそれぞれの違いが分かります。また冠婚葬祭それぞれの意味や行事・マナーも分かり、適切な対応でできるでしょう。
後半では突然、家族が亡くなった時や終活で頼りになる葬祭ディレクターについても解説していますので、どうぞ最後までお読みください。
「葬祭」の意味

葬祭には2つの意味があります。ひとつが故人が逝去された時に執り行う「葬送」、もうひとつがご先祖様を祀る「祭祀」です。人生の通過儀礼における儀式を表す「冠婚葬祭」の葬祭からきています。
葬祭にはご先祖様を祀り供養して、子々孫々と今在ることに感謝する意味合いです。
そのため故人が逝去された直後の葬送だけではなく、その後一周忌・三回忌と長く続くご先祖様への供養行事も含まれます。
このようなことから葬儀社のなかでも四十九日法要・一周忌等の法要(法事)を得意とする業者は、「葬祭業」と名乗ることもあるでしょう。
葬祭・葬儀・葬式等の言葉の違いにはさまざまな解釈がありますが、下記より一般的な分け方をご紹介します。
①葬儀との違い
「葬儀」は、通夜翌日に執り行われる故人とお別れし見送る儀式で、葬儀には故人の冥福を祈り死者を葬る儀式「葬送儀礼」を略した言葉です。
葬儀を執り行う目的は、故人が逝去後に安らかな気持ちで眠れるように祈ること、遺された遺族が家族の死を受け入れ整理するための儀式でもあります。
仏教において葬儀は故人の冥福を祈る儀式ですが、宗旨宗派により目的が異なります。
大まかには神道では神様へ感謝する儀式、キリスト教では遺された者の悲しみに寄り添う儀式です。
・【図解】キリスト教の葬儀マナーとは?献花の仕方やカトリック・プロテスタントの違い?
②葬式との違い
葬式は死者を葬る儀式「葬儀」と故人との別れの儀「告別式」を併せた総称、通夜の翌日に執り行う一連の儀式を指します。
一般的な葬式の流れは参列者の入場・着席後、僧侶の入場・読経供養・お焼香・弔電の読み上げ・僧侶の退場(説法)・閉会の挨拶・お別れの時間・喪主挨拶と続きます。
宗旨宗派にこだわらない自由葬であれば、僧侶による読経供養が省かれるでしょう。
葬式の後は遺族は故人とともに火葬場へ出発するため、参列者は斎場の出入り口等で待機し、火葬場へ向かう遺族と故人を見送る流れが一般的です。
③祭祀との違い
葬祭において「祭祀(さいし)」は神様・ご先祖様を祀り供養することを指します。仏壇に位牌を祀ることも祭祀にあたりますが、儀式を執り行うことも祭祀のひとつです。
仏教では僧侶へ「お布施」を包みお渡ししますが、神道では神葬祭(霊祭)にあたり神官へ「祭祀料」を包みます。神葬祭とは仏教における葬儀であり、その後の法要は霊祭・式年祭です。
相続発生後にお墓や仏壇等を「祭祀財産」と呼びますが、これはご先祖様を祀るための財産と言う意味合いです。祭祀財産は相続ではなく継承を行うため、相続税・固定資産税がかかりません。
通夜・葬儀・告別式の違い

故人の冥福を祈り死を葬る「葬儀」は、故人の看取りから始まると言う考え方もあります。
一方で通夜翌日に執り行う一連の儀式を「葬儀」とする人もいるので、こちらも解釈はさまざまです。
いずれにしても看取りで後悔することのないよう、家族が危篤状態になったら近しい家族・親族、故人と生前に特に親しくしていた知人・友人に連絡をしましょう。
担当医により死亡判定を受けた後、故人の唇に水を含ませる儀式「末期の水」を行い、病院で逝去された場合は、一度病院の霊安室へと移動します。
①通夜
通夜は葬儀の前日、お別れ前に家族・故人と生前に親しくしていた人々が集まって、故人と最期の一夜を過ごす前夜祭のようなものです。
自宅で遺体を安置していた昔は、お線香を夜通し絶やさずに故人の傍にいたことから「通夜」と呼ばれました。けれども現在では葬儀と同じように参列者が集まり、読経供養・焼香後に帰宅する流れが一般的です。
葬儀が正式に故人との別れを受け止める儀式であるのに対し、通夜は近しい人々が故人の傍で別れを惜しむ儀式と言えるでしょう。
②葬儀
葬儀は宗教的な儀式です。一般的に通夜の翌日、告別式の前に執り行います。
参列者・喪主・遺族が着席した後、僧侶が入場した後に読経供養が始まると、関係者よりお別れの言葉「弔事拝受の儀」、司会者による弔電の読み上げへと続くでしょう。
その後、僧侶の指示に倣い、遺族は喪主から順番にお焼香を行います。遺族のお焼香までが故人を葬る儀「葬儀」です。
③告別式
葬祭と弔事

葬祭も弔事も故人を供養するために執り行うものですが、弔事は故人を弔うための全ての事柄を指します。「弔う」とは故人の死を悼み悲しみ、悔やむことです。
或いは喪に服す人々の喪失を慰めることを指し、参列者が遺族へ「お悔やみ申し上げます」と声をかけることも弔いと言えます。
そのため弔い方は人によって異なります。遺族にとって弔いとは、悲しみのなかでも準備をして立派に葬儀や法要を執り行うことになるでしょう。
①法要との違い
法要は仏教の教えに倣い、故人の冥福を祈って行う僧侶の読経による供養です。
一般的に四十九日法要等を「弔事」「法事」と呼ぶ際には、法要後に施主が参列者へ振る舞う会食「お斎(おとき)」も含めているでしょう。
②葬送との違い
「葬式」の正式名称が「葬送儀礼」です。
葬送とは死者を葬り送り出す意味があり、危篤から看取り・末期の水・通夜・葬儀・火葬・遺骨の埋葬まで、一連の儀式を指します。
「弔事」は、通夜・葬儀・四十九日法要等のお悔やみ事を意味する言葉です。
故人との最期のお別れとして通夜・葬儀が営まれ、四十九日法要等の供養も弔事に含まれます。
どちらも結果的に人の死を慎み供養する儀式を指しますが、葬送は故人を見送ることであり、弔事はお悔やみ事全般です。
「冠婚葬祭」の意味は?

「冠婚葬祭」は人生の節目に訪れる通過儀礼を指します。人が亡くなってから行う一連のお悔やみ事、通夜・葬儀・四十九日法要等は「葬」です。
冠婚葬祭のなかには家族で祝う入学式・卒業式等の行事もありますが、一般的に「冠婚葬祭業」と呼ばれる業者は結納・結婚式等の慶事関連の企業、葬儀・法要等の葬祭業です。
日本では成人式・結納や結婚式・葬儀まで、なにかと費用がかかります。そのため「冠婚葬祭互助会」等の制度を利用して、人生の通過儀礼で発生する費用対策をする方も多いです。
①「冠」の意味と行事一覧
「冠(かん)」は人生の節目におけるお祝い事です。もともとは男性が成人した時の儀式「元服」において冠を被せる風習から、人生で節目となるお祝い事を「冠」としました。
子どもの成長を祝うお祝い事では七五三・成人式等、大人になって以降は還暦等の長寿祝いが冠にあたります。
近年では出産も冠として盛大に祝いますよね、一般的には家族で祝う行事となるでしょう。
卒業式・成人式等のお祝いに参加する時には、脇役として華やか過ぎない服装を心がけながらも、多少明るい色合いの服装でも良いでしょう。
冠のお祝い事で大切なポイントは、シミ・汚れがなく露出の少ない「丁寧な」服装、皇室の人々が着用する服装のイメージです。
②「婚」の意味と行事一覧
「婚」は漢字の通り結婚、それにまつわる婚約等の行事です。従来の日本で結婚は、個人同士の祝い事ではなく、家と家が結びつく祝い事です。
そのため結納・結婚式と儀式に倣い丁重に執り行う必要があり、冠婚葬祭業者に依頼して結納品等を準備しました。現代でも家や地域によって、お目出たい9品を揃えた結納の儀が執り行われます。
現代では核家族化が進み、結婚も個人同士のものと捉える方が増えています。結納のような堅苦しいものではなく、「両家顔合わせ」の会食の場を設ける家も多いでしょう。
結婚式に参列する時には光沢のある黒ドレス等、多少華やかでも問題はありませんが、白いドレス・素足やサンダルは控えましょう。また銀婚式等、結婚後のお祝いも「婚」と捉えます。
③「葬」の意味と行事一覧
「葬」は弔事全般です。通夜・葬儀・告別式等はもちろん、四十九日法要・一周忌・三回忌等の法要も葬に含まれます。
冠婚葬祭のなかでも「葬」は予測できない点が特徴的です。人の死は突然訪れますので、日ごろから参列する服や持ち物を準備しておくと良いでしょう。日本では成人したら喪服一式を準備する風習もありました。
葬儀へ参列する時には、光沢や飾りのない無地の黒で身を包む「略式喪服」が基本です。喪主・遺族であれば正式喪服として着物を着ることもあるでしょう。
法要の回忌が進むにつれ畏まった地味な服装「平服」での参列となります。地域によって異なりますが、三回忌・七回忌を目安とすることが多いです。
「葬」における服装について、詳しくは下記コラムをご参照ください。
・【図解】墓じまいの服装マナーは平服・喪服どっちが良い?持ち物やお布施を包む目安は?
④「祭」の意味と行事一覧
冠婚葬祭において「祭」はご先祖様をお祀りすることです。また一般的な「祭り」イメージの通り、神仏を祀り祈りを捧げる儀式・行事も「祭」にあたります。
また近年では四季を感じる年中行事も「祭」としますね。正月・節分・七夕等も「祭」に含まれるでしょう。ご先祖様をお祀りする行事ではお盆・お彼岸等がそれにあたります。
ご先祖様や神仏を祀り祈りを捧げる儀式を定期的に行うことで、子々孫々と今に続く今に感謝を捧げ、一族の繁栄を祈願する行事です。
⑤新しい冠婚葬祭の形
葬祭ディレクターとは

葬祭ディレクターは、葬儀プランニングや進行・サポートを担う仕事です。
葬祭ディレクターは家族葬・一般葬・社葬・密葬等、さまざまな葬儀に対応するため、遺族は葬祭ディレクターに相談することで、希望に対応した葬儀を進行してくれます。
もともとは葬送業者の2大組織「全日本葬祭業協同組合連合会」「全日本冠婚葬祭互助協会」が発足した資格となり、厚生労働省でも認定されました。
①葬儀の相談
葬祭ディレクターの主な仕事内容は葬儀の進行です。けれども危篤時の看取りからサポートを担ってくれる葬祭ディレクターも多くいます。
ご遺体の搬送・納棺・通夜の準備・遺影写真・霊柩車、火葬場、告別式会場の手配、会食会場の手配等、通夜や葬儀を進行する一切の段取りだけではなく、死亡届の手続き等を相談できる業者もあるでしょう。
一人身の喪主へ家族のようなサポートを担ってくれる葬祭ディレクターもいます。例えば葬儀社・僧侶との打ち合わせに帯同する、遺族の心のケアやサポート等です。
・【大阪の葬儀】喪主が決める葬儀の席順で、トラブルを避ける5つのルール|永代供養ナビ
②四十九日法要の相談
葬祭ディレクターの仕事内容には四十九日法要の進行まで含まれることも多いです。
四十九日法要にあたり僧侶・法要会場・会食会場等の手配等、葬儀同様に進行してくれます。また四十九日の忌明け後に送る香典返しの品を手配してくれる葬祭ディレクターもいるでしょう。
死後の手続きが多数ある遺族にとって、四十九日まであっと言う間です。四十九日法要の進行を任せることができたら、体力的な負担は大きく軽減します。
また生前に葬祭ディレクターに一切の葬送を相談して、遺族に負担をかけることなく通夜~四十九日法要まで進行を進めていただくことも可能です。
③仏壇・墓地の相談
四十九日法要と同日に納骨式や、仮位牌(白木位牌)から本位牌の交換式を行う遺族も多いですよね。遺骨の納骨先を決めて本位牌を仕立てたり、仏壇のない家では購入しなければなりません。
遺骨の納骨先等、墓地や仏壇相談ができる葬祭ディレクターもいます。
全ての葬祭ディレクターが納骨まで全ての相談に対応できるとは限りませんが、業者と繋いでくれるケース等があるでしょう。
・遺骨の納骨をしないで家に置くのはダメ?他にも納骨しない人はいる?しないとどうなる?
まとめ:葬祭の「祭」はご先祖様を祀ることです

人が亡くなると「葬儀」「葬送」「弔事」等さまざまな言葉を耳にしますが、どれも人の死を受け入れて慎み弔うお別れの儀式に伴う言葉です。
「葬祭」とは通夜・葬儀等で亡き故人の魂を弔い葬る儀式の他、四十九日法要・一周忌等のその後の先祖供養も含めた「祖先を祀る」儀式全般を指します。
一般的に日本では人が亡くなると仏教の教えに基づき葬送しますが、弔い方は人によってさまざまに異なっても良いのです。現代では読経供養を含めない自由葬・無宗教葬により故人を送る葬儀も増えました。
また以前はお墓に埋葬する葬送が一般的でしたが、現代では遺骨を自宅で祀り供養する「手元供養」や、遺骨を海へ散骨する自然葬「海洋散骨」等も増えています。
遺族が納得できる弔い方で、葬送方法を選ぶと良いでしょう。
お電話でも受け付けております
















