
固定資産評価証明書とは?必要となるシーンや申請する時のポイントを解説

「固定資産評価証明書って何だろう?」
「どんな時に必要で、申請する時は何に注意したらいいんだろう?」
固定資産を手にすることになったけれど、税金回りについてはあまり知識がなく、不安を抱えているという人も多いのではないでしょうか。
そういった疑問や不安に対して本記事では、固定資産評価証明書とは何かの説明と、どのような時に必要になるのか紹介しています。また、証明書を取得する人も限られていることや、取得方法、取得時期に関する注意点についても触れています。
この記事を読むことで不動産の相続や登記変更の際に必要になる、証明書の準備について理解できるでしょう。
相続や贈与も急なタイミングでやってくる可能性もあります。そのような時に困らないためにも、この記事をチェックしてみてください。
資産の評価額を証明する「固定資産評価証明書」とは?

土地や家屋等の固定資産の評価額や所有者などを証明するのが、固定資産評価証明書です。固定資産の課税対象は土地や家屋、事業用の償却資産などが対象となっており、対象によって記載される内容も異なります。
不動産の価値の目安が知りたい時や、固定資産税や相続税、贈与税などの税金を計算するタイミングで必要になります。
また、よく混同される固定資産課税明細書との違いについても学んでいきましょう。
固定資産評価証明書に記載される内容
固定資産評価証明書に記載される内容は土地や家屋、事業用の償却資産で異なります。以下にそれぞれの詳細を記載していきます。
土地については、毎年1月1日現在の所有者住所、氏名、地目、地積、評価額などが記載され、家屋に記載されているのは、毎年1月1日現在の所有者住所、氏名、所在地番、家屋番号・建物番号、構造・規模、種類、床面積、評価額などです。
事業用の償却資産は、毎年1月1日現在の所有者住所、氏名、資産所在地(申告がある場合)、種類、評価額などが記載されています。
固定資産課税明細書と違う部分
似たようなものに固定資産課税明細書といったものがあります。固定資産課税明細書は、申請せずとも固定資産税納付書と一緒に郵送で送られてくる点と、記載している内容が固定資産評価証明書とは異なります。
固定資産課税明細書は、固定資産税・都市計画税が課税されている土地や家屋の所在・地番や価格などの内訳を納税者に伝える目的の書類のため、非課税資産についての記載はありません。
固定資産評価証明書が必要になるシーン

不動産を相続や贈与によってゆずり受けた際には、登記上の所有者は変わりません。そのため、相続登記の変更が必要になり、その際に固定資産評価証明書が必要です。いつ必要なのかよくわからない場合は、各自治体の市区町村に問い合わせてみましょう。
以下で、詳しく紹介していきます。
相続税や贈与税を申告する時
不動産の相続税や贈与税を申告する場合、土地や家屋を評価する必要があります。土地の評価方法は2種類です。
1つめの路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法のことで、路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額のことです。
2つめの倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法のことで、土地の固定資産税評価額に1定の倍率をかけて計算します。
なお、家屋については、固定資産税評価額で評価します。
登録免許税を納付する時
不動産登記にかかる登録免許税を納付の際には、不動産の価格を評価するための、固定資産評価証明書が必要です。
しかしながら、地域によっては法務局に固定資産価格の電子通知を行っており、課税証明書で対応できる場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。
固定資産評価証明書を取得する時のポイント
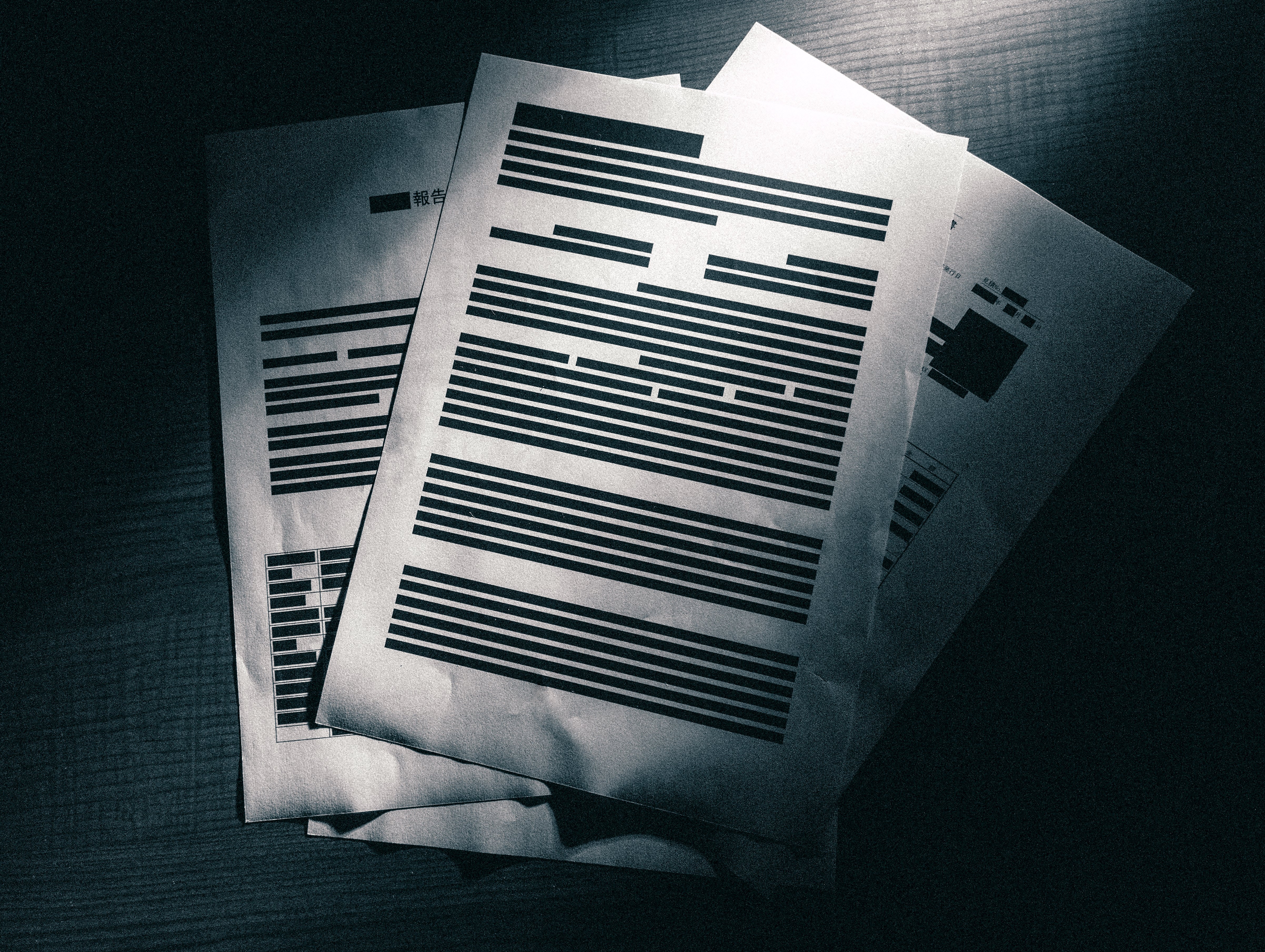
固定資産評価証明書を手に入れる際には申請できる人に限りがあり、取得書類や取得方法についても違いがあるため、注意する必要があります。
取得方法について述べておくと、郵送やホームページから入手したり、役場で取得したりと選択肢が異なります。書類の発行手数料についても、自治体によって違いがあるため、取得前に確認しておくと良いでしょう。
- 限られた人が取得できる
- 役場の窓口・郵送・電子で取得できる
- 必要な書類は取得する人によって変わる
- 発行手数料は自治体によって異なる
限られた人が取得できる
固定資産評価証明書は誰でも取得できるというわけではありません。資産に関する個人情報であるため、原則として固定資産の所有者本人と、その関係者となります。つまりは、所有者と同居する家族や、本人から委任を受けた代理人、相続人、借地人、借家人などに限られます。
役場の窓口・郵送・電子で取得できる
固定資産評価証明書は役場の窓口でもらうか、郵送や、各自治体のホームページから電子文書をダウンロードできます。自治体によっては、コンビニで取得できる場合もありますので確認してみてください。
なお、東京23区内であれば都税事務所でも取得できます。
必要な書類は取得する人によって変わる
取得時に必要な書類は、取得する人によってそれぞれ変わってくるため、注意する必要があります。固定資産所有者であれば運転免許証などの身分証明書や、直近の納税通知書が必要となります。代理人が取得する場合は所有者本人からの委任状が必要です。
また、相続人が取得する場合は、所有者の亡くなった事実と、相続人であることの証明書類が必要です。一般に所有者の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を指します。
発行手数料は自治体によって異なる
証明書の発行手数料は数百円程度ですが、自治体それぞれで価格が異なります。一件ごとに手数料がかかる場合や、数件までは同じ価格で対応できるところもあります。事前によく確認するようにしましょう。
固定資産評価証明書を取得する際に気をつけたいこと

不動産の登記の際に固定資産評価証明書を用いる場合は、申請時に最新年度のものでなければいけません。特に気をつけたいのが、固定資産評価証明書は毎年4月1日に更新されるため、4月1日以降に登記申請する場合は、新年度の最新のものを用意するようにしてください。
また、証明書を取得する際、特に郵送などは時間がかかることもあるため、必要な時に提出できるよう準備は前もって済ませるように心がけましょう。
固定資産評価証明書について知っておこう

本記事では固定資産評価証明書の意味や必要なシーン、申請時の注意点について紹介してきました。相続や贈与など、今は大丈夫と思っていても急にそのような状況になると、迷ってしまうものです。
書類の準備についても、思いがけないところで時間を要して、スムーズに準備が進まないこともあるでしょう。固定資産評価証明書について理解し、スムーズに進められるよう早めの準備を心がけるようにしてください。
お電話でも受け付けております















