
納骨堂の見学で後悔しないチェックポイント|個別法要はできる?確認したい「数字」とは
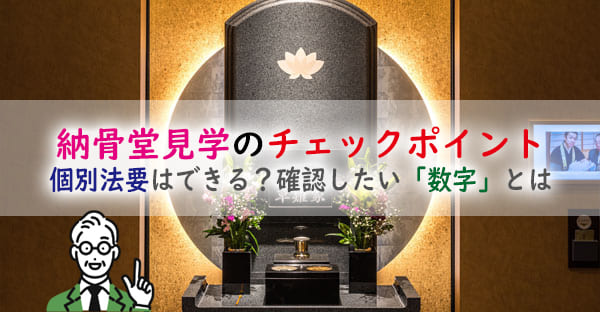
・そもそも「納骨堂」とは?人気の理由は?
・納骨堂の見学でのチェックポイントは?
・納骨堂の見学で確認したい契約内容は?
お墓のいらない遺骨供養の方法として、屋内で遺骨を安置する「納骨堂」が注目されています。
ただ、まだまだ新しい遺骨供養の方法ですので、納骨堂の見学でのチェックポイントが分からないまま契約をして、後々後悔した体験談も少なくありません。
本記事を読むことで、将来的に後悔しない納骨堂を見学する時のチェックポイントや、契約前に確認したい5つの契約内容・規約が分かります。
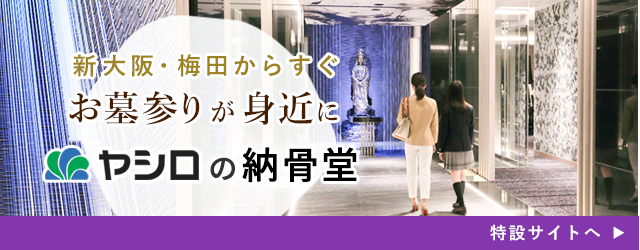
そもそも「納骨堂」とは?

◇「納骨堂」とは、遺骨を収蔵する屋内施設です
「納骨堂」とは遺骨を個別に収蔵する屋内施設で、基本的に家族に代わり施設が永代に渡って、遺骨の管理・供養をする「永代供養」が付いています。
永代供養が付いているので、家族は遺骨の維持管理への負担が軽減し、将来的に継承者を立てる必要がありません。
納骨堂にはロッカータイプや仏壇タイプなど、施設により形式はさまざまです。
また個人用・夫婦用・家族用など、納める人数によって広いスペースを提供する納骨堂もあります。
・納骨堂で永代供養を行う費用はどれくらい?納骨堂5つの種類で違う費用相場を詳しく解説!
納骨堂が人気の理由
◇都心部に近く、気軽に参拝できます
納骨堂をはじめとする、お墓のいらない・継承者のいらない遺骨供養の方法に注目が集まっていますが、なかでも納骨堂は参拝のしやすさが人気の理由です。
また、納骨堂は個別スペースがあるため、遺骨が個別に安置されます。
お墓のいらない遺骨供養の方法には、樹木葬や永代供養墓(合祀墓)などがありますが、樹木葬は屋外ですし、永代供養墓(合祀墓)は、一度埋葬すると再び個別に取り出すことができません。
この点、納骨堂は都心部に近い屋内施設が多く、天候に左右されず参拝ができる他、個別に遺骨が残るため、後々お墓などへ遺骨を移動する「改葬(かいそう)」も可能です。
・樹木葬の失敗しない選び方とは?欠点はある?目的で違う後悔しない選び方のポイント解説
・お金がない時の、最も安い永代供養はどれ?安い永代供養の注意点や選び方、対策も解説!
納骨堂見学のチェックポイント

◇納骨堂見学のチェックポイントを持参します
納骨堂見学は1日に2件、多くても3件ほどが、客観的に比較検討できる件数です。
納骨堂にはニーズに合わせたさまざまなタイプがあるため、予め「何を最も希望するのか?」を家族でまとめて、優先事項を整理すると良いでしょう。
・参拝のタイミング
・参拝時間
・どのような参拝がしたいか
・個別法要の有無
…などです。
納骨堂は一般的に屋内施設になるため、管理人が常駐する開館時間が設けられています。
そのため開館時間内に参拝できるのか?なども比較検討のポイントです。
なかには24時間、参拝ができる納骨堂もあります。
①アクセス環境
◇納骨堂の見学前に、希望をまとめておきましょう
また納骨堂見学は天候や時間など、条件の違う日に複数通った方が良いですが、もしも一度だけの見学で決める場合は、公共交通機関を利用していくと、より安心です。
今は車で行くという人も、将来的に免許返納の可能性があります。
公共交通機関でのアクセス環境を確認することで、後々まで安心できるでしょう。
一方、車で参拝することを考えて、駐車場の広さや台数、駐車場から納骨堂までの距離もチェックします。
②周辺環境
◇納骨堂に隣接する建物や、街並みも確認します
納骨堂に見学に来たら、館内だけではなく外を散歩して周辺をチェックしましょう。
ゴミが多い、夕方頃になると人々が集まり、通り抜けにくい環境だったこともあります。
・静かな環境、賑やかな環境など
・隣接している建物
納骨堂には雨天時にも参拝しやすいよう、駅からそのままアクセスできるものもありますので、周辺環境が静かな場所が良いのか、緑豊かな場所が良いのか、良し悪しは見学者の好み次第です。
家族が参拝しやすい環境にあるのか?故人が安らかに眠れる場所なのか?を意識しながら見学すると、おのずと自分なりの答えも見えてくるでしょう。
③公共設備
◇公共設備の掃除が行き届いているかは重要です
納骨堂見学では、トイレや駐車場、受付などの公共設備の清掃状況や衛星環境をチェックすることで、管理会社の質が見て取れます。
大きい施設で個別の参拝スペースや、休憩スペースがあるなど、施設内容はもちろん大切ですが、どんなに広く良い施設を設けても、清潔感がなければ利用しなくなるためです。
・トイレの清掃状況
・法要室の貸し出し
・待合室の環境
・車は止めやすいか
また納骨後も回忌法要など、個別法要を希望している家族であれば、施設内に個別で利用できる法要室が併設されていると便利でしょう。
この他、車でのアクセスを検討している家族は、駐車場の環境、車が止めやすいかどうかまでチェックすることで、快適なお参りができます。
④納骨場所
◇納骨堂のタイプにより納骨場所が異なります
納骨堂は遺骨を収蔵する屋内施設ですが、収蔵する場所はタイプによりさまざまです。
ロッカーが並ぶロッカータイプや、仏壇が並ぶ仏壇タイプは、多くが個別スペース内に遺骨を収蔵します。
けれども通された参拝スペースに、自動的に遺骨が送られてくる自動搬送タイプの納骨堂では、日ごろは別のスペースに収蔵されているでしょう。
また位牌を祀る位牌タイプの納骨堂では、遺骨は最初に施設内の永代供養墓に合祀されるもの、もしくは粉骨した遺骨を位牌に納める方法などがあります。
⑤受付や施設の雰囲気
納骨堂選びで後悔しない、5つのポイント

◇納骨堂を見学する時には、契約内容をスタッフに確認しましょう
納骨堂を見学する際、資料などから契約内容や規約を受け取りますが、文章が難しく理解が曖昧なままに契約をしてしまうケースは少なくありません。
納骨堂契約に関するトラブルは、契約前に契約書や規約の内容を理解することで、回避できるものも多くあります。
契約書や規約を熟読するとともに、スタッフに確認をすると安心です。
不安が伴う場合は、会話内容を録音し保管しておく方法も良いでしょう。
①納骨の人数と費用
◇納骨堂の人数と費用が見合っているかチェックします
昔の納骨堂は、個人用の施設が一般的だったため、納骨堂の多くは納骨する人数ごとの費用システムです。
お墓のように一基ごとの費用システムではありません。
お墓は小さなもので約6柱~8柱、大きなお墓では約8柱~12柱ほどが入ります。
| <納骨堂の人数と費用目安> |
|
| [人数] | [費用目安] |
| ・個人用 | …約50万円~60万円ほど |
| ・夫婦用 | …約60万円~100万円ほど |
| ・家族用 | …約100万円~150万円ほど |
ただ最近では、夫婦や家族が一緒のスペースに入る納骨堂プランも増えました。
納骨堂で個別スペースを契約する際は「何人まで納骨が可能か?」も確認し、費用と見合っているかを確認すると良いでしょう。
②個別安置期間の年数
◇納骨堂の個別安置期間は、永代ではありません
納骨堂は家族に代わり永代に渡って、遺骨の管理や供養を行うサービスです。
けれども遺骨は、必ずしも永代に渡って「個別で」安置される訳ではありません。
契約した一定年数のみ個別安置され、一定年数が過ぎると施設内の永代供養墓(合祀墓)に合祀され、他の遺骨とともに永代に渡って合同供養されます。
ただ個別安置期間内であれば、遺骨をお墓などへ移動する「改葬」が可能です。
一方で個別安置期間は一般的に、長ければ長いほど、費用も高くなります。
そのため納骨堂を契約する時には、遺骨を個別に安置する「個別安置期間」の年数もチェックしましょう。
③契約更新の有無
◇個別安置期間内に契約更新ができるかどうかをチェックします
納骨堂では個別安置期間が過ぎると、施設内の永代供養墓(合祀墓)に合祀される仕組みが一般的です。
けれども家族型や継承型の納骨堂では、個別安置期間内に残された家族が契約更新をすることで、個別スペースを残すことができるプランもあります。
「今は継承者の目途が立たないけれど、将来はお墓を建てるかもしれない」「ずっと、遺骨を個別に残したい」と希望するならば、契約更新ができるかチェックしても良いでしょう。
④合同法要の頻度と規約
⑤個別法要はできるか
◇回忌法要など個別法要ができるかを確認します
納骨後に遺骨を前に個別法要がしたい場合は、個別法要の可否も確認しましょう。
この場合、特定の僧侶に依頼したいならば、自分たちで僧侶をお呼びしても良いかどうかまで、確認が必要です。
寺院墓地が運営する納骨堂であっても、現代では宗旨宗派を不問とする施設が増えてきましたが、法要はご住職が執り行います。
また民営の納骨堂では僧侶を自分たちで呼ぶことができる施設が多いですが、相談すると僧侶を紹介してくれるでしょう。
⑥宗旨宗派
◇納骨堂に入るにあたり宗旨宗派の条件を確認します
民営の納骨堂では納骨にあたり、宗旨宗派を不問とする施設がほとんどです。
けれども寺院が運営する納骨堂の場合、納骨にあたり入檀が求められることがあります。
「入檀」とは、寺院に属して支える「檀家」になることを指し、檀家制度とは家の法要一切を寺院のご住職に委ね、寺院は家の供養を行う制度です。
現代では寺院でも入檀を求めない納骨堂が増えましたが、確認をしておきましょう。
また宗旨宗派を問わない納骨堂でも、合同供養では特定の宗派に倣うため、理解が必要です。
⑦納骨後の支払い
◇年間管理料を支払う納骨堂もあります
納骨堂には遺骨を個別に安置する「個別安置期間」があるため、この期間はお墓と同じく、年間管理料の支払いが生じるプランも多いです。
「年間管理料」とは、納骨堂の公共スペースにかかる維持管理費用で、毎年支払います。
費用目安は納骨堂の設備やラグジュアリー感によりさまざまですが、約5千円~2万円/年間が一般的でしょう。
生前契約の場合は、生前に個別安置期間の年間管理料を一括で支払うケースもあります。
納骨堂見学までの流れ

納骨堂の見学は、資料の取り寄せから始まります。
ただ、現存する先祖代々墓の墓じまいの後、納骨堂に納骨することを検討しているならば、まずお墓が建つ墓地に相談しましょう。
特に寺院墓地である場合、長くお墓を守ってきたご住職としての自負もありますから、相談とともに、今までお墓を守ってくださった感謝も伝え、気持ちよく墓じまいを進めたいところです。
・墓じまいをして永代供養をする流れは?選べる永代供養5つの種類と料金相場も詳しく紹介
①資料の取り寄せ
◇ネットやチラシで情報収集ができます
納骨堂の情報はネットや新聞の折り込みチラシなどで収集できるでしょう。
また地方のテレビCMなども、映像で雰囲気が分かります。
ネットで情報収集するならば、資料請求フォームに必要事項を記入するだけで、簡単に資料請求でき、必要があればチャット等を利用した質問も可能です。
もちろん電話による資料請求もできるでしょう。
電話であれば受け付けスタッフの応対や人柄を感じ取ることができて、複数の納骨堂を比較検討する材料にもなります。
②比較検討
◇複数の納骨堂から比較検討します
複数の納骨堂を比較検討するメリットは、納骨堂の費用相場が分かってくること、そして複数の納骨堂を知ることで、客観的に判断できることです。
現代の納骨堂は、顧客のニーズに対応してさまざまなタイプが登場しました。
そのため「自分たちがどのような希望を持っているのか?」ニーズを意識した比較検討が、後々後悔しない納骨堂選びのポイントになってきます。
費用を重視するのか、納骨後の参拝環境を重視するのか、手厚い供養を重視するのか、優先順位を付けて比較検討しましょう。
③納骨堂見学の申し込み
納骨堂見学の準備

◇納骨堂見学は、1日2件~3件ほどが理想的です
納骨堂見学に行くなら、1人2件程度、多くても3件程度に留めることで、最初の納骨堂での印象も残り、最後の納骨堂で疲れ切っている事態も防ぐことができます。
1件目の印象が薄れてしまうと、どうしても後半の納骨堂を重視しがちになりますし、最後に訪れた納骨堂で疲れていると、どうしてもチェックが行き届かなくなってしまいがちです。
①写真を撮影
◇画像を残すことで見学時の印象が戻ります
複数の納骨堂を見学するならば、冷静に比較検討するためにも、それぞれの納骨堂での画像を、カメラやスマホで残しておくと良いでしょう。
複数の納骨堂に行くと、どうしても最後の納骨堂など、いずれかの印象が強くなってしまいがちですが、画像を残すことで、見学時の感情や記憶が戻ってきます。
画像を並べて眺めると、自分に適した納骨堂が分かってくることもあるでしょう。
②チェック項目をまとめる
◇納骨堂見学時にチェックしたい事柄をまとめます
納骨堂に見学に行く際、前日などにノートにチェック項目を書き記しておきましょう。
スマホでも問題はありませんが、ノートに書き入れることで、より頭のなかの優先順位や希望が整理できることもあります。
また一人だけの意見だと、見逃したり偏ることもあるので、納骨堂の見学は夫婦や家族など複数で行くことは、チェック事項も増え、より適切な選択ができるためおすすめです。
③質問事項をまとめる
納骨堂の見学後の流れ

◇納骨堂の見学後は、一度持ち帰って検討します
納骨堂の見学が終わると契約です。
納得したら納骨堂の見学当日に、そのまま契約へと進む人も多いですが、必ずしも当日に契約しなければならない訳ではありません。
特に複数の納骨堂を見学しているなら、一度持ち帰って整理した後、改めて後日に契約することで、より後悔するリスクも軽減されます。
①納骨堂の契約
◇住民票や本人確認書類が必要です
納骨堂の契約では、住民票や本人確認書類、書類に捺印する印鑑を持参します。
また納骨堂の支払いがローンなど分割払いになる場合、口座番号や銀行印が必要になりますので、支払い方法まで決めてから契約へと進みましょう。
・住民票(戸籍謄本)
・本人確認書類
(マイナンバー、運転免許証など)
・印鑑
納骨堂の契約当日に現金で払うばかりではなく、契約後に振り込む形が多いです。
分割で支払う場合、納骨堂施設が提供する分割払いや、葬送を目的とした費用にのみ適用する「メモリアルローン」などがあります。
家族の遺骨を納骨する場合、兄弟姉妹や親族に費用負担を分担してもらうことも検討し、相談すると良いでしょう。
・メモリアルローンとは?永代供養での利用は?カードローンとの違い、メリットデメリット
・墓じまいで補助金はもらえる?自治体で違う補助金制度と費用を抑える方法|永代供養ナビ
②納骨
◇埋葬証明書を提出し、納骨します
遺骨を葬送する時は、地上に収蔵する納骨堂であっても「埋葬証明書」が必要です。
埋葬証明書は火葬場で発行される書類で、一般的には骨壺とともに保管しているでしょう。
民間霊園の納骨堂は生前契約ができる施設が多いので、契約者本人が亡くなったら、死亡証明書を役所へ提出し、火葬証明書をいただいた後、火葬場で埋葬証明書を受け取ります。
また納骨時には納骨式を執り行う家族が一般的です。
僧侶へ納骨式の依頼をする場合、約3万円~5万円ほどを目安にお布施を包み、お渡しをしてください。
・【図解】お布施マナーとは?封筒や書き方、金額は?お札の入れ方・渡し方もイラスト解説
まとめ:納骨堂の見学ではチェック項目を持参します

後々まで後悔しないため、納骨堂の見学に行く時にはチェックシートを持参して、目に見える形でチェックを進めながら見学すると良いでしょう。
現代の納骨堂は家族それぞれの希望やニーズに合わせた、さまざまなタイプが登場しているため、チェックシートは一般的なものを利用するのではなく、自分でノートに記載して準備すると尚、良いです。
納骨後の参拝や供養の様子をイメージして、チェックシートを自作しながら、自分が希望する納骨堂の優先順位も整理していくようにします。
また家族や夫婦など、複数で納骨堂の見学に出向くことで、より多くの視点から、客観的により良い納骨堂を選ぶことができるでしょう。
お電話でも受け付けております
















