
【大阪の葬儀・法要】初めて喪主・施主を勤める注意点は?押さえておきたい7つのコラム
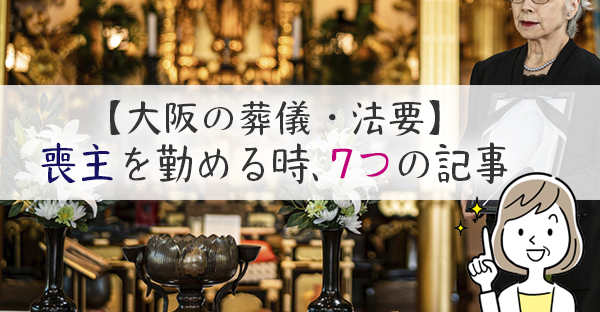
大坂で初めて葬儀の喪主になった時、何から始めれば良いかと戸惑う人は多いですよね。
家族が亡くなると、多くは病院の霊安室に安置されますが、霊園室も数時間、長くて24時間ほどしか安置できないことが多く、初めてのなか、バタバタしたまま手続きを進めなければなりません。
大坂で葬儀を進めるなら喪主はまず、病院の霊安室に安置できる時間内に葬儀社を決めて、ご遺体の搬送を依頼する流れが最もスムーズです。
ただ大阪の葬儀は多様で、喪主としては希望の葬儀の形を求めますよね。
希望の葬儀を得意とする葬儀社に依頼したいところです。
今回は、大阪の葬儀で初めて喪主を務める時の注意点やマナー、法要の段取りまでお伝えします。
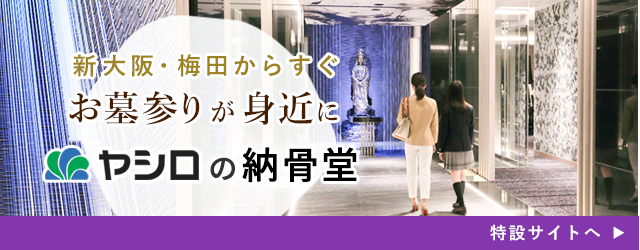
喪主は誰が勤めるの?

大坂で葬儀の喪主は一般的に、血縁として故人と最も近い立場の人が勤めます。
配偶者がいれば配偶者がいない場合は親や子どもが勤めることになるでしょう。
●喪主を勤める優先順位
・配偶者
・長男
・次男以降、直系の男性
・長女
・長女以降、直系の女性
・両親
・兄弟姉妹
ただしこれはあくまでも慣習なので、必ず最も近しい立場の人が喪主にならなければいけない訳ではありません。
例えば、配偶者を亡くしたショックで「立派に喪主を勤める自信がない」と思うのであれば、長男など子どもに喪主を代わってもらう方法もあるでしょう。
実際に喪主となるべき配偶者が高齢の場合、(高齢者が多い)大阪では、長男や長女が葬儀の喪主を勤める事例が多いです。
また親族がいない故人であれば、知人友人でも喪主になれますし、ご住職が喪主を勤めることもあります。
・喪主は誰がやるのか決まっている?決め方や役割と併せて服装のマナーも解説
葬儀社を決める
大坂の葬儀で喪主になったなら、まずは信頼できる葬儀社を選ぶと心強いです。
冒頭でお伝えしたように、病院の霊安室は数時間~24時間、ご遺体は葬儀社に頼んで搬送しなければなりません。
●病院が契約している葬儀社に搬送のみを任せることはできますが、この時点から葬儀社を決めておくと、後々までスムーズです。
特にご遺体を自宅搬送せず、安置施設を探している場合、葬儀社所有の安置室を利用できますし、そのまま通夜・葬儀・火葬までサポートが期待できます。
ただ葬儀社は、それぞれ葬儀の形の得手不得手がありますから、大阪の葬儀で喪主が選ぶ時には、希望の葬儀を決めておくと選びやすいです。
・音楽葬
・家族葬
・キリスト教式
…などなど
・大阪で遺族が行う葬儀の流れ。喪主決めから通知と協力依頼、葬儀社選びや打ち合わせまで
納骨式も施主の仕事

大坂でお通夜や葬儀で喪主を勤めたならば、法要でも施主を勤めることになるでしょう。
葬儀後の法要は、初七日・四十九日・納骨式がありますが、大坂では葬儀の日に、喪主は繰り上げ初七日法要を執り行うことも多いです。
(1)お通夜
(2)葬儀
(3)初七日
・二七日
・三七日
・四七日
・五七日
(4)四十九日(七七日)
・納骨式
(5)百か日
(6)一周忌
一般的に弔問客が訪れる法要は、初七日・四十九日・一周忌になるでしょう。
週忌法要(二七日~五七日)や百か日は行ったとしても、遺族のみです。
(僧侶を呼び読経供養を行う家はあります。)
また四十九日法要と納骨式を同日に執り行う慣習もあり、先祖代々墓など、入るお墓がすでにあるご遺骨は、四十九日法要の後に納骨される流れが多いでしょう。
・大阪の納骨式で施主が進める3つの段取り☆当日必要な持ち物のチェックリストまで紹介!
読経供養ではお布施を包む
大坂で葬儀の喪主を勤める場合、また法要を執り行う場合でも、僧侶に読経供養を依頼する場合には、「お布施」としてお礼を包むのも大切な仕事です。
「お布施」は読経供養に対する料金ではなく、仏教道への修行のひとつ「徳行」なので、明瞭な料金体系はありませんが、一般的な金額目安はあります。
・お布施…3万円~5万円/1回の読経供養
・御車代…5千円~1万円(お寺から葬儀会場までのタクシー代が目安)
・御膳代…3千円~1万円(会食1人分の料金が目安)
御膳代は葬儀や法要後に会食があり、僧侶がその会食の席を欠席する時に包みます。
またお布施は徳行のひとつと言いましたが、御香典ではないので、不祝儀袋には包みません。
大坂の葬儀では、喪主が白×黄色の袋や水引きで包むこともありますが、基本的には厚手の白封筒で包めば良いでしょう。
・大阪の法要でお布施を渡す時、施主が押さえるマナーとは。御香典とは違う渡し方を解説!
大阪の葬儀、喪主の服装マナー

大坂の葬儀で喪主になると、男性は基本的にブラックスーツであれば安心ですが、喪主の女性は喪服の「格」が高いものにする慣習があります。
「格」と言っても家の格と言う意味合いではなく、故人と近しい遺族としての服装がある、と言うことです。
●男性
・ブラックスーツ
・ブラックネクタイ
・光沢のないストレートチップ
(ネクタイの結びはプレーンノット)
●女性
・和装…黒無地、染め抜き日向5つ紋
・洋装…黒無地ワンピースなど
黒無地の和装であれば、弔事の第一礼服と考える地域が一般的なのでまず安心ですが、洋装で整えるならば、喪服の格はスカートの丈でも表すとされます。
そのためスカート丈の長いブラックワンピースで整えるのも良いでしょう。
・大阪の葬儀、喪主の服装マナーを解説。お通夜と葬儀、昼と夜で着る喪服でも違う作法とは
希望の葬儀スタイルを決めておく

前でも少し触れましたが、大阪の葬儀で喪主を勤めることが決まったら、早々に「どんな葬儀にしたいか」、希望の葬儀スタイルを決めておくと、葬儀社スタッフもサポートしやすくスムーズです。
あまりこだわらない人は、葬儀の規模によって一般葬や家族葬になります。
・一般葬
・家族葬
・自宅葬
・自由葬
・音楽葬
・密葬
・ゼロ葬
…などなど。
ただ予算を抑える目的で、規模の小さい家族葬を選ぶご遺族もいますが、規模が小さくとも葬儀によっては一般葬以上に費用が掛かるものもあるので、注意は必要です。
一方で「ゼロ葬」とは、火葬場で読経供養を済ませてご遺骨を引き取らない形式となり、予算は掛からないものの、あまりに質素で後悔するご遺族などもいます。
自由葬は無宗教の葬儀が多く現代的で、僧侶による読経を無くし、御香典を辞退して入場料(会員制)で執り行うスタイルが多いです。
いわゆるお別れ会や偲ぶ会のようなスタイルと言えるでしょう。
・お別れの会を行うときのポイントとは?葬儀との違いや参列する場合のマナーも紹介
見直される自宅葬
また近年では予算を抑えながらも心を込めた葬儀として、自宅葬も見直されています。
コロナ禍により家族以外の弔問客を受け付けない、規模の小さな葬儀が増えたことも、背景にあるでしょう。
●自宅葬では病院の安置室から直接、ご遺体を自宅に搬送するため、病院からの搬送後は長くても3日間内には通夜や葬儀を執り行う流れが多いです。
もしくは先に火葬を済ませ、ご遺骨の状態で7日後などに葬儀を執り行います。
昔ながらの自宅葬では、世話役や受け付けを知人友人、近隣の人々にお願いすることもありますが、この場合にはそれぞれ別にお礼を包んでお渡ししてください。
・大阪の自宅で葬儀を行う手順と流れ。世話役や通夜・葬儀での飲食、供花や供物まで解説!
最後に
いかがでしたでしょうか、今回は大阪で初めて葬儀の喪主を勤める時、理解しておくと役立つ7つのコラムをお伝えしました。
ともかく信頼できる葬儀社を選ぶこと、葬儀社スタッフとの出会いが、大阪で後々まで後悔しない葬儀を進める喪主の第一のポイントになります。
そのためにも葬儀のイメージは早々に決めて、葬儀選びを進めてください。
現在人気が高い葬儀は、自由葬や家族葬の他、花々に囲まれてお見送りができる「花葬」や、故人が生前に好きだった音楽を流してお見送りする「音楽葬」などもあります。
・音楽葬とはどんな葬儀?流れと併せてマナーや注意点もチェックしよう
まとめ
初めて喪主を勤める時に役立つ7つのコラム
・喪主は誰がやるのか決まっている?決め方や役割と併せて服装のマナーも解説
・大阪で遺族が行う葬儀の流れ。喪主決めから通知と協力依頼、葬儀社選びや打ち合わせまで
・大阪の納骨式で施主が進める3つの段取り☆当日必要な持ち物のチェックリストまで紹介!
・大阪の法要でお布施を渡す時、施主が押さえるマナーとは。御香典とは違う渡し方を解説!
・大阪の葬儀、喪主の服装マナーを解説。お通夜と葬儀、昼と夜で着る喪服でも違う作法とは
・大阪の自宅で葬儀を行う手順と流れ。世話役や通夜・葬儀での飲食、供花や供物まで解説!
・お別れの会を行うときのポイントとは?葬儀との違いや参列する場合のマナーも紹介
お電話でも受け付けております















