
精霊馬とは?お盆に供えるのはなぜ?作り方や飾り方、処理は?鬼灯や水の子も詳しく解説
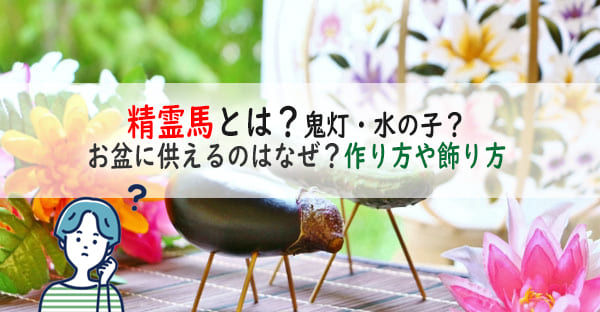
・精霊馬とは?
・作り方や飾り方は?
・お盆の後、どうやって処分するの?
精霊馬とは、ご先祖様が家に帰るための乗り物で、お盆になると盆棚に飾ります。ナスやキュウリで作りますが、キュウリが「精霊馬」・ナスが「精霊牛」です。
またお盆には精霊馬と並び、鬼灯(ほおずき)や水の子を盆棚に祀りますが、作り方が分からない人も多いですよね。
本記事を読むことで、お盆に飾る精霊馬とはなにか?作り方や飾り方、処分の仕方が分かります。
後半には鬼灯(ほおずき)や水の子の作り方・飾り方も分かりますので、どうぞ最後までお読みください。

精霊馬とは?由来は?

◇「精霊馬」とは、ご先祖様の霊が家に帰る時に利用する乗り物です
お盆はご先祖様があの世から家へ帰るため、家族でもてなす供養行事となります。お盆の精霊馬と言うと、キュウリとナスにお箸を差すイメージがありますよね。
実は精霊馬はキュウリのみで、ナスは「精霊牛」と呼ばれます。
・精霊牛(しょうろううし)…ナス
ではなぜ、お盆になると精霊馬と精霊牛の2頭を盆棚に飾るのでしょうか。それは、それぞれに役割が違うためです。
精霊馬は、行きの乗り物
◇精霊馬は、ご先祖様が家に来る時に乗ります
精霊馬はキュウリに4本のお箸を差し、馬を模したお盆飾りです。
その昔、急ぎの用事がある時に「早馬を出す」と言いました。
ご先祖様を迎えるにあたり精霊馬を出す理由は「少しでも早く家に帰ってきてほしい」との気持ちを表現するためです。
精霊牛は帰りの乗り物
お盆に精霊馬を飾るタイミング

◇精霊馬は、「盆の入り」以降に飾ります
「盆の入り」とは、お盆がある月の始まりで1日以降です。
一般的な8月13日~16日の「月遅れ盆」であれば、8月1日が盆の入りになります。
「お盆より早くに精霊馬を飾ると、ご先祖様が早くに家に来て居座ってしまう。」と言う方もいますが、あまり気にすることはありません。
ただ、お盆の時期が異なる地域もありますので注意をしてください。
| <精霊馬を飾るタイミング> | ||
| [お盆の種類] | [お盆] | [盆の入り] |
| ・月遅れ盆 | 8月13日~16日 | 8月1日 |
| ・七月盆(新盆) | 7月13日~16日 | 7月1日 |
盆の入りは精霊馬だけではなく「お盆の事始め」なので、精霊棚など飾り付けるタイミングで、一緒に精霊馬を飾る家が多いでしょう。
盆の入り後に、「お盆のご案内」にお墓参りをする地域もあります。この場合はお墓参りの前に飾り付けて行く家が多いです。
・2025年のお盆はいつ・どんな日程で行う?地域で違う3つのお盆?全国の行事も紹介!
精霊馬を作ろう

◇精霊馬はキュウリに割り箸4本、精霊牛はナスの割り箸4本を差します
ただキュウリは馬に、ナスは牛に見立てているので、それらしいキュウリやナスを選ぶのがポイントです。それぞれ、少し反りがある野菜を選ぶと良いでしょう。
・ナス
・きゅうり
・割り箸
もともとは麻の茎の皮を剥いだ「オガラ」を精霊馬の脚に使用してきました。
麻は神聖な植物として、穢れを祓うとされます。
スーパーやネットでも販売されていますが、割り箸を代用する家が多いでしょう。
割り箸であれば、丸箸が脚に使いやすいです。
・お盆の迎え火・送り火のやり方や手順は?いつ何時頃に焚くといいの?焙烙・オガラとは?
牛馬に見立てた、キュウリとナスがあれば簡単!
◇割り箸を適度な長さに切り、野菜の大きさに合わせて刺します
動物に見えるように形を整えます。反り返ったキュウリやナスを、お顔が上を向いているようなイメージで差すと良いでしょう。
割り箸は均一の長さに切ることで、早馬や牛のように立派に見えます。
精霊馬・精霊牛の飾り方
藁やちりめんの精霊馬
お盆の精霊馬では、地域によってナスやきゅうりを使わず、藁の精霊馬を見掛けることもあるでしょう。
今ではお盆の精霊馬として、きゅうりやナスを象ったロウソクや、ちりめん人形などの販売も見受けます。
一緒に飾る「水の子」とは

◇ご先祖様についてきた無縁仏に供えます
お盆の由来から、常に喉が渇いている餓鬼への供物ともされ、禊を祓い喉の渇きを止めるため、ミソハギ(禊萩)の花の傍に供えるとされました。
・お米…少量
・ナス…少量
・きゅうり…少量
・水…少量
水の子はお飾りの残り物などで作るので、お盆の精霊馬を作った時に一緒に作ると良いでしょう。食べ物なので8月13日頃から飾ると、腐りにくいです。
・お盆とは、なにをする?子どもにも分かるお盆の意味や由来とは。盆踊り大会はなぜ行う?
水の子の作り方
◇賽の目に切ったナスやきゅうりと、すすいだお米を混ぜるだけです
冥土の道には七つの関所があるため「お米は7回すすぐ」とも言われます。
ナスやきゅうりは、同じ大きさにカットしましょう。
・ナスときゅうりを賽の目にカットする
・お米とナス、きゅうりを混ぜて水を灌ぐ
ナスは空気に触れると酸化します。切ったらすぐに水にさらすと色止めになります。
一緒に飾る鬼灯とは

◇鬼灯(ほおずき)は、道を照らす提灯の役割を果たします
精霊馬はあの世とこの世を行き来する乗り物ですが、鬼灯はその道を照らす提灯の役割です。
橙色で先っちょが尖り、中が空洞の鬼灯は、確かに提灯のようにも見えるでしょう。鬼灯をお盆以降も長持ちさせたい家では、下記のような処理があります。
・透かし鬼灯
ただお盆は3日間~4日間なので、そのまま飾る人が多いです。お盆の後も長く飾りたい時に、お盆の後、それぞれの作り方を試してみてはいかがでしょうか。
ドライフラワーの鬼灯
美しい「透かし鬼灯」もおすすめ!

◇提灯のように透けて見える鬼灯が、「透かし鬼灯」です
精霊馬と同じく「透かし鬼灯」の作り方もとても簡単で、密閉できる容器に鬼灯がかかるように水を注ぐだけですが、注意点が3つあります。
新鮮な鬼灯を選ぶとキレイなので、最近はインスタ映えも狙えるとして、若い人々にも人気です。
・臭い漏れがない密閉容器を使用
・新鮮な鬼灯を使う
古い鬼灯を使用すると、中の実が腐り見栄えが悪くなってしまいます。
水に浸かっていない部分があると、黒く腐食が始まるので注意をしてください。
密閉容器は100円均一でも販売しているので、手軽に挑戦できるでしょう。
・【図解】お盆の飾り方とは?盆棚・精霊棚やお供え、初盆との違いもイラストで徹底解説!
お盆後の処分方法

◇昔は、送り火の火でお焚き上げをしました
ご先祖様をお見送りした後、お盆飾りはその日のうちに片づけます。
その昔は、ご先祖様をお見送りする「送り火」の後、その火で盆飾りを焚いて処理する地域が多くありました。
けれども今では集合住宅も多く、火の用心の観点から、あまり火を使わない処理方法が一般的です。
お焚き上げをしたい場合、近所の神社や寺院でお願いすると良いでしょう。
ただ、近年ではお焚き上げを受け付けない神社や寺院も増えていますので、確認をしてください。
お盆後に食べるのはNG!
◇精霊馬は野菜ですが、お盆を終えた後にいただくのは危険です
お供え物を下げた後、家族でいただく風習もあることから、野菜で作る精霊馬もお盆後にいただこうとする声もあります。
けれども真夏に数日間供えている野菜は危険ですので、避けてください。
●精霊馬は8月13日~16日の3日~4日間、外に出しっぱなしです。
…割り箸を刺したところから菌が入り込みやすく、野菜も傷んでいます。
なにより精霊馬はお供え物ではなく、ご先祖様をお送り迎えした乗り物です。
仏様へのお祀り物として扱い、処分を進めると良いでしょう。
昔は川に流す・土に埋めていた
◇その昔、精霊馬はお盆の後に土に埋めたり、川に流しました
ただ近年の日本では、川に流すことは法律的に認められないのでやめましょう。敷地がある方は土に埋めることをしてもOKです。
・花壇などの土に埋める
マンションでも花壇をベランダに用意して、塩で清めたきゅうりやナスを埋めて処理する家もあります。
精霊馬を清めて捨てる
◇精霊馬やお盆のお飾りは、清めてから燃えるゴミとして捨てます
近年、最も一般的な精霊馬やお盆のお飾りの処分方法が、清めてから燃えるゴミとして捨てる方法です。
・精霊馬に塩を振って清める
・白い紙に包む
・燃えるゴミ(生ゴミ)として出す
「白い紙」は習字で使う半紙の他、キッチンペーパーなどでも問題ありません。
精霊馬に塩を振ることで、祀り物からただの「物」に変わります。
精霊馬はご先祖様があの世と家を行き来する乗り物です

精霊馬・精霊牛はナスやきゅうりと割り箸があればできるので簡単ですが、生もので腐りやすいので、最近ではガラスやロウソクなどで模した精霊馬も多いです。
ご先祖様をお迎え、お見送りをする迎え火や送り火では、精霊馬を玄関先まで持ってくる地域もあるでしょう。
子ども達も楽しく作れる簡単な飾り物ばかりですから、本記事を参考にしながら、8月1日の盆の入り後、夏休みのイベントとして楽しんでみてはいかがでしょうか。
・【図解】お盆のやることチェックリスト:お供え物や進め方を
お電話でも受け付けております


















