
お盆とは、なにをする?子どもにも分かるお盆の意味や由来とは。盆踊り大会はなぜ行う?
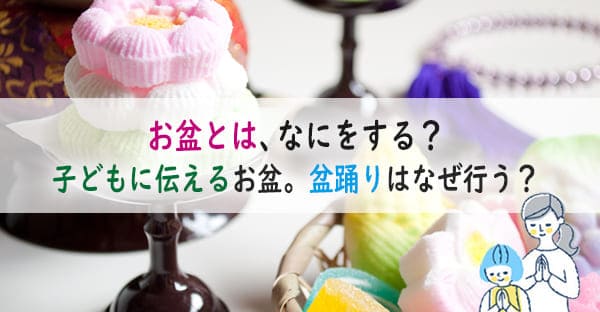
・お盆とは?
・お盆はなにをするの?
・盆踊り大会は、なぜ行うの?
お盆とは、ご先祖様の霊を迎え入れてもてなし、感謝を伝える日本の伝統行事です。子ども達にとってお盆とは、盆休みに田舎へ帰るイメージかもしれません。
今日まで残る日本の伝統行事「お盆」とはなにか?
本記事を読むことで、子ども達に楽しく、分かりやすく説明できるよう、解説しますので、どうぞ最後までお読みください。

お盆とは?

◇「お盆(おぼん)」とは、ご先祖様の霊を家に迎え入れ、一緒に時間を過ごす期間です
ご先祖様とは何世代も前の血縁者、亡くなったおじいちゃん・おばあちゃんの、そのまたおじいちゃん、おばあちゃん達を差します。
お盆は家に亡くなったご先祖様を招いて感謝を伝え、おもてなしをする「先祖供養」の期間です。
お盆とは:釜が開く8月1日
◇お盆の月となる8月が明けることを「釜蓋朔日(かまぶたついたち)」と言います
お盆の月である8月に入ることを「お盆の入り」と言い、この時期を目安にお盆の飾り物や準備を始めました。
「地獄の釜(かま)」などと聞けば分かりやすいですが、お盆の入りである8月1日は、あの世で釜の蓋(ふた)が開くとも言います。
あの世で釜の蓋(ふた)が開くと、ご先祖様の霊が外に出ることになりますね。
お盆とは:いつ行うの?

◇お盆は一般的に、毎年8月13日~16日の日程で行われます
8月13日~15日の3日間とする地域と、8月13日~16日の4日間とする地域あるでしょう。2023年は8月13日(日)~8月16日(水)がお盆です。
ただし全国には8月13日~8月16日日程とは違う暦で行う地域もあります。
| <お盆とは:3つの暦> | ||
| ・月遅れ盆 | 8月13日~16日 | 全国 |
| ・七月盆 | 7月13日~16日 | 主に関東圏 |
| ・お盆 | 7月31日~8月2日 | 東京都多摩地区など |
| ・旧盆 | 旧暦7月13日~16日 | 沖縄 |
「旧暦(きゅうぼん)」とは、明治5年前まで使われていた、月の満ち欠けによる暦「陰暦」です。そのため旧盆で行うお盆は、毎年日程が異なります。
お盆とは:どこから来たの?

◇お盆はもともと「盂蘭盆会」と言う仏教行事です
「盂蘭盆会(うらぼんえ)」では、お盆に先祖供養を行うことで親孝行になるとされます。ちなみにお盆は「盂蘭盆(うらぼん)」を略した言葉です。
また盂蘭盆会は、仏教に伝わるお話「盂蘭盆経(うらぼんきょう)」が由来です。
それではお盆がどのようにして親孝行行事になったのか、「盂蘭盆経」のお話をご紹介していきましょう。
お盆とは:由来

◇盂蘭盆経によると、お盆はその昔、お釈迦さまの弟子が亡くなられた母親を救う話から由来しています
お釈迦様の弟子は「目連尊者(もくれんそんじゃ)」です。目連尊者の母親は、あの世で餓鬼道(がきどう)に落ちてしまいました。
餓鬼道に落ちた者は、常に飲食することができません。常に飢えと渇きに苦しむ世界とされます。
それではなぜ、目連尊者の母親は餓鬼道に落ちてしまったのでしょうか。
目連尊者の母親はなぜ餓鬼道に落ちたの?
目連尊者は母親のために何をしたの?
生前の優しい母親を想い、目連尊者は「苦しんでいる母親を、どうにかして助けたい!」とお釈迦さまに相談します。そこでお釈迦様はこう答えました。
「夏の修行を終えた7月15日、僧侶を招き御供物を捧げ供養しなさい。」
目連尊者が実際にそのように供養したところ、母親は極楽往生を遂げました。
お盆とは:言葉の由来は?
◇お盆の語源となる「盂蘭盆」は、「逆さに吊る」ことを意味します
インド発祥の仏教でお盆の語源となる「盂蘭盆(うらぼん)」は、サンスクリット語で「ウランバナァ」です。この「ウランバナァ」は「逆さに吊る」を意味します。
餓鬼道に落ちた目連尊者の母親は、逆さに吊られていましたよね。
この目連尊者が母親を餓鬼道から救い出したお話が、親孝行の物語として「盂蘭盆経(うらぼんきょう)」となりました。
お盆の過ごし方は?

◇お盆ではご先祖様をお迎えし、供物でもてなし、感謝を伝えます
「お盆の入り」となる8月1日からお盆の準備を始め、8月13日のお盆の初日に、迎え火を焚いたら、ご先祖様をお迎えです。
お盆期間はご先祖様に鬼灯(ほおずき)や素麺(そうめん)、御膳などをお供えして、8月16日には送り火を焚いてお見送りをします。
お盆の準備
◇お盆まで精霊馬や鬼灯(ほおずき)を飾り、準備をします
精霊馬(しょうろううま)とは、ご先祖様の霊があの世から家まで移動する際に利用する乗り物です。
8月13日の初日、ご先祖様はキュウリに足となるお箸を差した「早馬」でぴゅんとやってきます。
8月16日の最終日には、ナスに足となるお箸を差した「牛」です。両脇にたくさんのこの世のお土産を付け、この世の名残りを楽しみながら、ご先祖様はゆっくりとあの世へ帰ります。
お盆の迎え火・送り火
◇ご先祖様が家にいらっしゃるため、迎え火で迎え、送り火でお見送りをします
お盆でご先祖様のお迎え・お見送りは、迎え火・送り火です。迎え火・送り火は、オガラを焙烙(ほうろく)と呼ばれる素焼きの浅い土なべのなかで焚きます。
「オガラ」は麻がら・麻幹とも言い、麻の茎の皮を剥いで内部を乾燥させたものです。
「迎えは早く、帰りは遅く」とされ、8月13日の日が沈み始めたら日没までには、迎え火を焚きましょう。
・お盆の送り火・迎え火のやり方や手順は?いつ何時頃に焚くといいの?焙烙・オガラとは?
始めてのお盆は「初盆」
◇家族が亡くなって初めて迎えるお盆では、初盆法要を行います
家族が亡くなってから四十九日が過ぎ、初めて迎えるお盆は「初盆(はつぼん)」です。家族は参列者にご案内し、僧侶をお呼びして初盆法要を行います。
初日と最終日には、送り火と迎え火を行うので、盆中日となる8月14日、4日間のお盆では8月14日・15日に執り行うと良いでしょう。
お盆は一斉に行うため2~3ヶ月前を目安に、僧侶の手配をします。菩提寺がある場合は、まず菩提寺のご住職へご相談をしてください。
・【2025年度版】初盆(新盆)法要とは?お布施相場は?初盆法要の進め方や服装マナー
お盆の帰省はなぜ?
◇分家の人々は、ご先祖様のお仏壇がある本家を訪ねます
分家とは実家から独立して家族を構えた人々です。本家は先祖代々のご先祖様を祀るお仏壇がある家で、多くは実家に帰省する人が多いでしょう。
そのためお盆休みには、おじいちゃん・おばぁちゃんの家へ行くのですね。
・お供物を供える
実家である本家へ帰省する時には、ご先祖様へのお供物として、渇き菓子などの手土産を持参します。
先方に着いたら「ご挨拶しますね」とお仏壇に最初に行き、お線香をあげて手を合わせてから、お仏壇前にお供物を供えると良いでしょう。
お供物を供える時にも、本家の人へひと言、断りを入れてください。
お盆のお墓参り
◇お盆の初日にお墓参りをして、ご先祖様を家まで迎える風習もあります
地域によってはご先祖様を家に迎えるにあたり、お墓までご案内に行く風習も残っています。なかにはお盆前の8月1日~12日の間にお墓参りを行い、お盆のご案内を掛ける地域もあるでしょう。
ただし「お墓参りはお彼岸」として、お盆のお墓参りをしない地域や家も多いです。
・お盆のお墓参りに行ってはいけない日があるって本当?タブーの日取りや時間、5つの作法
お盆に盆踊り大会をするのはなぜ?

◇盆踊り大会は、ご先祖様にこの世で楽しい時を過ごしてもらうための催しです
お盆に行われる盆踊り大会は、ご先祖様をもてなすために行いました。1年に1度だけの、この世の時間を楽しく過ごしてもらうためです。
また盆踊りには農耕儀礼としての意味合いもあります。
「より多くの農作物が収穫できますように」と豊作祈願を行うため、神様へ捧げるに踊りを献上する意味もあるでしょう。
お盆の盆踊りのお話
◇盆踊りは、餓鬼道から解放された霊が喜ぶ様子とも言われます
前述しようにお盆はもともと、目連尊者が餓鬼道に落ちた母親を救い出すために行った、親孝行です。
餓鬼道で逆さ吊りにされていた霊達が、餓鬼道の飢えや苦しみから解放され、両手を上げて踊り喜んでいた様子を表している、とも言われています。
お盆とは、ご先祖様に感謝する先祖供養です

お盆とはご先祖様を家に迎え入れてもてなし、自分達が今ここにあることへの感謝を伝える先祖供養の行事です。
神道や沖縄など、一部地域ではご先祖様は家を守る守護神としても尊ばれ、お盆行事は今日まで、日本の人々に深く根付いてきました。
今ではお盆よりもお盆休みがフューチャーされますが、子ども達から「お盆とはなに?」と聞かれた時には、後々まで伝え継ぎたいですね。
本記事を参考にしながら、楽しく子ども達へお盆とはなにか?を伝えてみてはいかがでしょうか。
お電話でも受け付けております
















