
お盆の迎え火・送り火のやり方や手順は?いつ何時頃に焚くといいの?焙烙・オガラとは?
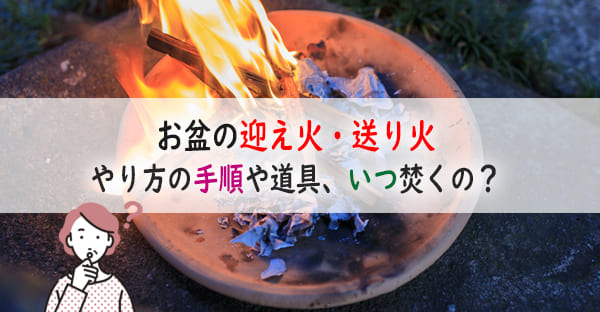
・お盆の迎え火や送り火のやり方は?
・使う道具は?いつ頃に行うの?
伝統的な先祖供養行事であるお盆では、ご先祖様の霊を家へ迎えるため、初日に迎え火を、最終日に送り火を焚きます。
本記事を読むことで迎え火・送り火のやり方や手順、いつ頃に行うのかが分かる他、使用する道具についても詳しく分かりますので、どうぞ最後までお読みください。

お盆の迎え火・送り火とは

◇お盆の迎え火・送り火は、家の目印です
お盆の迎え火・送り火とは、1年に1度帰省するご先祖様の魂が迷わぬよう、玄関先で焚いて目印とする炎を指します。
お盆の迎え火では、ご先祖様へ迎え火で目印を示すことが目的です。
お盆の送り火では、「私たちはご先祖様を確かにお見送りしていますよ」と証明するために炎を灯し見送ります。
またお盆の煙はあの世へ届くとされてきました。
そのためお盆の送り火では、お供え物を送り火と一緒に焚いて、煙としてあの世へ「この世の手土産」届ける役割もあります。
お盆の初日はいつ、何時頃から行う?
◇お盆の迎え火は、迎え盆の夕方頃に行います
迎え火は一般的にお盆初日の夕方~日没にかけて行いますが、正確な時間の決まり事はありません。
全国的に多い8月13日~15日に行う「月遅れ盆」の日程であれば、8月13日の夕方頃が迎え火を焚く頃です。
・2025年のお盆はいつ?お盆休みは最大9連休!地域で違う3つのお盆、全国のお盆行事
お盆の最終日はいつ、何時頃から行う?
お盆の迎え火・送り火はどこで行うの?

◇お盆の迎え火・送り火は、玄関先や門前で行います
お盆の初日「迎え盆」にお墓参りをして、ご先祖様を家までご案内する風習がある場合、迎え火を墓前で行う地域もあるでしょう。
・玄関先
・門前
・墓前
・ベランダ
…など
また近年では分譲マンションなどの集合住宅も増え、近隣住民への配慮から、ベランダなどでお盆の迎え火・送り火を焚く家庭も見受けます。
お迎えを忘れてしまったら、どうする?
◇お仏壇に手を合わせます
お盆の迎え火を忘れてしまったら、その時にお墓参りをしても良いですし、お仏壇に手を合わせてお詫びをしても良いでしょう。
迎え火を忘れても特に決まり事はないため、8月13日の迎え盆当日であれば、遅くても気づいた時点で行っても問題はありません。
その際には「遅くなりまして申し訳ございません」とひと言添えて迎え火を焚くと良いです。
現代では少人数での迎え火も多いですので、その場に居合わせた人々のみで良いでしょう。
火を付ける「火種」はどこから?
◇迎え火・送り火は提灯の火をロウソクへ移します
迎え火・送り火の火は本来、提灯の火をロウソクへ移し、その日をオガラに付けて焚く風習がありました。
またお墓が家の裏山、集落の菩提寺など、家から近い距離にあった集落では、お盆初日の迎え盆に、ご先祖様をご案内する目印となる、提灯を持ってお墓参りへ行きます。
その提灯の火から迎え火を焚くためです。
ただお墓参りに行かない地域では、先に迎え火を焚いて、その火を盆提灯に移すこともあります。
| <迎え火・送り火の火はどこから?> |
|
| [迎え火] | |
| ①お墓参りに行く | ・墓前や寺院で火をおこす ・盆提灯に火を灯す ・盆提灯の火をロウソクに移す ・ロウソクから迎え火を焚く |
| ②自宅で迎える | ・門前で迎え火を焚く ・迎え火をロウソクに移す ・ロウソクから盆提灯の火を灯す ・盆提灯を御仏前に持って行く (ご先祖様を室内へご案内するため) |
| [送り火] | |
| ①お盆飾りは焚かない | ・盆提灯を門前に持って行く ・盆提灯の火をロウソクに移す ・ロウソクから送り火を焚く |
| ②お盆飾りを焚く | ・盆提灯を門前に持って行く ・盆提灯の火をロウソクに移す ・ロウソクから送り火を焚く ・お盆飾りを焚く |
けれども現代では火の用心の観点から、電気式の提灯も増えました。
また遠方にお墓がある家庭も少なくないため、提灯を持ってお墓参りを行い、家までご先祖様をご案内する家庭も少なくなっています。
そのため現代は、マッチやライターなどから迎え火を焚く家庭も多いでしょう。
詳しくは下記より解説していきます。
お盆の火を焚かない方法はある?
お盆の迎え火・送り火の準備

◇お盆の迎え火・送り火は、オガラを焙烙のなかで焚きます
「オガラ」とは、麻の茎を剥いで内部を乾燥させた麻がらのことで、昔から灯明などで用いられてきました。仏教でオガラの煙は、天界の霊をこの世に降ろすとも言われます。
・オガラ
・焙烙(ほうろく)
・盆提灯
焙烙(ほうろく)とは、素焼きの底が浅い鍋です。
その昔のお盆の迎え火・送り火では、地面に焚いてきましたが、残り跡や火の用心の観点から、いつしか焙烙(ほうろく)を使用するようになりました。
・お盆の迎え火・送り火セット
火を付ける正しい方法は?
◇小さく切ったオガラを重ねて焙烙に乗せ、火を付けます
現代ではベランダで行うお盆の迎え火・送り火も多いため、周囲に燃えるものがないか、注意をして焚きましょう。
ご先祖様の霊が家に帰るための乗り物「精霊馬(しょうろううま)」や、盆提灯もその場に用意します。
精霊馬とは、ナスやきゅうりに足となる4本のお箸を差したものですが、今ではガラスの置物なども販売されるようになりました。
お盆の迎え火のやり方
◇お盆の迎え火は、初日の迎え盆8月13日の夕方頃に行います
「なかなか着火しない!」との声もありますが、オガラをたくさん重ねると火柱が立ちやすくなってしまうので、注意をしてください。
・焙烙にオガラを重ねて着火する
・迎え火を焚く
・迎え火で盆提灯に火をともす
火が着火しやすいようスキマを開けてオガラを重ね、少量で点火することがポイントです。
昔の盆提灯は迎え火の日で灯しましたが、現代は電気式のものがほとんどですよね。電気式の盆提灯であれば、最後の日を灯す手順を省きます。
・【図解】お盆の飾り方とは?盆棚・精霊棚やお供え、初盆との違いもイラストで徹底解説!
お盆の迎え火を終えたら
お盆の送り火のやり方

◇お盆の迎え火は、最終日の送り盆8月15日の夕方頃に行います
全国的な月遅れ盆でも、4日間日程でしたら最終日の送り盆は8月16日になりますね。いずれにしても最終日の夕方頃が、お盆の送り火を焚く時間の目安です。
・焙烙にオガラを重ねてセットする
・盆提灯の火を、オガラに付ける
・送り火を焚く
・盆提灯の灯りを消す
お盆の送り火のやり方は、迎え火とは反対の手順です。
お盆の迎え火では、迎え火の火を盆提灯に付けますが、お盆の送り火では反対に、盆提灯の火を送り火のオガラに着火します。
ただし、前述したように電気式の盆提灯では、その限りではありません。
お盆の送り火を終えたら
◇お盆の送り火を終えたら、すぐに片付けをします
お盆の飾りつけをいつまでもそのままにしていると、ご先祖様が「後ろ髪を引かれて」あの世へ帰れないとされるため、送り火を終えたらすぐに片付けましょう。
ただし、お盆の送り火自体は夕方以降から行います。
送り火が映えることはもちろん、ご先祖様をできるだけ長い時間おもてなしするために、最終日の夕方以降、日が暮れてから迎え火を焚くためです。
また昔のお盆では、お盆の送り火で盆提灯など、お盆で使用した飾り物や供物を焚きました。
オガラはあの世へ供物を届けてくれますから、お供え物など、ご先祖様に届けたい時にも、お盆の送り火で焚く地域もあります。
・お盆とは、なにをする?子どもにも分かるお盆の意味や由来とは。盆踊り大会はなぜ行う?
浄土真宗の場合
マンションでの安全な、送り火・迎え火の代用方法は?

マンションやアパートなどの集合住宅では、火災報知器の作動や近隣トラブルを避けるため、お盆の迎え火や送り火をそのままの形で行うのが難しいケースもあります。
ですが、火を使わずともご先祖様を丁寧に迎え、見送ることは可能です。ここでは、マンションでも実践できる迎え火・送り火の代用方法をご紹介します。
地域により、集合住宅では火を焚かない家庭が増えています
現代の集合住宅では、防災上の理由からベランダや共用スペースでの火気使用が禁止されている場合がほとんどです。そのため、伝統的な迎え火・送り火の方法に代わって、火を使わない代用方法が広く取り入れられています。
お盆の意味や供養の心を大切にしながら、現代の住環境でも無理なく取り入れられる方法を工夫する人が増えています。以下に代表的な例を紹介します。
● 屋内や玄関周辺で使える簡易線香セット(※規約確認が必要)
● オガラや焙烙を飾るだけで迎え火・送り火を象徴する方法
火を使わなくても、ご先祖様への思いを込めた迎え方であれば、十分に供養になります。暮らしに合わせた形で、心のこもったお迎えができると良いですね。
時間を気にせず、電気式ロウソクや提灯で代用する方法
もっとも一般的な代替方法が、電気式のロウソクや盆提灯を使用する方法です。火を使わないため安全性が高く、集合住宅や高層マンションでも安心して使えます。
設置する場所については、住環境やルールをふまえた上で、以下のような工夫がされています。
● 可能であれば、玄関先に電池式の盆提灯を飾る
● マンション1階や管理ルールに従って、控えめにベランダに配置するケースも
電気式の光でも、「ここに家がありますよ」という目印にはなります。気持ちを込めて飾ることで、迎え火・送り火の意味合いはしっかり保たれるでしょう。
火を使わない迎え火・送り火のおすすめ代用品
火の使用が難しい環境でも、お盆の迎え火・送り火を表現する方法は複数あります。伝統にこだわりすぎず、現代の住環境に合わせた工夫を取り入れてみましょう。
具体的に取り入れやすい代用品には、以下のようなものがあります。
● LED盆提灯(室内用・屋外用など多数)
● 火を付けずに飾るだけのオガラと焙烙のセット
● お線香を室内用香炉に焚いて、ご先祖様を迎える
こうした代用品を組み合わせれば、形式にこだわらずともご先祖様の供養を十分に行うことができます。
「本来の迎え火・送り火」を守るための心がけ
迎え火・送り火は、あくまでご先祖様を「お迎えし、お見送りする」という象徴的な行為です。火を使うかどうかよりも、ご先祖様を敬い、家族でその存在を思い返す心が何より大切です。
たとえ代用品であっても、気持ちを込めて飾り、静かな時間に手を合わせれば、それは立派な供養になります。
● 家族でお仏壇に手を合わせる時間を持つことが大切
● 可能なら精霊馬やお供え物も一緒に用意すると丁寧
形式にとらわれすぎず、今の暮らしに合ったやり方で、心を込めたお盆を迎えましょう。
お盆は迎え火で始まり、送り火で終わります

お盆は迎え火・送り火で区切りとなるため、全国的なお盆行事でも大切な役割を果たします。
またお盆の最終日となる8月15日・16日頃には、全国的にご先祖様や精霊を送り出す伝統行事が、各地で行われることでしょう。
なかでも精霊送りとも言われる京都府の五山送り火などは有名ですね。
本記事を参考にお盆の迎え火・送り火の意味を理解しながら、伝統行事に参加するのも良いかもしれません。
・【2025年度版】全国お盆イベントはどこ行く?五山の送り火、精霊流しはいつ・どこ?
お電話でも受け付けております
















