
永代供養の領収書は発行してもらえる?お布施も納めた場合は?

「永代供養の領収書は発行してもらえる?」
「永代供養料の相場が知りたい」
「支払うときのマナーや注意点は?」
このように、永代供養料を支払う際の領収書の発行や、費用の相場について疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、永代供養料の領収書についての基本的なことや支払うときに気をつける点、永代供養の費用に関するポイントを解説します。
この記事を読むことで、永代供養料の領収書を発行してもらう際の知識や支払い方、費用の詳細を把握することができます。その知識をもとに、安心して永代供養を依頼できるようになり、後から契約に関するトラブルを回避しやすくなるでしょう。
永代供養の依頼を考えている方は、是非この記事を参考にしてください。
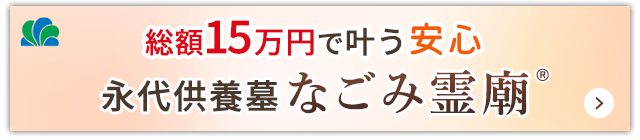
永代供養の領収書は発行してもらえる?
永代供養における領収書に関するポイント

永代供養の費用を支払う際は、寺院や霊園によって支払い方法や領収書の取り扱いが異なります。まずは契約前に、どのような形で費用を支払い、領収書を受け取れるかを事前に確認しておくと安心です。
また、後々のトラブルや確認のためにも、費用の支払い後には必ず領収書を受け取って保管しておくことをおすすめします。
なお、永代供養料とは別に、お布施(僧侶への謝礼など)を渡す場合もあります。お布施は宗教行為に対する感謝の気持ちとして渡されるものであるため、必ずしも領収書が発行されるとは限りません。必要があれば、「受領証」や「記録のための書面」をお願いできるかどうか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
領収書には収入印紙はいらない
永代供養料を支払った際の領収書については、発行主体が宗教法人であり、供養やお布施などの宗教活動に関連する金銭の受領書であれば、印紙税法上の非課税文書に該当するため、収入印紙は不要です。
一方で、墓所の永代使用に関する契約書は、土地の賃借権に関する契約書として印紙税の課税対象となり、契約金額に応じた収入印紙が必要になる場合があります。
なお、印紙税の取り扱いは、発行主体が一般法人か宗教法人か、契約内容が営業行為にあたるかどうかにより異なるため、不明な場合は事前に税理士や寺院・霊園に確認しておくと安心です。
お布施を行った場合も領収書を発行できるか確認する
お布施は、読経や供養をお願いした際に、その感謝の気持ちとして僧侶にお渡しする謝礼です。
お布施は宗教行為に対する謝礼であり、基本的に課税対象ではありません。
領収書については、宗教法人(お寺)に発行義務はありませんが、依頼すれば「受領証」などの形で発行してもらえる場合もあります。
ただし、領収書が発行されたとしても、すべてのお布施が相続税の控除対象になるわけではありません。
葬儀や火葬など、**直接的に葬儀に関係するお布施(読経料・戒名料など)**についてのみ、相続税の葬式費用として控除の対象となることがあります。
控除の可否は支出内容によって異なるため、判断が難しい場合は税理士など専門家に確認するのが確実です。
永代供養やお布施の領収書を発行できないときの対処法

領収書の発行はお寺や霊園の義務ではなく、契約書自体が用意されていない場合もあります。永代供養は歴史が浅く、口頭での契約も可能であるためです。
もし契約書の発行がない場合は、自身で作成できます。その際は、委託する側と受託する側の署名と捺印の欄を設ける必要があります。
しかし、契約書の発行も難しい場合はどのようにすればよいのでしょうか。下記の方法を参考にしてください。
支払いの記録をしっかり残す
お寺や霊園などの委託先に領収書の発行を依頼するのが比較的スムーズですが、事情により用意されない場合もあるでしょう。日頃からお世話になるお寺に対しては、言いにくいケースもあります。
この場合は、どれだけ支払ったかという記録をしっかりと残しておくことが大切です。支払いの内訳を残しておくことで、トラブルや行き違いを防ぐことができます。
自治体によるお墓の条例が変わることがあるため、文書にして契約状況を明白なものにしておくことが有効な手段といえます。
お布施の内容をメモしておく
お寺にとってお布施は読経などの対しての謝礼であり、宗教事業と位置づけされていないため、領収書の発行義務がありません。実際に、領収書を出してくれるお寺は少ない傾向があります。
領収書がない場合も内容をメモしておくことで、控除の対象となります。この場合は、お寺の名前、住所、連絡先、支払い受領日、支払いの内容、金額を忘れず残しておきましょう。
永代供養の領収書に関する知識とあわせて覚えたいこと

永代供養料を渡すときには、どのような点に気をつける必要があるでしょうか。こちらでは、永代供養料を用意するために必要なものや書き方、渡すときのマナーについて紹介します。
現金での支払いの際に必要な準備
受託側により支払いの方法が異なるため、先に確認しておくことをおすすめします。ここでは、永代供養料を現金で支払うときに必要な準備について解説します。
用意するものは、現金を入れるのし袋、お札を包む半紙、筆ペン、水引きの4点です。のし袋の用意がない場合、白い無地のものであれば封筒でも構いません。また不祝儀でないため、筆ペンは濃黒のものがよいでしょう。
表書きの書き方
表書きには、のし袋か封筒の中央上側に縦書きで「永代供養料」と書き、その下に依頼者のフルネームか遺族代表として◯◯家と記載しましょう。
また、お札は半紙で包みますが、表面には金額を旧漢字で書きます。一万円の場合は「金壱萬園也」となるように、「金」+「金額」+「也」と記しましょう。半紙の裏面は名前を書きますが、お返しがある香典とは異なるため、住所の記載は不要です。
永代供養料を支払うときの方法やタイミング
支払いの方法は、通常ご僧侶から説明があるため、契約前によく確認しておきましょう。現金で支払う準備をしていても、振り込みなど他の方法を指定される可能性があります。
また、お布施は多くの場合納骨後や法要後にお渡しします。忙しい儀式の前は避けて、落ち着いたタイミングでお渡しするのがおすすめです。
永代供養料を支払う際のマナー
のし袋に入れるお札は新札でも構いません。香典のように不祝儀の場合は、不幸を予想していた印象を与えないよう新札を避けることがマナーですが、お布施は不祝儀ではないため、新札でもよいとされています。
また、お布施は袱紗(ふくさ)から取り出して渡します。袱紗とは長方形の布の入れ物で、お布施や香典を包むときに用いられています。直接手渡しするのではなく、お盆に乗せて差し出しましょう。
トラブルを避けるため契約書が必要
永代供養はお寺や霊園で内容が異なり、また子孫や後継者の代まで長く続く可能性があります。繰り返しになりますが、依頼する際はトラブルを避けるためにも契約書が必要です。
契約書は、契約後に受託者と依頼者のあいだで齟齬が生じた場合に大切な書類となります。契約書の内容には、しっかりと目を通しておきましょう。
契約項目には、お墓の種類や永代の期間があります。お墓には一般的なお墓と、ひとつのお墓に他の人の遺骨をまとめて納骨する合祀墓があります。また期間については、年忌ごとに分けられているため、依頼者が契約時に選択します。
なお、契約後の解約については、依頼したときの契約書に「解約できる」旨の内容がある場合は可能です。ただし合祀墓の場合は、他の人の遺骨まで取り出すことが不可能なため、解約することができません。
・永代供養で起こりうるトラブルとは?問題が起きないためのポイントを解説
永代供養の費用に関するポイント

永代供養は、費用の安さがメリットにあげられています。それでは、具体的な費用はどのくらいなのでしょうか。
ここからは、一般的な相場や費用の内訳なども併せて解説します。
永代供養の費用相場
永代供養料はお墓の種類で変わります。一般的な個人墓の場合は70~150万円ほど、合祀墓で10~30万円ほどが相場です。
また、石碑などに期間を定めて納骨する集合墓は30~70万円ほどでしょう。ちなみに、お布施は3~5万円ほどが相場です。
・永代供養の費用について 費用の内訳・相場と失敗しない選び方も紹介
永代供養にかかる費用項目
永代供養にかかる費用には、「お墓の管理費にあたる永代供養料」「遺骨を納める納骨料」「戒名などを彫刻する刻字料」があります。その他、付属契約を選択する場合はプラスアルファの費用が必要です。
永代供養料は相続税の控除対象外
残念ながら、永代供養料は葬儀費用にあたりません。遺産総額に含まれるため、相続税の控除の対象外となります。葬儀のように、お寺の事業にかかる費用と考えられていないことが要因といえます。
永代供養における領収書関連について把握しておきましょう

この記事では、永代供養の領収書や支払い方法、相場、マナーについて解説しました。
永代供養は、寺院や霊園がご遺族に代わって継続的に供養をおこなう仕組みで、現代のライフスタイルに合わせて広がりつつある供養のかたちです。
運営主体やプラン内容によって費用や手続きが大きく異なるため、契約前にはしっかりと比較検討し、納得できる方法を選ぶことが大切です。
大切な方のご供養を託すからこそ、十分に調べて後悔のない選択をしましょう。
お電話でも受け付けております
















