
納骨式っていつ何をするの?必要な準備と当日の流れを詳しく紹介

「納骨式ってどのようなことをするの?」
「納骨式を行う時期や費用を知りたい」
「納骨式で準備する物やマナーはある?」
このように、納骨式の全体の内容について疑問を感じているのではないでしょうか。とくに、初めて納骨式を行う方は不安や迷いがあるでしょう。
この記事では、納骨式とはどのような儀式なのか、ふさわしい時期や儀式の流れ、費用などについて解説します。儀式のマナーなど社会人として気になる情報もあるため、納骨式のことを全く知らない方にとって有益な記事内容となっています。
記事を読むことで、納骨式の基本から詳しい情報を入手できるため、スムーズに儀式を終えることができるでしょう。また、納骨式について詳しくなるため今後予定があっても怖くありません。
納骨式について詳しく追求したい方や勉強したい方は、ぜひこの記事を参考にして下さい。
納骨式とは

納骨式とは、故人の遺骨をお墓などに埋葬する儀式です。人が亡くなると葬儀を行い、その後火葬して拾骨します。遺骨は、故人を弔うために埋葬して供養することが一般的です。埋葬先にはお墓や納骨堂などがあります。
儀式の具体的な内容や詳細について知らない方は、全体の流れを知っておきましょう。
納骨式を行うのはいつ?
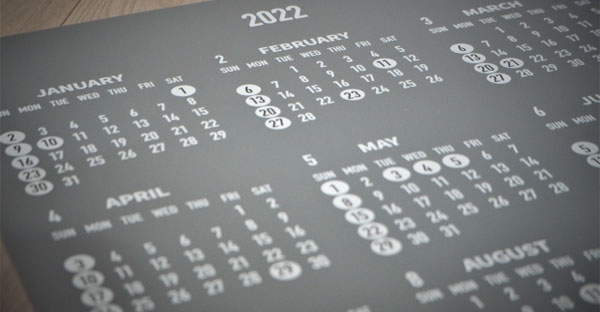
納骨式には、この日でなければならないという決まりがありません。遺族の意向で行う儀式であるため、日程やスケジュールは家庭環境によって様々です。
納骨式は、一般的に葬儀が落ち着いた頃に行う傾向があります。例えば、四十九日法要のときや、お盆などの区切りの時期などです。逆に、火葬した後すぐに納骨する場合もあるでしょう。
遺族が親族や知人友人と日程を調整して行う儀式であるため、家庭環境によりスケジュールが変わりますが、よく行われるタイミングをご紹介するため参考にして下さい。
四十九日の法要をするとき
納骨式の時期として、四十九日法要のときがあります。四十九日法要とは、逝去した日から四十九日目の日を指します。仏式では、故人は法要を終えると冥界に向かうとされているため、この世に魂がある最後の日といえるでしょう。
遺族に所有するお墓がある場合は、この四十九日法要のタイミングで納骨式を行う傾向があります。お墓がない場合は、法要の日に間に合わないケースがほとんどのため、別のタイミングで行います。
百箇日の法要をするとき
百箇日とは、故人が亡くなって百日目に行う法要です。四十九日法要後に迎える儀式であり、一般的に納骨式のタイミングとされています。
百箇日にあまり馴染みのない方もいるでしょうが、「卒哭忌(そっこくき)」とも呼ばれていて、亡き故人への失意の思いに別れを告げる意味を持つ法要です。儀式では遺族が集まり、僧侶に読経を読んでいただきます。
遺族が四十九日法要で納骨できなかった場合に、百箇日を区切りの時期と考えて納骨式を行うのです。
新盆を迎えるとき
新盆も納骨式が行われるタイミングです。新盆は初盆とも呼ばれていて、故人が逝去してから初めてのお盆を指します。親族が集まり故人を供養する代表的な儀式の一つです。
遺族の都合によりますが、忌明け後に初盆を迎えることが通常の流れであるため、四十九日法要前に新盆を迎えた場合は、翌年に行うことが一般的です。
節目の儀式であるため、日程が明確でないときはお寺など周囲に尋ねてみることが良いでしょう。
一周忌の法要をするとき
故人が亡くなって一年目の法要を一周忌と言います。このタイミングで納骨式を行うケースもあります。
仏式では、亡くなって一年間を喪中とします。遺族が故人に哀悼の気持ちを表すための期間です。喪明けとなる一周忌法要は納骨式にふさわしいタイミングでしょう。
ちなみに、喪中は遺族が慎む期間であるため慶事などは避けなければなりません。お祝い事は喪明けに行うことが基本です。
三周忌の法要をするとき
三回忌法要は故人が亡くなって、満二年目に行う法要です。三回忌までに納骨することが通常の流れとされています。
遺骨を手放し埋葬することは悲しいと感じる場合もあるでしょう。しかし、納骨には故人の冥福を祈る最後の儀式の意味があるため、良いタイミングで行うことが遺族の務めとする考え方もあります。故人の魂をお墓に宿すことが本当の供養となるのです。
納骨式にかかる費用は?

こちらでは、納骨式にかかる費用を項目別に分けてご紹介します。
内訳として、儀式やお寺にかかる費用や作業費などがあります。新しくお墓を建てるときは、この金額にプラス200万円ほどかかるでしょう。お墓を所有しているときの費用は、高い場合で10万円ほどが相場です。
お布施
お布施とは、お寺の僧侶にお勤めいただく謝礼として遺族が差し出す金銭です。納骨式の際は、僧侶をお招きして行うため渡すことがマナーとされています。
お布施の金額に決まりはないため、遺族の感謝の思いを金額にすることが基本ですが、一般的な相場費用は3~5万円ほどでしょう。
また、別途お車代として僧侶が会場までの道のりに交通機関を利用したときは、5,000円~10,000円ほど差し出す場合があります。
会食費
住まいの地域によって異なりますが、納骨式の終了後に会食を行う場合があります。故人の納骨式のために参列いただいたお礼として食事でもてなすのです。また、生前の思い出を語り合う場として開かれます。
会食費は一人あたり5千~1万円ほどが目安です。僧侶が会食を欠席した場合は、お布施とは別でお膳料として5千~1万円ほど差し出します。
お供え物や供花
納骨式では、お供え物や供花の準備をします。遺族は祭壇に供えるために事前の手配が必要でしょう。
お供え物には線香やお花、ロウソクなどがありますが、費用は全部で5千~1万円ほどでしょう。他にお菓子や酒、果物などがあります。
宗派や地域によってお酒のお供えを禁止していることがあるため、注意して下さい。あらかじめお寺などに聞いておくと良いでしょう。
彫刻代
埋葬するお墓の墓誌や墓石に故人の名前を彫刻することが一般的です。名前の他に戒名や生年月日などがあります。こちらも費用が発生しますが、相場は約4万円前後でしょう。彫刻する文字の数で前後することや、依頼する業者によって差があり一律ではありません。
なお、墓誌や墓石には白色で彫刻してもらいますが、最初に赤色を用いて彫刻されている場合もあります。
塔婆を立てる費用
塔婆(とうば)とは、細長い形で木の板を使用した物でお墓の後ろに立てられる仏具です。短い物で50センチ、長い物で150センチほどあります。
「卒塔婆(そとうば)」とも呼ばれていて、古来のお釈迦様の時代には供養の象徴として考えられていました。
お寺によりますが、費用は塔婆一本あたり3,000~5,000円ほどです。高い場合は1万円ほどになることもあります。
法要を行う部屋の使用料
納骨作業を行うときの費用
遺骨を納骨する際は、納骨室の入り口を開ける作業が必要です。入り口は石で閉ざされているため、石材店などの業者に依頼します。
この場合の費用は、安くて5千円ほどでしょう。お墓の形態などから高額な作業費用が発生するケースがあるため、契約する前に見積もりを出してもらいましょう。
なお、納骨室の入り口を遺族が開けられるタイプのお墓の場合は業者に依頼する必要がないため、納骨作業の費用は発生しません。
納骨式を行う前の準備

遺族は、納骨式の準備が必要です。円滑に儀式を行うためにも準備をしっかりしておきましょう。
遺骨を埋葬するときは、新しいお墓を決めることや役所での書類の手続きが必要です。また、儀式の参列人数を把握しておくことも大切な準備の一つでしょう。これから、納骨式を行う前の準備について詳しく解説します。
納骨する場所を決める
まず、故人の納骨を埋葬する新しい供養先を決めます。所有するお墓がなく、新しくお墓を構える場合は、あらかじめお寺や霊園をいくつか見学して決めると良いでしょう。
納骨式にお墓が間に合わないときは、葬祭社や納骨堂など遺骨を一時的に預けられる施設を利用しましょう。突然の訃報で困った遺族のための救済サービス場であり、預骨とも呼ばれています。
埋葬許可証を準備する
お墓の埋葬には「埋葬許可証」という書類が必要です。「埋葬許可証」は、お墓を管理するお寺へ提出することが定められています。
「埋葬許可証」は、遺骨を火葬すると火葬場から受け取ることができます。お寺へ提出するまで紛失しないように保管しておきましょう。
石材店に字の刻印をお願いする
お墓へ故人の名前などを彫刻しますが、納骨前に終えておく必要があります。刻印は字のバランスなどを調整するなどの繊細な作業があるため、長期間かかる可能性もあります。早めに石材店を選定しておきましょう。
また、納骨式の際に納骨室を開閉する作業の依頼も同時に行っておきましょう。自分で開くタイプの納骨室の場合は依頼する必要がありません。
参列する人へ連絡をする
親族や知人友人など、納骨式に参列する人へ連絡しましょう。参列者に決まった定めはありません。少人数の場合は電話などで連絡しますが、大人数の場合は招待状を出しましょう。
招待状には、納骨式日時やお墓の住所、集まる場所、地図、差出人の連絡先などを記載します。その際、参加人数を把握するため返信用のはがきを添えて送りましょう。
お供えする物を準備する
お供え物にはお花や果物、菓子などがあります。お花の種類はとくに決まりがありませんが、トゲのあるバラや花びらが取れやすい物は縁起が悪いため避けましょう。
一般的に季節の果物や賞味期限の長い菓子などが良いとされていますが、地域や宗派により決まりがあるときは従う必要があるためお寺などに確認して下さい。他には線香やロウソクなどがあります。
料理などの準備をする
納骨式の後で会食を予定している場合は、料理などの手配をしておく必要があるでしょう。儀式に何人ほど参列するのか把握できたら、お店を探して席や料理の予約をします。
会食には、席順があるため注意が必要です。部屋の上座に僧侶の席を設けましょう。その隣に施主、参列者が並んで親族は下座に座るようにセッティングします。
名義変更の手続きをする
お墓を所有すると管理料を支払わなければなりません。故人がお墓の名義人だった場合は名義変更して、誰が引き継ぐのか明確にしておく必要があるでしょう。
名義変更の手続きは、お墓を管理するお寺で行います。必要書類を一式揃えて提出し速やかに変更手続きを終えましょう。
納骨式当日に必要な物

納骨式当日必要な物があるため、遺族は前日までに用意をしておく必要があるでしょう。忘れるなどして、納骨式ができなかったという事態は避けなければなりません。主に、金銭的な物や証明書など、急に用意できない物もあるため、余裕のあるときに揃えておきましょう。
お布施
お布施は、僧侶への感謝の印を表した大切な物であるため、失礼のないように差し出しましょう。
お布施は、無地の白い封筒に包みます。このとき、封筒は郵便番号欄が記載されていないデザインを選びましょう。
表書きには「御布施」と記載して、差出人の名前か遺族代表として◯◯家などと書くことがマナーとされています。裏書きには、金額や差出人の住所、連絡先を記載しましょう。
塔婆
墓地使用許可証
納骨式の流れは?

納骨式の流れを把握しておくと、当日落ち着いた気持ちで参列できます。心に余裕を持って対応するために、納骨式の全体の流れを掴んでおきましょう。
遺骨の埋葬時には、僧侶による二度の読経があります。故人が死後の世界で迷うことがないように冥福を祈りましょう。
納骨式と同日に年忌法要を行う場合は、全ての儀式を終えた後に会食をすることが一般的とされています。
参列者へお礼を言う
はじめに、お墓が正しく準備できているかを確認しましょう。墓前に立ち、お供え物や線香、ロウソクなど儀式に必要な物を整えます。
次に、施主が参列いただいた方に対して挨拶をします。足を運んでくれた親族や知人友人、僧侶に向けて感謝の気持ちを述べましょう。同時に、生前受けたご厚誼のお礼や、遺族としての心情、会食の案内なども伝えます。
僧侶にお経を読んでもらう
挨拶を終えると、僧侶に読経をお勤めいただきます。通常は、お墓の前でそのまま読経を行いますが、室内に場所を変えて行う場合もあるでしょう。故人の冥福を祈り供養します。
納骨を行う
一度目の読経が終わると遺骨をお墓に納めます。納骨室の開閉は、石材店の方にお任せするか、遺族が入り口を開けます。お墓のタイプによって異なるため、それぞれ適切な対応をしましょう。
骨壷を納骨室に納めますが、地域によっては骨壷から一度遺骨を取り出して、埋葬するケースがあります。自分の住まいの風習をよく確認しておきましょう。その際、納骨室の入り口側に新しい遺骨がくるように納めます。
再び僧侶にお経を読んでもらう
再度、僧侶にお経を読んでいただきます。二度目の読経には「納骨経」といってお墓に故人の魂を宿して供養するという意味合いがあります。また、浄土真宗では法要を同日に行う場合があり、読経も場面ごとで異なるでしょう。
焼香を行う
読経中は僧侶の指示で、焼香を行います。指示があるまで待ち、勝手に動かないようにしましょう。焼香は、施主、親族、一般参列者の順番で行います。宗派によりますが、時間は30~1時間が目安でしょう。
会食を行う
儀式が終わると遺族をはじめ知人や友人、僧侶など、参列者を招いて会食をします。お店に到着したら、施主は開式の挨拶をします。このとき、お酒を器に注いで故人の位牌に向けておくことがマナーです。
挨拶では、参列いただいたお礼の気持ちや故人の生前の気持ち、遺族の今後の決意などを述べます。長々とした挨拶は避けて2分以内に済ませることが良いでしょう。
会食の場では、宴会のように大声を出すことや騒ぐことはタブーとされています。声のトーンを落として故人との生前の思い出を語りましょう。
施主は、閉式の挨拶を行います。再度お礼などを丁寧に述べて、参列いただいた方に返礼品を渡しましょう。
納骨式のマナーは?

納骨式のときはどのようなマナーに気をつけたら良いのでしょうか。静粛な儀式の場で、参列いただいた方々に対して失礼な態度を取らないように十分気をつけましょう。
こちらでは、迷いやすい香典の書き方や身出しなみのマナーにポイントを当ててご紹介します。礼節を重んじて儀式に臨みましょう。
四十九日前と後では香典の表書きが違う
納骨式が四十九日以前か以後かで香典の書き方が異なります。大人として恥ずかしくないように、ポイントを押さえておきましょう。
一般的に、故人が亡くなってから四十九日法要までは「御霊前」と書きます。全ての宗派で使用できるため、故人の宗派が不明なときは「御霊前」が良いでしょう。四十九日後は、故人が仏式の場合「御仏前」の使用がマナーです。他には「御香料」「御香典」などがあります。
一周忌を迎えるまではブラックフォーマルで参列する
納骨式の服装は行うタイミングによって異なります。親族は、一周忌を迎えるまではブラックフォーマルなどの喪服を着用しましょう。
とくに、四十九日法要までは親族以外の参列者も黒のスーツやワンピースなどがマナーとされています。男性の場合は、ネクタイや靴なども黒で統一して、女性の場合はストッキングや靴を黒で揃えましょう。服装に迷うときは周囲に聞くなどして合わせることが重要です。
納骨はしなくてもいい?

納骨をしない場合はどのようになるのでしょうか。故人と離れることが寂しいなどの理由で納骨になかなか踏み切れない場合があります。
納骨をせず手元に遺骨を置いておくことは、法律違反にはなりません。納骨までの期間などは定められていませんが、将来供養する後継人がいなくなる可能性があることや、遺骨にカビが生えるケースがあるため、いずれは供養するべきでしょう。
供養方法には、手元供養として自宅で管理することや、遺骨を納めるための骨壷をインテリア風の物にして部屋に飾るなどがあります。
永代供養の場合

新しい納骨先に永代供養を選択する方法があります。永代供養では、お寺や霊園にお墓の供養を依頼できます。
生活や家庭環境の変化から、お墓の後継者がいない方や、自分でお墓の管理ができない方から注目されています。
屋内墓地の場合は骨壺安置が多い
永代供養には様々な納骨方法があり、希望のタイプを選択することが可能です。屋内墓地の場合は、ロッカー型や個別部屋のような霊廟型、機械式納骨堂など遺骨を骨壷のままで安置する方法があります。これらは一定の期間を個別で供養できることがメリットといえます。
最終的には知らない人と埋葬される
永代供養は一定の期間が過ぎると、他の人の遺骨が埋葬されている場所に合祀されます。そのため、後から手元供養や分骨したい場合に遺骨を取り出すことができません。お寺や霊園によりますが、三十三回忌のタイミングで合祀する傾向がみられます。
樹木葬というスタイルもある
樹木葬とは、樹木や花などの自然が広がるスペースに納骨する方法です。モニュメントの下に遺骨を埋葬するシステムで、ガーデン風の物から芝生スタイル、庭園風など様々あります。
こちらも、お墓の管理が依頼できるため子孫がいない方や、一時的に納骨したい方から注目されています。
宗派の異なるお墓に納骨したい場合

故人が生前に信仰していた宗派と異なるお墓に納骨する場合は、どのようにすれば良いのでしょうか。この場合は、宗派についてくくりがない霊園であれば可能です。
ただし、お寺に入る場合、直前の連絡は、断られるケースもあるため、お通夜やお葬式の時点で連絡をして事前に相談しておくことが一般的な決め方でしょう。
納骨式に必要な準備や流れを把握しておこう

この記事では、納骨式をスムーズに行うための準備や全体の流れをご紹介しました。儀式には様々な工程があることや、事前にしておかなければならない手続きがあるため、ひとつひとつ確認しながら慎重に進めて下さい。
また、宗派による考え方や地域の違いで儀式内容に差が出るため、十分に下調べをしておく必要があります。
故人へ哀悼の意を表すためにも、細かい内容は親族間で相談しながらしっかりと決めて、気持ちにゆとりがある状態で臨みましょう。
お電話でも受け付けております















