
自分で墓じまいをする9つの手順と注意点とは?必要な準備・書類と行政手続きも解説

「墓じまいって何をするの?」
「自分で墓じまいをする時の手順が知りたい」
「墓じまいを検討する上で気をつけるポイントは?」
このように、墓じまいに対して不安や疑問を感じている人は多いのではないでしょうか。
近年の生活変化の影響で、墓じまいを検討している人が増えています。
本記事では、自分で墓じまいをする時の具体的な手順や流れ、書類の手続き方法、注意する点などを紹介します。
この記事を読むことで、契約の手続きから改葬先で納骨するまでの手順をスムーズに終えられるため、トラブルや問題を未然に防ぐことが可能でしょう。
現在自分で墓じまいを考えている方、これから検討したい方は、この記事の内容を参考にしてください。
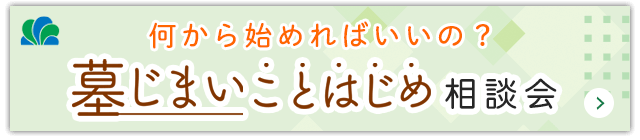
墓じまいとは

近年、生活の変化により「自分でお墓の管理ができない」「継承者がいない」など、ご先祖様の供養ができない家庭が増えている傾向にあります。
お墓を放置することで、罪悪感や精神的な負担を抱えている方も多いでしょう。また、無縁仏を避けるために墓じまいを選択するケースもあります。
墓じまいと改葬の違い
墓じまいはお墓で供養する形式を終わらせること、改葬はお墓の引っ越しをすることで、お墓で供養する形式が終わるわけではないという違いがあります。
そのため、墓じまいをしたからといって供養すること自体を終わらせたという意味ではありません。年齢や体力的な面、または交通手段などの都合でお墓に行くことが難しくなった場合などに墓じまいを考える方もいらっしゃるでしょう。
出典|参照:墓地、埋葬等に関する法律|厚生労働省
・墓じまい・改葬の方法とは?違いや遺骨を納骨する場所についても紹介
自分で墓じまいをする前に必要な準備

墓じまいは、方法や費用・流れをしっかりと理解した上で進めていく必要があります。
墓じまいをする場合、中に納めている遺骨の保管方法などを考えなければいけません。費用や流れが地域や霊園、お寺によって違う場合があるためきちんと確認しておきましょう。
事前に親族とよく相談して理解を得ておく
墓じまいすることに他の親族が納得しない恐れもあるため、事前に理解を得ておくことが重要です。
他の親族が遠方に住んでいて、実質お墓を管理しているのが自分だけだったとしても、親族には墓じまいの相談をしておきましょう。
現在の墓地管理者や菩提寺の理解も必要
墓じまいには、墓地管理者や菩提寺の理解が必要です。
墓じまいをする際には、魂を抜く特別な供養を行います。そのため、菩提寺には墓じまいを考え始めた段階で相談しておくと良いでしょう。
遺骨の新しい供養方法・受け入れ先を決める
墓じまいした後で遺骨をどのように供養するかをあらかじめ決めておくようにしましょう。その方法としては、「永代供養墓」「納骨堂」「樹木葬」「散骨」などがあります。
また、お墓の中に長年保管していた遺骨は、カビなどの菌類に侵されている可能性があります。お手入れも含めて、新しい遺骨の供養方法を考えると良いでしょう。
・墓じまい後の遺骨の供養方法は?取り出す際の注意点や処分方法も解説
自分で墓じまいをする9つの手順

実際に、自分で墓じまいをする際には、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか。
ここでは、具体的な9つの項目を流れに沿って解説します。墓じまいについてお悩みの方は、参考にしてください。
・墓じまいの手続きって?改葬許可申請についてや大まかな7つの手順について紹介
1:親族と相談する
はじめに、墓じまいすることを親族に相談します。墓じまいには高額な費用が掛かるため、独断で行った場合に、後から親族間のトラブルに発展するケースも少なくありません。
また、現在のお墓の管理方法を続けたいといった考え方を持つ方もいます。墓じまいをすることで、親族や関係者がお墓参りする機会をなくしてしまうことも、頭に入れておかなければなりません。そのため、事前に親族全員の了承を得ることは必須といえるでしょう。
・永代供養のお墓参りの流れとは?お供え物などの注意点や法事についても解説
2:現在の墓地管理者・お寺と相談する
所有するお墓の管理者への相談は、忘れずに行いましょう。自分で墓じまいをする上で、管理者の了承が得られないと手続きを進められません。
また、自分が檀家の場合は離断する形となるため、お寺の収入源が減り運営にも大きく関わってきます。お世話になっているお寺と今後の関係を円満にするためにも、墓じまいする旨を事前に伝えておきましょう。
3:新しい供養方法・受け入れ先を決める
親族・お墓の管理者への事前連絡を終えたら、新しい供養先を決めます。常に霊園に空き状況があるかは定かでないため、あらかじめ候補を絞っておくとよいでしょう。
また、お墓の種類や掛かる費用など、具体的なイメージがあると素早く決めることができます。お墓を管轄する地域によっては、新しいお墓が決定していることが手続きの条件になるケースもあるため注意が必要です。
・お墓を購入したい際はどうすればいいのか?気を付けたい注意点もあわせて紹介
4:墓石の解体を頼む石材店を決めておく
墓石の解体・撤去を依頼する業者を決めます。一般的に石材店に依頼することになるでしょう。地域によっては、申請書類に石材店の情報の記載欄を設けている場合があります。
また、解体・撤去費用が高額になる場合があるため、契約前に見積もりを出してもらいましょう。できれば複数の石材店に依頼して比較すると、金額の差がよくわかります。施設によっては石材店が指定されていることもあるため、お墓の管理者に確認しましょう。
5:墓じまいに必要な行政手続きをする
お墓を引っ越しする許可を受けるために、所有するお墓を管轄する自治体で書類の手続きをします。墓じまいには法的な手続きが必要なため、自治体への申請をしなければなりません。
許可の証明である「改葬許可証」を発行してもらうために、窓口で「改葬許可申請書」を受け取り手続きをしましょう。
出典|参照:墓地、埋葬等に関する法律|厚生労働省
6:閉眼供養をして遺骨を取り出す
「閉眼供養(へいがんくよう)」とは、仏式で墓じまいの際に行う儀式です。お墓に眠る故人やご先祖の魂を通常の状態に戻す意味があり、「お性根抜き(おしょうねぬき)」「魂抜き(たましいぬき)」とも呼ばれています。
お世話になっている菩提寺があればそちらに依頼でき、ない場合は近くのお寺に手配することも可能です。儀式ではお寺のご僧侶による読経が行われます。儀式は事前に行えるため、墓石の解体・撤去工事の当日ではなく、1週間ほど前に済ませることもできます。
・永代供養でも読経は必要?お布施の費用相場や納める方法もあわせて紹介
7:石材店に墓石を解体撤去してもらう
墓石の解体・撤去の工事を行います。作業を確認したい人は現場で立ち会うことが可能です。
地域や石材店によって変わりますが、一般的なお墓のサイズで相場は10万円前後と言われています。墓石を置いていた土地は更地にして返還するため、業者選びは慎重に行いましょう。
8:原状回復した墓地を返還する
石材店による工事を終えると、墓地を更地にして元のお墓の管理者へ返還します。不完全な状態で返還すると後からトラブルに繋がる恐れがあるため、最後によく確認しておきましょう。
9:新しい受け入れ先で遺骨を供養する
墓じまいが終わると、新しい改葬先に遺骨を納めます。遺骨を運ぶ際、自分の車やタクシーを利用する場合は骨壷が壊れないように注意することが必要です。
また、公共交通機関を利用する際は、他の乗客に配慮しながら運びます。骨壷用の持ち運びバッグなどもあるため、状況に応じて使うこともできるでしょう。飛行機に持ち込む場合は、各航空会社で定められたルールを順守してください。
・納骨する場所別骨壷のサイズとは?検討すべきことと相場や種類など解説
自分で墓じまいをする時に必要な書類と行政手続きの流れ

自分で墓じまいをするとなると、その複雑な手順や申請に不安や迷いもあるでしょう。お墓の解体・撤去には自治体の許可が必要なため、それらに必要な書類や手続きを順番に説明します。
改葬許可申請書
お墓を撤去するためには、現在の墓地を管轄する自治体で許可を得る必要があります。勝手に遺骨を取り出すことは認められていないため注意しましょう。
はじめに「改葬許可申請書」を取り寄せて必要事項に記入します。現在遺骨が存在する地の市区町村役場に提出するもので、遺骨1体につき1通必要です。自治体によっては、ホームページから様式をダウンロードできる場合があります。
詳しくは該当する自治体に尋ねてください。
出典|参照:墓地、埋葬等に関する法律|厚生労働省
遺骨を埋葬している墓地等の埋葬証明書
埋葬の事実を証明するため、役場に提出する「改葬許可申請書」に墓地管理者の署名と捺印が必要です。郵送で受け付けてもらえる場合もあるため、管理者に確認するとよいでしょう。
なお、自治体によって申請の仕方が異なるケースがあり、「改葬許可申請書」への署名・捺印ではなく証明書(埋蔵証明書)が必要な場合もあります。
出典|参照: 改葬許可申請|文京区
墓地の名義人の承諾書
現在墓地を使用している人と、改葬許可申請者が異なる時は「承諾書」の提出が必要です。所有する墓地の名義人が改葬許可申請者と異なる場合に限り、名義人の署名と捺印が求められます。
承諾書の様式は墓地を管轄する自治体から取り寄せます。ホームページから入手できる場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズでしょう。
出典|参照:改葬の手続き|宮崎市
出典|参照:改葬許可申請 |文京区
遺骨の受け入れ証明書
自治体によりますが「受入証明書」を添付する必要があります。「受入証明書」とは、新しい改葬先での遺骨の受け入れを証明する書類です。
「受入証明書」に改葬先の管理者の名前や住所などを記入、捺印してもらいます。なお、「墓地使用許可証」などの写しがあれば「受入証明書」の提出が不要な場合もあります。詳細は各自治体に問い合わせて確認してみましょう。
出典|参照:お墓を移すとき・分骨するときは|我孫子市
出典|参照:お墓を移す手続きについて |板橋区
必要な書類を役場に提出する
上記の必要書類一式(改葬許可申請書、承諾書、受け入れ証明書)を揃えたら、役場の窓口に提出しましょう。
自治体によって、認印やその他の書類が必要な場合があります。必ず自治体のホームページなどで確認の上で申請に行きましょう。
改葬許可証の発行
自治体に申請書類を提出したら「改葬許可証」が発行されます。「改葬許可証」はお墓の移動許可を証明するための書類であるため、撤去日までに発行が間に合わなければ工事自体ができません。
また、即日発行できない場合もあるため、時間が掛かることを想定して早めに申請しましょう。「改葬許可証」は遺骨を移転先に納骨する際に必要になる大切な書類です。紛失することがないように注意しましょう。
出典|参照:墓地、埋葬等に関する法律|厚生労働省
・改葬許可証に関連する7つの情報とは?申請に必要な書類や墓じまいの流れも解説
自分で墓じまいをする時の注意点

墓じまいをした後で後悔することは避けたいものです。自分で墓じまいをする時、どのようなことに気をつける必要があるのでしょうか。
ここからは、手続き前に押さえておきたいポイントを紹介していきます。
改葬許可申請書は自分で記入する
「改葬許可申請書」は申請者本人の記載が必要となっています。申請自体は委任状があれば代理申請が可能ですが、「改葬許可申請書」の所定欄は本人の記載が求められます。誰かに代理をお願いする時は、直前になって慌てないよう書類には早めに目を通しておきましょう。
なお「受入証明書」は代筆が可能となっています。ただし、委任状の添付が条件となっているため忘れないようにしてください。
「改葬許可申請書」は遺骨1体につき1枚必要です。複数の遺骨を改葬する場合は、「改葬許可申請書」1枚では申請できないため注意しましょう。
ただし、自治体の様式の中には、1枚の「改葬許可申請書」で複数分を全て記載できるパターンもあります。手続きする前に担当部署へ問い合わせてみましょう。
墓石撤去工事前に行政手続きを済ませる
お墓の撤去・解体工事までに手続きを終わらせておくことが重要です。石材店による工事が終わると、遺骨を新しい改葬先に移送する、もしくは自分で引き取ることが通常の流れとなっています。
仮に工事が完了していても、改葬先が未定の場合手続きが進みません。遅くても工事日の1ヶ月ほど前から自治体を訪ねることや、ホームページから申請書類を取り寄せるなどしておく必要があります。
ギリギリになってはじめるのではなく、早めに行動することが墓じまいを円滑に行うポイントといえるでしょう。
墓石撤去費用の見積もりで目途を確認しておく
石材店とのトラブルで多い事案に、墓石の高額な撤去費用の請求被害があります。撤去費用は墓石の大きさや墓地の面積、機材の導入の有無など様々な条件で決まりますが、工事が終わってから予想以上の費用を請求されてトラブルになるケースが往々にしてあります。
石材店を決める時は、ひとつではなく気になる複数の店舗に見積もりを出してもらいましょう。前もって支払う費用が把握できるため、急な請求で驚くことがありません。
菩提寺には礼を尽くして理解を得る
現在のお墓の菩提寺の檀家である場合は、離檀するための「離檀料」を請求されるケースがあります。離檀料の金額に明確な決まりはなく、一般的には1万~20万円程度が相場でしょう。お墓を建てる際に、金額があらかじめ決められていることもあります。
離檀料は今までの感謝の気持ちとして贈与する意味があるため、金額は遺族が決めることが基本とされていますが、まれにお寺から高額請求されるケースがあります。そうならないためにも、礼を尽くしてきちんと相談しておくと良いでしょう。
トラブルがある時は専門家に相談すること
墓じまいに関して何かしらのトラブルに発展した場合は、お寺の総括者に相談するか専門の弁護士に依頼しましょう。
その他にも、国民生活センターへ相談することもできます。1人で抱え込まずに、専門家を頼ってスムーズに解決する手助けを得ると良いでしょう。
自分で墓じまいする時に掛かる費用の相場は

墓じまいを検討する際には、費用がどのくらい掛かるのか気になる方も多いでしょう。
墓じまいに掛かる費用の相場は30万~300万円程度です。費用に幅がある理由として、改葬先をどのようにするかがあげられます。永代供養する、新しい墓地を建てる、散骨するなど、墓じまい後の手続きによって費用が変動します。
・お墓を買うお金がない?!費用を抑えて供養する方法を紹介
行政手続きに掛かる費用
行政手続きに掛かる費用は、受け入れ証明書・埋葬証明書などの発行費用が数百円から1,000円程度発生します。
住んでいる自治体によって金額が変わるため、事前にチェックしておくと良いでしょう。
墓石の撤去・解体費用
墓石の撤去・解体だけの費用をみると、墓地1平方メートルあたり10万円程度です。
墓地の敷地が広い場合や、墓石が特殊な場合は更に金額が上乗せされるでしょう。事前に数社見積もりを取っておくと高額請求トラブルを防ぐことができます。
また、ご遺骨の取り出しを一緒に行ってくれる業者もあります。その場合は別途料金の請求があるため、併せて金額をチェックしておきましょう。
閉眼供養のお布施
墓じまいの際は、仏式の場合閉眼供養という儀式を行います。こちらの費用は3万~5万円程度が相場です。いくら包むか迷った時は、お寺に相談してみると良いでしょう。
墓じまいの際に行う閉眼供養は、魂を抜く供養です。閉眼供養を行うことが決まった時点で、菩提寺へ連絡をしておくようにしましょう。
離檀料
現在のお墓の菩提寺から離れる場合の離檀料は3万~20万円程度が相場となっています。離檀料は宗派・寺院などによって異なるため、事前にお墓の菩提寺に聞いておくと安心して用意できるでしょう。
離檀料は、今まで供養してもらったことへの感謝の気持ちを込めてお渡しするお布施です。支払いの義務はないと言われることもありますが、気持ちを込めてお渡しすると良いでしょう。
遺骨の受け入れ先への納骨等の費用
遺骨の受け入れ先への納骨等の費用は、供養の仕方によって大きく異なります。ご遺骨の移送や「開眼供養」など、ご遺骨を受け入れするための費用は全て含めて数万円~100万円前後と相場の幅も広いでしょう。
費用相場に開きがありますが、単に安価な場所を選ぶよりも今後の供養やお参りのことを考えて選ぶと良いでしょう。
墓じまいを自分でする際は手続きや費用をしっかり確認しておこう

この記事では墓じまいの流れや必要な準備や書類、また行政手続きについて紹介しました。
流れや手続きについて知識があれば、自分で墓じまいすることは難しくありません。親族や自治体、お墓の管理者と連携を図って円滑に手続きを進めましょう。
また、費用に関しては自治体や業者、宗教・宗派によって変動があります。高額請求トラブルに巻き込まれないためにも、自分であらかじめ近隣相場を調べておくと良いでしょう。
お墓が遠方にある場合や、1人で管理をしていてお参りが難しくなったなど、墓じまいを検討するタイミングは人それぞれです。その後の供養が楽になるよう、理想の墓じまいを実現させましょう。
お電話でも受け付けております















