
喪中と忌中のお中元・お歳暮のマナー|いつまで・表書き・品選び
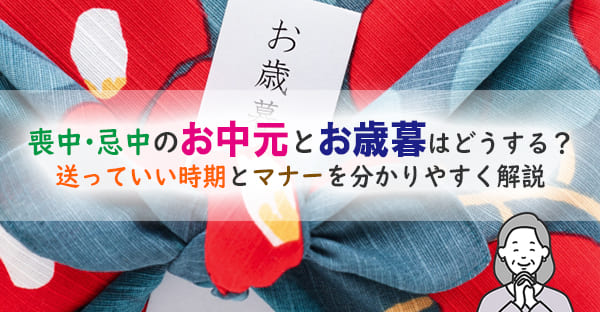
喪中や忌中の時期に、お中元やお歳暮を贈ってよいのか迷う方は多いものです。
結論として、喪中であっても季節の挨拶である中元・歳暮は控える必要はありません。ただし、忌中の期間やお中元・お歳暮を送る際の表書き、品選びには注意が必要です。
本記事では、この時期にお歳暮・お中元を贈るタイミングのマナー、避けたい表現、相手が喪中・忌中の場合の対応、送る時期の判断まで分かりやすく解説します。
喪中とは?忌中の意味や違いは?

◇喪中は故人を悼み静かに過ごす期間、忌中は四十九日までの慎む期間という意味があります。
故人との関係性によって喪中期間は異なりますが、一般的に家族が亡くなってから、一周忌を迎える1年間を喪中と言います。
一方で忌中は四十九日法要までの四十九日間を指し、この期間、故人の魂は冥土の道を辿る道程にあり、成仏していないと信じられてきました。
ただし人が亡くなるとすぐ成仏する「往生即成仏」の考え方を持つ浄土真宗では、忌中の考え方はありません。
喪中期間は何日まで?
◇喪中期間は、故人との関係性で変わります
喪中期間は一般的に一周忌までの1年間が目安ですが、「喪中(もちゅう)」は「喪に服す期間」であるため、正確には故人との関係性で異なり、故人との関係性が近いほど長いです。
故人との関係性が両親や配偶者である場合、喪中期間は約12か月~13か月ですが、兄弟姉妹であれば約3か月~6か月で喪が明けます。
ただし故人の祖父母は約1か月~6か月、故人の子どもは約3か月~12か月と、地域によって喪中期間が大幅に違う関係性もあるでしょう。
忌中期間は何日まで?
◇忌中期間は四十九日です
「忌中(きちゅう)」は仏教の教えにおいて、故人が冥土の道を辿り成仏するまでの期間を指すため、どの地域でも四十九日までが忌中期間となります。
忌中も故人を偲び喪に服しますが、それ以上に「死は穢れ(けがれ)」として、死の穢れを他者に移さぬよう、ご遺族は静かに四十九日間を過ごすのがマナーです。
浄土真宗では忌中期間はありませんが、一般的に忌中のお祝い事は忌まれますので、家が浄土真宗であっても、一般的なマナーに倣いお祝い事は控える方が多いでしょう。
[喪中と忌中の違い、やってはいけないこと]
忌中期間は?
◇忌中期間は四十九日です
「忌中(きちゅう)」は仏教の教えにおいて、故人が冥土の道を辿り成仏するまでの期間を指すため、どの地域でも四十九日までが忌中期間となります。
忌中も故人を偲び喪に服しますが、それ以上に「死は穢れ(けがれ)」として、死の穢れを他者に移さぬよう、ご遺族は静かに四十九日間を過ごすのがマナーです。
浄土真宗では忌中期間はありませんが、一般的に忌中のお祝い事は忌まれますので、家が浄土真宗であっても、一般的なマナーに倣いお祝い事は控える方が多いでしょう。
・喪中と忌中の違いとは?やってはいけないことは?初詣や七五三、お祭りに行ってもいい?
喪中にお中元・お歳暮は送ってもよい?マナーと注意点

◇喪中のお中元やお歳暮は、マナーを守って送ります
お正月や結婚式、新築祝いなど、喪中のお祝い事は出席せずに控えるのがマナーです。
けれどもお中元やお歳暮は、本来、季節の変わり目に贈る相手の健康を気遣い、ご無沙汰している相手へのご挨拶、お伺いを立てることを目的とし、お祝い事ではありません。
そのため喪中であってもお中元やお歳暮を送ることはできます。
ただし、喪中のお中元やお歳暮は通常とは違うため、喪中であることへの配慮が必要です。
自分が喪中のお中元やお歳暮
◇自分が喪中であってもお中元やお歳暮を送って構いません
自分が喪中であってもお中元やお歳暮を送り、上半期・下半期のお付き合いへの感謝を伝えると良いでしょう。
故人を亡くしてからの心遣いや支えに感謝する一文を添え、元気に残された家族で一歩・一歩を歩んでいる現状を、それとなくお伝えします。
相手が喪中のお中元やお歳暮
◇相手が喪中でも、お中元やお歳暮を送ります
相手が喪中である場合、お中元やお歳暮を送ることを躊躇う方々も少なくありません。
けれども喪中だからこそ、先方の健康や心を気遣い、マナーに配慮した品を送ると心が伝わりやすいでしょう。
喪中に贈るお中元やお歳暮の基本的なマナーの他、一筆箋で良いので手紙を添えて、ひと事、相手を労う言葉を添えると丁寧です。
お年賀は送っても良い?いつから届ける?
◇喪中の場合、お年賀は新年を祝う意味を持つため控えるのが一般的です。
…中元や歳暮とは異なり、お年賀は「新年の慶事」に当たるため、喪中の期間は避け、松の内を過ぎた頃に「寒中御見舞い」として贈ると丁寧です。
忌中(四十九日以内)にあたる場合も同様で、落ち着いてから改めて挨拶します。
[喪中の初詣について詳しく]
喪中にお中元やお歳暮をもらったらどうする?送るタイミングは?(宅配で家に届いた場合)

喪中の時期にお中元やお歳暮をいただいた場合、まずは有難く受け取りましょう。 たとえこちらが喪に服している状態でも、贈ってくださった相手の気持ちを素直に受け取ることが大切です。
亡くなる前に届いた場合はどうする?
◇不幸を知らずに発送したお中元・お歳暮は、そのまま受け取っていただいて問題ありません。
相手に迷惑をかけたと感じる場合は、一言お詫びとお悔やみを添えると丁寧です。故人宛てに届いた場合は、ご遺族に対して弔意とお礼を伝える文面を添えると安心です。
訃報とともに、お礼を伝える(礼状の文例)
ときには、故人宛てで贈り物が届くこともあります。 先方が訃報を知らなかった場合には、丁寧なお礼とともに、さりげなく連絡が行き届かなかったことへのお詫びと、訃報を伝える文面を添えるとよいでしょう。
●一言文例
「母〇〇〇〇は、○月○日に永眠いたしました。この度はご連絡が行き届かず申し訳ありません。 お中元の品とお心遣いを、家族一同、感謝しております。」
そのうえで、お返しについての対応やマナーについては、次項で詳しくご紹介します。
「お返し」は必要?マナーとタイミング
喪中にお中元やお歳暮をいただいた際、どのように「お返し」すればよいか悩む方も多いのではないでしょうか。 形式的にお返しをしなければいけないという決まりはありませんが、相手の気遣いに対して感謝を伝えることが大切なマナーです。
・ 紅白の水引や「御中元」などのお祝い表現は避ける
・ のしは無地の短冊や「御礼」など、控えめなものを選ぶ
・ 時期としては、四十九日以降、または年明け(落ち着いてから贈る)
まずは、お礼状や一筆箋で「お気遣いありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えましょう。 品物でお返しする場合は、いただいたギフトと同等か、やや控えめな品を選ぶのが一般的です。 寒中見舞いや御礼の名目で、落ち着いた包装のギフトを贈ると丁寧な印象になります。
お返しに悩むときは、形式よりも「気持ち」を優先に。 心を込めたシンプルなお礼が、相手の心にも残る贈り方となります。
[挨拶状の書き方]
[寒中見舞いの書き方]
喪中・忌中でお中元やお歳暮を控えるケース(いつ送る?時期の判断)

◇忌中はお中元・お歳暮ともに贈りません
故人の魂が成仏せずに冥土の道を辿る四十九日間「忌中(きちゅう)」は、家族を亡くした遺族は「死の穢れ(けがれ)」をまとっているとされます。
人の死を穢れとするのは本来、神道の考え方で、神道では神社の敷地内にお墓やそれに倣うものを建てる風習はありません。
けれども日本では広く、忌中に遺族は死の穢れを他者へ移さぬよう外出を控え、贈り物を送ることを控えてきました。
そのため香典返しも、四十九日の忌中を過ぎてから送ります。
同じく喪中は良しとするお中元やお歳暮ですが、忌中に送ることは忌まれるでしょう。
・喪中と忌中の違いとは?やってはいけないことは?初詣や七五三、お祭りに行ってもいい?
お中元を贈る時期
◇東日本では7月1日~15日頃、西日本では8月1日~15日頃です
夏の暑い盛りに先方の健康を気遣い贈るお中元は、お盆を目安に送ると良いでしょう。
ただ全国的にお盆の日程が異なる地域もあり、東日本と東日本で送る時期が異なります。
目安としては東日本が7月1日~15日頃、西日本が8月1日~15日頃が適切です。
お盆はもともと旧暦7月13日~15日に行う行事でしたが、東日本では新暦に充てて7月13日~15日に行う「新暦盆」の地域もあるためです。
一方で西日本では、1か月遅れの8月13日~15日に行う「月遅れ盆」が多いでしょう。
・2026年のお盆はいつ?お盆休みは最大9連休!地域で違う3つのお盆、全国のお盆行事
お歳暮を贈る時期
◇全国的に12月13日~20日頃までが適切な時期です
お歳暮は忙しい年末に1年の感謝とご挨拶を伝える贈り物ですので、12月上旬頃から届き始めます。ただ年末はお正月の準備で忙しくなる時期ですから、12月20日頃までには届けましょう。
また12月13日は日本の風習として、お正月の準備を始める「事始め」とされ、いよいよ年末が始まる日ですので、ご挨拶としては12月13日~20日頃が適切です。
相手との関係性に配慮しよう
喪中に中元や歳暮を贈る際には、相手との関係性や贈る目的を意識することがマナーの基本です。
たとえば、毎年ギフトを交わしている親しい相手であれば、「贈ってくれて嬉しかった」と前向きに受け取ってもらえることもあります。 一方で、あまり親しくない相手や、形式を重んじるご家庭の場合は、「このタイミングで贈るのは控えてほしかった」と受け取られる可能性も否定できません。
判断に迷った場合は、あらかじめ確認を取るか、時期をずらして“残暑見舞い”や“寒中見舞い”といった形でギフトを贈る方法もあります。 喪中は心の整理をする大切な時期だからこそ、贈る側の思いやりと、相手を尊重する姿勢が何より大切です。
相手が忌中のお中元やお歳暮は?忌明けに送るのが正しい?
◇送る相手が忌中の場合も、時期をずらすと丁寧です
送る側が忌中であれば、時期をずらして挨拶状を添えて贈るなど、お中元やお歳暮は控えることがマナーですが、では、送る相手側が忌中の場合はどうすれば良いでしょうか?
忌中は故人が亡くなって四十九日が経たない時期、先方は大切な家族を亡くして、未だ心の整理が付いていない時期でもあります。
そのため、迷うようならばお中元やお歳暮は控えて、時期をずらして送ると、先方にお悔やみの気持ちも伝わり丁寧です。
お中元やお歳暮の時期を過ぎた時の対応(寒中見舞い・暑中見舞い)
◇「暑中御見舞い」「寒中御見舞い」として送ります
もしも忌中がお中元やお歳暮の時期と重なるようであれば、時期をずらして遅れた頃に、夏であれば「暑中御見舞い」、お歳暮ならば「寒中御見舞い」として送ると良いです。
夏の贈り物は「暑中御見舞い」の表書きで良いですが、立秋が過ぎたら「残暑御見舞い」へと変わります。
| <お中元やお歳暮の時期が過ぎたら> |
|
| ①暑中御見舞い | ・毎年7月16日~立秋まで ・2026年7月16日(月)~8月6日(木)まで |
| ②残暑御見舞い | ・毎年立秋~8月末頃まで ・2026年8月7日(金)~8月31日(月) |
| ③寒中御見舞い (寒中御伺い) |
・毎年1月7日~立春の前日まで ・2027年1月7日(木)~2月3日(水) |
残暑御見舞いは毎年8月31日までが送る目安ですが、遅くとも二十四節気の「処暑」の候が終わる頃までには送りましょう。
寒中御見舞い(寒中御伺い)は、お正月としてお祝いをする7日間「幕の内」が明ける1月8日~立春の前日までに送ります。
会社関係やビジネス相手へのお中元やお歳暮はどうする?

ビジネスシーンでは、日頃から中元や歳暮を贈り合う習慣のある企業も多く、喪中の場合でも判断に迷いやすいものです。以下では、会社関係や取引先が喪中だった場合の対応や、避けたいマナー違反について解説します。
ビジネス相手が喪中の、お中元やお歳暮は大丈夫?
会社関係の相手が喪中の場合、お中元やお歳暮を贈ってもよいか悩む方は多いでしょう。 基本的には、ビジネス上の贈答であれば、喪中でも問題なく贈ることができます。ただし、表書きやタイミング、品選びには細心の注意を払いましょう。
特に、取引先の社長や役員などが亡くなった場合は、贈るタイミングを四十九日後にずらす、もしくは寒中見舞いや御伺いの形式に変更するのが丁寧です。 相手先が喪に服している状況を尊重し、あくまで「お付き合いの継続」や「感謝の気持ち」を伝えるギフトとして、控えめに贈るのがマナーです。
「会社名義」で贈るお中元やお歳暮の注意点
会社名義で中元や歳暮を贈る場合は、個人の感情よりもビジネス上の慣例を優先するのが基本です。 ただし、相手が喪中であることが明確な場合は、例年通りの贈答スタイルがマナー違反と受け取られないよう配慮が必要です。
表書きは「御中元」「御歳暮」ではなく、「御伺い」や「御礼」に変更する、のしを外すまたは無地の短冊にするといった対応が求められます。 また、名刺や企業ロゴ入りのカードを添えることで、形式的でありながらも誠実さを演出できます。
発送前に「このような状況ですが、例年通りご挨拶をお届けいたします」と一言添えると、より丁寧な印象になります。
喪中の取引先におすすめのお中元・お歳暮とは?
喪中のビジネス相手に贈るギフトは、派手さを避けた実用的かつ上質なものが好まれます。以下のような品物が特におすすめです。
● 落ち着いたパッケージのコーヒー・紅茶ギフト
● 老舗の焼き菓子や和菓子
● 高級だしや調味料セット
● 季節感のある消え物(ゼリー、スープなど)
● カタログギフト(弔事用もあり)
いずれも、のし紙は無地または「御伺い」とし、包装は落ち着いた色味でまとめるのがポイントです。 感謝の気持ちを込めながらも、相手の心情に配慮した選び方を意識しましょう。
喪中のビジネスシーンで避けたいNG例
喪中の相手に贈るビジネスギフトでは、自分では気づかないうちに、無意識にマナー違反となるケースもあるため注意が必要です。
● 表書きに「御中元」「御歳暮」と記載
● 華やかすぎる包装紙やリボン
● 肉・魚・酒など、忌避されがちなギフト
● 故人宛てで送ること(部署名や役職名が残っていることに注意)
● 忙しい時期に再三の催促や到着確認をする
ビジネスシーンでは、形式的な贈答が多いとはいえ、相手の社風や過去のやり取りを尊重した対応が信頼につながります。 迷ったときは、事前に先方へ一言確認するのも誠実な対応のひとつです。
喪中にお中元やお歳暮(お年賀)を贈るマナー・正しい書き方

◇喪中のお中元やお歳暮はお祝い色を控えます
喪中にお中元やお歳暮自体を送ることは問題ないのですが、お中元やお歳暮はしばしば、「めでたい」意味がある熨斗を掛けるなど、お祝いとして包む品が多いです。
そのためお中元を贈る時には、あくまでも相手の健康を伺い、日ごろのお付き合いに感謝する目的であることを強調し、お祝い色を避けます。
①熨斗や水引は掛けない(無地の掛け紙のみ)
◇喪中のお中元やお歳暮は「掛け紙」です
喪中に送るお中元やお歳暮に掛けるものは、熨斗(のし)や水引を付けない、シンプルな白い紙のみで掛けた「掛け紙」のみで包みます。
しばしば短冊を用いる方もいますが、目上の方には失礼にあたるため、掛け紙が良いでしょう。
白い掛け紙の中央に、黒い文字で「お中元」「お歳暮」などの表書きのみです。
掛け紙には内のし・外のしがありますが、郵送の際は内のしが多いものの、どちらでも問題はありません。
②故人宛てに贈らない
◇故人宛てのお中元やお歳暮には注意しましょう
普段からお中元やお歳暮を送る相手を登録していると、うっかり送ってしまうこともありますが、故人宛てのお中元やお歳暮を送ることは失礼にあたります。
一般的に故人へ毎年送っていた場合、亡くなったらお中元やお歳暮自体を辞めるでしょうが、ご家族とも親交がある場合、ご家族向けにお中元やお歳暮を送る流れが一般的です。
反対に故人へお中元やお歳暮をいただいた時には、有難く受け取って、訃報を添えたお礼状とともに、お礼の品を贈ると良いでしょう。
③お祝いの言葉を控える(手紙の文例も紹介)
◇お中元やお歳暮に添える手紙にお祝いの言葉を控えます
喪中の人がお中元やお歳暮を送る・喪中の相手に送る、いずれにしても手紙を添える時には、お祝いの言葉は控えるのがマナーです。
喪中であれば葬儀への参列への感謝を伝えるとともに、相手の健康を気遣う一文を添えましょう。
一方、喪中の相手へお中元やお歳暮を送る場合、敢えて喪中には触れずに、相手の健康を気遣う言葉を添える方が、相手への心遣いとなるでしょう。
喪中に送るお中元やお歳暮に添える手紙や、いただいたお中元やお歳暮に対する、お礼の手紙の例文は、下記コラムをご参照ください。
・喪中のお中元やお歳暮に添える手紙・いただいたお中元やお歳暮へのお礼状の例文をご紹介
④品選びに注意をする
◇お祝いをイメージする品は避けましょう
お中元やお歳暮は紅白まんじゅうや、色とりどりの素麺、鯛など、お祝いやおめでたさをイメージさせる品も少なくありません。
けれども喪中のお中元やお歳暮はお祝い色を控えるため、まんじゅうであれば白まんじゅう、白い素麺など、紅白などのお祝いをイメージさせるものを避けます。
⑤縁起の悪い品を避ける
◇刃物など、縁起の悪い品も避けましょう
喪中のお中元やお歳暮に限らず、刃物類は「縁を切る」または血をイメージする物として、贈り物には避けるべき品です。
また筆記用具や時計などの仕事や勉学に関する品物は、「もっと頑張りなさい」のメッセージと取られる可能性もあるので、あまりふさわしくありません。
長期間保存ができる個包装のゼリーや、果物など、季節を感じる食べ物がおすすめです。
喪中のお中元やお歳暮|のし紙・表書きの例と注意点
喪中の時期に贈り物をする際、気をつけたいのが「のし紙」や「表書き」のマナーです。 一般的なお中元やお歳暮では、紅白の水引に「御中元」「御歳暮」といった表書きを使いますが、喪中の方に贈る場合はこれらを避け、控えめな形式にするのが基本です。
● 「御中元」「御歳暮」など祝い事を連想させる表書き
● 赤白の水引がついた華やかなのし紙
● 「寿」「祝」「御礼」など、慶事の言葉を含む表書き
● 「御伺い」
● 「御礼」
● 「粗品」
● 表書きを記載しない「無地の短冊」
包装紙やのし紙の色も、落ち着いた白やグレー系など、弔事用にふさわしい控えめな色合いを選びましょう。 贈る側の丁寧な心配りが、相手に安心感を与えます。
また、故人宛てではなく、必ず喪主や遺族の名前を宛先にするのがマナーです。 会社名義で贈る場合でも、表書きや送付状に気配りを加えることで、ビジネス上の信頼にもつながります。
喪中のお中元・お歳暮は、失礼にならない品物を送る

◇喪中に送る品は、お祝い色のない食べ物や消耗品が人気です
喪中に送るお中元やお歳暮は、果物や長期保存のできる食べ物など、香典返しでも選ぶことの多い、弔事にも通用する品々が選ばれる傾向です。
時計や置き物などの後々まで残る品は「悲しみが残る」としてあまり好まれません。品物であれば日用品であるタオルなどの他、洗剤などの消耗品が良いでしょう。
ここでは喪中のお中元やお歳暮でも喜ばれやすい、おすすめの品々を特集として、いくつかご紹介します。
①白まんじゅう
◇喪中のおまんじゅうは、白まんじゅうが好まれます
高齢の方々へ送るお中元やお歳暮には、まんじゅうや大福もちなども人気です。
けれども日頃のお中元やお歳暮では、元気な色をイメージしてカラフルであったり、紅白まんじゅうになっているものも少なくありません。
そのためまんじゅうを送るならば、美味しい白まんじゅうや茶色まんじゅうを選びます。
・塩瀬総本家「志ほせ饅頭・焼菓子詰合せ」
②カタログギフト
◇品選びに迷ったら、カタログギフトが安心です
喪中に送るお中元やお歳暮は品選びに迷いがちですので、まよったら、相手が品を自由に選べるカタログギフトが良いでしょう。
現金や商品券は金額が分かるためタブーとされますが、現代ではカタログギフトは贈り物の他、香典返しなどの法事でも多く扱われます。
・京線香詰合せ「彩雲の風+カタログギフト野宮&アイリス」
③コーヒーギフト
◇コーヒーやお茶なども選ばれるギフトです
香典返しなどの弔事に嗜好品はタブーとされますが、多くの家庭で日常的に愛されるお茶やコーヒーなどは、会葬御礼品としても多く選ばれてきました。
夏に送るお中元ならアイスコーヒー、お歳暮であればさまざまなフレーバーを詰め合わせたコーヒーセットもおすすめです。
・マキシム&ハマヤコーヒーバラエティギフト
④ゼリーやアイス
◇夏のお中元では、冷たいゼリーが人気です
夏に送る喪中のお中元であれば、体力が落ちた夏もするっといただけるゼリーやアイスを選ぶ方が多いでしょう。
喪中の相手へ送るならば特に、忙しかったりと体力も落ちてしまいがちですので、誰でも食べやすいゼリーやアイスはおすすめです。
・京都萬屋琳窕「京のひんやりギフト」
⑤力の付く食べ物
◇食が進む食べ物で、相手の健康を気遣います
暑い夏は食欲が落ちる方も多いですよね。
そのため食べやすい冷たいゼリーやアイスを送る方もいますが、精力を付けていただくよう、食が進む品を選ぶことで、相手の健康を気遣うこともできます。
喪中は品選びが難しいところですが、お茶漬けや海苔、食が進むご飯のおともなどを送るのも良いでしょう。
・永楽屋「あまから」お詰合せ
忌明け後のハムや肉類は送っていい?(家族でもOK?)
◇忌明け(四十九日後)であれば、ハムや肉類のギフトを贈って問題ありません
…喪中だからといって肉類がタブーという決まりはなく、多くの家庭で日常的に受け取られています。気になる場合は、落ち着いた包装や日用品など控えめな品を選ぶとより無難です。家族間でも、忌明け後は通常どおりの贈答で構いません。
おいしいスイーツはOK?人気ギフトの注意点
喪中の時期に贈るお中元やお歳暮では、「おいしいスイーツ」や「人気のギフト」が候補に上がることも多いですよね。 特に取引先や親しい間柄では、気軽に楽しんでもらえるお菓子類が選ばれやすい傾向にあります。
ただし、喪中にスイーツを贈る際は、品選びや包装、メッセージの内容に注意が必要です。 たとえば、以下の点に配慮しましょう。
● 華やかすぎるケーキや高級洋菓子は避け、落ち着いた色合いの和菓子や焼き菓子がおすすめ
● 賑やかでカラフルな包装ではなく、シンプルで上品なパッケージを選ぶ
● のし紙は「御中元」ではなく「御伺い」「無地の短冊」に
● メッセージカードに「お祝い」「喜び」などの表現を含めない
また、相手が甘いものを好むかどうか分からない場合は、お茶やだし、調味料など汎用性の高い“食のギフト”を選ぶのも安心です。
2025年に人気だったネット通販ギフト|喪中でも贈りやすい中元・お歳暮特集

2025年は、ネット通販を利用してお中元やお歳暮を贈る方が増加しました。特に、喪中の方にも配慮したギフトを扱うショップが注目を集めました。以下に、2025年に特に人気だった通販サイトと、そのおすすめ商品をご紹介します。
①【楽天市場】落ち着いた包装と選べる弔事ギフト
楽天市場では、弔事向けギフト特集ページが2024年も大きな注目を集めました。 白を基調にした包装や「無地のし」対応商品が多く、喪中の方にも贈りやすい焼き菓子やお茶の詰め合わせなどが人気です。
レビュー数も豊富で選びやすく、ポイント還元などの特典もあり、個人・法人ともに利用者が増えています。
● 【銀座千疋屋】フルーツゼリー詰合せ
● 【京都・宇治】老舗茶舗の高級煎茶セット
● 【北海道】スモークサーモン&ホタテギフト(SWH-50)
②【高島屋オンラインストア】フォーマルな場面にも安心
高島屋オンラインストアは、老舗百貨店ならではの信頼感があり、弔事用の贈り物として「御伺い」や「御礼」の表書きが選べるギフトが多数揃っています。 2024年は特に、上質な和菓子や料亭監修の食品ギフトなどが、喪中の方への贈り物として高い支持を集めました。
控えめな包装と上品な見た目で、個人・法人問わず使いやすいラインナップが特徴です。 メッセージカードやのし対応も充実しており、ビジネスの贈答品としても安心して選べます。
● 【選べる】カタログギフト「百花一選」
● 【京都・わらびの里】料亭一膳と最中スープ
● 【京都限定】羊羹 ゆるるか詰合せ
これらの商品はどれも、「派手すぎない」「日常に役立つ」「日持ちがする」など、喪中の贈り物として大切な要素を満たしており、気遣いの伝わる選択肢です。
③【Amazon】配送の速さと選択肢の多さで人気
Amazonでは、「弔事 ギフト」や「喪中 中元」などのキーワードで検索すると、シンプルなスイーツセットやお茶ギフト、調味料など、実用的で静かな印象の商品が豊富に表示されます。 即日配送にも対応しているため、急ぎで準備したいという方に特に支持されています。
● 【京都利休園】お茶 玉露・煎茶詰合せ
● フルーツセット 果物セット
● 【銀座千疋屋】銀座フルーツジュレ(12個)
喪中のお中元・お歳暮に関するよくある質問

喪中の時期にお中元やお歳暮を贈る・受け取る際、「これってマナー違反?」「どう対応すれば?」と迷うケースは少なくありません。ここでは、よくある3つの疑問にお答えします。
Q1:故人に毎年贈っていた場合、喪中のお歳暮はどうする?
故人に毎年お中元やお歳暮を贈っていた場合、喪中の初年度は特に「今年も贈るべきか」「先方はどう受け取るか」と迷いますよね。
基本的には、故人宛てへの贈り物は控えるのがマナーとされています。 ただし、遺族の方とのご縁が続いている場合は、その方宛てに贈り直すことで失礼にはあたりません。
その際は、表書きを「御伺い」「御礼」とするほか、一筆添えて故人を偲ぶ気持ちとご家族への気遣いを伝えると丁寧です。
Q2:喪中はがきをもらったら、贈らない方がいい?
喪中はがきには「新年のご挨拶はご遠慮申し上げます」といった文言が記載されていることが多く、「贈り物も遠慮したほうがいいの?」と感じる方も多いでしょう。
しかし、喪中はがき=贈答NGというわけではありません。 あくまで年賀状などの慶事的な挨拶を控えるという意味であり、お中元やお歳暮といった季節のご挨拶をすべて断っているわけではないのです。
不安な場合は「寒中見舞い」や「御伺い」として時期をずらし、控えめなギフトを贈る方法もおすすめです。 無理に避けるよりも、思いやりある形で気持ちを届けることが大切です。
Q3:喪中でも会社関係には贈っていい?
喪中・忌中のお中元とお歳暮はいつまでに送る?マナーまとめ

お中元は暑い真夏に相手の健康を気遣い、お伺いをすることを目的としています。
またお歳暮は年末に向けて、1年の感謝を伝えるための品です。
お中元やお歳暮自体にお祝いの意味は込められていないので、喪中であっても送ることはできます。
ただしお祝いをイメージする熨斗や水引を避け、選ぶ品もシンプルなお祝いをイメージする紅白などは避けましょう。
また喪中はお中元やお歳暮を送っても構いませんが、忌中は控えます。
忌中に掛かるようならば、少しずらして暑中御見舞い・寒中御見舞いとして送りましょう。
お電話でも受け付けております
















