
墓じまいをして永代供養にする手順は?それぞれの違いや費用についても解説!

「永代供養ってどんなものなの?」
「墓じまいをして永代供養をする際の手順とは?」
「永代供養の費用やメリットが知りたい」
このように、永代供養を検討している方の中には疑問や不安をお持ちの方も多いでしょう。永代供養は近年注目されているお墓の管理の仕方です。本記事では永代供養の契約までの流れや、墓じまいとの違い、気になる費用やメリットについて紹介します。
この記事を読むことで、永代供養のスムーズな契約の方法や、墓じまいから永代供養までの流れ、経済的な事情について深堀りできます。普段仏事に触れる機会がない方や、これから契約を考えている方には有益な情報となるでしょう。
本記事を読んで、永代供養の仕組みに触れ今後の終活に役立てましょう。
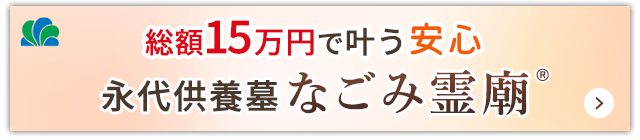
墓じまいと永代供養の違い

「墓じまい」とは様々な事情でお墓を手放すことで、「永代供養」とは新しいお墓の管理の仕方を指します。近年、生活の多様化や家族のあり方の変化から、お墓を管理できない遺族が増えています。
ここからは、「墓じまい」と「永代供養」のそれぞれの意味を解説しますので、参考にしてください。
墓じまいとは
「墓じまい」とは、所有するお墓を撤去・解体することです。お墓の遺骨を取り出して墓石を解体した後、墓地を更地に戻し使用権を管理者に返還します。
遺族が高齢となりなかなかお墓参りに行けないことや、遠方でお墓掃除ができないなどの理由から無縁仏となることを避けるために、やむを得ず「墓じまい」を行う方が増えています。
また、「改葬」はお墓を引っ越して遺骨を移動するまでの作業を指します。
▼詳しくはこちら
永代供養とは
永代供養とは、お寺や霊園にお墓の供養・管理を依頼する方法です。定期的な読経や法要、お墓の清掃なども任せられます。
お墓の管理を継承しなくてもよいことから、子孫に引き継ぐことが困難な方や、事情があり遺族が管理できない場合などに用いられています。
依頼した後も遺族がお墓参りできることや、骨壷を個人的に安置する期間が終了した後は別の人と同じ場所に納骨するため、無縁仏となることを避けられるでしょう。
▼詳しくはこちら
»永代供養についてわかりやすく紹介!費用や選び方なども詳しく説明
墓じまいした後に永代供養にする4つのメリット

墓じまいをした後の供養をどのようにするか、悩む方も多いのではないでしょうか。
墓じまいをした後「永代供養」を選択することで、精神的な負担や経済的な負担を軽減することが可能です。ここからは、永代供養にするメリットを4つにまとめましたので、今後の参考にしてください。
- お墓の管理負担が軽減される
- 通常のお墓より費用負担が軽減される
- 承継者がいなくても問題がない
- 檀家を抜けることができる
1:お墓の管理負担が軽減される
永代供養ではお墓の管理をお寺や霊園に全て任せられるため、遺族の負担が軽減します。定期的な読経や年忌法要もお勤めいただけるほか、お墓参りもできることが一般的です。
家からお墓が遠くてなかなか管理できない方や、体が不自由なためお墓の清掃などができない高齢の方、お墓を継続的に維持するのが困難な場合方にとって利点といえるでしょう。
2:通常のお墓より費用負担が軽減される
一般的なお墓の維持費用に対して、永代供養にかかる費用の方が安価になる傾向があります。
一般的に、契約時に永代供養料を支払った後は追加費用が発生しません。お寺や霊園など施設の管理費用や運営費用、修繕費なども初期費用に全て含まれているためです。
現在のお墓の維持で経済的に負担を抱えている方や、費用を抑えたい方にはメリットといえるでしょう。
▼詳しくはこちら
3:承継者がいなくても問題がない
核家族増加の影響で家族のあり方も多様化しており、承継者がいないなどの理由から、将来のお墓について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
永代供養は将来の供養を保証してくれるため、継承する子孫がいない方や、身寄りがない方には大きな利点といえます。
お寺や霊園が責任を持って大切にお墓を管理してくれるため、先祖代々受け継ぐお墓の供養を任せられるという安堵感や精神的な悩みから解放されるでしょう。
4:檀家を抜けることができる
永代供養は宗派が無関係であるところが多く、檀家でいる必要がありません。仏式以外の宗派の方でも通常通り供養してもらえることが特徴です。現在のお世話になっているお寺の檀家から離れたい場合にも向いているでしょう。
ただし、契約自体は無宗教で締結できても、供養や法要は宗派が指定されているケースがあるため事前によく確認しておきましょう。
▼詳しくはこちら
墓じまいをして永代供養にする8つの手順

墓じまいから永代供養まではどのような手順で、どういった手続きが必要なのでしょうか。墓じまいは人生で何度も経験することではないため、知識を備えておきましょう。
ここからは、墓じまいをして永代供養にする具体的な手順について紹介します。
1:親族に墓じまいの相談をする
親族の中には、永代供養は「ご先祖様に対して失礼」「道理に外れている」などと反対する方がいる場合もあるでしょう。また墓じまいには費用が発生するなど、様々な要因でトラブルにいなる可能性があります。
トラブルを避けるためにも親族とは必ず話し合いの場を設けて、全員の合意を得るようにしましょう。
2:寺院に墓じまいの相談をする
現在のお墓の菩提寺に墓じまいの相談をします。とくに檀家となっている場合は離檀料が発生することもあり、経済的な問題に発展しかねません。
また、菩提寺にとっても檀家の支援は運営資金となっているため、離檀されることは先方にとって大きな負担となるでしょう。お墓の引っ越しを円満に進めるためにも、事前に必ず説明し理解してもらうことが重要です。
3:受け入れ先の永代供養墓を決める
新しい受け入れ先である永代供養墓を決めます。お墓には故人やご先祖様の魂が宿るといわれているため、末永く大切に管理してくれる施設を選びましょう。
依頼先のお寺や霊園は、パンフレットを取り寄せたりインターネットで検索したりして積極的に探しましょう。お墓の管理方法や供養、費用、交通面などの詳細をみて、気になる施設があれば実際に訪ねることも大切です。
4:お墓を撤去してもらう業者を決める
お墓の撤去は専門の石材店に依頼することが一般的ですが、お店ごとに料金が異なるため、様々な石材店を訪ねて見積もりを出してもらうことが重要です。
費用は墓石の大きさや墓地の面積などでも変わるほか、外柵や巻石の有無なども大きく関わります。契約した後から高額請求されるケースもあるため、トラブルを未然に防ぐためにも内容を事前に確認しておきましょう。
▼詳しくはこちら
5:墓じまいに必要な手続きをする
墓じまいには公的な書類手続きが必要です。必要な書類を準備し、お墓の土地がある市町村役所を訪ねて「改葬許可申請書」を受け取ります。郵送してもらえる場合もありますので役所に確認しましょう。
6:閉眼供養を執り行う
墓じまいの前に「閉眼供養」という儀式を行います。「魂抜き」や「お性根抜き」と呼ばれ、故人やご先祖様の魂を通常の状態に戻す意味があるとされています。
儀式では、撤去するお墓にお花や線香などお供え物をして、僧侶に読経をお勤めいただくことが一般的です。
7:お墓の撤去・遺骨の取り出しを行う
閉眼供養を終えると、お墓を撤去し遺骨の取り出しを行います。墓石を解体・撤去し更地に戻し、最終的に管理者の元へお返しします。
墓石が大きいなどの理由で解体に機械を使用する場合は、割増の費用が発生する可能性があります。また、墓地の面積や墓石の形でも費用の変動が見込まれますので、不明な点があれば石材店に確認しましょう。
8:受け入れ先の永代供養墓に遺骨を埋葬する
新しい永代供養先に遺骨を埋葬します。遺骨は骨壷の状態で移動することが一般的です。契約時に永代供養料を支払いますが、金銭面でわからないことがあればお寺や霊園の関係者に尋ねましょう。
墓じまいと永代供養にかかる費用は?

墓じまいと永代供養にはそれぞれ費用がかかります。家庭の経済に響かないよう費用を正確に把握しておくとよいでしょう。
墓じまいから永代供養を行うまでの一般的な相場は50~150万円ほどです。ここからは、費用の内訳をそれぞれの過程ごとで紹介しますので、参考にしてください。
墓じまいの場合
墓じまいでは「墓石の撤去費用」「閉眼供養のお布施」「離檀料」の3つの費用が発生します。お墓の条件や、菩提寺との関係性などにより相場に変動があることが特徴です。
ここからは、一般的に墓じまいでかかる費用の相場を紹介します。
墓石の撤去費用
墓石の撤去費用は、墓地の面積や墓石の形で相場が変動します。一般的に墓地面積1平方メートルあたりにかかる費用相場は8~15万円ほどです。平均的には1平方メートル10万円ほどでしょう。
依頼する石材店の人件費や、用いられる解体専用の機材などの使用で相場が異なります。また、地域によっても相場に差が生じることがあるため、事前によく確認しましょう。
閉眼供養のお布施
閉眼供養では、儀式の中で僧侶に読経をお勤めいただきます。遺族は謝礼としてお布施を包みます。
相場は3~10万円ほどですが、お布施は菩提寺との関係性が影響します。日頃の菩提寺との付き合い方で金額を決める必要があるでしょう。
離壇料
お寺の檀家である場合、墓じまいすることは離檀を意味します。離檀料とは檀家を離れる際に支払う費用のことで、遺族が今までお勤めいただいた感謝の気持ちとしてお寺に渡します。
相場は大体3~20万円ほどで、お寺によりあらかじめ金額が一律で定められている場合や、明確な決まりがないなど金額の基準が異なることが特徴です。不明な場合はお寺関係者に相場を尋ねましょう。
永代供養の場合

永代供養の納骨方法には「個人墓」「集合墓」「合祀墓」の3種類があり、それぞれで費用が異なります。
「個人墓」は一般のお墓のように個別で骨壷を安置して、一定の期間が経過した後他の人と同じところに納骨する方法です。費用の相場は50~150万円ほどでしょう。1人や家族単位で安置できて、全体の管理費用が含まれるため、他の納骨方法と比べて費用が高めの傾向があります。
「集合墓」とは、共有のスペース内で個別に安置する方法です。こちらも一定期間を過ぎると、他の人と同じ場所に納骨します。費用の相場は20~60万円ほどでしょう。
個別で安置せず最初から他の人と納骨するタイプが「合祀墓」です。管理費用を抑えられることから、お墓の種類の中では安価で5~30万円ほどが相場でしょう。
墓じまいの費用が払えない場合はどうすれば良いのか?

墓じまいにはまとまった金額が必要になりますが、もし費用が払えない場合はどのように対処すればよいのでしょうか。
まず1つ目に、自治体による補助金制度の申請です。無縁仏の増加は自治体としても避けたいため、補助金制度を設けている場合があります。金額などは市町村により異なるため、管轄する自治体を確認しましょう。
次に金融機関で借り入れできるサービスの利用です。お墓に関する費用のための「メモリアルローン」は、墓じまいや墓石を建てる際に契約が可能です。比較的審査が早いので通過すればすぐに利用できます。
墓じまいをして永代供養にする時に気を付けること
永代供養では、どのような納骨方法であっても最終的には合祀になります。後から分骨したい場合や手元供養したい場合でも、遺骨を取り出すことができない場合があります。
納骨方法や安置期間をはじめ、永代供養を取りやめたい場合の対応など契約書の内容はよく目を通しておきましょう。
墓じまいをして永代供養にする時の手順や注意点について知ろう

この記事では墓じまいから永代供養までの流れや手順、費用などを紹介しました。永代供養は、故人やご先祖を末永く供養するための現代のお墓のスタイルです。
永代供養を検討される方は、本記事の内容を参考にし納得のいく供養方法を見つけましょう。
お電話でも受け付けております















