
喪中と忌中の違い・期間とやってはいけないこと|いつまで何を控える?
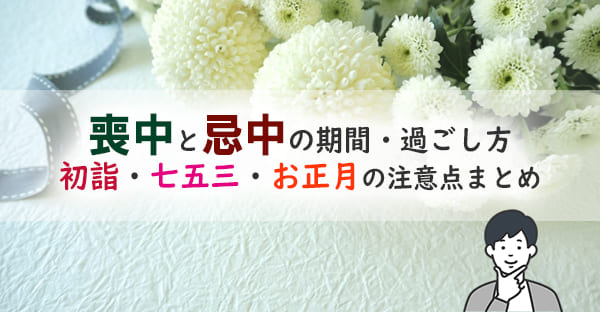
家族を亡くした後に迎える「喪中」と「忌中」は、どちらも身を慎む期間ですが、意味や期間、控えるべきことには明確な違いがあります。
特に、喪中と忌中では初詣・七五三・お祭りといった行事の扱いも異なり、どこまで参加して良いのか迷う人も多いでしょう。
本記事では、喪中と忌中の違い、期間の目安、やってはいけないことを分かりやすく整理し、結婚式や飲み会の招待を受けた際の対応まで、実務的に役立つ内容をまとめてご紹介します。
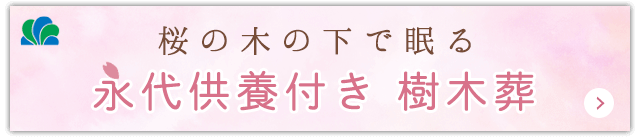
喪中と忌中とは?違いと意味(読み方)

喪中(もちゅう)と忌中(きちゅう)はどちらも身を慎む期間ですが、その意味や目的には違いがあります。まずは両者の基本的な考え方を整理しておくと、後の判断がしやすくなります。
喪中とは?期間と意味(読み)
◇喪中(もちゅう)とは、家族を亡くした後に迎えるおよそ1年間の期間を指します。
…故人を偲びながら日常をゆっくり取り戻していくための時間とされています。この期間は祝い事を控え、心身を落ち着かせることを目的としています。
喪中は多くの家庭で一周忌までの約一年間とされ、両親・配偶者・子どもなど親しい家族を中心に設けられます。兄弟姉妹や祖父母などは三ヶ月〜半年を目安とする地域もあります。
忌中とは?期間と意味(読み)
◇忌中(きちゅう)とは、家族が亡くなってから四十九日法要までの期間を指します。
…「死の穢れ(けがれ)を他者に移さない」という意味を持つのが特徴です。喪中よりも宗教的な意味合いが強く、特に神道では忌み慎む期間として扱われます。
忌中は一般的に四十九日までですが、故人との関係によって二十日〜三十日程度とする地域もあり、家の習わしに従うことが多いでしょう。
喪中と忌中の主な違い
◇喪中と忌中は混同されることが多いものの、目的と期間が異なります。
…喪中は一年を通して故人を偲び、祝い事を控える期間であるのに対し、忌中は宗教的な意味が強く、四十九日まで「穢れ」を慎む期間です。
また、忌中は特に神社参拝や慶事への参加を控える一方、喪中は家族や地域により柔軟に対応されることもあります。両者の違いを知っておくことで、年中行事やご招待を受けた際の判断がしやすくなるでしょう。
喪中の期間はいつ・どの範囲まで?

喪中の期間は「いつまでか」が家族の関係性によって変わります。まずは一般的な目安を押さえておくと判断がしやすくなります。
家族・親族別の喪中期間
◇喪中の期間は、故人との近さによっておよそ三ヶ月から一年ほどまで幅があります
…もっとも長いのは配偶者・両親・子どもといった近親者で、一周忌までの約一年を喪中とするのが一般的です。
兄弟姉妹や祖父母・孫などの二親等は三ヶ月から半年を目安とする地域も多く、家のしきたりで期間が決められていることも少なくありません。
・ 配偶者・両親・子ども:一周忌まで(約一年)
・ 兄弟姉妹・祖父母・孫:三ヶ月〜半年
いずれも厳密な決まりがあるわけではなく、家庭や地域の習慣に従うケースが多いでしょう。
年賀状や挨拶の対応
◇喪中の期間は、お祝いの意味を持つ挨拶や年賀状を控えるのが基本です。
…毎年やり取りしている相手には、11月末〜12月初旬をめどに「喪中はがき」を送り、年賀状を欠礼する旨を伝えます。
喪中はがきは新年の挨拶を控える連絡であり、相手への感謝や近況報告を兼ねた丁寧な文面にするのが一般的です。また、親しい間柄には、あらためて落ち着いた頃に寒中見舞いを送ることもあります。
喪中の初詣や正月行事
◇喪中の期間は祝い事を控えます
…そのため正月飾りや「おめでとうございます」といった新年の挨拶は避けるのがマナーです。
一方で、初詣に関しては「忌中と違い、喪中は参拝しても良い」とする考えが広がっています。
ただし、家の方針や地域の風習で控える場合もあるため、周囲と相談しながら判断すると安心です。しめ縄や門松などの装飾を控えつつ、静かに過ごす家庭も多く見られます。
[喪中の初詣について詳しく]
忌中の期間はいつまで?

忌中はいつまで続くのかは、故人との関係によって変わります。まずは一般的な忌中期間と、四十九日までの流れを把握しておくと判断がしやすくなります。
関係別の忌中期間の目安
◇忌中とは、家族が亡くなってから四十九日法要までの期間を指します
…もっとも長いのは配偶者・両親・子どもなどの近親者で、四十九日まで忌中とするのが一般的です。
兄弟姉妹や祖父母など二親等にあたる親族は、20日〜30日前後を忌中とみなす地域もあります。また、旧来の「服忌令」では親族ごとに忌中期間の細かな目安が示されていますが、現代では四十九日を基準にする家庭が多くなりました。
・ 配偶者・両親・子ども:四十九日(忌明け)まで
・ 兄弟姉妹・祖父母・孫:20日〜30日前後
家の習慣で異なることもあるため、最終的には家族の方針に合わせると安心です。
[服忌令とは]
四十九日と忌明けとは
◇忌明けとは、四十九日法要を終えた時点を指し、忌中の期間が終了する節目となります。
…仏教では亡くなった人が四十九日を経て成仏すると考えられ、この日に法要を行う家庭がほとんどです。
四十九日法要の後には、神棚封じを解く、香典返しを贈る、納骨式を行うなど、忌中には控えていたことを進めます。忌明けは喪中と違い、日常生活の制限がひとつずつ解かれていく重要なタイミングといえるでしょう。
仏教と浄土真宗における考え方
仏教では、死を穢れとする考えがないため、忌中であっても寺院への参拝は問題ありません。忌中をとくに宗教的に定めているのは神道であり、神社参拝を控える理由も神道の教えによるものです。
そのため忌中や喪中の期間を設けない家庭もあり、寺院での初詣や法要を中心に過ごすことが一般的です。
神社参拝はなぜ控える?

◇忌中に神社参拝を控えるのは、神道において「死」を穢れと考えるためです。
…神さまの前に穢れを持ち込まないよう、四十九日までは神社を避ける家庭が多く見られます。
忌中と喪中が混同されることがありますが、参拝を控える必要があるのは神道の忌中であり、仏教とは理由が異なります。
忌中の「神棚封じ」とは?
◇忌中の間は、神棚に白い半紙を貼って扉を閉じる「神棚封じ(神棚閉め)」を行います。
…これは、死の穢れが神さまに触れないようにするための神道の慣習です。
封じる期間は四十九日までが一般的で、この期間中は神棚に手を合わせたり供物を置いたりしません。忌明け後、白紙を外して普段どおりに戻します。
忌中のお祓いはしてもいいの?
忌中の神社参拝は控えますが、「お祓い」や「厄払い」など特別な祈祷が必要な場合、神社によっては境内への立ち入りを許可しているところもあります。
ただし、どの神社でも可能というわけではないため、事前に確認するのが安心です。忌中に祈祷を受けるかどうかは家庭の方針や地域の慣習によっても異なるため、迷う場合は家族で相談すると良いでしょう。
喪中と忌中にやってはいけないこととは

喪中と忌中は、どちらもお祝い事や華やかな行事を控える期間です。ただし、避けるべき内容には違いがあるため、それぞれのポイントを整理しておくと判断がしやすくなります。
喪中に控えるお祝い行事
喪中は一年間、故人を偲び静かに過ごす期間とされ、結婚式や新築祝いなどのお祝い事は控えます。また、お正月の挨拶や年賀状、「おめでとうございます」といった祝い言葉も避けるのが一般的です。
七五三や誕生日などの身内のお祝いは、家族の判断で行われることもあります
忌中に避ける慶事と参拝
忌中は四十九日までの期間で、神道では「死の穢れ」を他者へ移さないために、慶事への参加を避けます。結婚式や大きな行事はもちろん、神社参拝もしばらく控えるのが一般的です。
この期間は外出や会食を控える家庭もあり、できるだけ静かに過ごすことが重んじられます。
贈り物(お歳暮・お中元)の扱い
喪中の場合でも、お中元やお歳暮は日頃の感謝を伝える贈り物であり、お祝い事ではないため、贈っても問題ありません。落ち着いた品を選ぶなど、相手に配慮した形で贈る家庭が多いです。
一方、忌中(四十九日まで)の期間は贈り物を控え、忌明け後にあらためて届けるのが一般的です。年末に忌中が重なる場合は、歳暮を避けて寒中見舞いとして贈る方法もあります。
[喪中のお中元・お歳暮マナーについて詳しく]
喪中・忌中の七五三・お祭り

七五三や地域のお祭りは「お祝い」「華やかな行事」にあたるため、喪中・忌中では判断に迷いやすい場面です。期間の違いや地域の慣習を踏まえて、家族で方針を確認しながら進めると安心です。
七五三や誕生日祝いは?
喪中の場合、家族の節目である七五三や誕生日祝いは「静かに行う」「写真のみ残す」など、形を控えめにすれば問題ないとする家庭が多くみられます。ただし、盛大な祝い方や親族を招く会食は避けることが一般的です。
一方、忌中の間(四十九日まで)は祝い事を控えるのが基本です。七五三や誕生会は、忌明け以降に改めて行うのが無難でしょう。
お祭り・旅行・飲み会への参加は?
喪中は外出や娯楽を禁じる決まりはありませんが、華やかな場への参加は控えめにする家庭が多いです。
地域のお祭りは「賑やかな場に出ない」という考えと、「行事は生活の一部なので参加する」という考えが分かれるため、周囲と相談して判断すると安心です。
忌中の場合は、故人の供養を優先し、旅行・飲み会などの娯楽や大きな集まりへの参加は控えるのが一般的です。家で静かに過ごし、忌明け後に普段の生活へ戻っていくのが自然な流れです。
喪中・忌中のお正月の過ごし方とは

お正月は一年の中でも特に「お祝い色」が強い時期です。喪中と忌中では、控えるべき内容が異なるため、まずは基本の考え方を押さえておくと安心です。
正月飾り(門松など)はどうする?
◇喪中の期間は、門松・しめ縄・鏡餅などの飾り物は控えるのが一般的です。
…これは飾り自体が「新年を祝う意味」を持つためです。一方、忌中(四十九日まで)は、祝い事を徹底して避けるため、飾り付けは行いません。
飾りを控える場合でも、静かに年を越すだけで問題はありません。地域によっては簡素な飾りを許容する考え方もあるため、家庭の方針に合わせて判断します。
初詣はどうする?
◇喪中は宗教的な制限はなく、寺院への参拝であれば問題ありません。
…ただし、神社参拝については「新年の祝い事」と捉える家庭もあるため、控える場合もあります。
忌中は神道の考え方に基づき、神社参拝を控えるのが基本です。寺院での参拝や家族で静かに祈る形であれば差し支えないとされています。いずれも家の方針や地域の慣習を確認した上で判断すると良いでしょう。
おせちは食べてもいい?
おせちは縁起物という性質から、華やかな料理を避けたい場合は控えめにしたり、普段の食事にする家庭もあります。喪中でも「祝い膳を避ける」というだけで、食べてはいけない決まりはありません。
忌中の場合は祝いの意味合いが強いため、四十九日まではおせちを控える家庭が多いです。必要であれば、通常の食事に置き換えるなど、静かな形でお正月を過ごします。
お祝いの言葉はどう言い換える?
喪中の期間は「おめでとうございます」といった直接的なお祝いの表現は避けます。代わりに、控えめな挨拶を選ぶと自然です。
● 「今年もよろしくお願いいたします」
● 「本年もどうぞよろしくお願い申し上げます」
いずれも祝いの意味を含まない表現であり、喪中・忌中のどちらでも安心して使える挨拶です。
年末年始に葬儀が重なる時の対応
◇年末年始に不幸があった場合でも、葬儀を行うこと自体に問題はありません
ただし、火葬場や式場・僧侶が休業している地域もあるため、年末は混雑や休業日を避けて日程を調整することがあります。
…すでに年賀状を投函していた場合は、松の内(1月7日)以降に「寒中見舞い」で訃報とお詫びを伝えるのが一般的です。
喪中はがきを出せなかった年でも、寒中見舞いで十分にマナーは守れます。
喪中・忌中の期間そのものは、年末年始に重なっても変わることはありません。年内に不幸があった場合は、翌年は喪中として新年の挨拶を控え、静かに過ごします。
喪中や忌中の招待を断るとき
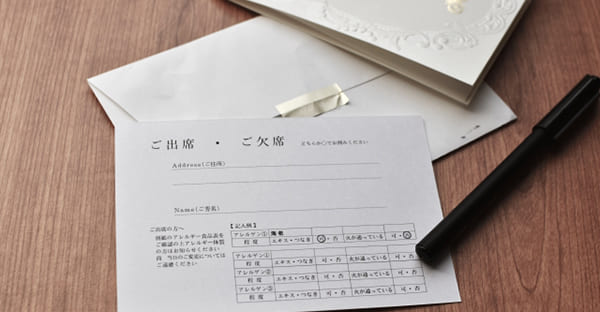
喪中や忌中の期間に結婚式や会食へ招かれた場合は、無理をせず辞退してかまいません。相手に負担をかけない伝え方を押さえておくと、丁寧な印象で断ることができます。
結婚式の断る場合の例文
結婚式を断る際、喪中・忌中であることを直接の理由として書くのは避けます。祝いの場に余計な気遣いを与えないためです。やんわりとした表現で欠席を伝えると丁寧です。
「このたびはご結婚おめでとうございます。
せっかくお招きいただきましたのに、都合により出席が叶わず申し訳ございません。
お二人の末永いお幸せを心よりお祈り申し上げます。」
喪中・忌中だからこそ参加を控える場合でも、理由はあえて伏せて伝えるのがマナーです。
飲み会・交流会の断り方
親しい相手の飲み会や交流会は、結婚式ほど形式にこだわらなくてかまいません。喪中や忌中で心の整理がつかない旨をやんわり伝えると自然です。
「まだ身内のことで落ち着かず、今回は参加を見合わせます。」
「気を遣わせてしまうので、しばらく集まりは控えています。」
この程度の簡潔さで十分伝わります。
事前に喪中はがきを出しておく(書き方)
招待やお祝いごとが多い相手には、事前に喪中はがきを出しておくと、相手も予定を立てやすくなります。喪中はがきでは、故人の続柄と亡くなった時期を簡潔に伝え、新年の挨拶を控える旨を記します。
● 喪中はがきの基本構成
・ 故人が亡くなったことの報告
・ 喪中のため年始の挨拶を控えること
・ 平素のお礼と今後のお願い
喪中はがきを出せなかった場合でも、後から寒中見舞いで丁寧に伝えれば問題ありません。
[喪中はがきの書き方や出す時期について詳しく]
まとめ|喪中と忌中の違いと注意点

喪中と忌中はどちらも身を慎む期間ですが、目的や過ごし方には違いがあります。喪中は一年を通してお祝い事を控える期間であり、忌中は四十九日まで“神道における穢れを慎む期間”として、特に神社参拝や慶事を避けます。
七五三・お祭り・初詣・正月飾りなど、判断に迷いやすい場面も多いため、家の方針や地域の慣習を確認しながら進めることが大切です。贈り物や招待の対応も、無理をせず丁寧に伝えれば十分にマナーは守れます。
喪中・忌中の考え方は家庭によって異なります。期間の違いを知り、過ごし方のポイントを押さえておくことで、安心して日常を整えていけるでしょう。
お電話でも受け付けております
















