
永代供養と永代使用の違いとは?永久ではない?管理費とは違う?その意味を3分で解決!
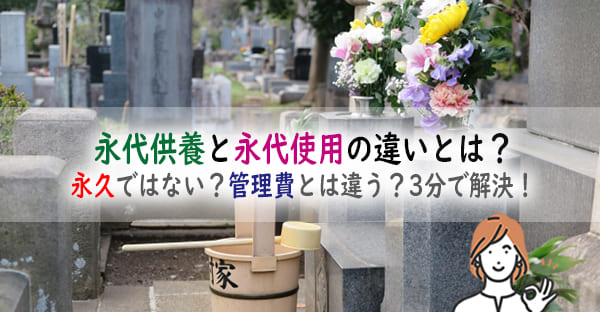
・永代供養と永代使用の違いとは?
・永代供養、永代使用は永久ではない?
・永代使用料と管理費とは違う?
お墓を建てる際、見積もりを取ると「永代供養」「永代使用」の項目があり、「同じ内容なのでは?」と混乱してしまう人もいますよね。
言葉が似ているので同じもののように思えますが、永代供養と永代使用は全く違うものです。
本記事を読むことで、永代供養と永代使用の違いや、管理費と永代使用料の違い、知っておきたい永代供養料・永代使用料の注意点が分かります。

永代供養と永代使用の違いとは?

◇永代供養は、永代に渡り供養をすることです
「永代供養」と「永代使用」はお墓を購入するにあたり、同じ内容と勘違いする人もいますが、子々孫々と永代に渡る「永代」の言葉が重なるだけで、意味は全く違うので注意をしてください。
| <永代使用料と永代供養料の違い> | |
| ①永代使用 | ・永代に渡り墓地を使用すること |
| ②永代供養 | ・永代に渡り供養をすること |
お墓を建てる時には墓地区画を購入するのではなく、墓地区画を永代に渡り使用する権利「永代使用権」を購入します。
一方で「永代供養料」を支払う時は、霊園や寺院などの墓地管理者に遺骨の管理や供養を永代に渡り任せる時です。
「永代供養」とは?
◇「永代供養」とは、永代に渡り遺骨の管理や供養を行うことを指します
遺骨の供養で使用される「永代供養」は、主に霊園や寺院などの墓地管理者が、家族に代わって永代に渡り、遺骨の供養・管理を担うことです。
従来の日本では先祖代々墓に遺骨を納骨し、お墓の継承者が代々墓主としてお墓のお世話やご先祖様の供養を行ってきました。
けれども現代は少子化などの理由で、お墓の継承問題が深刻です。
このような時に、墓じまいをして取り出した遺骨の永代供養を行い、墓地管理者に遺骨の供養を担ってもらいます。
「永代使用」とは?
◇「永代使用」とは、墓地区画を永代に渡り使用することです
お墓は「あの世の住まい」と例えられますが、家と違い墓地は購入できません。
お墓を建てる時は「永代使用料」を支払い、永代に渡り墓地区画を使用できる権利「永代使用権」を購入します。
永代使用料を支払うと、霊園や寺院などの墓地管理者から、特別区画を使用する証明書「永代使用承諾書」が発行されます。
永代供養料と永代使用料の注意点

◇永代供養料・永代使用料と管理費は違います
永代供養料や永代使用料は契約時に一括で支払われることの多い費用です。
一方で管理費は毎年支払われる費用となり、永代供養料と永代使用料、管理費とは、全く異なります。
●「管理費」は、霊園やお寺の維持管理費です。
…主に公共部分や設備の維持管理に使われ、費用目安は約3千円~2万円/年ほどとなります。
霊園では「年間管理料」、寺院では「護持会費(ごじかいひ)」などとも呼びますが、いずれも管理費に相当するでしょう。
なかには「お布施」として管理費をお渡しする寺院もあります。
永代供養料も永代使用料も支払いは一括
◇永代供養料や永代使用料は、原則的に「初期費用」です
永代供養料は主に遺骨を霊園や寺院にお任せする時の初期費用として支払われます。
一方で永代使用料は、お墓を建てる墓地区画を契約する際の初期費用です。
決して安い金額ではないので、一括で支払うことが難しいこともあるでしょう。
霊園(墓地管理者)に相談をすると、いくつかの分割方法を提案してくれます。
・一括納入
・霊園(墓地管理者)による分割払い
・メモリアルローンを組む
・多目的ローンなどを組む
一般的には契約後、「納入通知書」が郵送されます。
その通知書に倣い、金融機関の窓口で永代供養料や永代使用料を納入すると、霊園や寺院から「使用許可証」が届くでしょう。
永代使用料は所有権ではない
◇「永代使用権利」は所有権ではなく「使用権」です
近年、継承者問題により墓じまいが増えました。
墓じまいを進めるにあたり、墓地区画を住居の土地購入と同じように考える人もいますが、墓地は個人が所有できる土地ではありません。
墓地の所有者は霊園や寺院など「墓地管理業者」となり、土地のように自由に扱うことはできない点に注意をしてください。
・売買する
・他者に譲渡する
・他者に貸す
継承者がいないなどの理由で墓地を使用しなくなった時には、遺骨を取り出し墓石を撤去する「墓じまい」を行い、墓地管理業者へ返還します。
また「永代使用権」は、賃貸住宅の契約などで支払う敷金とも性質が違う料金ですので、返還してもお金は返ってきません。
以上のことをあらかじめ理解してから、墓じまいを進めましょう。
永代供養の「個別供養期間」とは
◇永代供養は必ずしも、個別に供養をする訳ではありません
永代供養は遺骨を家族に代わって永代に渡り供養・管理をしますが、必ずしも個別に遺骨を安置して、供養・管理を行うことではないので注意をしてください。
納骨堂など、個別スペースを設けた永代供養では、契約した最初の一定期間のみ「個別供養期間(個別安置期間)」を設けています。
個別供養期間は施設により異なり、約3年~33年とさまざまです。
この個別供養期間が長くなるほど永代供養料も高くなる傾向にあります。
また個別供養期間に家族が延長申請をして契約をすると、個別供養期間を延長できる霊園や寺院もあるでしょう。
永代供養料と永代使用料の費用相場は?

◇永代供養料は遺骨に対して、永代使用料は墓地に対してかかります
永代供養料と永代使用料は前述したように、全く性質の異なる費用です。
「永代供養」は永代に渡り遺骨を供養すると言う、形のないサービスになりますが、一般的に永代供養に付随する費用も含みます。
そのため価格幅が広いのですが、他の遺骨と一緒に合祀埋葬される「合祀墓(永代供養墓)」などによる、最も安い永代供養料になると、約3万円~5万円です。
| <永代供養料と永代使用料の費用相場> | |
| ①永代供養料 | …約3万円~80万円/1柱 |
| ②永代使用料 | …約30万円~100万円/一区画 |
単位を見ても分かるように、そもそも永代供養料は遺骨1柱につき算出され、永代使用料は墓地の一区画に対して算出されます。
そのため永代使用料の費用幅は、主に墓地の大きさや立地環境です。
永代供養料の費用相場は?
◇永代使用料の相場は、約60万円~100万円/一区画です
永代使用料の計算方法は一般的に「面積×1㎡当たりの費用」となります。
近年では全国的にお墓がコンパクトになったため、区画は1.44㎡ほどが目安です。
大きさに比例して永代使用料も高くなるため、一般的な墓地よりも大きな区画で大きなお墓を建てる場合には、それだけ費用もかかり、地価も影響します。
・墓地の面積
・都心と地方(地価)
・アクセスなど霊園の立地
・区画の場所(墓地内の立地状況)
・霊園全体の施設などの充実度
霊園のアクセスの良さ、立地はもちろんですが、広い霊園のなかで奥まった森林側で、カビが生えやすい、落ち葉が積もりやすいなど、お墓の管理が大変そうな区画は安くなる霊園もあるでしょう。
永代使用料の費用相場は?
◇永代供養料の相場は、約3万円~80万円/1柱です
永代供養料の場合、永代供養の方法によって費用が大幅に変化します。
永代供養料は個別供養期間の有無や期間の長さで調整すると良いでしょう。
| <永代供養料の相場> | ||
| [種類] | [相場] | [個別安置] |
| ①個別墓 | ・約70万ほど~ | ・あり (33年、50年など) |
| ②納骨堂 (集合墓) |
・約30万ほど~ | ・あり (3年・5年・15年など) |
| ③合祀墓 (永代供養墓) |
・約3万ほど~ | ・なし |
一般墓(個別墓)を建てる際、永代使用料と併せて永代供養料を支払うケースでは、約30万円~80万円、平均的には約40万円ほどが目安です。
永代使用料には消費税がかからない
◇宗教行為にあたる費用には、消費税がかかりません
永代使用料や永代供養料は、消費税の課税対象ではありません。
ただしお墓を建てる場合、永代使用料に消費税はかかりませんが、墓石やお墓を建てる工事費用には消費税がかかります。
これは永代供養料に対しても同じで、永代供養料自体に消費税はかからないものの、永代供養に付随する石碑などの墓標や彫刻、骨壺などに消費税がかかります。
| <消費税の有無> | |
| [料金] | [消費税] |
| ①永代使用料 | ・かからない |
| ②永代供養料 | ・かからない |
| ③建墓費用 | ・墓石代 ・建立工事など ・かかる |
ただし寺院墓地でお墓を建てた時、檀家に入る時にかかる「入檀費用」や、ご住職にお渡しする年間管理料「護持会費」、お布施などは宗教行為にあたるため、消費税の非課税対象です。
永代使用料は地価が影響する?
◇永代使用料は郊外の方が安くなります
永代使用料は地価が影響するため、都心部に近いほど高くなる傾向です。
土地購入と同じように、都心部でも地域によって大きな価格幅があるでしょう。
| <東京都の永代使用料相場> ●約1.20平米で比較 |
|
| ①東京23区 | …約160万円~200万円 |
| ②東京23区外 | …約40万円~60万円 |
けれども都心部に近い霊園や寺院墓地は、公共交通機関によるアクセスが良いなど、お墓参りにあたり好条件でもあります。
価格が安いだけで決めることなく、現地見学をして総合的に判断をしてください。
永代供養・永代使用の「永代」とは?

◇「永代」とは「永久」ではありません
永代供養の「永代(えいたい)」を「永久(えいきゅう)」と捉えて、未来永劫永久に続くことと思う人もいますが、「永代」と「永久」は似て非なるものですので注意が必要です。
| <永代と永久の違い> | |
| ①永代(えいたい) | …長い年月 |
| ②永久(えいきゅう) | …いつまでも限りなく続くこと |
永代を他の言葉で例えるならば、「永世中立国」などと使われる「永世(えいせい)」が最も近いでしょう。
「永世」は限りのない長い年月を指します。
永代供養に期間はある?
◇永代供養の期間に決まり事はありません
霊園や寺院であつかう「永代供養」の期限は、その霊園や寺院で提供する永代供養プランによって決めています。
永代供養の個別供養期間はさらに施設によりさまざまで、3年・5年・13年・33年・50年と幅広いでしょう。
一般的に永代供養を終えて弔い上げを済ませると、遺骨は霊園や寺院墓地内の合祀墓(永代供養墓)や供養塔に合祀埋葬されます。
墓じまいをすると永代供養料・永代使用料はどうなる?

◇墓じまいでは、遺骨を取り出さなければなりません
近年ではお墓の継承者がいない問題が深刻化しています。
お墓の継承者がいない、墓主が高齢になってお墓の維持管理が困難、などの問題がある場合、墓じまいによりお墓を閉じて解決する家が増えました。
取り出した遺骨を放置することは法的に違法であり、一般的に合祀墓(永代供養墓)や納骨堂、樹木葬などの永代供養を行います。
永代供養料はかかる
◇取り出した遺骨を永代供養します
墓じまいで取り出した遺骨の供養方法で、最も多い選択肢が永代供養です。
個別供養期間を設けた永代供養ならば納骨堂や屋外集合墓など、最初から遺骨が残らない方法であれば、合祀墓(永代供養墓)などがあります。
そのため永代供養料がかかりますが、「永代供養料」に全ての費用が含まれるプランも少なくありません。
・墓じまい後の永代供養に掛かる費用。納骨後も支払いはある?選ぶ時の3つのポイント
永代使用料はかからない
◇墓じまいでは永代使用料はかかりません
「永代使用料」は墓地区画を使用する権利「永代使用権」に対する費用ですので、墓じまいにより永代使用料はかかりませんが、「永代使用権」は返還します。
永代使用権を返還すると言うことは、墓地区画を霊園や寺院などの墓地管理者に返還することです。
墓地区画を返還する時には、墓石を撤去し墓地区画を更地にしなければなりません。
そのため墓じまいでは、遺骨の取り出し、墓石の撤去・更地工事費用がかかります。
・【墓じまいの費用まとめ】平均や僧侶費用、離檀料は?遺骨供養まで手順5つでかかる費用
永代供養をするメリットは?
◇お墓の維持管理の負担がなくなります
墓じまいをして、取り出した遺骨を永代供養にすることで、家族はお墓や遺骨の維持管理への負担がなくなり、継承者を立てる必要がありません。
個別供養期間がある永代供養は、個別供養期間に比例して永代供養料が高くなる傾向ですが、その分、永代供養をした後も故人へのお参りや供養ができます。
永代供養には納骨堂や樹木葬(永代供養付き)、合祀墓(永代供養墓)など、さまざまな選択肢があるため、家族の希望に合わせた永代供養が可能です。
ただし個別供養期間が過ぎると合祀墓(永代供養墓)に合祀埋葬され、遺骨は返らなくなるので、個別に遺骨を残したい場合は個別供養期間や延長の可否を確認する必要があるでしょう。
まとめ:永代供養と永代使用は全く違うものです

永代供養は永代に渡り供養すること、永代使用は永代に渡り(墓地を)使用できることを指し、永代供養と永代使用は違いを比べることのできない、全く違うものです。
お墓を建てる際、墓地は必要ですので永代使用料は必ず支払いますが、永代供養料は支払う必要のない霊園や寺院もあります。
ただ近年では、墓主が亡くなったまま継承者がいなくなり、年間管理料が払われずに撤去される無縁墓も増えたため、お墓を建てるにあたり永代供養料が項目に含まれる霊園や寺院も増えました。
けれども家族にとって無縁仏にしないメリットもあります。
お電話でも受け付けております















