
香典返しはいつ送る?「当日返し」とは?早く送るとダメ?品選びのタブーや金額相場は?
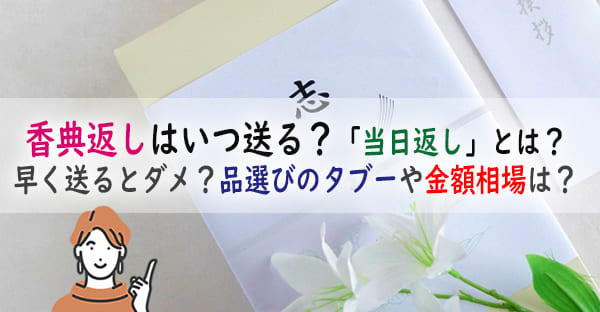
・香典返しを送るタイミングはいつ?
・最近増えた「当日返し」とは?
・香典返しの金額相場は?
・香典返しの品にタブーはある?
「香典返し」とは、通夜や葬儀でいただいた香典のお礼として送る品です。
香典返しは四十九日法要を終えたご報告とともに送る風習があります。
本記事を読むことで、香典返しを送るタイミングやマナー、選ぶ品のタブーや金額相場、最近増えた「当日返し」とは何かが分かります。

香典返しを送るタイミングとは?

◇香典返しを送るタイミングは、四十九日法要から7日間ほどの間です
「香典返し」とは、香典をいただいた人々へのお礼の品です。
香典には、家族を亡くしたご遺族の哀しみに寄り添い慰め励ます、また通夜や葬儀費用に対しての相互扶助の役割を果たします。
そこでお礼の品を送り「おかげさまで無事に四十九日法要まで済ませることができました。」と報告をすることが「香典返し」です。
| <香典返しを送るタイミングは?> | |
| [考え方] | [目安] |
| ・忌明け後 | ・四十九日法要後 |
| ・当日返し | ・葬儀当日 |
| ・初七日 | ・初七日法要後 |
| ・約1カ月まで | ・葬儀から30日 |
| ・納骨の後 | ・四十九日法要後 |
昔は四十九日法要の後、香典返しを持ってご報告に廻りました。
ただ今は、遠方の参列者も増えたため現実的ではありません。
香典返しの挨拶状と添えて郵送する方法が一般的です。
忌明け後に送る香典返し

◇忌明けの四十九日法要後、2週間~1ヶ月以内
従来の香典返しの作法では、四十九日法要の後、1ヶ月以内を目安にお贈りします。
現代では1ヶ月以内であれば良いとされますが、昔は少なくとも、四十九日法要後の2週間以内に送るとされた時代もありました。
| <香典返しを送るベストなタイミング> ●四十九日法要後 |
|
| ①7日間まで | …ベスト |
| ②2週間まで | …従来の指標 |
| ③1ヶ月まで | …現代の指標 |
高齢の親族などに送る時には、2週間以内を目安にすると良いでしょう。
ただベストなタイミングとしては、四十九日法要から7日間ほどです。
仏式以外の葬儀
◇神式では五十日祭、キリスト教式では追悼ミサを目安にします
香典返しを四十九日法要後に送るタイミングが一般的なのは、全国的に仏式で執り行う葬儀が一般的だからです。
そのため神式やキリスト教式など、宗旨が違う葬儀を執り行った場合には、仏式の四十九日法要に相当する儀礼の後に、香典返しを送ると良いでしょう。
| <神式、キリスト教式の場合> ●四十九日法要に代わる儀式の後 |
||
| [宗旨] | [儀式] | [行う時期] |
| ①神式 | …五十日祭 | (50日以降) |
| ②キリスト教式 | ||
| ・カトリック | …追悼ミサ | (30日以降) |
| ・プロテスタント | …昇天記念日 | (1ヶ月後) |
キリスト教や神道では、仏教の「四十九日間の冥土の旅を経て成仏する」考え方がありません。
ただ、香典返しを送り「無事に追悼ミサ(五十日祭・昇天記念日)が済みました」と報告する意味合いがありますから、それぞれの儀礼を済ませた後、2週間~1ヶ月以内が望ましいです。
早く香典返しを送るとダメ?

◇「死の穢れ」を他者に移さないためです
日本で一般的な仏式の葬儀や法要は、仏教の教えに倣い進めます。
四十九日間は故人の魂が冥土の旅に出て成仏するまでの期間です。
「死を穢れ」とする考え方は神道ですが、神仏習合により家族が亡くなって四十九日間は、遺族も「死の穢れ(けがれ)」をまとっていることから、品を送って「死の穢れ」を移してはならないとされてきました。
| <忌中に行ってはいけないこと> | |
| ①死の穢れを移さない | ・品を送らない ・交流の場を控える |
| ②お祝い事をしない | ・慶事への参列 ・お正月などを祝う |
| ③神社参拝 | ・神様の眼に触れる ・神棚にお参りする |
実は仏教では人の死を穢れとする概念はありません。
けれども神仏習合の文化が根付く日本では、家族が亡くなるとご遺族は「死の穢れ」をまとうとし、他者に移さぬよう、身を慎む四十九日間がありました。
●そこで基本的には忌中の四十九日間は、香典返しを送りません。
・早く香典返しを済ませるならば、当日返しが良いでしょう。
そこで死の穢れがまとう四十九日間を経た「忌明け(きあけ)」後に、香典返しを送るとされてきたのです。
香典返しの「当日返し」とは?

◇「当日返し」とは、香典返しを葬儀当日にお渡しする方法です
香典返しを葬儀当日、帰宅の際にお渡しする「当日返し」の選択も増えました。
ただ香典返しの当日返しでは、参列者の香典額を予め予測できません。
そこで、全員に同じ香典返しを用意します。
| <当日返しの金額目安> ●香典返しは、香典の1/3~1/2が目安 |
|
| ・香典返しの金額目安 | …約2千円~3千円 |
知人友人や会社関係者など、一般的な御香典で包む金額は約5千円~1万円なので、その半額として約2千円~3千円が当日返しの目安です。
約3万円以上など、想定よりも大きな金額を包んでいただいた相手には、四十九日法要後に改めて送る喪主が多いでしょう。
詳しくは後ほど詳しく解説します。
当日返しの会葬礼状
◇「当日返し」を知らない高齢の人々も多いため、会葬礼状にひと言添えます
昔は香典返しを忌明けの四十九日法要後に送る方法が、一般的な作法でした。
そのため現代の葬儀で増えた「当日返し」を知らない高齢の人々も多いです。
「あの人は香典返しも送らない」と勘違いをしかねません。
「尚、香典返しは本日の返礼品をもって、代えさせていただきます。」
葬儀当日に清めのお塩や会葬品とともに添える「会葬礼状」には、香典返しの「当日返し」を準備した説明として、上記の一文を添えると良いでしょう。
・【家族が亡くなったら】昔と今、大阪の葬儀が変わった?決める3つのこと|永代供養ナビ
高額な香典をいただいた場合
◇香典金額が大きい相手には、改めて香典返しを送ります
そのなかでも約3万円以上の高額な御香典をいただいた場合には、(仏式であれば)四十九日法要の後1ヶ月以内を目安に、改めて香典返しを送ると失礼になりません。
| <当日返し、改めて香典返しを送る場合> | |
| [送る時期] | ・忌明け(四十九日法要)後 (2週間~1ヶ月以内) |
| [金額目安] | ・[香典額の半額]-[当日返しの金額] |
一般的な香典返しと同じく、約5万円以上など高額な額をいただいた場合には、香典額の1/4~1/3ほどの品でもかまいません。
香典返しにはお礼状を添えると良いでしょう。
・香典返しの挨拶状(お礼状)の書き方ポイントとは?マナーや5構成、3つの例文を紹介!
香典返しを1ヶ月までに送るケース

◇宗旨宗派を問わない自由葬では、四十九日にこだわりません
日本で仏式の葬儀は全体の8割以上と言われ、江戸時代からの檀家制度により仏教が根付く日本では、一般的に仏式の葬儀・法要が営まれます。
仏式の葬儀では、四十九日法要後を目安に香典返しを送りますが、近年では宗旨宗派を問わない葬儀「自由葬」なども増えました。
| <香典返しを1ヶ月以内に送るケース> | |
| ①宗旨宗派を問わない | ●菩提寺がない ・自由葬 ・家族葬 ・ホテル葬 ・直葬 …など |
| ②宗教者による儀式がない | ・読経供養、焼香がない(仏教) ・献花がない(キリスト教) ・玉串奉奠がない(神道) |
| ③香典辞退 | (予定外に) ・香典をいただいた ・供物や供花をいただいた |
宗旨宗派を問わず、僧侶を呼ばずに読経供養を行わない自由葬を執り行った、香典を辞退したものの、参列者が香典を持参していただいた場合などが挙げられます。
また地域性によっても、四十九日法要を待たずに全てが落ち着いたタイミングで香典返しを送る場合があるでしょう。
・【家族が亡くなったら】大阪で広がる家族葬。ホテル葬や自由葬6つのスタイル|永代供養ナビ
・「檀家」とは?かかる費用や義務、檀家になる・やめるには?檀家にならず法要はできる?
納骨後に香典返しを送る

◇「無事に納骨を済ませました」の報告とともに送ります
昔の風習では、家族が亡くなると四十九日法要を目安に納骨先を用意し、四十九日法要の後に納骨式まで済ませてきました。
現代でも先祖代々墓に納骨する、納骨堂など建墓期間を必要としない施設などにご遺骨を納骨する予定のご遺族は、親族が集まり執り行いやすいため、四十九日法要の後に納骨式まで済ませるケースが多いでしょう。
| <香典返しを納骨式の後に送る> | |
| [納骨式] | [タイミング] |
| ①四十九日法要の後 | ・四十九日法要後7日後頃 |
| ②別日に執り行う | ・百箇日法要までが目安 |
納骨式を目安に香典返しを送る場合、決まった期限はありません。
けれどもあまりにも遅くなっては失礼にもあたります。
目安として遅くとも百箇日法要までの納骨式であれば、納骨後の香典返しでも良いでしょう。
香典返しの金額目安は?

◇香典返しの品は、香典の1/3~1/2の金額が目安です
一般的な知人友人からいただく香典の金額目安は約5千円~1万円なので、一般的に2千円~3千円の品が多いです。
ただ香典が高額になるとお返しの品も大変ですよね。
例えば10万円の香典をいただいたら、約5万円で用意しなければならない計算です。
| <香典返しの金額目安> | |
| ①約1万円まで | ・香典の1/2ほど ・5千円の香典…約2,500円 |
| ②約3万円まで | ・香典の1/3ほど ・3万円の香典…約1万円 |
| ③約5万円以上 | ・香典の1/4ほど ・5万円の香典…約1万2,500円 |
香典は喪主の気持ちを励まし、相互扶助の役割を果たします。
そこで高額の香典を準備した人は親族や、喪主を慮ってのことでしょう。
あまりに高額な香典返しを送り、厚意を無碍にすることも良くありません。
高額の香典をいただいたら、香典返しはその金額に合わせ1/4~1/3ほどを目安に準備をすると良いでしょう。
・【大阪の葬儀・法要】お供え物に掛ける熨斗(のし)・掛け紙。場面に対応する5つの作法
香典返しに人気の品々

◇現代はカタログギフトが好評です
約2千円~3千円の品を香典返しには、カタログギフトを選ぶ人が増えました。
ネットはもちろん大手デパート等でも、金額に合わせた何種類ものカタログギフトが販売されています。
| <香典返しのカタログギフト> | |
| [カタログギフト] | [HP] |
| ・シャディ(Shaddy) | ・https://shaddy.jp/ |
| ・ハーモニック | ・https://www.harmonick.co.jp/ |
| ・リンベル | ・https://www.ringbell.co.jp/ |
ただ「自分で選んで贈りたい」人も多いでしょう。
高齢の人であれば品を送った方が適切な時もありますので、この場合は、下記のような品々が良く選ばれています。
| <香典返しに人気の品々> | |
| ●賞味期限が長い | ・お茶 ・コーヒー/紅茶 ・海苔 ・砂糖 …などなど |
| ●日用品 | ・タオル ・洗剤 ・石鹸 ・漆器 …などなど |
香典返しで避けたい品々
◇仏教に倣い、殺生を連想させる肉類は避けます
反対に香典返しにタブーとされる品は、仏教の教えに倣い殺生を連想されるものや嗜好品、「おめでたい」としてお祝い事で人気がある品々などです。
| <香典返しで避けたい品々> | |
| [タブーの品] | [具体例] |
| ●殺生を連想 | ・肉 ・魚 (四つ足生もの) ・革製品 |
| ●嗜好品 | ・お酒 ・タバコ |
| ●おめでたい品 | ・昆布 ・鰹節 ・花 |
香典返しに限らず、引き物などでは明瞭に金額が分かる品々は好まれません。
カタログギフトは現代の定番になっているのですが、例えば金券や商品券などは、「下品」と取る人々もいますので、注意をしてください。
返礼品(会葬御礼)と香典返しは違う
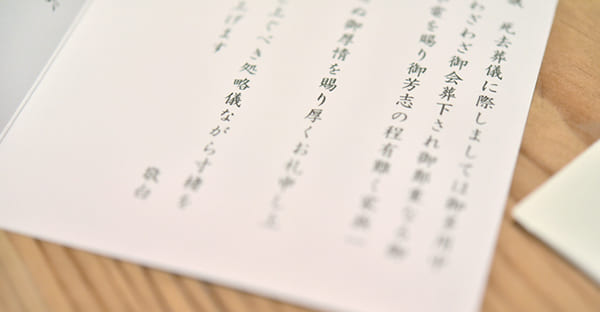
◇葬儀当日にお渡しする「返礼品」は、香典返しではありません
最近は香典返しの「当日返し」が増えました。
そこで葬儀当日にお渡しする返礼品(会葬御礼)と混同する人も少なくありません。
けれども従来の返礼品(改葬御礼)と香典返しは違うものです。
| <香典返しと返礼品(会葬御礼)の違い> | |
| [引き物] | [目的] |
| ●香典返し | ・香典へのお礼 |
| ●返礼品(会葬御礼) | ・葬儀参列へのお礼 |
返礼品(会葬御礼)は、約5百円~千円ほどの手軽な品を用意します。
内容はハンドタオルやコーヒーなどを見受けますが、会葬御礼には会葬礼状と清めの塩がセットされているのが特徴です。
まとめ:香典返しは四十九日法要後に送ります

基本的に香典返しは、忌明けの四十九日法要後、7日間までを目安に送ることが、最もタイミングの良い判断です。
ただ近年は「香典返しは送らなければダメ?」との質問が増えました。
例えば一家の家計を担う家族が亡くなると、香典は「相互扶助」の役割が大きくなります。
本来の葬儀で香典返しは省略するものではありませんが、お礼を丁重に行うことで、理解も得られるかもしれません。
ご理解を得るためにも、四十九日法要を済ませたタイミングで、無事に法要を済ませたことをご報告する挨拶状(お礼状)を送るようにしましょう。
・納骨式を済ませた後の挨拶状マナーとは?押さえる5つの構成と3つの例文|永代供養ナビ
まとめ
香典返しの金額目安、送るタイミング
●香典返しを渡す5つのタイミング
(1)忌明け後(49日後)
(2)当日返し
(3)初七日
(4)1カ月後を目安に
(5)納骨の後
●金額目安
・当日返し…約2千円~3千円
・一般的な香典返し…香典の半額
・高額な香典の場合…香典の1/4~
●香典返しと会葬御礼は違う
・香典返し…香典へのお礼
・会葬御礼…会葬へのお礼
お電話でも受け付けております
















