
【相続対策】自筆証書遺言を絶対無効にしない!押さえるべき5つのチェックポイントとは
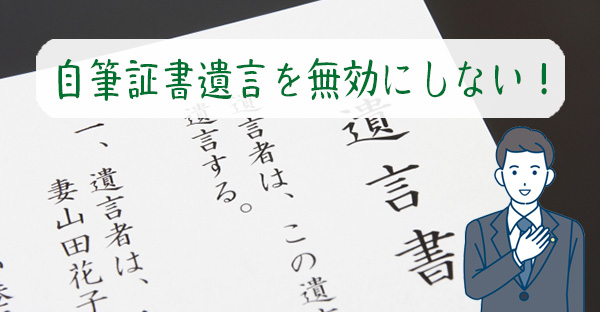
本人が全文、日付け、氏名を書いて捺印を押した自筆証書遺言は、無効になりやすい点が大きなデメリットです。
費用も掛からずいつでも思い立った時に、被相続人が証人の必要もなく、自分で手軽に作成できる自筆証書遺言は、その分無効になりやすい要素(作成時のミスや紛失など)を多く孕んでいます。
反対に言えば、自筆証書遺言が無効にさえならなければ、遺言の存在や内容を秘密にしながら、手軽に用意できる遺言の種類です。
 
【相続対策】自筆証書遺言を絶対無効にしない!押さえるべき5つのチェックポイントとは

自筆証書遺言のあらまし

自筆証書遺言は、被相続人が自分で全文を書き、日付けと氏名を署名して捺印を押して残す遺言書となり、ワープロ文書などは自筆証書遺言としては無効になります。(秘密証書遺言では有効)
・費用がほぼかからない
・証人の必要がない
・いつでも作成できる
・作り直しが簡単
・要件を満たさないと無効
・紛失の可能性
・変造の可能性
・遺言書を隠す(隠ぺい)の可能性
・相続発生後に発見されない可能性
・家庭裁判所の検認が必要
…そのため内容は法定相続人に分かってしまうものの、確実に効力のある遺言書を残したい被相続人は、公証役場で司法書士や弁護士などの専門家である公証人が、2人の証人を前に作成する「公正証書遺言」を選びます。
けれども公正証書遺言は費用も掛かり、さまざまな手続きが必要です。
(公証役場手数料約17,000円ほど(遺産総額500万円~1000万円として)~+公証人の報酬+証人への報酬など)
※参考:日本公証人連合会「法律行為に関する証書作成の基本手数料」より
自筆証書遺言が無効にならないために
自筆証書遺言を無効にしないためには、大前提として要件を満たした遺言書を作成すること(詳しくは後述)ですが、それ以前に遺言書が正しく保管され、発見されなければなりません。
(1)要件を正しく満たした自筆証書遺言書を作成
(2)被相続人が自分で遺言書を保管
(3)被相続人亡き後、遺言書の発見
(4)家庭裁判所で遺言書の検認
(5)遺言書の執行
より自筆証書遺言の執行を確実にしたいならば、執行者を指定すると良いでしょう。
●遺言執行者は、相続発生時に成人(未成年は不可)であり、破産していない者ならば誰でも指定できます。(民法1009条により)
→一般的に遺言執行者は、専門的な第三者である弁護士や行政書士、司法書士などの他、信託銀行による「遺言信託」の選択もひとつです。
民法1021条により、遺言執行に掛かる費用は相続財産から出されるので、相続人には負担は掛かりません。司法書士や弁護士、遺言信託などによる遺言執行者指定を行うのであれば、自筆証書遺言のチェックも依頼すると良いでしょう。
自筆証書遺言を無効にしない要件

自筆証書遺言は法によって6つの規定が定められています。この規定を確実に守ることができれば、自筆証書遺言は無効にはなりません。
(1)遺言者による直筆で作成
(2)遺言者の遺言能力
(3)作成日の明記
(4)署名と捺印
(5)遺言者単独の遺言
(6)家庭裁判所による検認
自筆証書遺言の特徴として、「何度でも気軽に作成できる」とお伝えしましたが、有効になるのは日付けが最も新しいものです。そのため、作成日の明記がなければ要件を満たさず、自筆証書遺言は無効になります。
遺言者による直筆で作成
自筆証書遺言では遺言者(被相続人)が直筆で作成しなければなりません。遺言者(被相続人)が、手足の不自由など、何らかの事情で直筆での遺言が残せない場合は、他の方法を選ぶと良いでしょう。
秘密証書遺言であればワープロ文書でも署名と捺印で有効性が認められ、遺言の内容も法定相続人に秘密にしたまま、遺言書の存在のみを周知できます。
ただ平成30年7月6日に成立した改正により、財産目録を添付する場合、財産目録に関しては自筆でなくとも署名捺印により有効になるよう、緩和されました。
(法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります」より)
遺言者の遺言能力
自筆証書遺言に限った条件ではありませんが、遺言者(被相続人)が遺言書作成当時に、認知症など、充分な判断能力を備えていない場合、その自筆証書遺言書は無効です。
また基本的にありませんが、遺言者が15歳未満の場合も遺言能力がないと判断されます。
作成日の明記
遺言書は作成日の明記が必須ですが、曖昧な書き方の自筆証書遺言は無効になるでしょう。例えば、「○年の誕生日に記す」などと〆た遺言書は無効になった事例があります。
手紙や自分史などではありませんので、「〇年〇月〇日」と、誰でも分かる日付けを明記してください。
署名と捺印
秘密証書遺言及び自筆証書遺言では、署名と捺印がないと無効になります。(民法968条一項より)
過去の判例を参考にすると、捺印をする印鑑は必ずしも実印でなければいけない訳ではなく、拇印(ぼいん)や指印でも朱肉や墨による押捺でも良い判例がありました。
けれども一般的には、より確実に残すために、実印による捺印が良いでしょう。
遺言者単独の遺言
ほとんどの遺言書が、ひとつの遺言書に対して一人の遺言者(被相続人)による遺言が書かれていますが、しばしば共同の遺言書が発見されます。
ひとつの遺言書に対して、複数の遺言者(被相続人)による共同の遺言が残されていた場合、その自筆証書遺言は無効になるので、注意をしてください。
家庭裁判所による検認
家庭裁判所による検認は前項でお伝えしましたが、そこで多いのが「自筆証書遺言を発見後、開封された場合はどうなるのか?」と言う質問です。
結論から言うと、相続発生後に自筆証書遺言書が開封されても、無効にはなりません。
けれども開封した人には、過料として5万円が課されます。
自筆証書遺言を無効にしない5つのチェックポイント
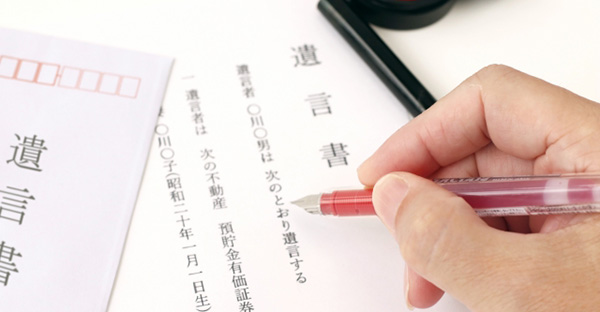
以上、自筆証書遺言の6つの要件を理解したうえで、実際に遺言書が無効になった事例から、封を閉じる前に、下記5つのチェックポイントを見返ると良いでしょう。
(1)遺言者(被相続人)は遺言能力があるか
(2)「遺留分」を考慮した内容か
(3)書き間違えはないか
(4)分かりにくい内容になっていないか
(5)正しい方法による修正や加筆
遺言者の遺言能力があるか
前項でもお伝えしましたが、作成前に遺言能力を疑われるような病状の診断を医者から受けていたならば、その自筆証書遺言書が無効になるかもしれません。
・認知症
・精神障害など
前述したように15歳未満の遺言者(被相続人)も無効になり得ますが、これは基本的にいないでしょう。
認知症や精神障害などの疑いがあった場合、法定相続人の一人が意義を唱えた時には無効になる可能性があります。
遺留分を考慮した内容か
「遺留分」とは、今後の生活のために法定相続人一人が最低限に相続できる財産の取り分です。この遺留分が配分されない内容の遺言書だった場合、その法定相続人は遺留分の請求ができます。
(1)法定相続人が配偶者のみ → 1/2
(2)法定相続人が子どものみ → 1/2
(3)法定相続人が直系のみ → 1/3
(4)法定相続人が兄弟姉妹のみ → 遺留分無し
(5)法定相続人が配偶者と子ども → 配偶者1/4・子ども1/4
(6)法定相続人が配偶者と父母 → 配偶者1/3・父母1/6
(7)法定相続人が配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者1/2
…このような場合、兄弟姉妹は法定相続人にはなりますが、遺留分はありません。
遺留分は遺産分割の指標ですので、法定相続人全員が同意した上であれば、その通りに分割する必要はありませんが、法定相続人の誰かが遺留分を請求した場合、遺産分割協議が複雑になります。
相続発生後のトラブルを避けるためには、予め遺留分を考慮した配分で指定すると良いでしょう。
書き間違えはないか
自分で作成する自筆証書遺言の場合、書き間違えによる無効が少なくありません。
また、自筆証書遺言が無効にならないよう、鉛筆など書きにくいものは避け、ボールペンなど、筆致の残る物を利用してください。
書き間違え自体は、あっても自筆証書遺言が無効にはなりませんが、書き間違えの訂正は厳格なルールがあります。
修正液など、誰もができる修正は無効になりますので、後述する書き間違えた時の「訂正ルール」を守って訂正をしましょう。
分かりにくい内容ではないか
「分かりにくい内容」は曖昧な表現ですが、特に不動産財産の住所などがこれに当たります。
相続財産の分配について残す遺言書の場合、多くは財産目録を添付して指定する方法が多いです。
●特に注意をしたいポイントは、不動産財産を特定するための書き方です。正確に地所を特定できるよう、登記簿に沿って不動産財産を指定します。
・所在
・番地
・地番
・地目
・地籍
・家番号
・構造
・床面積
以上の数字を登記簿に沿って正確に記すことで、自筆証書遺言が無効になる可能性は低くなるでしょう。もちろん、財産目録を添付する方法も有効です。
※財産目録の書き方については、別記事「【相続対策】財産目録の書き方☆記載する5つの項目や注意点|書き進める5つのポイント」をご参照ください。
加筆修正、5つのルール
自筆証書遺言は加筆修正自体が無効になる訳ではありません。けれども正しく加筆修正をしないと、遺言書自体が信用性が失われ無効になってしまうでしょう。
(1)遺言書(被相続人)本人が加筆修正を加えること
(2)加筆修正の箇所を正しく指定する
(3)変更した旨を付記する
(4)遺言者(被相続人)による署名を行う
(5)加筆修正をした箇所に捺印をする
加筆修正を加えた部分には二重取り消し線を書き、横書きではその上、縦書きではその右側に正しいものを書き入れます。
さらに余白に訂正文(加筆文字数/削除文字数など)を自筆で書き入れ(付記)、二重取り消し線に重ねて捺印をする流れです。
※詳しくは別記事「【相続対策】自筆証書遺言を無効にしない、加筆修正5つのルール|修正サンプルで解説!」で詳しくお伝えします。
自筆証書遺言は、遺言者(被相続人)が全て自筆で書かなければならない点が大変でした。特に財産目録は不動産財産など、ひとつひとつの財産を登記簿に沿って正確に特定しなければなりません。
けれども2020年7月以降、改正により財産目録に関してはパソコンによる作成が可能になり、この他通帳や不動産登記簿などの書類関係も、コピー添付ができるようになり、非常に作成しやすくなっています。
より確実に有効な遺言書を残したいなら、お金は掛かりますが公正証書遺言が良いでしょう。紛失や発見されない心配もなく、原本も公証役場で保管されるので、紛失や変造の可能性はほとんどありません。
※遺言書の種類や公正証書遺言について、詳しくは下記記事でお伝えしています。
・【相続対策】公正証書遺言でも無効になるって本当?有効を保つ、5つのチェックポイント
・【相続対策】遺言の有効性が高い種類を選ぶ。遺言3種類のメリットとデメリットを解説!
まとめ
自筆証書遺言6つの規定と5つのポイント
●6つの規定
(1)遺言者による直筆で作成
(2)遺言者の遺言能力
(3)作成日の明記
(4)署名と捺印
(5)遺言者単独の遺言
(6)家庭裁判所による検認
●5つのポイント
(1)遺言者(被相続人)は遺言能力があるか
(2)「遺留分」を考慮した内容か
(3)書き間違えはないか
(4)分かりにくい内容になっていないか
(5)正しい方法による修正や加筆
お電話でも受け付けております















