
要介護と要支援の違いとは?要介護認定の早わかり表|要介護状態や利用サービス・注意点
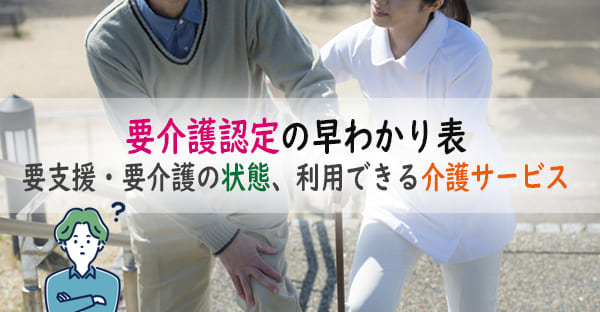
・要介護認定の段階とは?
・要支援、要介護の段階で違う状態とは?
・要支援、要介護で受けられるサービスとは?
・要支援、要介護認定の手順は?
・要介護認定によるトラブル体験談は?
家族が生活の介護を必要とした時、働き続けながら介護ができるか不安ですよね。
日本では要介護認定制度があり、認定された要支援・要介護認定の段階に応じて、家族をサポートする介護サービスの利用ができます。
本記事では、要支援・要介護認定の7段階、それぞれの状態の目安や、段階で違う介護サービスが分かります。
要支援・要介護認定が下がったことで起きたトラブル体験談とともにお伝えしているので、どうぞ最後までお読みください。

要支援と要介護の違いとは?

●厚生労働省では①自立、②要支援(1・2)、③要介護(1~5)の段階で状態を区分しています
そこで日常生活において介護や支援を必要としない状態が「自立」です。
介護保険を利用する際に受ける「要支援・要介護認定」では、要支援が1・2の2段階、要介護は1~5の5段階となります。
| <要支援・要介護の違いとは> | ||
| [3段階] | [状態] | [事例] |
| ①自立 | ・日常生活は自分でできる ・介護サービスが必要ない |
|
| ②要支援 | ・日常生活は自分で「ほぼ」できる ・多少の介護サービスが必要 |
・入浴や食事は自分でできる ・浴槽の掃除などが困難 |
| ③要介護 | ・日常生活全般が困難 ・誰かの介護が必要 |
・入浴介助が必要など |
小谷美保子さん(65歳:仮名)は5年前、10歳年上で独身の兄(当時70歳)が実家でひとり暮らしをしていたところ、脳梗塞を発症!
病院に救急搬送され懸命なリハビリを続けるなかで要介護3認定を受けました。
そこで約半年ほどのリハビリ専門病院でのリハビリ期間を終えた後、要介護3の人が入所できる特養老人ホーム施設への入所をしています。
・厚生労働省「介護保険制度における要介護認定の仕組み」
要支援・要介護の違いが分かる、7つの区分

◇要介護認定は、介護サービスの必要度を計るものです
要介護認定では、誰かの支援や介護を必要とする要支援1から要介護5まで7段階に分かれ、保険者である介護認定審査会(市町村に設置)で決定されます。
| <要支援・要介護の違い:7段階> | ||
| [区分] | [状態] | [具体例] |
| ①要支援1 | ・日常生活がほぼ自分でできる | ・掃除などの支援が必要 (食事や入浴などは自分でできる) |
| ②要支援2 | ・日常生活がほぼ自分でできるが、要支援1と比べてより支援が必要 | ・立ち上がる時の補助 ・移動時の支え ・入浴時に背中を洗えない |
| ③要介護1 | ・歩行、立ち上がりが不安定 ・部分的に介護が必要 ・思考力や判断力の低下 |
・衣服の着脱(排泄/入浴) ・意識の混乱 |
| ④要介護2 | ・食事、排泄などで介護が必要 ・立ち上がり、歩行が不安定 ・日常生活全般で介護が必要 |
・認知症の症状 ・排泄、入浴の介助 ・着替えの見守り |
| ⑤要介護3 | ・立ち上がり、歩行に介助が必要 ・認知症の症状 ・日常的に介助が必要 |
・認知症の症状 ・排泄、入浴、着替え時の介助 |
| ⑥要介護4 | ・自力で立ち上がり、歩行は困難 ・日常生活が介護がないと成り立たない ・意思疎通がやや困難 |
・著しい認知症の症状(暴言・暴力) ・排泄、入浴、着替え時の介助 ・徘徊行動など |
| ⑦要介護5 | ・ほぼ寝たきり状態 ・日常生活全般に介助が必要 ・理解力の低下 ・意思疎通が困難 |
・食事の介助 ・おむつ交換 ・寝返りの介助 ・コミュニケーションが取れない |
※以上は一例であり、同じ区分でもさまざまな症例があります。
美保子さんの兄である康彦さんは、脳梗塞の後遺症により右半身にこわばりがあったため、お風呂のふちを自分でまたぐこともできず、歩行も困難、重い荷物を持つと右側がぐんと沈み、物を持った歩行でできない状態でした。
当時は手先にもこわばりがあり、お箸を自分で扱えないなどしていたため、排泄時にもトイレでズボンの上げ下ろしの介助を必要としています。
要介護認定を受けるには?

◇役所窓口で「介護保険要介護・要支援認定申請書」を提出します
要支援・要介護認定を受けるには、まず居住地域の役所窓口で「介護保険要介護・要支援認定申請書」を提出すると良いでしょう。
聞き取り調査のため、後ほど自宅へ認定調査員が訪れます。
認定調査員は市区町村役場の職員や、委託を受けたケアマネージャーなどです。
| <要介護認定を受ける流れ> | |
| [手続き] | [場所] |
| ①「介護保険要介護・要支援認定申請書」の提出 | ・役所窓口 |
| [一次判定] | |
| ②認定調査員による聞き取り調査 | ・自宅訪問 |
| ③主治医意見書の提出 | ・かかりつけ医 |
| ④要介護認定 | ・自動判定 |
| [二次判定] | |
| ⑤審査判定 | |
| ⑥認定通知書の受け取り (被保険者証) |
・自宅 |
要介護認定には申請書の提出から約30日ほど掛かるでしょう。
一次判定では、聞き取り調査・かかりつけ医による「主治医意見書」・コンピューターによる自動判定により、大まかな介護に要する時間を基に、要介護区分が判断され、二次判定へと移ります。
要介護認定の有効期間
◇要介護認定には有効期間があります
厚生労働省では原則として6ヶ月が、要介護認定の有効期間です。
要介護状態に応じて3ヶ月~48ヶ月で設定されます。
美保子さんの兄、康彦さんのケースでは要介護3認定を受けた時点で18ヶ月(1年半)の設定でした。
要介護認定期間を過ぎると手続きもより複雑になるため、期間内に認定の更新手続きを取りましょう。
| <要介護認定の更新手続き> | |
| [忘れたら?] | ・介護保険サービスの利用ができなくなる (全て自己負担になる) |
| [更新期間] | ・有効期間の60日前~最終日まで |
| [申請方法] | ●住民票がある役所へ更新書類を提出 ・要介護(要支援)認定更新申請書 ・介護保険被保険者証 |
| [申請後の手順] | ・要介護(要支援)認定更新申請書を提出 ・要介護認定調査 ・「主治医意見書」を役所に提出(主治医) ・介護認定審査会で審査 ・新しく介護保険被保険者証が配布 |
申請をした後、介護認定審査会で要支援1の必要もないと判断されると「非該当」となり、介護保険サービスを利用できなくなります。
要介護区分で違う介護サービス一覧

◇更新で要介護3から要支援2になり、特養老人ホームの利用ができなくなりました
兄の康彦さんは純粋に喜んでいたのですが、美保子さんには頭の痛い問題がありました。
それは、現在兄の康彦さんが介護サービスを受けている特養老人ホームが、要介護3以上の人々を対象にしていたことです。
要支援・要介護7区分で、利用できる介護サービスはこれだけ違います。
| <要支援・要介護の違い:介護保険サービスの違い> | ||
| [介護サービスの種類] | [要支援(1.2)] | [要介護(1~5)] |
| ●訪問型サービス | ・訪問介護 ・訪問入浴 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 |
・訪問介護 ・訪問入浴 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型、訪問介護看護 |
| ●通所型サービス | ・デイサービス ・デイケア ・ショートステイ |
・デイサービス ・デイケア ・ショートステイ |
| ●訪問+通所型サービス | ・小規模多機能型居宅介護 ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 ・グループホーム(要支援2~) ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 |
・小規模多機能型居宅介護 ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 ・グループホーム ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 |
| ●入居型サービス | ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
|
| ●環境 | ・福祉用具貸与(要件あり) ・特定福祉用具販売 ・住宅改修費の支給 |
・福祉用具貸与(要件あり) ・特定福祉用具販売 ・住宅改修費の支給 |
要介護3以上でなければ、施設に入居して介護保険サービス受けることはできません。
美保子さんの兄康彦さんは、現在の特養老人ホームを退所しました。
特養老人ホーム退所による不安
◇入所型の特養老人ホームを退所すると、ひとり暮らしになります
家族があるため、兄の康彦さんが特養老人ホームを退所することで、ひとり暮らしになる点が、美保子さんが最も不安を感じた点でした。
つい昨日まで老人ホームのスタッフにケアしてもらっていたため、火の元はもちろん、下記の点が不安です。
| <特養老人ホーム退所後の不安> | |
| ①古い実家 | ・階段の段差が高い ・お風呂の敷居などが高い ・和式トイレ |
| ②夜間訪問介護がない | ・訪問介護サービス…週2回 ・デイケア…週2回 |
| ③自宅改修の支援額が少ない | ・限度額20万円(原則1回) |
※美保子さんの事例です、全ての人が同じとは限りません。
子どもも大きくなったとはいえ在宅、美保子さん自身も仕事をしています。
一方、兄の康彦さんが住む実家は、電車で2時間の距離です。
仕事と家事の両立を計りながら、毎日通うには負担が大きすぎると判断しました。

リバースモーゲージを介護に充てる

◇リバースモーゲージにより介護資金に充てました
美保子さんは兄の康彦さん、自分の家族を交えて相談し、実家を担保に入れて融資を受けるリバースモーゲージにより資金を作ることを決めました。
| <リバースモーゲージとは> | |
| [仕組み] | ・家を担保に融資を受ける ・死後に家を売却し返済 ・生前は利息のみの支払い |
| [支給形態] | ・一括 ・年金型(分割) |
一時金を受けた後、残る融資は「年金型」で月々支給される方法を選んでいます。
リバースモーゲージには、家の売却で返済ができなかった場合、相続人が返済責任を負うリスクも感がられますが、下記の点で利用を決めました。
・老人ホームの入居に対応
・相続放棄の可能性が高い
また康彦さんが将来的に要介護区分が上がり特養老人ホームに入居する可能性もあるでしょう。
今後も「実家に戻ることはないだろう」と判断した場合、家を売却して残高を返済しようと考えています。
要支援で進めた介護対策
リバースモーゲージによる融資を受け、利用した費用は下記です。
自分達の人生もあるため、美保子さんは自分達の財産から出すことは控えています。
①自宅のバリアフリー
(自宅改修支援20万円+一時金)
②民間介護サービスの利用
(年金型の月々の支給から)
調べると行政でも、ひとり暮らし老人宅への定期的な見回りサービスがあり、民間サービスでは整備会社による見守りなど、さまざまな介護サービスがありました。
費用が掛かるため制限はありますが、民間サービスも賢く利用することで、バランスを取っています。
・ひとり暮らし脳梗塞の発症リスクとは!初期対応の分かれ道や、要支援まで3つのリハビリ
まとめ:更新による要介護区分の変化に注意

実家でひとり暮らしをしていた独身の兄、康彦さんが脳梗塞により、突然の要介護3になった、小谷美保子さん(65歳:仮名)の体験談とともにお伝えしました。
●要介護3でも要支援1でも、自己負担額割合に違いはありません。
…美保子さんのケースは、いずれも基本の1割でした。
この自己負担の割合は要介護の区分ではなく、前年の合計所得(各種経費や控除を差し引く前の所得)から計算されるためです。
ただ、利用する介護サービスによって自己負担額も大きくなるため、ケアマネージャーと予算をしっかり立て、介護プランを進めてください。
・【老後に破産しない資金計画】公的介護保険でどこまでできる?介護問題に備える5つの知識
お電話でも受け付けております















