
ひとり暮らし脳梗塞の発症リスクとは!初期対応の分かれ道や、要支援まで3つのリハビリ
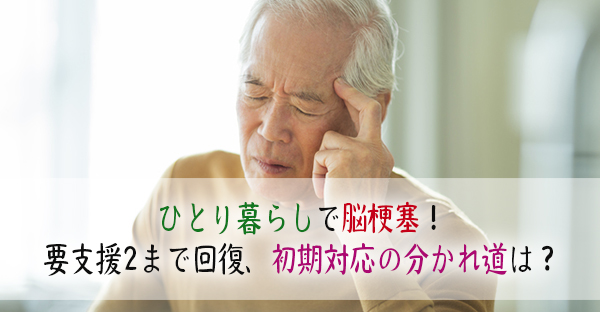
小谷康彦さん(75歳:仮名)がひとり暮らしで脳梗塞を発症したのは5年前、脳梗塞の症状自体は、テレビなどで知る程度でした。
けれども朝起きて、顔や体の動きに違和感を感じ、危険を察知したそうです。
・脳梗塞の初期症状とは?
・ひとり暮らしで脳梗塞を察知したら?
・脳梗塞の後遺症とリハビリとは?
今回は、ひとり暮らしで脳梗塞を発症した小谷康彦さん(75歳:仮名)が、自分で救急車を呼び、最終的には要支援2まで回復した体験談をお伝えします。

独身ひとり暮らしで、脳梗塞を発症

●独身ひとり暮らしだった兄、康彦さん(当時70歳)は、自分で救急車を呼び搬送されました
康彦さんが脳梗塞に気づいたきっかけは、体の右側の手足に感じる痺れです。
「歯が入れ歯のように浮いた感じ」がしたと言い、箸が上手く使えない、思うように歩けない症状を感じました。
| <ひとり暮らしの脳梗塞とは:症状> | |
| ●体の片側に顕著に表れます | |
| ①体の様子 | ・顔の歪み ・思うように歩けない ・片側の手足のしびれ、力が抜ける ・文字が書きにくい ・細かな作業ができない(箸など) |
| ②言語 | ・言葉が出ない ・言葉が分からない ・呂律が回らない ・口が思うように動かない |
| ③視界 | ・半分の視界が見えない ・二重に見える |
特に以前から調べていた訳ではありませんが、片側のみに痺れや違和感を感じることに危険を感じた康彦さんは、救急車を呼んでいます。
しゃ、しゃべれない!
●119番に連絡を取り何とか繋がったものの、思ったように話せなくなっていました
気づいた時には「あー」「うー」としか話せなかったと言う康彦さん、ひとり暮らしだったために、救急車を呼び相手が出るまで、自分がここまでしゃべれない状態だったとは思わなかったそうです。
けれども康彦さんが功を奏したのは、携帯電話ではなく家の固定電話から電話をした点でした。
①携帯電話…GPS機能により居場所を特定
・電波状態により正確に表示されない
・密集した居住区域の場合、詳細な場所が分からない
②固定電話…発信者情報が表示される
・住所の特定が可能
康彦さんがひとり暮らしをしている実家は、戸建て住宅ではあったものの、家と家の間も狭く、家が密集している地域でした。
ひとり暮らしで脳梗塞を発症した康彦さんにとって、いち早く気づいて救急車を呼んだこと、固定電話から119番したことが、大きな分かれ道です。

入院後、すぐにリハビリ開始!

●康彦さんがリハビリを開始してから1年間は、状況に合わせて施設を点々としています
康彦さんの脳梗塞による後遺症は、右半身がこわばりなどです。
脳梗塞を発症してすぐに入院した病院では、ともかく体を動かすリハビリが続きましたが、6ヶ月ほど経つとリハビリ専門病院へ転院、生活に必要な歩行や食事などをリハビリしました。
①急性期リハビリテーション
●入院時の病院…発症後すぐ~4週間頃
・身体を動かす
・運動麻痺リハビリ
②回復期リハビリテーション
●リハビリ専門病院など…発症後5・6ヶ月頃~
・歩行のリハビリ
・日常生活を想定したリハビリ
③生活期リハビリテーション
●施設…発症後6ヶ月頃~
・症状が悪化しないためのリハビリ
回復期リハビリテーションの段階を終えた後、康彦さんは要介護3の認定を受けたことで、脳梗塞の後遺症(主に右手のこわばり)を受け入れてくれる老人ホーム(特別養護老人ホーム)へ入所しています。
①脳梗塞の後遺症
・右手が重たい
・右手を動かすと固くなる
・長時間、右手を動かせない
・手首や指がこわばる
・右肩が重い、痛い
②リハビリ結果
・食事で箸を使用できる
・手首を動かして歯磨きができる
・荷物の持ち運びができる
本を読むことも好きだった康彦さん、ひとり暮らしの実家で脳梗塞を発症した日から1年半が経った頃には、大きな本をベッドで読むこともできるようになりました。
妹しか保証人になれない?
●ひとり暮らしの実家で脳梗塞を発症した当初、病院に入院するにあたり、保証人は友人にお願いしています
けれども回復期リハビリテーションが終わり、リハビリ専門病院へ転院する際、「友人では緊急時に対応してくれない」として、血縁関係者以外の保証人であることを理由に、受け入れを拒否されてしまいました。
●病院の「医療福祉相談室」へ相談
・友人は引き続き保証人をしてくれる
・脳梗塞だが、判断能力はある
・厚生年金、預貯金により支払いに問題はない
…複数の施設に問い合わせてもらいましたが、なかなか受け入れに良い反応がなく、「妹には迷惑を掛けたくない」と思っていましたが、結果的に妹に保証人になってもらいます。
では、身内がいないひとり暮らしの人が脳梗塞を発症したら、施設入所時はどうすれば良いのでしょうか?
実際に、身内がいないとして問い合わせてみました。
①厚生労働省による通知(2018年)、ガイドライン(2019年)
「身寄りがいないという理由で受け入れを拒否しない」
②地域の医療機関、医療ソーシャルワーカー(MSW)による返答
・身寄りがないからと、受け入れない施設はない
…けれども康彦さん以外にも、「いくつもの施設に問い合わせていただいて、1つの施設で受け入れてもらえた」などの体験談があります。
実際の現場では「緊急時に身寄りがないと困る」と考えているのかもしれません。
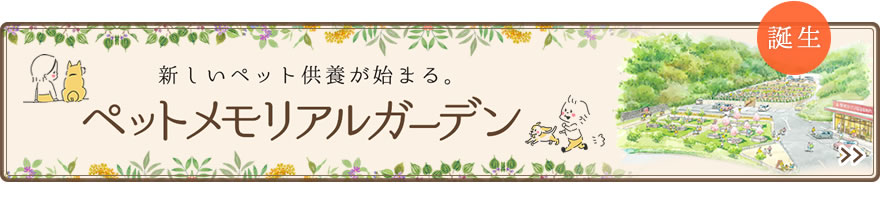
リバースモーゲージで費用を作る
●民間サービスは費用が掛かるため、実家を担保とした「リバースモーゲージ」で賄いました
「リバースモーゲージ」とは、家を担保にしてまとまった資金の融資を受けながら、死亡時に家を売却することで、生前は家に住みながら金利の支払いのみで賄うことができる融資です。
一般的にリバースモーゲージのデメリットも取り沙汰されていますが、康彦さんと妹の美保子さんは、家に住み続けられることから、選んでいます。
●メリット
・年金型/一時年金型の選択
・家に住んだまま融資が可能
・生前は利息のみの返済
●デメリット
・家の評価額が下落する可能性
・長生きした時のリスク
・金利が上昇する可能性
康彦さんの場合、毎月支給される年金型を選択して、厚生年金、少しの貯蓄に加えて、リバースモーゲージによる融資を利用し、民間サービスへの支払いをすることになりました。
・【老後に破産しない資金計画】リバースモーゲージとは?決定前に押さえたい6つの基礎知識
懸命なリハビリで、要介護3から要支援1に!

●ひとり暮らしの実家で脳梗塞を発症してから1年と半年、介護認定の更新で要支援2まで下がりました!
康彦さん自身は要介護認定の区分が下がり、「努力が実った!」と嬉しく受け止めていましたが、困っていたのはケアマネージャーと相談してくれていた、妹の美保子さんです。
「せっかく入所した老人ホーム(特別養護老人ホーム)の入所を継続できない」と美保子さんは言います。
特別養護老人ホームは、要介護3以上が入所できる施設だからです。
●康彦さんは、再び実家でひとり暮らし
①要支援2の介護サービスを利用
・訪問リハビリテーション…週2回
・ディサービス…週2回
・杖の貸与
②民間サービス
・配食サービス
・警備会社の見守りサービス
・家事代行サービス
介護認定の更新により、要支援2まで回復したとは言え、少し前までは要介護3の状態…、突然、ひとり暮らしで脳梗塞の後遺症を残し暮らすため、妹の美保子さんとしても、毎日が心配の種でした。
そこで要支援2で受けられる保険サービスにプラスして、民間の見守りサービスを利用しています。
最後に
以上、定年退職後のひとり暮らしで脳梗塞を発症した康彦さん(75歳:仮名)の体験談です。
脳梗塞は初動が肝心と言いますが、脳梗塞の5年生存率は62.8%、脳卒中全体でも5年生存率は62.3%と考えると、日ごろから「あれ?」と思った時の初動を意識したいところでしょう。
また、要支援2で再びひとり暮らしになった康彦さんは、脳梗塞の心配から民間サービスを重ねて利用していますが、その資金繰りとして、リバースモーゲージ以外にも「リースバック」と言う方法もあります。
・リバースモーゲージ…所有権がある(家は担保)
・リースバック…所有権がない
リースバックは家を売却して、毎月の家賃を払いながら暮らす方法です。
また民間サービスのなかでもNPO法人など、費用が掛からない、安いものもあるので、探してみるのも良いでしょう。
まとめ
ひとり暮らしで脳梗塞になった体験談
●脳梗塞の症状(体の片側)
・顔の歪み
・思うように歩けない
・片側の手足のしびれ、力が抜ける
・文字が書きにくい
・言葉が出ない
・呂律が回らない
・半分の視界が見えない
・二重に見える
●救急車の呼び方
・携帯電話より固定電話
●リハビリの流れ
・急性期(入院時の病院/~4週間頃)
・回復期(リハビリ専門病院など/5・6ヶ月頃~)
・生活期リハビリテーション(施設/6ヶ月頃~)
●要介護3から要支援2へ
・特養老人ホームの入所ができない
●後遺症とひとり暮らしの工夫
・介護サービスの利用
・民間サービスの利用
・費用はリバースモーゲージで調達
お電話でも受け付けております
















