
おひとりさま老後に多い6つの不安を解決!身元保証・介護問題、お金や不動産管理は?
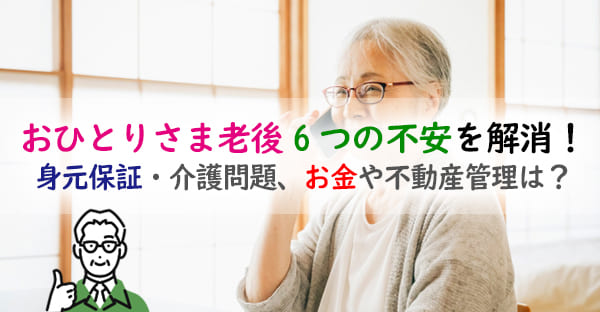
・おひとりさま老後の不安を解消したい!
・身元保証や病院の付き添いをしてくれるサービスは?
・入院や施設入居になった時、財産管理や不動産はどうする?
・亡くなった後の手続きは誰に依頼する?
身寄りのないおひとりさまの老後暮らしは、突然の病気や認知症など不安が付きものですよね。
高齢化社会の今、おひとりさま老後の不安を解消する制度やサービスがありますが、それぞれに有効な時期や業務内容が異なります。
本記事を読むことで、おひとりさまの老後暮らしに役立つ制度やサービスを理解し、不安を解消できるでしょう。
おひとりさま老後の不安①身元保証

病院の入退院や介護施設の入居では、身元保証人が必要です。
一般的には家族や親族(甥っ子・姪っ子など)が身元保証人になりますよね。けれども「頼める家族や親族はいない」「そこまで頼めない」などの声は多いです。
身元保証人が身近にいない場合、法人・民間企業の「身元保証サービス」があります。
「身元保証サービス」とは、病院への入退院・介護施設や高齢者施設への入居・賃貸契約などのシーンで、身内に代わり身元保証人になってくれるサービスです。
●身元保証サービスとは
家族や親族に代わり身元保証をしてくれるサービスです。主に病院の入退院や高齢者施設への入居契約、賃貸契約時に助かります。
近年では孤独死が増え、高齢者の入居を渋る賃貸オーナーが増えました。高齢者が賃貸住宅へ入居する際にも身元保証人は必須です。
元気なうちに身元保証契約を交わし、いざ必要になった時に身元保証人になってもらいましょう。
・身元保証人
・ご遺体の引き取り
・医療費・施設利用費の連帯保証人
・本人が意思表示できない医療行為への同意(認知症など)
・病院・介護施設からの対応
身元保証サービスは家族・親族に代わる役割になるため、内容は多岐に渡ります。そのため基本的には「身元保証支援契約+生活支援契約」のセットサービスが多いでしょう。
生活支援契約を交わすと身元保証サービスだけではなく、買い物・通院での付き添いを依頼できます。
・おひとりさま老後に心強い、家族の代わり「身元保証サービス」とは?費用相場はいくら?
●身元保証サービスの料金相場
一般的に身元保証サービスのみを利用する場合、約30万円~50万円が相場です。
ただ前述したように「生活支援契約」も併せて依頼するケースが多いので、必要な生活支援の内容により料金が追加されます。
入会金や毎年会費が発生する団体もあるでしょう。
身元保証サービスは終身契約として一括払いが多いですが、生活支援契約は月々・年間払いとする料金システムが多いです。
・一般社団法人結福祉ステーション
●身元保証サービスの疑問
近年では財産管理などの代理権を担う契約「任意後見人契約」を行っていれば、身元保証はなくても良いとする病院や介護施設もあります。けれども任意後見人の義務は、あくまでも契約や事務手続きで、身元保証人が担うべき全ての責任は果たしません。
なかには家族・親族のように対応する任意後見人もいますが、一般的に業務範囲は契約や事務手続き関連に限るため、救急搬送時に病院や施設に駆け付けるなどの行為は業務外です。身元保証人は家族など別の人々が行います。
・身元保証
・救急時の対応
・入退院時の付き添い
そのため任意後見人がいても身元保証人の役割を求めるために任意後見人がいても、他の身元保証人の署名を求める高齢者施設も多いです。
おひとりさま老後の不安②介護手続き

おひとりさまの老後生活では、介護が必要になった時の不安もありますよね。
基本的には地域包括センターに行って相談をしますが、行政が管轄する地域包括センターは家族のように相談者の生活状況を見て、積極的に介入してくれるものではありません。
そのため認知症などの病状により本人の判断能力が低下した時、おひとりさまの老後生活では、どのように介護体制を整えるのかが問題であり不安要素です。
この場合、認知症になった後・認知症になる前で有効な契約が異なります。ただいずれにしても元気なうちに契約を済ませておくことが重要です。
●任意後見契約とは
「任意後見契約」は財産管理や各種契約の代理権を持ち、認知症などにより本人の判断能力が低下した時に、代わって契約手続きができます。本人の意思で契約や管理を任せる人を決めることができます。
預貯金を代理で管理できるため、介護施設や病院への支払いも任せることができるでしょう。
任意後見契約は本人の判断能力が低下してから有効な手段ですが、元気なうちに契約を済ませておくことがポイントです。本人に判断能力がないと認められた後では契約ができません。元気なうちに任意後見人を探しておきましょう。
●任意後見人の業務内容
任意後見人は本人から代理権を受け取り、本人に代わって財産管理や各種手続きを行う役割です。本人が認知症や病気などで判断能力が低下した時点~亡くなった時までを担います。
| <任意後見人の業務内容> | |
| ①財産管理 | ・預貯金の管理 ・税金や保険料の納付 ・不動産 ・有価証券(売買・賃貸・贈与等) ・遺言書(作成・保管) ・債権(支払い・回収) |
| ②身上保護 (本人同意の上) |
・介護施設の入居手続き ・介護サービスの契約手続き ・医療行為への同意 ・医療行為への拒否 ・生活用品の購入等 |
公正証書により契約を交わし、家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行うことで業務開始です。任意後見人には弁護士など士業による任意後見監督人が付きます。
・任意後見人は必要?できること・できないこと・費用相場を徹底検証!後悔しない対策も!
②見守り契約
おひとりさま老後の不安③不動産

おひとりさま老後では不動産の処分や売却にも不安がありますよね。
賃貸住宅は入居を拒まれるケースも多く、持ち家に住む高齢者が増えました。けれども持ち家であっても、介護施設への入居をきっかけに持ち家を売却するケースも少なくありません。
終の棲家として在宅介護を希望しても、おひとりさま老後の在宅介護は高額の費用を要します。例えば24時間体制での在宅介護になると、月額約100万円~180万円の費用が発生するケースもあるほどです。
けれども介護施設へ入居が必要になってからでは、なかなか自分で不動産の処分や売却ができません。このように持ち家のおひとりさま老後であっても、任意後見人契約は有効です。
●不動産の処分・売却手続き
任意後見人に不動産の処分・売却を依頼する時には、契約時に条件を付けましょう。
任意後見人は、本人が元気だった頃の希望を実行する役割があるからです。
任意後見人契約では、一般的に「代理権目録」「ライフプラン」などと呼ばれる希望を詳細に残す書類があります。このような契約書類に不動産の処分・売却のタイミングを明示しておくと安心です。
例えば「契約者が介護施設に入居した時点で、不動産の処分・売却を任せる」もしくは「契約者が認知症になった時点で、不動産の処分・売却を任せる」などがあります。
●賃貸でも任意後見契約が役立つ
賃貸住宅でも介護施設への入居が必要になれば、今まで住んでいた賃貸住宅から退去します。部屋をキレイに片づけて出て行かなければなりません。
さらに賃貸住宅契約では原状回復が必要ですが、認知症や病気により退去時の手続きができない場合はどうすれば良いでしょうか。任意後見契約をしておくとスムーズに進みます。
また賃貸住宅のおひとりさま老後暮らしでは、不意に自分が亡くなってしまう「孤独死」もあるでしょう。
●賃貸住宅での孤独死
賃貸住宅で孤独死が発生しても賃貸契約は勝手に切れません。誰一人相続人がいない方でない限り、法律上で賃貸契約に関わる手続きは相続人に受け継がれます。
けれども、相続人は居住者本人の状況を理解していない方も多くトラブルも多いです。
特に原状回復や片付けを誰が行うのかで揉めやすく、賃貸住宅オーナーが困り果てたり、原状回復や片付けを担うケースもあります。
亡くなった時に賃貸住宅をスムーズに返すためにも、死後事務委任契約は有効です。
賃貸住宅のなかには、高齢者の入居条件として死後事務委任契約が求められることもあります。
おひとりさま老後の不安④お金の管理

おひとりさま老後暮らしでは突然入院すると銀行に行けないなど、自分で預貯金管理ができない事態も起きやすいです。自分が認知症になってお金の管理ができないケースもありますよね。
本人が判断能力を失った後では、誰かに委任する契約は認められません。認知症や病気による入院等の可能性を見越して、元気なうちに契約を進めることが肝心です。
●病院の「財産管理委任契約」
病院では「財産管理委任契約」を利用することができます。
「財産管理委任契約」とは、信頼できる特定の親族・友人・知人などに財産管理・病院や福祉サービスの手続き全般を委任できる契約です。
●銀行の「指定代理人制度」
「指定代理人制度」を設けた銀行もあるでしょう。
「指定代理人制度」とは、認知症や病気などで口座名義人が判断能力を失った時に代理権を持ち、口座の預貯金取引を担うことができます。
ただし指定代理人は血縁関係のある家族・親族に限られる銀行が多いです。指定代理人制度は、口座を開いた支店で行うため注意をしてください。
●判断能力がある「財産管理契約」
指定代理人制度で解説したように病院や銀行で交わす契約は、血縁関係のある家族や親族に限られる条件が少なくありません。
そのため頼れる家族・親族がいないおひとりさま老後では、第三者に委任できる「財産管理委任契約」があります。
「財産管理契約」は判断能力があるものの、病気による入院・ケガ・寝たきりなどにより、預貯金の引き出しなど生活費の管理が難しくなった時に有効です。
預貯金の引き出し・病院への支払い・家賃など生活費の支払いを委任できます。
財産管理委任契約ではトラブル回避のため、確かに財産管理を依頼した人へ委任したことを証明する「財産管理委任契約書」を交わしましょう。
●判断能力がない「任意後見契約」
おひとりさま老後の不安⑤お墓

おひとりさま老後では本人が亡くなった後も不安ですよね。認知症などで有効な任意後見制度も、本人が亡くなる直前までの権利ですのでご注意ください。
生前にお墓を撤去する「墓じまい」を済ませる方法もありますが、問題を残したまま墓主不在で亡くなるケースも少なくありません。
また墓じまいを済ませても自分の遺骨まで考える必要があります。
●死後事務委任契約
本人が亡くなった後の各種行政手続き・財産管理は「死後事務委任契約」により委任します。自分亡き後のお墓や遺骨の葬送も、生前の死後事務委任契約で解決するでしょう。
死後事務委任契約は本人に代わり死後に必要な各種契約手続き等を行う権利です。そのためお墓問題は、石材業者・霊園など各種専門家に依頼して進めます。
生前の故人の遺志を反映する目的があるので、生前に希望を細かく明記しておきましょう。お墓のない自分の遺骨も、永代供養墓・樹木葬・海洋散骨など、どのように供養して欲しいかを明確にして委任します。
●死後事務委任契約の業務内容
「死後事務委任契約」は、自分が亡くなった後に必要な諸々の契約を、特定の人に責任をもって行ってもらうための事前契約です。
| <死後事務委任契約の業務内容> | |
| ①葬儀 | ・葬儀社の手配 ・ご遺体の引き取り ・搬送、仮安置 ・葬儀費用の清算事務 |
| ②納骨 | ・ご遺骨の搬送 ・ご遺骨の納骨など ・納骨に関する各種清算事務 ・墓じまい、改葬など |
| ③行政手続きなど |
・親族への訃報 ・死亡届の提出 ・自治体への各種手続き ・年金手続き ・医療費、施設利用費などの清算事務 ・家賃光熱費などの停止、清算事務 ・遺品整理、遺品処分 ・賃貸住宅、施設等の清掃や返還事務 |
例えば葬儀・納骨・死後に行う各種事務手続き・入院費用など諸々の清算事務などがあります。身近に頼れる親族がいないおひとりさまには役立つ終活ツールです。
おひとりさま老後の不安⑥財産

自分亡き後の財産「遺産」の行方に希望がある場合は遺言書が必要です。一般的にはおひとりさまの老後でも遠い親族など相続人がいますが、相続人のいない方も少なくありません。
例えば故人がひとりっ子・生涯独身で子どももいないケースなどですが、この場合遺産は国庫へと渡ります。「相続人がひとりもいないなんて!」と驚くかもしれませんが、2023年度に遺産が国庫へ渡った金額は647億円でした。
近年では「どうせ国庫に行くならば寄付したい」と考える方も増えました。地域のNPO団体などへ遺産を寄付するなどです。
この場合にも遺言書を作成し死後事務委任契約を交わすことで、希望の団体へ寄付することができるでしょう。
・【相続対策】遺言の有効性が高い種類を選ぶ。遺言3種類のメリットとデメリットを解説!
死後事務委任契約と身元保証サービスの違いとは

病院の入退院や施設入居・賃貸契約など、元気な高齢者でもあらゆるシーンで身元保証人が必要です。そのため身寄りのないおひとりさま老後暮らしでは、任意後見契約ではなく身元保証サービスを交わす高齢者が増えています。
そこで「死後事務委任契約と身元保証サービスはなにが違うの?」との質問が多いのですが、有効な時期・業務内容・担い手・契約形態まで全く違う契約です。
身元保証サービスは必要な時に契約することもできますが、任意後見契約や死後事務委任契約はいざと言う時には間に合いません。
契約内容の違いを理解して、元気なうちに事前に契約する必要があります。
①時期の違い
「死後事務委任契約」は本人が亡くなった直後から、相続手続きに入るまでの期間に発生します。
対して「身元保証サービス」は生きている時の保証支援です。本人が入退院・もしくは介護施設などの入所から、亡くなる直前までの期間で役立つでしょう。
②業務内容が違う
有効な期間が違うため業務内容も大幅に異なります。死後事務委任契約では、本人が亡くなった直後からの細々とした手続きを委任できるでしょう。
それぞれの業務内容をまとめたため、比較確認してください。
| <業務内容の違い> | |
| ①死後事務委任契約 | ・葬儀 ・納骨 ・行政手続き ・その他の死後事務 |
| ②身元保証サービス | ・入退院時の身元保証 ・介護施設入所時の身元保証 ・いざと言う時の身元引き取り ・医療費や施設利用費の支払い ・連帯保証 ・病院や施設からの依頼対応 |
任意後見人も病院の入退院時や施設入所手続きを行いますが、本人の判断能力が低下してからの業務です。また家族代理ではなく、手続き関連を主に行います。
身元保証サービスは家族代わりの役割を果たすため、本人の病状・介護状況の説明を受けることも可能です。
また業者により異なりますが、入退院や施設入居に、必要な物品を用意するサービスもあるでしょう。そのため身元保証サービスは料金から選ぶよりも、親身に寄り添い昼夜問わず施設からの連絡に対応してくれる業者を選ぶと安心です。
③担い手が違う
死後事務委任契約は専門業者・行政書士事務所や弁護士事務所などの士業の他、友人・知人や遠い親族が受任者になることもあります。
死後事務委任者は身寄りのいないおひとりさまのご遺族と同じ役割です。そのため葬儀や納骨であれば喪主・施主の立場に立ち、葬儀社の手配・納骨式の主催などを行います。
生前の故人の希望を聞き取り、死後に遺志を反映できる方であれば、誰でも死後事務委任契約の受任者になることが可能です。
任意後見人も業者や士業だけではなく、身近な知人・友人が担うこともあるでしょう。
一方で身元保証サービスはほとんど専門業者が担います。身元保証を依頼できる人が身近にいない場合に、身元保証サービスを利用するケースが多いためです。
④契約形態が違う
まとめ:おひとりさま老後の不安は制度やサービスを利用します

身寄りのないおひとりさま老後の不安は、頼りになる家族・親族が身近にいないために生じる内容がほとんどです。そのため地域コミュニティーではカバーできない内容が多いでしょう。
けれども家族が担う内容も適した契約を交わすことにより解消できます。生前のおひとりさま老後暮らしであれば、身元保証サービス・任意後見契約などが有効です。状況により財産管理のみを託す契約もあるでしょう。
死後の手続きや葬送について不安があるならば、死後事務委任契約を交わします。公的な契約なので詳細を記載することで、より安心して託すことができるでしょう。
お電話でも受け付けております
















