
【2026年】鏡開きとは?どんと焼きとの違い・正月飾りの片付け方や処分方法まで解説

「鏡開きとは?」
「どんと(どんど)焼きは何をする行事?」
「鏡餅や正月飾りはどう片付けるのが正しい?」
お正月が明ける頃、迷うこともありますよね。
鏡開きは、お正月に祀った鏡餅を開いていただく大切な節目、どんと焼きは正月飾りのお焚き上げです。 地域によっては正月飾りをどんと焼き(どんど焼き)で焚き上げて処分する風習もあります。
本記事では、鏡開きの意味や進め方、包丁を使わない理由、どんと焼きとの関係、 正月飾りの片付け方や処分の注意点まで、2026年の日程とあわせて分かりやすく解説します。
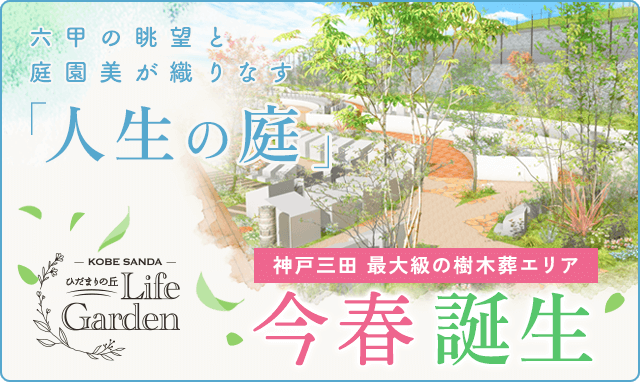
「鏡開き」や「どんと焼き(どんど焼き)」とは?詳しく解説!

◇「鏡開き」とは、鏡餅を開く(割る)行事です。
…どんと焼き(どんど焼き)では、正月飾りを燃やして天へとお返しする「お焚き上げ」行事です。
「鏡開き」とは、お正月に飾っていた鏡餅を木槌などで開いて(割って)、鏡餅の福徳を家族でいただく行事を差します。
鏡餅はその家の一年を守護する「年神様(としがみさま)」の依り代です。
そのため鏡餅を開く鏡開きは、年神様に失礼のないよう、慎重に行わなければなりません。
鏡餅は年神様の依り代
お正月には年神様(歳徳神・としとくじん)が家にいらっしゃるので、家族はみなで正月飾りを飾ったり、おせちなどのご馳走で年神様をもてなします。
鏡餅はお正月期間に年神様が家にいる際の依り代として祀られてきました。 ちなみに、しめ縄は家に結界を張る行為です。
鏡開きを行うことで年神様はお帰りになります。 そのため鏡開きは、おもてなしのために飾ってきた正月飾りを片付け、人々が日常生活に戻る節目です。
なぜ鏡餅は白餅を重ねるの?
2つの白餅が重なる鏡餅は「円満に年を重ねる」と言う意味があります。
丸餅が選ばれるのはかつての銅鏡に姿形が似ていることからですね。また円満の円やご縁(ごえん)との語呂合わせとも言われます。
銅鏡に似た姿形から「鏡餅」と呼ばれる他、一説では物事を冷静になって良き手本と照らし合わせ、他と比べ合わせながら良い答えを導き出す「鑑みる」から「鑑みる餅」「鏡餅」になったともされてきました。神道の鏡と似た考え方です。
鏡餅の下に敷かれる紙「裏白」は生命力・長寿を意味します。その上に乗せるユズリハは代々世代が譲られて繁栄していくこと、鏡餅の上に乗せる橙(だいだい)も語呂合わせで「代々栄える」ことを表すものです。
鏡餅のご利益は?
鏡餅の「鏡」は平和・調和・円満を意味します。
また鏡餅に宿る年神様のご利益は一年の豊穣、五穀豊穣(現代では収入)・家内安全・家庭円満・無病息災です。
鏡開きでは鏡餅を開いて(細かく分けて)から、お汁粉や雑煮などに調理し家族でいただきます。開いた鏡餅をいただくことで、年神様のご利益・福をいただくためです。
鏡開きやどんと焼き(どんど焼き)のタブーとは?

◇鏡開きに、鏡餅を包丁で「切る」行為はタブーです。
鏡餅は年神様が宿る依り代、ひいては年神様そのものですので、この点を意識して扱う必要があります。
特に江戸時代は武家から始まった鏡餅は、おろした鏡餅を刃物で切ることを忌み嫌いました。
武家社会で刃物で切るは、斬首や切腹をイメージするためです。そこで包丁などの刃物以外のもので細かくしてきました。
①鏡開きは木槌を使う
◇包丁が利用できない鏡開きでは、木槌を使います。
鏡餅は木槌や金槌で開き、食べやすく細かくするため、扱いやすい通常の木槌で構いません。
近年では鏡開き用の金槌なども販売されています。
鏡餅と同じくお祝い用の酒樽なども「鏡開き」などと言い、木槌や金槌を使用して蓋を割りますから、このような機会がある家では購入しても良いでしょう。
②鏡餅は全ていただく
◇鏡餅にはその年の福を詰め込んだ年神様(歳徳神)の依り代、いわば年神様そのものです。
…年神様のご利益を鏡餅と一緒に捨ててしまうのは、あまりにももったいないですし失礼ですよね。
そのため鏡餅を捨てたり、残すことはタブーです。 鏡開き当日にお汁粉やお雑煮で食べきれなかった時には、庭先で乾燥させて揚げておせんべいにするなどしてはいかがでしょうか。
③「割る」「切る」はタブー
本記事では分かりやすいよう「割る」説明を加えましたが、本来鏡餅は「開く」ものです。「割る」「切る」は縁起が悪いとして鏡開きでは使いません。
縁起の良い語呂合わせとして、末広がりの「開く」が使われてきました。
④正月期間は食べない
鏡餅は年神様が宿る依り代です。年神様へおもてなしをするお正月ですから、正月期間に鏡餅を開くことは避けましょう。
では「正月期間」はいつか?と言えば全国的には「松の内(まつのうち)」と呼ばれる元旦~1月7日までの7日間です。「松七日」とも呼ばれます。
ただし京都の一部地域では正月三が日のみの「松三日」になるなど、地域によって正月期間が分かれることもあるため、事項からの解説も確認しながら周囲にも聞いてみると安心です。
2026年、鏡開き(どんと焼き・どんど焼き)はいつ?

◇一般的な鏡開きは2026年1月11日(日)です。
全国的な鏡開きは毎年1月11日とされます。2026年は1月11日(日)ですね。かつては集落で正月飾りのお焚き上げ「どんと焼き(どんど焼き)」などが開催されてきました。
ただし正月飾りを飾る期間「松の内」・鏡餅を開く「鏡開き」は、日程が関東と関西を中心に地域によって違いがあります。
①2026年関東地方ではいつ?
主な関東地方の鏡開きは毎年1月11日に行われます。2026年は1月11日(日)ですね。主に関東地方・東北地方・九州地方の鏡開き日程です。
これらの地域では多くが松の内(正月期間)を元旦~1月7日までの「松七日」としています。松の内明けに鏡餅をはじめとした正月飾りを片付けて、1月11日に鏡開きを行う流れです。
②2026年関西地方ではいつ?(小正月・二十日正月との関係)
関西地方では毎年1月15日の「小正月」、もしくは1月20日の「二十日正月」に鏡開きを行う地域が多いでしょう。2026年は1月15日(木)・1月20日(火)ですね。
小正月(1月15日)を鏡開きとする関西地方では正月期間の松の内は1月15日まで、二十日正月(1月20日)を鏡開きとする関西地方では松の内を1月20日までとしています。
小正月・二十日正月はいずれも正月祝いで忙しくしていた、主に家事を担う家族・かつては奉公人がひと息付いて正月を祝う日とされてきました。
・小正月や二十日正月とは何?正月飾りを片付ける節目はいつ?処分方法は?行事食も紹介!
③2026年京都一部地域の鏡開き・どんと焼き(どんど焼き)
京都の一部では正月期間を「松三日」の正月三が日とする地域があります。翌日1月4日には正月明けとし、鏡開きも1月4日に行う風習がありました。2026年は1月4日(日)ですね。
【おまけ】現代の鏡開き・どんと焼き(どんど焼き)
鏡開きの歴史

◇その昔は関東も関西も、全国的に二十日正月が祝い納めでした。
二十日正月は1月20日、2026年は1月20日(火)です。
忙しい正月行事がひと通り終わり、女性や奉公人が一休みして、台所などでお正月を祝うタイミングとされます。
けれども江戸時代に徳川家光の月命日が20日になったことから、関東地方と関西地方で鏡開きの暦に誤差が生まれました。
①三代将軍徳川家光の命日
かつては関東・関西地方ともに1月20日の二十日正月を正月祝い納めの節目としてきました。この時期に鏡開きも行い正月飾りを処分しています。
1651年(慶安4年)4月20日に三代将軍徳川家光が48歳で亡くなると、毎月20日が月命日になりました。そこで関東地方では1月11日を鏡開きにしたとされます。
関西地方で二十日正月に鏡開き・正月祝い納めとする風習が続くのには、幕府から離れていたこと、天皇家とご縁がより深いことから影響を受けにくかったこともあるでしょう。
②明暦の大火
さらに1657年(明暦3年)には正月明けの1月18日~20日にかけて、江戸の町の中心部6割以上が消失し壊滅状態にまで追い込んだ「明暦の大火」が発生します。この年は元旦から火災が度々起きていたことが今も残っています。
江戸幕府は道幅の拡大や火の見蔵・防火用水の設置を進めるとともに、正月飾りを火の用心のため早く処分するよう、鏡開きの日程を早めたとされます。
寒く乾燥しやすい冬は火事になりやすく、正月飾りのしめ縄などは燃えやすい藁(わら)を使用する正月飾りは、1月7日の早々に片付けるお触れが出ました。
③蔵開きが1月11日
江戸時代に諸大名家や商家で行われてきた、新年に初めて蔵を開ける儀式「蔵開き」が1月11日でした。(一部では初荷の折りに蔵開きをする商家もありました。)
江戸時代の「蔵開き」では、奉公人やお得意様などへおとそ(お酒)などを振る舞う行事もあり、蔵開きと併せて鏡開きを行ったともされます。
簡単、新しい!鏡餅レシピ

◇鏡開きの行事食、おしるこや雑煮を簡単に作りましょう!
鏡開きと言えば、固くなったお餅を鍋で煮て柔らかくいただける料理、おしるこや雑煮が行事食です。
①おしるこ
②雑煮
③餅巾着を入れた鍋
④餅の肉巻き
⑤餅の味噌マヨネーズグラタン
…などなど、現代ではこの他にも、餅巾着で鍋にしたり、お餅の肉巻き焼きも人気ですが、今回は昔ながらの鏡開き行事食レシピとして、簡単!おしるこや雑煮レシピをご紹介します。
①おしるこレシピ
◇茹で小豆缶を利用することで、簡単に5分~10分ほどで作れます!
茹で小豆缶と水が同量の割合でしるこを作り、塩で調整すると良いでしょう。
お餅は木槌などで割ったら、後は手で割り分けます。
| <鏡開きとは:おしるこレシピ> | |
| [材料] | ・お餅(3~4枚) ・茹で小豆缶…1缶(150g) |
| [レシピ] | ①お餅を茹でる ②茹で小豆缶を鍋に入れる ③缶を目安に同量の水を入れる ④弱火に掛ける ⑤味見をしながら、塩で調整する ⑥お椀に①の餅を入れる ⑦餅を入れた椀に⑤のしるこ(あん)を注ぐ |
切り餅などは、トースターなどで焼いても美味しいでしょう。
おしること言えば、関東でも関西でもこしあんを利用する家庭が多いですが、田舎汁粉として粒あんを利用しても、餅に粒あんが絡みついておすすめです。
②雑煮レシピ
◇鶏だしやつゆの素などを上手に利用して、簡単に雑煮を作っちゃいましょう!
雑煮を美味しくいただくポイントは鶏だしです。
根菜類は大根やにんじんが多く、5mm幅のいちょう切りにすると良いでしょう。
鍋で煮て柔らかくする時間がない時は、お餅を含めて具材をラップに包み、電子レンジを使用すると時短になります。
家庭用電子レンジ600Wを目安として、根菜類なら約50秒、お餅は約30秒ほどです。
| <鏡開きとは:雑煮> ●3~4人分 |
|
| [材料] | ・大根…約8分の1 ・にんじん…約半分 ・鶏肉…約150g ・ほうれん草…約2分の1束 ・切り餅…約3~4個 |
| ●だし汁 | ・かつお節のだし汁…4.5カップ ・料理酒…約大さじ1 ・醤油…約大さじ3 |
| ●飾りつけ |
・三つ葉…適量 ・かまぼこ…適量 |
| [レシピ] | |
| ●下準備 | ①鶏肉 ・一口大に切る ②根菜類(大根、にんじん) ・5mm幅ほどのいちょう切り ・レンジにかける(600wで約1分) ・竹串がスッと通るくらい ③ほうれん草 ・4cmほどに切り分ける ④餅 ・鍋にたっぷりの水を入れる ・沸騰させてから弱火~中火にする ・お餅を入れて低温で柔らかくする (レンジなら600wで約30秒) |
| ●雑煮の汁 | ①だし汁を火にかけて煮立てる ②鶏肉とほうれん草を入れて煮る ③大根、にんじんを入れて煮る ④こまめにアクを取る |
| ●完成 | ①椀に餅を入れる ②椀に雑煮の汁を注ぐ |
だし汁はたっぷりのかつお節、どんこなどを煮立たせて作ることができます。
まためんつゆや白だしなど、市販のだしを利用すると便利でしょう。
最近では、鶏のコンソメなどを入れて、洋風に仕立てる家庭も見受けます。
鏡開き後の「どんと焼き」

◇どんど焼きは、正月飾りを焚き上げる地域行事です
鏡開きの日に「どんど焼き」が開催される地域もあります。
「どんど焼き」は、しめ縄などの正月飾りをお焚き上げで処分する行事です。
その昔は、鏡開きとどんど焼きが同じ日になる地域も多く、神社や寺院、集会所や学校の校庭で行われました。
どんと焼きには開いた鏡餅を持参して、お焚き上げの火のなかに入れ、焼いていただき盛り上がったものです。
| <どんと焼きとは> ●正月飾りを焚き上げる地域行事 |
|
| [焼くもの] | [具体例] |
| ①お焚き上げ | ・正月飾り ・開いた鏡餅 (アルミホイルや串に刺す) |
| ②縁起物 | ・正月の祈願事 ・書初め ・祝い団子 (紅白の繭玉) |
開いた鏡餅だけではなく、「正月の祝い団子」として知られる、紅白の繭玉(まゆだま)を串に刺して持参し、焼いていただくこともあります。
餅もどんど焼きの大きさによっては、アルミホイルで包んで先に針金を付け、引っ張って取れるように仕上げて行く人も多かったでしょう。
どんと焼き(どんど焼き)のご利益
◇どんど焼きは年神様をお見送りする行事です
正月飾りのお焚き上げを地域で行う便利さもありますが、年中行事としてのどんと焼きは、新しい一年を守護する「年神様」をお見送りする儀礼でもあります。
正月祝い納めの鏡開きの日、正月に来訪していた年神様がお帰りになるためです。
どんど焼きには、下記のようなご利益があるとされてきました。
| <どんど焼きのご利益> ●煙とともに天に昇る、年神様をお見送りする |
|
| [若返り] | どんと焼きの火に当たりと若返る |
| [祈願成就] | 書初めの祈願事が天に届く |
| [技芸上達] | 書初めの炎が高いと、文字が上達する |
| [無病息災] |
どんと焼きで焼いた餅を食べると一年健康 |
「どんと焼き」はもともと「どんとや」から来ています。
この「どんとや」は小正月を表す言葉で、平安時代の宮廷ではどんと焼きではなく、「三毬枝(さぎちょう)」と呼ばれる儀礼でした。
地域によってどんと焼きは「火祭り」などとも言いますね。
「三毬枝(さぎちょう)」から、他の地域ではどんと焼きを「左義長(さぎちょう)」と呼ぶこともあるでしょう。
鏡開きの注意点|どんと焼き行事に間に合わない!
まとめ|鏡開きやどんと焼きの日、年神様は帰ります

鏡開きは鏡餅を開く行事、鏡餅には一年の福徳を持って訪問した「年神様」の依り代ですから、木槌で慎重に開きます。
「どんと焼き」としてお伝えしましたが、どんと焼きだけではなく地域により呼び名はさまざまです。
関西地方でどんと焼きは「とんど焼き」「どんとや」で親しまれています。
| <地域で違うどんど焼き> | |
| [呼び名] | [地域] |
| ・とんどさん | …鳥取県 |
| ・とうどうさん | …愛媛県 |
| ・しんめいさん | …広島県 |
| ・あわんとり | …千葉県 |
| ・やははいろ | …東北地方の一部 |
地域の家々が持ち寄ったしめ縄などの正月飾りを焚き上げますから、炎は燃え盛りキャンプファイヤーのようですよね。
このような様子から、「どんどん」「とんど」「どんと」焼ける、燃える、とうとうと燃える、などの意味合いで呼ぶ地域もあるでしょう。
お電話でも受け付けております

















