
葬儀の喪主挨拶に役立つ例文とは?丁寧に挨拶する5つのタイミング、失礼のない例文とは
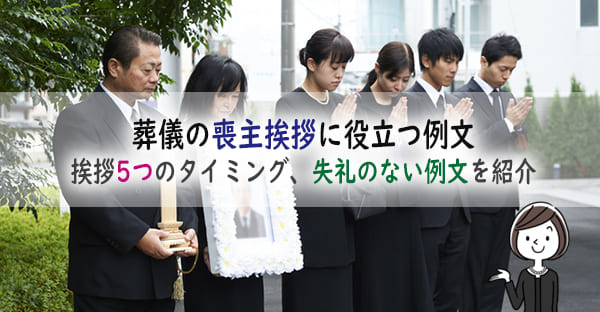
・葬儀で喪主挨拶はいつするの?
・葬儀の喪主挨拶、5つのタイミングとは?
・喪主挨拶で参考になる例文はある?
葬儀での喪主挨拶は、全体へ向けた出棺時の喪主挨拶の他、僧侶や参列者のお出迎え、精進落としのご案内など、5つのタイミングがあります。
本記事を読むことで、喪主挨拶5つのタイミングに沿った、僧侶や参列者にも失礼にならない喪主挨拶のポイントと、参考になる5つの例文が分かります。

喪主挨拶の他に行うことは?

◇いただいた花輪の配置など、参列者をもてなす配慮が必要です
葬儀の進行は葬儀スタッフに任せることができますが、故人と参列者との関係性を知る喪主にしか配慮できない仕事があります。
喪主挨拶も参列者へ感謝を伝える、おもてなしです。
・喪主挨拶
・遺影の準備
・花輪(供花)の配置
・参列者の席順
・世話役(必要な場合)の依頼
特に葬儀において喪主挨拶は、他の近しい身内やご遺族にできるものでもないため、文例を元に事前に準備をしておくと安心です。
葬儀で喪主挨拶は5つのタイミングがあります。
これからお伝えするのは、それぞれの機会に適切な文例です。
喪主挨拶5つのタイミング

◇主な喪主挨拶は、出棺のタイミングです
葬儀当日、一般参列者は告別式で帰宅となり、火葬場の立ち合いは身内のみとなりますが、火葬場へ向かう出棺の際、一般参列者が玄関先で待ち、故人をお見送りしてくれるでしょう。
この時が主な喪主挨拶のタイミングです。
また一般参列者への喪主挨拶は、告別式が終わる際、会場で済ませる葬儀もあります。
(1)僧侶を迎える
(2)出棺時の喪主挨拶
(3)お布施を渡す喪主挨拶
(4)精進落としでの喪主挨拶
(5)精進落とし終了のご挨拶
一般参列者が告別式で帰宅しているため、精進落とし前後の喪主挨拶は、身内のみが残っている状態です。
昔は火葬後、焼骨したご遺骨へのお勤めである還骨法要の後に精進落としが行われてきましたが、現代では還骨法要を初七日法要で行う家が増えました。
(1)僧侶を迎える
◇僧侶のお迎えは喪主が行います
一般的に葬儀告別式を午前10時頃の開始を目安に行う家が多いでしょう。
この場合、約1時間前の午前9時を目安に受け付けを始めます。
「おはようございます。
昨日はご丁寧なお勤めとご法話を、ありがとうございました。
本日もどうぞ、よろしくお願いいたします。」
読経供養を依頼した僧侶も、午前9時半頃にはいらっしゃいますので、喪主やご遺族で迎え、控室へお通ししてください。
(2)出棺時の喪主挨拶

◇出棺時、参列者に向かい行う喪主挨拶です
葬儀の出棺時に行う喪主挨拶では、故人との別れ告げた後、お見送りをしてくださる一般参列者へ向かって行います。
喪主挨拶を済ませたら、棺を霊柩車に乗せて火葬場まで出棺する流れです。
「皆様、本日はお集まりいただき、まことに感謝しております。
本当にありがとうございました。
生前の妻は家族を愛し、休日の日には趣味の手芸を楽しみながら、友人知人との会話や出来事を楽しそうに話していました。
49歳の若さで亡くなったことは残念ですが、妻と過ごした楽しかった日々を、忘れることはありません。
最後まで家族の手を握りながら微笑み、妻らしい生き様を見せてくれました。
本日は、皆様にお見送りいただき妻も大変喜んでいると思います。
昨日の通夜、告別式共に遅れがなく無事に終了することが出来ました。」
また今回は、大阪の葬儀で行う出棺前の喪主挨拶についてご紹介していますが、地域によっては喪主挨拶のタイミングが異なる地域もあるかもしれません。
会場によっても出棺時に喪主挨拶を行わない場合があります。
事前に葬儀社との打ち合わせで、確認をしてください。
(3)お布施を渡す喪主挨拶
◇お布施は控室に戻ったタイミングでお渡しします
葬儀告別式では火葬場に僧侶が同行する場合と、しない場合があります。
火葬場に僧侶が同行する場合には、火葬開始前の読経供養がありますが、火葬場まで同行しない場合には、お焼香時の読経供養で、僧侶のお勤めは終わりです。
「本日はお心込められたお勤めをいただき、誠にありがとうございます。
お陰様で無事に葬儀を執り行うことができました。
こちらは、私どもの気持ちです、どうぞお受け取りください。」
僧侶の読経供養が終わり控室に戻ったタイミングで、喪主よりお布施をお渡しします。
お布施をお渡しする時は、テーブルを越えてお渡しするのではなく、テーブルを除け、何もまたぐものがない場所でお渡ししてください。
(4)葬儀後、精進落としの喪主挨拶

◇火葬後の精進落としは主に身内のみの席で行います
出棺をしたら斎場から火葬場へ移動し、火葬を行います。
火葬後は場所を移動し、葬儀後の会食「精進落とし」を行う流れが一般的です。
葬儀では、精進落としの前後でも喪主挨拶をします。
葬儀が無事に終わったことを報告し、お礼の言葉を伝えてください。
「本日はお集まりいただき、誠に感謝しております、心からお礼をいたします。
皆様のおかげで無事に告別式も終わり、妻も安心して天国に旅立ったと思います。
我々一同からささやかな気持ちでございますが、お食事の用意をさせていただきました。
お時間の許す限りごゆっくりと召し上がってください。」
また葬儀で精進落としの喪主挨拶の後、生前に故人と親しくしていた人から献杯(けんぱい)をお願いすることがあります。
献杯(けんぱい)の掛け声前に挨拶を行うことも多いため、事前に依頼をしておくと良いでしょう。
(5)精進落とし終了のご挨拶
◇精進落とし後の喪主挨拶は、次回の法要をご案内します
精進落としは前日の通夜振る舞い同様、会場の時間もあるため、一般的に開始から2時間程度を目安に、締めの挨拶を行います。
頃合いを見計らい締めの合図として行いますが、この場は基本的にご遺族や近親者が多いため、次回の法要についてご案内を行う喪主挨拶が一般的です。
「本日は誠にありがとうございます。
お陰様で私どもも知らなかった、妻のさまざまな顔を知ることができました。
まだまだ、妻の思い出に浸りたいところではありますが、夜も更けて参りますので、このあたりで終了とさせていただきます。
なお、次回の四十九日法要は○○月○○日を予定しております。
どうか、家族ともども今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。」
…このようになりますが、通夜振る舞い同様に、お悔みの席では「お開き」の言葉を使わず、「終了」の言葉を使うなど、忌み言葉には注意をしてください。
まとめ:葬儀の喪主挨拶は、個人へのご挨拶も大切です

葬儀での喪主挨拶は、全体へ向けたものも大切ですが、僧侶や参列者、それぞれへ向けた喪主挨拶も敬意を表し、丁重に行うことは思う以上に重要です。
以前は葬儀当日に還骨法要を行っていたため、この還骨法要の後に行う会食を「精進落とし」と呼んでいました。
この風習が、還骨法要を初七日へ繰り上げるようになった今も続いています。
ただ本来の「精進落とし」は、精進料理から日常食へ戻すことを差す言葉で、正確には会食や、「お斎(おとき)」などの言葉が正しいです。
・葬儀の費用は平均的にどれくらい?一般葬と家族葬では何が違う?抑えたい費用内訳とは?
まとめ
大阪の葬儀での喪主挨拶、5つのタイミングと例文
(1)僧侶を迎える
(2)出棺時の喪主挨拶
(3)僧侶にお礼とお布施をお渡しする
(4)精進落としでの喪主挨拶
(5)精進落とし終了のご挨拶
お電話でも受け付けております
















