
【お墓Q&A】ロッカー式納骨堂は誰が管理しているの?生前契約したいが、その実態は?
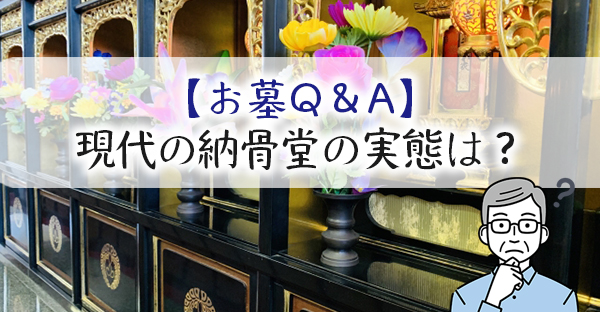
テレビでロッカー式納骨堂が放映され、一緒に見ていた母親が「自分が亡くなったら、納骨堂に入れてね。」と言うようになったとの、山本信子さん(仮名)38歳からのご相談です。
信子さんは母と娘2人暮らしで、マンションに暮らしています。
そのため母も信子さんもロッカー式納骨堂をテレビで見た時に抵抗はなく、お墓を建てるには負担も大きいため、本格的にロッカー式納骨堂について調べ始めたところです。
「母が生きている内にロッカー式納骨堂を購入したいので、現状を教えて欲しい」とのことでした。
【お墓Q&A】ロッカー式納骨堂は誰が管理しているの?生前契約したいが、その実態は?
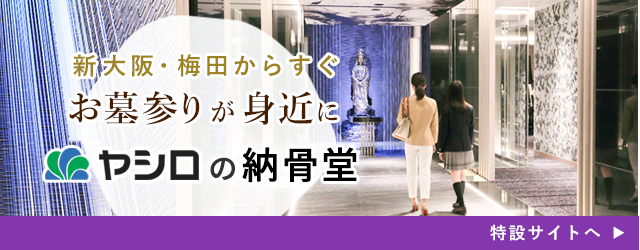
寺院納骨堂と共同墓地の納骨堂

今回、信子さんはロッカー式納骨堂をテレビで見て興味を持ったとのことですが、もともと「納骨堂」はロッカー式ばかりではありません。
古い納骨堂は、寺院が経済的な理由などからお墓を建てることができない檀家(※)のために用意したスペースが多いです。
(1)昔の寺院納骨堂
(2)昔の共同墓地の納骨堂
後述しますが、運営による納骨堂の違いばかりではなく、近年は葬送のひとつの形として認知され、ロッカー式の他、仏壇型やお墓型、ビル型(自動搬送式)などの形式に分かれます。
(※)檀家(だんか)とは、特定の寺院を信仰する家や人を差し、江戸時代から続く檀家制度の元、寺院墓地に先祖代々墓がある家では、その寺院の檀家になる仕組みです。
また家が信仰する寺院は「檀那寺(だんなでら)」「菩提寺(ぼだいじ)」などと呼びます。
家族が亡くなると戒名をはじめ、法要まで菩提寺のご住職に相談することが多いでしょう。
(1)昔の寺院納骨堂
昔からある寺院の納骨堂は、檀家さんのために遺骨を安置するスペースを用意したものでした。
現代では檀家さん個々のスペースとして、ロッカー式納骨堂を設置する寺院も増えましたが、昔ながらの納骨堂は棚を設けて、骨壺を並べて安置する形態が多かったのではないでしょうか。
・古い寺院納骨堂では、「一時的に遺骨を預かり供養やお世話をする」目的のものが多く、菩提寺と檀家の信頼関係があるからこその形態でした。
例えば分家など、さまざまな事情で寺院墓地に建っているお墓に埋蔵できないものの、新しくお墓を建てるには予算を貯めるのに時間が掛かる…、など、一時的な預かり場所としての役割が強くありました。
(2)昔の共同墓地の納骨堂
昔から知られる共同墓地の納骨堂も、お墓が建つまでの一時的な遺骨の預かり場所としての役割が大きい傾向でした。
●寺院納骨堂が檀家と菩提寺の信頼関係を前提に預けられたのに対して、公営墓地や民間霊園など、共同墓地の納骨堂は管理者が自治体や民間企業なので、宗旨宗派を問いません。
ただ公営墓地の納骨堂は、今でも一時的な遺骨の預かり場所として利用されることも多いですが、民間霊園が運営する納骨堂は、より身近な葬送ニーズが高まる現代において、お墓に変わる葬送の形として、大きく変化を遂げています。
現代の納骨堂

一方、忙しい現代において納骨堂は、より気軽にお参りに行ける、身近な新しい葬送の形として認識されるようになりました。
法的には「遺骨を預ける」とされますが、昔の古い寺院納骨堂のように棚に遺骨を並べる訳ではなく、個別スペースが用意されているので、納骨堂の運営側とのお付き合いに苦慮する必要もありません。
(1)遺骨を預かるのではなく置く感覚
(2)都心部に多い
(3)納骨堂の運営側とのお付き合いがほとんどない
(4)種類が豊富(費用も種類によってさまざま)
(5)納骨堂によって設備が違う
(6)永代供養が付いている納骨堂が多い
(7)宗旨宗派を問わない
(8)年間管理料が掛かる
…などなどがあります。
(1)遺骨を預かるのではなく置く感覚
大きく違う事柄は、お墓を建てるまでの一時的な預かり場所ではなく、納骨堂そのものがお墓として機能している、と言う点ではないでしょうか。
ただし公営墓地の納骨堂など、昔ながらの一時的な預かり場所としての納骨堂も見受けます。
このような納骨堂は費用も安い一方、納骨堂だけの施設です。
(2)都心部に多い
納骨堂はお墓と違い、屋内で多くの個室スペースを取りやすいため、地価が高い都心部を中心にこの10年~20年で開発されています。
忙しい現代、都心部に建つ納骨堂はお墓参りがしやすく、遠方にある家墓を墓じまい(※)して、都心部の納骨堂へ改葬(お墓の引っ越し)をする事例が増えました。
●お墓の継承問題が深刻化する現代、お墓の継承後に墓じまいをして、納骨堂へ改葬することで、継承問題を解消するケースが増えています。
また納骨堂は屋内にあるので、お墓掃除の必要もなく、お墓の維持管理がしやすい点も、現代のニーズに合っているのでしょう。
(※)「墓じまい」とは、先祖代々墓など今までのお墓を閉じることを差します。
詳しくは下記記事をご参照ください。
・【墓じまいの手続きまとめ】スムーズに進める7つのステップ|取り出した遺骨の永代供養
(3)納骨堂の運営側とのお付き合いがほとんどない
昔の古い寺院納骨堂は、檀家と菩提寺の信頼関係の元で遺骨を預ける形だったため、運営する寺院側と預ける檀家の間では、立ち入ったお付き合いも多くありました。
●けれども現代の納骨堂は、それぞれ個別スペースに遺骨が安置されるので独立していて、納骨堂経営者との深いお付き合いはほとんどありません。
特に民間霊園が運営する納骨堂は、面倒なお付き合いはほどんとなく、法要を行いたい時のスケジュール確認程度でしょう。
(4)種類が豊富
前にも少し触れたように、現代は都心部の納骨堂を中心にニーズが高まっているため、さまざまな納骨堂の種類が増えました。
今回、信子さん親子はロッカー式納骨堂を検討されていますが、この他にも仏壇型やお墓型など、さまざまな納骨堂の種類が見受けられます。
・ロッカー型納骨堂 (約20万円/1柱ほど~)
・仏壇型納骨堂 (約30万円~100万円/1柱ほど~)
・ビル型(自動搬送式)納骨堂 (約50万円~100万円/1柱ほど~)
・墓石型(堂内墓所)納骨堂 (約100万円/1柱ほど~)
・位牌型納骨堂 (約10万円/1柱ほど~)
…などなどです。
例えば個別の法要スペースや参拝スペースを設けているなど、施設の設備によって価格帯には幅がありますが、大まかな納骨堂の費用目安とともにご紹介しています。
※納骨堂の種類については、別記事をご参照ください。
・【納骨堂まとめ】納得できる納骨堂を選ぶ基礎知識。種類の違いや費用相場5つのポイント
(5)納骨堂によって設備が違う
納骨堂には遺骨を収蔵するスペースのみを設けた施設もありますが、現代では葬送のひとつの形として注目されはじめ、納骨堂内にさまざまな設備を設けている施設も増えました。
・個別の法要スペース
・個別の参拝スペース
・斎場
・待合室
・登録カード
…などなど。
特に参拝時に遺骨が自動搬送で参拝スペースに運ばれる、ビル型(自動搬送式)納骨堂では、登録カードで受け付けを済ませ、指定された個別の参拝スペースに行って、参拝を行います。
予約をすることで、法要スペースや斎場を利用することができるなど、至れり尽くせりの施設も少なくありません。
(6)永代供養が付いている納骨堂が多い
今回、信子さんが心配していた事柄は、「自分亡き後の継承者がいない」と言うものでした。
けれども現代の納骨堂では、ほとんどの施設で納骨堂に永代供養がついているので、継承者を必要としません。
●「永代供養」とは、家族に代わり永代に渡り施設管理者が遺骨のお世話や供養を行う仕組みです。
→25年、50年など、契約時に定めた一定期間は納骨堂の個別スペースに遺骨が安置され、一定期間が過ぎると合祀墓などに合祀埋葬されます。
信子さんのように母と子2人の生前契約を行う場合、最後に収蔵された遺骨から年数がカウントされます。
ただし納骨堂の個別スペースに遺骨が安置される「一定年数」は施設によって違うので、事前に確認をしてから契約を進めましょう。
(7)宗旨宗派を問わない
現代の納骨堂は宗旨宗派を問わない施設が多いです。
最近では寺院が運営する納骨堂であっても、宗旨宗派を問わない施設が増えています。
●永代供養を付加した納骨堂がほとんどなので、毎月の合同供養などでは、運営側が契約する特定の宗旨宗派の寺院で読経供養を行いますが、個別法要での宗旨宗派は自由です。
そのため近年では無宗教として、読経供養を行わない家も増えました。
(8)年間管理料が掛かる
納骨堂は永代供養が付いていますが、個別スペースに安置されている期間は、一般的なお墓と同じように年間管理料が掛かります。
●納骨堂の年間管理料は、一般的に約1万円~2万円/年が相場です。
ただし、納骨堂は終活で生前契約を交わすケースも多いので、契約時点で個別スペースに安置する契約年数、全ての年間管理料を支払う場合も多いでしょう。
無縁仏になる可能性

ただし契約時点で期間が決まっておらず、更新をする形式だった場合には、滞納すると遺骨は無縁仏として整理されてしまう可能性があります。
●契約期間が定まっておらず、年間管理料が一定年数滞ってしまった場合、その遺骨は無縁仏として供養塔などに埋葬されることになるでしょう。
→今回のように、予め継承者の不在が気に掛かる場合には、契約時に年数を決めて購入すると、より安心です。
一般的な霊園に建つお墓も、最初に墓地を永代に渡り使用する「永代使用権」を購入した後、墓主は毎年年間管理料(寺院であればお布施の場合も)を支払います。
そのため納骨堂でもお墓でも、年間管理料の納入が滞ってしまった場合の対処は同じです。
最後に
以上が、現代納骨堂のあらましです。
都心部で注目される葬送のひとつの形として注目され、年間管理料が掛かるなど、納骨堂は形式としてはお墓と同じですが、同じ納骨堂でも種類が豊富にあるので、予算に合わせた納骨堂を選ぶことができるでしょう。
この他、お墓を持たない葬送の形としては、納骨堂の他にも樹木葬や自然葬などのニーズも高まっています。
この他、遺骨を自宅の仏壇に祀る手元供養や、粉骨した遺骨を海や山林へ散骨する散骨なども見られるようになりました。
※樹木葬については下記をご参照ください。
・【樹木葬の選び方】自然(土)に還るシンボルツリー型樹木葬|仕組みで選ぶ6つのポイント
まとめ
現代納骨堂の特徴
(1)遺骨を預かるのではなく置く感覚
(2)都心部に多い
(3)納骨堂の運営側とのお付き合いがほとんどない
(4)種類が豊富(費用も種類によってさまざま)
(5)納骨堂によって設備が違う
(6)永代供養が付いている納骨堂が多い
(7)宗旨宗派を問わない
(8)年間管理料が掛かる
お電話でも受け付けております















