
「生前墓」とは?生前にお墓を購入するメリット・デメリット、家族の意見は?購入の流れ
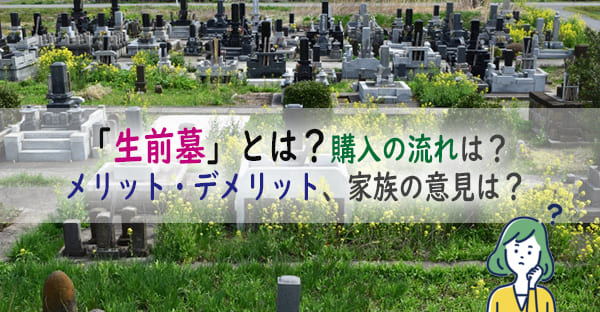
・「生前墓」とは?
・生前にお墓を購入するメリットは?
・生前にお墓を購入するデメリットは?
・生前墓を購入する流れは?
生前に自分亡き後の葬儀や供養の準備をする「終活」の広がりから、生前墓の購入も増えましたよね。
墓守や継承の必要がない永代供養により、さらに生前墓のニーズが広がっています。
本記事を読むことで、生前墓が増える理由やメリット・デメリット、家族の意見や購入の流れ、注意点が分かります。

生前墓とは?

◇「生前墓」とは、生きている内に自分が入るお墓を建てることです
生前墓(せいぜんはか・せいぜんぼ)は、生きている内に自分自身でお墓を選び、亡くなる前に建てておくことを差します。
生前墓は一般のお墓と違い、赤い文字で名前や戒名を彫刻することが多いでしょう。
| <「生前墓」とは> | |
| [生前墓とは] | ・生前にお墓を建てる ・寿陵墓(じゅりょうぼ) |
| [目的] | ・自分でお墓を決める ・子孫繁栄に繋がる ・長寿を祈願する ・相続税対策 ・時間を掛けてお墓を選ぶ |
近年、生前墓が注目される背景は、自分亡き後の葬儀や遺骨の供養を、生きている内に自分自身で選び段取りを進めておく「終活」の広がりです。
生前の遺骨の供養方法を決めて、自分のお金で契約を済ませることで、残された家族の負担を軽減しようと、生前墓を購入する人が増えました。
生前墓を建てても良いの?
◇生前墓は「寿陵墓」とも呼ばれ、長寿や子孫繁栄を祈願する縁起の良いものです
現代の日本では、しばしば「生前墓を建てると死期を早める」「生きている内に死後の準備をするなんて、縁起悪い!」と反対を受けることもあります。
けれどもその昔、生前墓は中国や日本で「寿陵墓(じゅりょうぼ)」とも呼ばれ、聖徳太子や秦の始皇帝など、歴史人物も生前墓を建てて来ました。
| <生前墓は縁起が良い> | |
| [寿陵墓(じゅりょうぼ)] | ・長寿 ・子孫繁栄 ・家庭円満 |
寿陵墓の「寿」は「ことぶき」で縁起の良いお祝いを意味する言葉です。
寿陵墓の「陵」は「みささぎ」とも呼ばれお墓を意味します。
中には「生きている内に死後の準備をするなんて!」との声もありますが、生前に自分亡き後の準備をすることは、「逆修(ぎゃくしゅう)」と呼ばれ、縁起の良いことです。
| <「逆修」とは> | |
| [逆修とは] | ・自分亡き後の準備をする ・生前に冥福を祈る ・大きな功徳を積む行為 ・大きな幸福を招く ・子孫の徳を積む |
| [具体例] | ・生前墓 ・位牌 ・法事 ・戒名 |
生前墓を建てたり、位牌を仕立てるにあたり戒名をもらう人もいるでしょう。
現代の日本では、人が亡くなって初めて戒名をいただくことが一般的ですよね。
けれども「お釈迦様の弟子としての名前」が戒名なので、生前にいただくことは何も問題はなく、むしろ生前に仏門にはいるとして良い行いです。
現代はほとんどありませんが、生前に法事を執り行い冥福を祈る行為も、逆修として大きな功徳を積みます。
生前墓を購入するメリットとは?

◇生前墓を購入する理由に多い事柄は、残された家族の負担軽減です
この他、生前墓は子どもや孫がいない「おひとりさま終活」でも注目されています。
おひとりさま終活での生前墓の購入は、自分亡き後、遺骨の扱いを自分で決めることができる点です。
・残された家族の負担を軽減
・本人の財産から費用を捻出
・お墓を選ぶ時間がある
・相続税が掛からない
・家族で話し合う機会ができる
お伝えしたように生前墓は縁起が良いことはもちろんですが、それ以上に現実的には、生前にお墓を購入することで子どもや孫に金銭的な負担が掛かりにくい点が評価されています。
背景には一般的な霊園で基本のサービスとなった、永代供養があるでしょう。
永代供養の登場により、一代のみでお墓を建てる「個人墓」も実現しています。
永代供養とは?
◇「永代供養」とは、施設管理者へ遺骨の管理や供養を任せることです
「永代供養(えいたいくよう)」とは、墓地霊園や納骨堂などの施設管理者が、家族に代わり永代に渡って遺骨の管理や供養をしてくれるサービスを差します。
現代の民間霊園では一般墓に永代供養が付くことが基本にもなっていて、約25年・50年など、契約年数内に更新をすることで永代供養の更新も可能です。
| <永代供養とは> | |
| [永代供養とは] | ・管理者が遺骨を管理・供養 ・継承者の必要がない ・契約年数を過ぎたら合祀供養 ・契約年数内の更新により継続 |
ただ管理者が永代に渡り保証するのは、お墓ではなく遺骨の管理・供養となります。
そのため墓地霊園や納骨堂などの施設により年数は異なりますが、永代供養の契約年数内に更新がない場合、遺骨は取り出して合祀墓へ合祀供養され、お墓は撤去されるでしょう。
生前墓で家族の負担を軽減
◇生前墓を建てることで、残された家族のやるべき事がひとつ減ります
家族が亡くなると必ず遺骨の供養が求められますが、現代は先祖代々墓に入る予定はなく、お墓を持たない人も少なくありません。
・経済的負担を軽減する
・哀しみのなかでやる事が減る
・親族間でのトラブルを避ける
家族を亡くした哀しみのなかでお墓を建てる行為は、経済的・精神的な負担が掛かりますが、生前墓の購入により、お墓を準備する負担が軽減されます。
また、故人本人が決めた遺骨の供養方法ですから、残された家族が決めた方法よりも、親族が納得する流れが多いです。
・墓じまいや仏壇じまいで親族間トラブル☆話し合いがまとまらない事態を解決した3つの対策
本人の財産から費用を捻出
◇本人が生前にお墓を建てることで、残された家族がお墓を建てる費用の工面に困りません
生前墓をはじめとする「終活」は、子どもや孫に負担を掛けたくないとして進める人々が多いです。
そのなかでも遺骨の供養は費用が高く、経済的負担が伴います。
| <生前墓の費用目安> | |
| [個別墓] (永代供養付き) |
・約40万円~200万円 (平均値約175万円) |
| [集合墓] (納骨堂など) |
・約20万円~100万円 (平均値約60万円) |
| [合祀墓] | ・約5万円~30万円 (平均値約10万円) |
個別墓に掛かる費用の平均値は約175万円です。
一般的に納骨式は故人が亡くなってから四十九日後、四十九日法要の後に行うことが多いでしょう。
正式に故人から財産を相続する前に慌てて建てる事例も多く、遺品整理など他の手続きも含めて、残された家族に一度に経済的負担が掛かることも少なくありません。
※ただし葬儀費用は、故人の貯金から支払うことが認められています。
お墓を選ぶ時間がある
◇生前墓は、お墓を選ぶ余裕があります
一般的に納骨式は四十九日法要の後に行うため、かつては四十九日法要に向けてお墓を準備する遺族が多くいました。
四十九日法要を過ぎても、お墓が建つタイミングで納骨式を執り行うことはできますが、その間の遺骨の安置場所は検討しなければなりません。
| <生前墓はお墓を選ぶ余裕がある> | |
| [生前] |
●じっくりお墓を選べる ・お墓の形式 ・デザイン ・墓地の場所 |
| [亡き後] |
●お墓を選ぶ時間が限られる ・四十九日法要を目安に ・一周忌を目安に ・遺骨の安置場所を検討 |
遺骨の安置場所は自宅でも構いません。
ただ従来、お墓が建つまで遺骨は納骨堂などの安置施設に預けていました。
納骨堂の利用には料金も掛かりますので、余計な費用もあるでしょう。
相続税が掛からない
◇祭祀財産に相続税は掛かりません
お墓や仏壇など、ご先祖様を供養する財産は「相続」ではなく「継承」です。
そのため故人を供養するための道具「祭祀財産」の継承に相続税は掛かりません。
けれども相続した財産には相続税が掛かります。
故人が生前墓を建てることで、祭祀財産として家族に継承できます。
| <相続税が掛からない> | |
| [生前墓] |
・生前にお墓を建てる ・建墓費用は本人の財産 ・お墓を継承 ・相続税は掛からない |
| [一般墓] |
・亡き後にお墓を建てる ・故人の財産を相続する ・相続した財産から建墓費用を出す ・相続税が掛かる |
一例として、9,000万円の預貯金財産がある場合で単純計算してみましょう。
両親が生前墓を800万円で建てた時と、子どもが相続後に両親のお墓を800万円で建てた時の相続税差額は、「7,480万円-7,280万円=200万円」です。
・お墓の生前購入で相続税や贈与税はどうなる?相続後の相続税との差額は?葬儀や戒名は?
家族で話し合う機会ができる
◇子ども世代のアンケートでは、約60%の人々が想いを残して欲しいと答えています
親が存命している男女400名に向けた調査では、約60%以上の人々が、残された家族へ遺志を伝える「エンディングノート」を残して欲しいと答えました。
また親が存命する男女1200人に向けたアンケート調査によると、エンディングノートに残して欲しい事柄のトップが「葬儀・墓について」です。
| <子ども世代へのアンケート調査> | |
| [エンディングノート] |
・残して欲しい…29% ・早いが残して欲しい…35.5% ・必要はない…34.5% ・すでにある…1% |
| [残す内容] |
・葬儀や墓について…62.6% ・相続や財産について…58.6% ・終末期医療について…50.6% |
親としては子どもや孫に負担を掛けたくないとして、自然葬や0葬などの遺骨の残らない供養を契約する人もいます。
けれども供養する対象としてお墓が欲しい子ども世代も少なくありません。
親子で話し合いながら生前墓を準備することで、お互いに納得できる供養方法を選ぶことができます。
・ライフメディアリサーチバンク(2014年)
生前墓を購入するデメリットは?

◇生前墓は契約できない墓地もあります
特に市区町村など自治体が運営する公営霊園は、安い費用でお墓を建てたい住民のために開放された墓地となり、遺骨のない状態での契約ができない墓地が一般的です。
・生前墓の制約がある墓地
・自分亡き後の支払い
また終活全般に言えることですが、現代の日本で終活が広がっているものの、まだまだ全国的には「生きている内に亡き後の話をするなんて!」と考える親族は少なくありません。
生前墓を購入するにあたり、事前に親族にも理解してもらえるよう話しておくことをおすすめします。
生前墓の制約がある墓地
◇公営墓地などは、生前墓の契約ができない墓地がほとんどです
前述したように遺骨の納骨ができない住民に向けた提供を目的とする公営墓地では、遺骨のない状態での契約が一般的に難しいです。
そこで生前墓の契約を受け入れる民間霊園や寺院墓地でのお墓選びとなるでしょう。
ただ、近年では終活の広がりにより、生前墓の契約を受け入れる公営墓地も見受けるようになりました。
| <生前墓を受け入れる公営墓地> | |
| [神奈川県] |
・横浜市営納骨堂「日野こもれび」 |
| [東京都] |
・八王子市営緑町霊園 |
| [兵庫県] | ・宝塚市長尾山霊園 |
ただ生前墓の契約を受け入れる全ての公営墓地で、個別墓が建つ訳ではありません。
他の遺骨とともに合祀埋葬する合祀墓などで、生前契約できるものもあります。
自分亡き後の支払い
◇生前墓でメモリアルローンを組んだ場合、返済期間に注意をします
生前墓の購入は、相続税対策や子や孫の負担軽減を目的とするため、多くは将来的に子や孫が相続する財産を費用に充てるでしょう。
生前墓の購入をメモリアルローンで購入する場合、返済期間に注意が必要です。
メモリアルローンとは、葬儀やお墓など供養にまつわる費用のローンを差します。
| <自分亡き後の支払い:注意点> | |
| [返済期間中に亡くなる] (ローン残高が残る) |
・保証人に返済が移る可能性 |
| [維持管理費] |
・年間管理料の支払い |
また自然葬や合祀墓など、他の遺骨とともに供養される場合は年間管理料が掛からない墓地霊園が多い一方、個別墓や納骨堂は年間管理料が掛かる施設が多いです。
一般的に民間霊園や納骨堂では約5千円~3万円、平均値では約9千円~1万5千円ほどが目安になるため、家族で相談して決めましょう。
生前墓を購入する流れ

◇生前墓の多くは、墓地霊園見学から始まります
生前墓の購入を検討し始めたら、最初に複数の墓地や霊園のパンフレットや資料を取り寄せましょう。
いくつかの墓地霊園に絞り込んだら、見学日時を電話で取り付けます。
現代はインターネットで見学予約ができる施設もあるでしょう。
| <生前墓を購入する流れ> | |
| [0~3ヶ月] (契約前) |
(1)家族・親族間で話し合い (2)墓地霊園の資料請求 (3)3~5か所の墓地霊園に絞る (4)墓地霊園の見学 (5)生前墓の申し込み |
| [4~6ヶ月] (契約後) |
(6)建墓の打ち合わせ(石材業者) ・墓石デザイン ・石材のランクや種類 ・彫刻する文字 (7)墓石工事契約 (8)墓石の完成 |
| [7カ月以降] | (9)開眼供養 |
生前墓のなかには約40万円~100万円弱で購入できる、ワンプレート型墓石のガーデニング型樹木葬もあるでしょう。
ガーデニング型樹木葬での打ち合わせは彫刻する文字くらいです。
石材業者との墓石工事契約を済ませると、後は2~3ヶ月ほどで完成します。
「開眼供養」とは墓石に魂を込める仏式儀礼で、納骨する故人がいなくても、墓石に向かい開眼供養のみを執り行うことが可能です。
まとめ:生前墓は縁起が良くメリットも豊富です

生きているうちにお墓を購入する「生前墓」は、相続税が掛からないだけではなく、子や孫に経済的負担や精神的負担を軽減します。
経済的な負担ばかりではなく、残された家族にとって遺骨の供養方法は、選択に迷う事柄でもあるでしょう。
遺骨の扱いについて「遺志を残してくれていれば…」「本人の希望を知りたい」とする遺族は少なくありません。
生きている内に本人が納得できる遺骨の供養方法を選び、契約することで、家族は本人が残した道筋に迷いなく、添うことができるでしょう。
お電話でも受け付けております















