
継承者のいない永代供養でも個別に安置できる?終活でできる5つの選択肢|永代供養ナビ
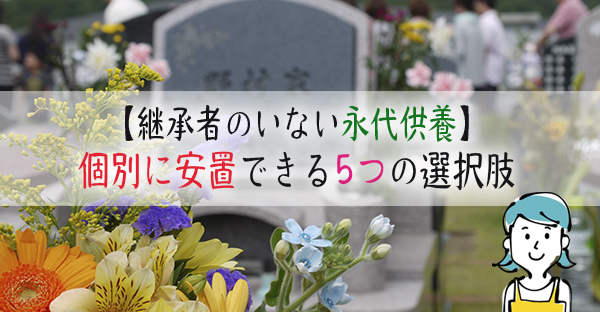
永代供養を付けながら個別で遺骨を安置する希望は、年々増えていますよね。
永代供養を付けても個別に遺骨を安置すると、お墓と同じように、お参りをしたり、三回忌や七回忌では、個別に法要を執り行うことも可能です。
けれども永代供養を付けたからと言って、個別に遺骨を安置できるものの、遺骨を取り出して他のお墓へ埋葬する「改葬(かいそう=遺骨の引っ越し)」ができない選択肢もあります。
今回は継承者やお墓の管理維持を必要としない永代供養に、一定の個別安置期間がある5つの選択肢をご紹介します。

永代供養を個別にできる5つの選択肢

●永代供養とは、墓地管理者が家族に代わり遺骨を永代に渡って管理・供養をしてくれるサービスで、継承者を必要としません
継承者を必要としないため、お墓の継承問題の解決策にもなりますし、個別区画がある一般的なお墓のように、定期的なお墓掃除や修繕、建て替えなどの墓主にのしかかる負担もない点が魅力です。
けれども一方で一般的には合祀による永代供養ですが、一定期間は個別に遺骨が安置されることで、お墓の負担を解消しながら、お墓参りなどの供養はできます。
(1)納骨堂
(2)集合墓
(3)個別タイプの樹木葬
(4)ガーデニング型樹木葬
(5)永代供養付き個別墓
永代供養の個別安置期間は、墓地管理者が提供するサービスにより差があるでしょう。
1年・3年・5年などの比較的短い期間で、費用を安く抑えるものもあれば、25年・33年など四半世紀を超えた永代供養の個別安置期間を設けるものもあります。
特に永代供養の個別安置期間が長い設定では、お墓の代わりとなる葬送のひとつと捉えられているかもしれません。
・お墓購入の項目「永代使用料」ってなに?永代供養料や管理費とは違うの?|永代供養ナビ
(1)納骨堂
●納骨堂は遺骨の永代供養が付いた、屋内の個別収蔵スペースです
昔はお墓を建てるまでの一時的な遺骨の安置場所でしたが、屋内で都心部にも近いアクセスの良さと、永代供養が付きながら個別の法要にも対応するなど、葬送サービスの充実により、現代の葬送のひとつの形として定着しています。
そのためお墓同様、納骨堂も個人で入るタイプだけではなく、夫婦2柱が収蔵できるタイプ、家族6~8柱ほどが収蔵できるタイプも見受けるでしょう。
家族で入る納骨堂は、「屋内墓所」などとも呼ばれます。
・個別タイプ
・夫婦タイプ
・家族タイプ
永代供養の個別安置期間は、最後の人が納骨された日からカウントされる仕組みが多い
期間内に遺族が契約更新をすることで、永代供養の個別安置期間を延長できる
遺族の希望で遺骨を改葬(お墓などに引っ越し)できる納骨堂は、永代供養であっても個別安置期間は年間管理料を必要とする施設が多いでしょう。
●生前契約の時には、永代供養の個別安置期間だけ、事前に年間管理料の支払いを済ませる契約が多いです。
・【納骨堂まとめ】納得できる納骨堂を選ぶ基礎知識。種類の違いや費用相場5つのポイント
(2)集合墓
●屋外にある納骨堂のような造りで、永代供養を付けた個別スペースが提供されます
墓石でできたロッカーのような造りの集合墓が多く、生きている人の住まいで言えば分譲マンションにも似ているでしょう。
仕組みは納骨堂と同じく、永代供養を付けた個別の収蔵スペースで、お墓と納骨堂の間を取っているため、永代供養でも個別スペースに納骨している間は年間管理料が掛かります。
・個別タイプ
・夫婦タイプ
・ペットと一緒タイプ
屋外に建つ集合墓では、しばしばペットと一緒に収蔵できる施設も見受けるでしょう。
家族タイプは少ないものの、「夫婦2柱+子ども1柱」や「夫婦2柱+ペット1柱」などを受け付ける施設も見受けます。
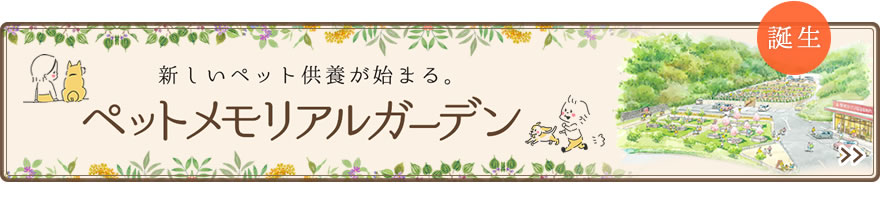
(3)個別タイプの樹木葬
●樹木葬では、個別に埋葬されるものもあります
永代供養が付いた樹木葬では、合祀墓と同じく他の遺骨とともに合祀埋葬されるシンボルツリー型樹木葬が知られていますが、個別に埋葬される個別タイプの樹木葬が人気です。
・個別スペースに遺骨が埋葬される
・参拝は合同スペースが多い
・遺骨は取り出すことができない
ただし樹木葬は最終的に土に還る自然葬のひとつなので、個別スペースに埋葬されはするものの、納骨堂や集合墓のように、後々遺骨を取り出しすお墓や遺骨の引っ越し「改葬」はできません。
遺族にとって、個別に埋葬された大まかなエリアは分かるものの、植樹型でなければ個別の墓標もなく、樹木葬一体エリアで合同に使用される、焼香台や供花スペースを利用して参拝します。
・【樹木葬の選び方】自然(土)に還るシンボルツリー型樹木葬|仕組みで選ぶ6つのポイント
(4)ガーデニング型樹木葬
●ガーデニング型樹木葬は、草花に囲まれた庭園のなか、永代供養付きで個別に遺骨が安置されます
ワンプレート型のシンプルで小さい墓石の下、永代供養を付けて一定期間は個別安置される仕組みが多く、小さいながらも「お墓」にお参りができる点は魅力です。
費用面でも抑えながら草花に囲まれた良い環境で、家族にも墓標があるため、今最もニーズが高い永代供養の個別安置型ではないでしょうか。
・小さなワンプレート型墓石が付いたものが多い
・手入れをされた草花に囲まれた庭園
・ペットと一緒に納骨されるものもある
ガーデニング型樹木葬も永代供養で一定期間は個別安置されますが、契約時に交わした一定期間を過ぎると、霊園施設内の合祀墓に合祀埋葬されます。
夫婦など複数で契約した場合、最後に納骨された人からカウントされる仕組みです。
・【自然葬の種類】自然葬の種類と特徴。個別の墓標を残す自然葬もあるの?|永代供養ナビ
(5)永代供養付き個別墓
●永代供養付きの個別墓では、お墓の形を取りながら継承者は必要ありません
ただし墓石が建つ一般墓に永代供養が付いたも個別墓なので、費用面では一般墓と変わりはありません。
・昔ながらの一般墓
・永代供養が付いている
・費用は一般墓と同等で約150万円/1基ほど~
・お墓と同じく、家族6~8柱ほどが納骨できる
・個別の法要やお墓参りも一般墓と同じ
・永代供養の個別期間を長く設定
・年間管理料が掛かる(約9千円~2万円ほどが目安)
現代はコンパクトでシンプルなお墓が多いため、平均的に約150万円ほどが建墓費用となるでしょう。
また近年では、霊園などの墓地管理者が無縁墓対策として、全ての一般墓に予め永代供養を付けていることも多いです。
・お墓を建てる費用はどれくらい?平均的な費用と内訳、安く抑える方法まで|永代供養ナビ
永代供養の個別安置、選ぶポイント

●永代供養で個別に安置するのであれば、契約時に規約を入念に確認します
永代供養で個別に安置できる葬送は、契約時に規約を通して交わした「一定期間」が過ぎると、合祀埋葬されて合同供養されるため、家族はその仕組みを理解しなければなりません。
そこで永代供養を決める際は改めて、①個別に安置したい期間はどれくらいか、②将来的に更新する可能性があるのか、を整理しておくと良いでしょう。
・予算と優先順位を決める
・費用と個別安置期間は比例する
・お墓参りの仕方を確認する
・個別の法要ができるかを確認する
・年間管理料の有無や料金を確認する
・更新の可否や更新料、システムの確認
同じ永代供養で個別に安置される葬送を選んだ場合でも、そもそも子どもがいない夫婦のみの生前契約であれば、それほど安置期間を長く設定する必要はありません。
子どもや孫が後々まで供養していきたいけれど、管理維持がしやすく負担の少ない永代供養の個別安置を選ぶことは多いので、この場合には、納骨後の個別法要やお墓参りなど、供養の仕方を細かく確認できると安心です。
・秋のお彼岸、お墓参りの作法はある?納骨堂や樹木葬など形式によっても違う5つのマナー
最後に
今回は継承者を必要としない永代供養でも個別に安置される、5つの選択肢と選ぶ時のポイントをお伝えしました。
永代供養には大まかに2つの種類があり、傾向としてそれぞれに希望や目的、環境が違いますが、特に個別型では残された遺族が、後々まで供養したい希望が大きいでしょう。
・個別型
・合祀型
合祀型を選ぶ人は家族親族がすでに他界して、より自由度が高い人々などが多く、この場合には納骨後の供養方法まで気にしない人も少なくはありません。
けれども永代供養に個別安置期間を希望する人々の多くは、お墓の継承や維持管理はできないものの、お墓参りや七回忌などの個別法要は執り行いたい家が多い傾向です。
そのため永代供養の個別安置を希望する人は、ぜひ契約前に「希望の供養方法と、優先順位」を家族親族で整理して、規約をしっかりと確認した後、分からない箇所は遠慮せずに質問しながら、契約を進めると良いでしょう。
・【手元供養の体験談】娘の手元供養。娘の遺骨を納骨できないまま5年、分骨をして祭壇へ
まとめ
永代供養で個別に安置する5つの方法
●個別スペースがある5つの永代供養
(1)納骨堂
(2)集合墓
(3)個別タイプの樹木葬
(4)ガーデニング型樹木葬
(5)永代供養付き個別墓
●個別の永代供養を選ぶ6つのポイント
・予算と優先順位を決める
・費用と個別安置期間は比例する
・お墓参りの仕方を確認する
・個別の法要ができるかを確認する
・年間管理料の有無や料金を確認する
・更新の可否や更新料、システムの確認
お電話でも受け付けております

















